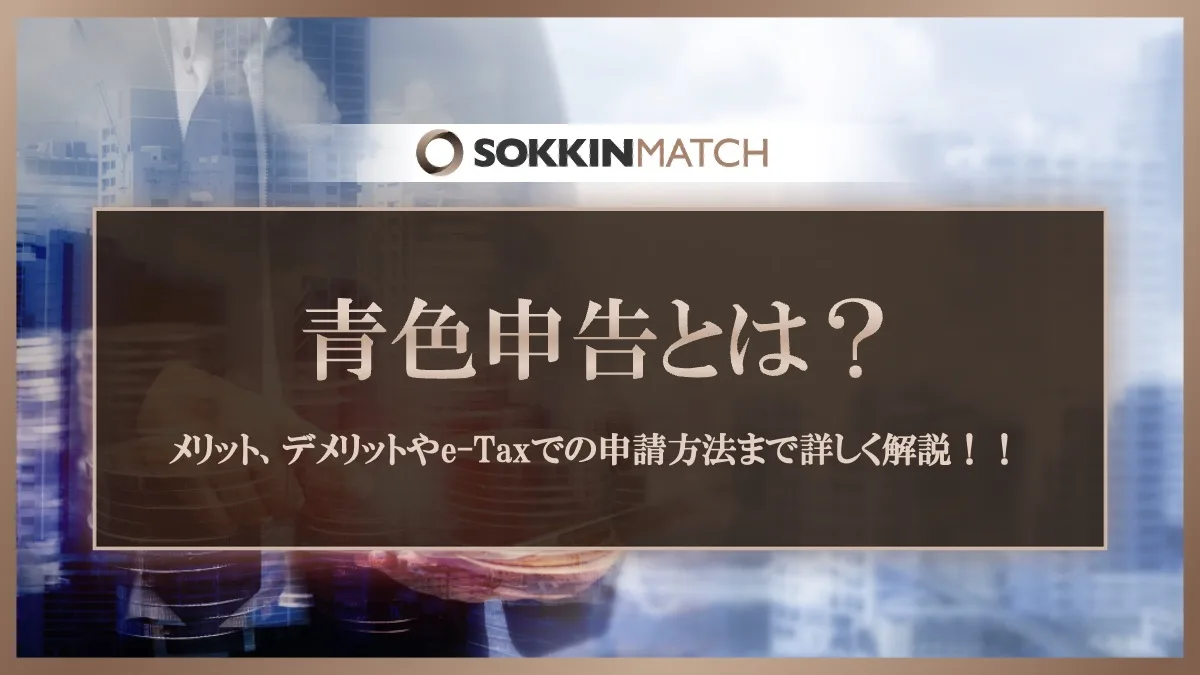確定申告のひとつの方法として用意されている青色申告は、白色申告と比較した際に納税者にとってメリットが多い申告方法でもあります。しかしその一方でデメリットもあり、すべてのケースにおいて青色申告が向いているとは限りません。
青色申告を選択したほうがよい事業者にはどのような特徴があるのでしょう。

青色申告のメリット・デメリットとあわせてe-Taxでの申請方法など網羅的に解説します。白色申告とどちらにしようか迷っている人は、青色申告に関する知識・理解を深めたい人はぜひ参考にしてください。
青色申告とは
青色申告は確定申告方法のひとつで、国税庁によって定められている会計処理に基づいて帳簿を作成して所得税の申告・納税を行います。
しかし適用できる所得は限られており、どのような収入・収益に対しても適用できるわけではありません。青色申告が可能な所得は以下の3種類です。
|
所得の種類
|
概要
|
| 不動産所得 | ・土地や建物などの不動産貸付(賃貸料・家賃収入など) ・借地権など権利設定および貸付 ・船舶や航空機の貸付 ・不動産売却益は対象外 |
| 事業所得 | ・事業活動によって得られる所得 ・小売業、サービス業、卸売業、漁業、製造業、農業、その他の事業が対象 |
| 山林所得 | ・山林の伐採や立木の譲渡によって得た所得 ・山林取得5年以内の譲渡所得については対象外 |
(出典:No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁、No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁、No.1480 山林所得|国税庁)
白色申告との違い
確定申告の方法には青色申告以外に白色申告もありますが、この2種類には以下のような違いがあります。
|
青色申告
|
白色申告
|
|
| 所得種類の制限 | あり(3種類のみ) | なし |
| 事前登録 | 必要 | 不要 |
| 特別控除 | あり | なし |
| 帳簿の記帳方法 | 原則は複式簿記 | 簡易簿記 |
| 確定申告時の提出書類 | 4種類 | 2種類 |
| 保存が必要な帳簿 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳など | 簡易簿記で作成した帳簿 |
「所得種類の制限」については、前述で解説した通りです。それ以外の5つの項目については青色申告のメリット・デメリット内で詳しく解説するので、そちらもあわせて参考にしてください。
▼ 白色申告のメリットについて詳しく知りたい方はこちら。

青色申告のメリット
青色申告の主なメリットは、以下の通りです。
・少額減価償却資産の一括計上
・青色事業専従者給与
・支出額50%以下の家事関連費の経費計上
・赤字の繰越・繰戻(3年間)
上記にあげたそれぞれのメリットを詳しく確認していきましょう。
最大65万円の特別控除が受けられる
青色申告の代表的なメリットは、青色申告特別控除です。10万円・55万円・65万円の3段階が用意されており、金額に応じて設けられている要件を満たすことで適用できます。
|
控除額
|
適用要件
|
| 55万円 | ・不動産所得または事業所得が発生する事業活動 ・複式簿記による記帳 ・複式簿記による記帳で作成された貸借対照表および損益計算書を確定申告に添付 ・確定申告の法定期限内に必要書類を提出 |
| 65万円 | ・55万円の要件すべてに該当 ・仕訳帳および総勘定元帳の電子帳簿保存または確定申告書等の必要書類をe-Taxにて法定期限内に提出 |
| 10万円 | 55万円および6万円の要件に該当しない青色申告者 |
(出典:No.2072 青色申告特別控除|国税庁)
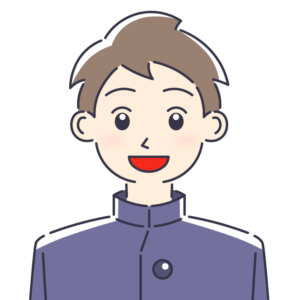
65万円控除の適用要件に明記されている「電子帳簿保存」とは、仕訳帳や総勘定元帳などを単にパソコンに保存しておけばいいんですか?

そうではありません。
会計ソフトでの作成を前提として、一定の要件を満たした電子計算機処理システムの使用や保存方法などが細かく定められており、これらを満たさなければ「電子帳簿保存をしている」とは認められません。
経理の電子化による生産性・記帳水準の向上を目的として、「令和3年度 税制改正」において電子帳簿保存法が改正されました。これに伴い国税関係帳簿についての優良な電子帳簿の要件が整備され、青色申告特別控除のなかでも65万円の適用を受ける際の必須条件に追加されています。
詳しい条件については、国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」にて確認可能です。満たさなければならない要件は税制改正で変更になる可能性があるので、こまめに確認してください。
30万円未満の固定資産が全額経費になる
30万円未満の少額減価償却資産を一括経費計上できる特例制度も、青色申告のメリットのひとつです。
通常、取得価額が10万円以上または耐用年数1年以上の固定資産は減価償却をしなければなりません。しかし一定の要件を満たすことで取得価額30万円未満の固定資産について、減価償却をせずに一括経費計上ができます。これを「少額減価償却資産の特例」といい、以下の要件を満たすことで適用が可能です。
2. 取得価額30万円未満の減価償却資産
3. 確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付
4. 青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に「取得価額の合計額」「租税特別措置法第28条の2を適用する旨」を明記
5. 取得価額の明細を別途保管
(出典:「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について |国税庁、No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁)
家族への給料を経費にすることが可能
青色申告者の場合、家族に支払う給料の経費計上が可能な青色事業専従者給与の特例が利用可能です。
白色申告でも従業員として雇用した家族に支払った給与の一部は経費として計上できますが限度額が設けられており、全額を計上できるとは限りません。
一方の青色事業専従者給与の場合、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、相当であると認められる金額の経費計上が認められています。計上できる金額に限度額は設けられておらず、業務内容・条件などを確認した税務署が「相当である」と判断すれば、全額計上が可能です。
限度額が設けられている白色申告とは異なり、条件次第では全額計上ができる青色事業専従者給与の制度は有効な節税対策としても役立つでしょう。
家賃、電気代などを経費にすることが可能
白色申告も青色申告も家賃・電気代などは、家事按分して事業分を経費計上できます。
家事按分とはプライベートと事業用にわけて家賃・電気代などを算出し、事業用分のみを経費計上する方法です。
例えば家賃の場合、事業用として利用している面積が全体の何割を占めているかで支払家賃を計算します。
青色申告の場合、家事按分で算出したこれらの費用に限度額は設けられていません。
一方の白色申告では割合が50%未満については経費計上が認められておらず、事業分の費用が全体の半分に満たない場合は原則として計上不可です。
ただし、事業分として利用していると明確に証明できる場合は50%未満でも計上可能なので、その根拠を明確にしましょう。
(参考:〔家事関連費(第1号関係)〕|国税庁)
▼ 経費の条件について詳しく知りたい方はこちら。

赤字を3年間繰り越し可能
青色申告を行うと、赤字を3年間繰越・繰戻が可能です。
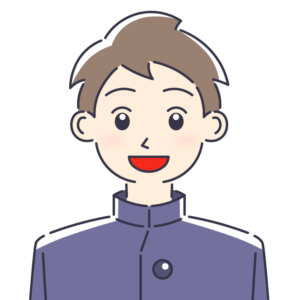
例えば2022年の年間総所得が250万円の赤字だったとしたら、翌年2023年を100万円の黒字で終えた場合、前年に出た250万円分の赤字と相殺して年間総所得額を0円にできるってことですか?

そうですよ!
さらに2024年を200万円の黒字で終えたと仮定します。2022年に出した赤字250万円のうち、150万円分がまだ残ったままの状態です。これを2023年の200万円と相殺することで年間総所得額を50万円と計上できます。
繰戻も同様であり、2022年に出した赤字250万円をその前の年の黒字と相殺すれば、2021年分として納税した所得税を還付金として受取可能です。
これは青色申告のみに与えられた特例制度であり、白色申告では繰越・繰戻のいずれも認められていません。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは、主に以下の2つです。
2.複式簿記の記帳が必須
それぞれのデメリットを確認していきましょう。
必要書類が多く、手間がかかる
青色申告のデメリットとして、必要書類と手間の多さがあげられます。
青色申告は誰でも可能な申告方法ではなく、適用を受けるためには事前に「所得税の青色申告承認申請書」に必要事項を記入して税務署に提出しておかなければなりません。また、申請書の提出期限も以下のように定められています。
|
対象
|
提出期限
|
| 新規事業 | 開業から2カ月以内 |
| 白色申告からの変更 | 対象年の3月15日まで |
また確定申告時の提出書類も白色申告は2種類に対して、青色申告は4種類必要です。申告時に作成しなければならない書類が多い点も、青色申告のデメリットと感じる人がいるでしょう。
65、55万円の特別控除は複式簿記での記帳が必要
複式簿記での記帳が原則な点も、青色申告のデメリットとしてあげられます。
特に青色申告特別控除のなかでも55万円・65万円の適用を受ける場合、複式簿記での記帳が必須条件です。
複式簿記とは借方・貸方にわけて記帳する方法であり、簿記・経理の知識がない場合には困難に感じるかもしれません。また、複式簿記の借方・貸方は合計数が一致していなければならず、日頃の会計処理でミスがあると合計が一致しないためにその原因を究明して解消する必要も出てきます。
青色申告をおススメしたい人の条件
青色申告をおすすめする人の主な条件は以下の通りです。
・事業・副業を考えている人
・白色申告者
それぞれの条件・理由について解説するので参考にしてください。
節税したい人
所得税等の節税をしたい人は、青色申告がおすすめです。
青色申告には、青色申告特別控除・青色事業専従者給与など節税対策として活用できる特例制度が多く設けられています。これらを上手に活用することで白色申告よりも年間所得額が抑えられ、所得税の納税額も低くなるでしょう。
事業、副業を始めることを考えている人
事業を始めたいと考えている人も、青色申告をおすすめします。その理由は赤字の繰越・繰戻が可能だからです。
事業活動を始めても、すぐに一定の所得が得られるとは限りません。またスタート時は必要経費がかさみ、支出が年間総所得額を上回ることもあるでしょう。
このようなケースで赤字決算になった場合、翌年を起算日として3年は繰越が可能です。翌年の年間総所得額が黒字だった場合、前年の赤字と相殺すれば所得税の納税額が発生しないケースもあります。
青色申告は複式簿記での記帳が必要ですが、会計ソフトなどを利用すれば簿記・経理の知識がなくてもソフトが自動で振り分けてくれるので迷うことは少ないでしょう。
白色申告で事業を行っている人
白色申告者も、青色申告への切り替えをおすすめします。その理由は2014年から白色申告も帳簿作成が必須に変更されたからです。
以前は白色申告者に限り、帳簿の作成は必要ありませんでした。そのため日頃の会計処理は必要なく、経理・会計処理を面倒に感じる人にとってはメリットのある申告方法だったといえます。
青色申告に必要な申請書
青色申告承認申請書とは、該当する所得を得る事業を展開している申告者が青色申告での確定申告を希望する場合に必要な書類であり、正式名称を「所得税の青色申告承認申請書」といいます。
原則として新規事業の場合は事業開始日を起算日として2カ月以内、白色申告から変更する場合には対象年の3月15日までに税務署に提出しなければなりません。ただし、期限内に提出しなかったからといって何らかの罰則が課せられるわけではなく、白色申告に分類されるだけです。
青色申告で確定申告する際の必要書類
青色申告で確定申告をする際に必要な書類は主に以下の通りです。
2. 所得税青色申告決算書
そのほか提出の必要はありませんが、申告書作成時に必要な書類・その保管方法などもあわせて確認していきましょう。
確定申告書
確定申告書は第一表・第二表の2種類があり、いずれも必要事項に金額を記入して提出しなければなりません。
第一表の記入内容は主に年間の総収入額・年間所得額とあわせて、適用可能な控除制度の金額などです。最終的な納税額または還付金額も第一表で計算・記入するので、確定申告書のメインの書類であると認識しておいたほうがよいでしょう。
第二表では所得・生命保険等の内訳を明記し、最終的な合計額を第一表の該当欄に転記します。配偶者や親族に関連した控除制度の適用を受ける際には、氏名・個人番号なども記入しなければなりません。対象者のマイナンバー(個人番号)をあらかじめ調べておきましょう。
確定申告表参考:確定申告表|国税庁
所得税青色申告決算書
所得税青色申告決算書は、「一般用」「農業所得用」「不動産所得用」「現金主義用」の4種類です。事業活動によって対象の決算書を入手し、必要事項に記入します。なお医師及び歯科医師の場合は「一般用」とあわせて「付表」も作成・提出しなければなりません。
決算書は主に年間の売上高、経費の内訳などを記入します。売上・収入については月別に記入する欄も設けられているので、毎月の金額を明記しましょう。
全部で8枚ありますが、青色申告特別控除のなかでも10万円の適用を受ける場合は8枚目の「貸借対照表」は不要です。55万円・65万円の控除適用を受ける際には8枚すべてに必要事項・金額等を記入して提出してください。
所得税青色申告決算書青色申告する際に保管するべき書類
青色申告をする際にはさまざまな帳簿・書類が必要ですが、これらの保存期間は国税庁によって以下のように定められています。
|
種類
|
例
|
保存期間
|
|
| 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
| 書類 | 決算関係 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
| 現金預金取引等関係 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(前々年分の所得額が300万円以下の場合は5年) | |
| その他 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 | |
(出典:記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁)
最短でも5年の保管が必要な関連書類ですが、期間終了前に誤って廃棄してしまうと税務調査が入ったときに提出できません。保存期間前に廃棄した場合、会社法第976条に基づき、100万円以下の過料に処される可能性があります。
書類の種類・保存期間を正しく認識し、適切に保管しましょう。
青色申告(確定申告)の提出方法
青色申告の主な提出方法は、以下の3通りです。
・郵送
・e-Tax
それぞれの特徴・具体的な方法について確認していきましょう。
手渡しで提出
手渡しは確定申告書類を提出する際の最もポピュラーな方法といえます。管轄の税務署に直接提出書類を持参する方法であり、提出時には書類の過不足がないかのチェックもしてもらえるので便利です。
具体的な中身の確認までは行いませんが、申告書類・身分証明書のコピーなどの過不足をその場でチェックしてもらえるので、初めて確定申告を行う際にはありがたいと感じる人もいるでしょう。
税務署職員への直接手渡しは税務署の開庁時間に限られますが、それ以外の時間帯は回収ポストが設置されます。提出時の過不足チェックは受けられませんが、ポストに投函すれば開庁日時に左右されることはありません。
郵送で提出
郵送での提出も可能です。郵送する場合は、管轄する税務署の住所宛てに送付しましょう。
郵送分については当日消印まで有効であるため、回収時間によっては法定期限最終日にポストに投函しても期限内提出が認められる可能性があります。
郵送で青色申告書類を提出する際は、早めに書類を作成して投函しましょう。
e-Taxで申告
e-Taxでの申告も可能です。
e-Taxの場合、法定期限最終日の23時59分までに必要書類を作成して送信すれば期限内提出として認められます。また、手渡しのように税務署の開庁日時に左右されることもなく、好きな場所・タイミングで作成・送信が可能です。
e-Taxを利用した作成・提出については次の項目で解説するので、合わせて参考にしてください。
e-Taxで青色申告(確定申告)を申請するメリット
e-Taxで青色申告を行う主なメリットは以下の通りです。
・好きな場所で作成・申請が可能
・期限内の修正が容易

e-Taxはパソコン・スマホなどさまざまなデバイスでの利用が可能であることから、好きな場所・時間に申告書類の作成・申請が可能です。提出も税務署の開庁日時に関係なくできることから、夜中に作成〜提出まで一気に片付けるといったこともできます。
また一度提出した申告書に誤りがあった場合、期限内なら修正・上書き保存が可能であり、紙媒体のように新規作成する必要はありません。
以下の項目でe-Taxを利用する際の準備・手順などを確認していきましょう。
e-Taxで青色申告(確定申告)する際の準備
e-Taxで青色申告をする際には、利用者識別番号を取得しなければなりません。主な取得方法は以下の7通りです。
2.「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から利用者識別番号を取得
3.マイナポータルの「外部サイトとの連携」機能からe-Taxを利用
4.「確定申告書等作成コーナー」からマイナーバーカードを使ってID・パスワード方式の届出を作成・送信
5.税務署にてID・パスワード方式の戸溶けでを作成・送信
6.国税庁から「電子申告・納税等開始(変更等)の届出」を入手・作成し、税務署に送付・持参
7.税理士に依頼
(出典:ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス))
1〜4の方法で利用者識別番号を取得する場合はマイナンバーカード・ICカードリーダライタ・マイナンバーカードの読み取りに対応したデバイス・推奨環境を満たしたPCなども合わせて準備しなければなりません。
一方、5または6の方法で取得する場合は必要書類・本人確認書類などを用意するだけです。
ICカードリーダライタ・読み取りに対応したデバイスなどの準備が難しい場合は、税務署での手続きをしたほうがよいでしょう。
e-Taxで電子申告する3種類の手順
e-Taxで確定申告の電子申告をする方法は以下の3パターンです。
・Web版
・スマホアプリ
それぞれの手順を確認していきましょう。
インストール版で電子申告
国税庁ではインストール版のe-Taxソフトを提供しており、青色申告に必要な書類の作成・申告が可能です。
「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」からソフトのダウンロードができますが、単純にe-Taxソフトをダウンロードしただけでは利用できません。
2.利用環境の確認
3.ルート証明書等のインストール(「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」からダウンロード可能)
4.「信頼済みサイト登録ツール」のダウンロードおよびポップアップブロックの許可サイト編登録(「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」からダウンロード可能)
5.e-Taxソフトのダウンロード
6.税目プログラムのインストール
(出典:e-Taxソフトのダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス))
e-Taxソフトをダウンロード・使用するために必要なシステム・マニュアル等はすべて同サイトに用意されておりダウンロードできるようになっています。
「2.利用環境の確認」についてはソフトのバージョンアップに伴い更新される可能性があるので、ダウンロードする際には必ず推奨環境を確認してください。
Web版で電子申告
e-Taxには前述したダウンロード版以外に、Web版も用意されています。こちらは事前に「確定申告書等作成コーナー」で必要書類を作成し、e-TaxのWeb版に連携させて送信させる方法です。
国税庁では所得税の確定申告について、e-Taxのインストール版よりも「確定申告書等作成コーナー」を利用したWeb版の利用を推奨しています。

その理由はWeb版のほうが自動計算などの機能が搭載されているからです。自分で計算する必要がないことから作成指示のケアレスミスの軽減にも役立ちます。
・「税務署への提出方法」にて「マイナーバーカードあり」を選択
・「認証方法」にて「スマートフォン」「ICカードリーダライタ」「e-Tax(ID・パスワード方式)」のいずれかを選択
・「作成する申告書等の選択」にて「決算書・収支内訳書(+所得税)」にアクセスし、画面案内に沿って作成・保存
・「作成する申告書等の選択」にて「所得税」にアクセスし、画面案内に沿って作成・保存
・e-Taxで税務署に送信
申告書類の作成は途中保存が可能であり、「確定申告書等作成コーナー」のトップ画面から「保存データを利用して作成」を選択すれば申告書類の作成再開が可能です。
スマホアプリで電子申告
2019年からスマートフォンでも青色申告の電子申告が可能になりました。ただし顔写真入りのマイナンバーカードとマイナポータルアプリのダウンロードが必要です。
確定申告に必要な申請書等の書類作成は、「確定申告書等作成コーナー」で行います。このサイトはPC以外のデバイスからアクセスすると、それに合わせて画面が最適化されるのでスマホでも作成がしやすいでしょう。
作成後、マイナポータルと連携させることでe-Taxでの電子申告が可能です。
よくある質問
よくある質問とその回答を紹介します。
確定申告の期限は?
確定申告の法定期限は原則として2月16日〜3月15日までの1カ月間です。
ただし初日・最終日が土日と重なる場合は、翌平日に延長されます。例えば2月16日が土曜日だった場合、確定申告の法定申告期限初日は2月18日の月曜日に延長されるので注意してください。
記帳はどのようすればいい?
青色申告の記帳は原則として複式簿記です。
ただし青色申告特別控除のなかで10万円の適用を受ける際は、単式簿記での記帳が認められています。
55万円・65万円の控除適用を受ける際には複式簿記が必要条件として定められているので、借方・貸方にわけた方法で記帳しましょう。
まとめ
青色申告について解説しました。
青色申告は白色申告と比較してメリットが多い確定申告の方法です。記帳方法は原則として複式簿記ですが、10万円控除は単式簿記が認められており白色申告と同様の記帳方法でも控除が適用されます。
そのほかにもさまざまな点でメリットが多いことから、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかに該当する場合は事前に税務署に申告書を提出して青色申告を行ったほうがよいでしょう。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。