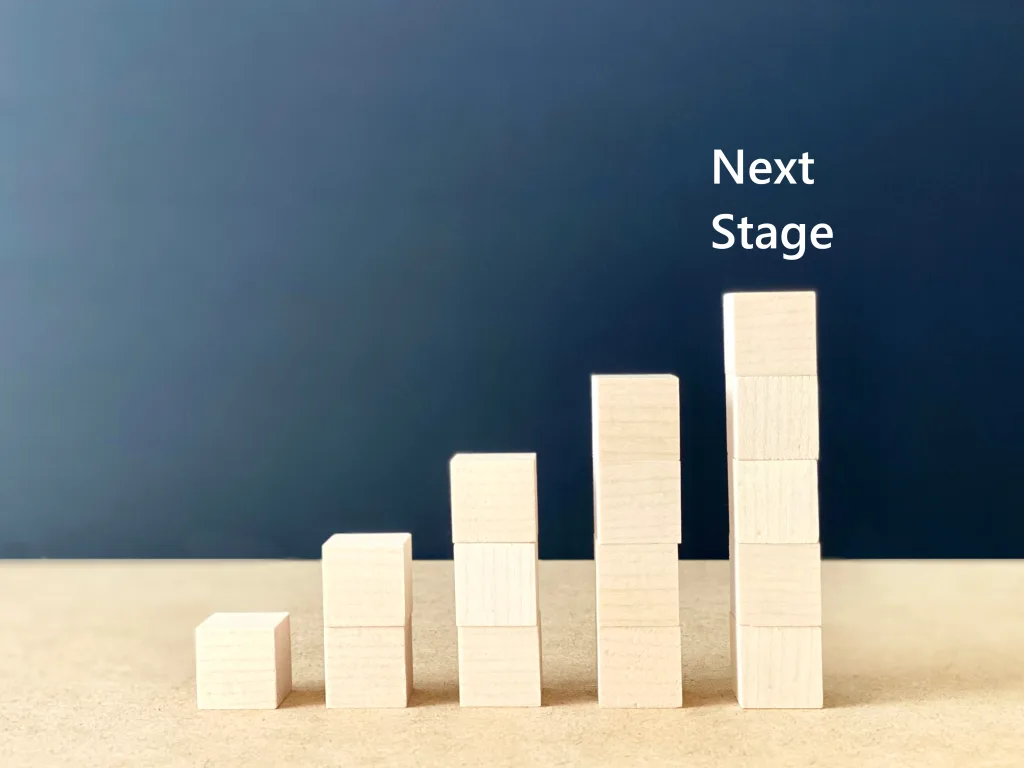副業で本業以外の収入を得ると、気になるのが税金や確定申告についてですよね。
たとえば、「会社員が副業する場合、いくらまでなら確定申告は不要なの?」という疑問をお持ちの方は多いでしょう。
その他に、「住民の申告はいくらから?」「扶養内で副業できるのはいくらまで?」「消費税の申告が必要になる条件は?」など、副業をするうえでの制約についてご存知でしょうか?
▼ 副業について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
副業で20万円超稼いでいる人は確定申告が必要
まずは副業の収入について、確定申告が必要になる金額の条件を見ていきましょう。
給与所得者は勤務先で年末調整を行いますので通常は確定申告は不要です。ただし、副業で年間20万円超稼いでいる人は確定申告が必要となります。
この「年間20万円超」には、以下の3つのパターンがあります。
2. 副業がパート・アルバイト以外の場合、副業の年間所得が20万円超
3. 複数の副業をしている場合、それぞれの所得を合計して20万円超
副業がパート・アルバイトの場合は、副業の勤務先から支給される給与が年間20万円を超えると確定申告が必要です。たとえば、土日だけのアルバイトをして毎月2万円ずつ稼いだ場合、給与は年間で24万円となりますので、確定申告が必要です。
副業がパートやアルバイト以外の場合とは、副業で事業所得を得たり、不動産や株式の投資をしたりするケースです。この場合は、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
また、複数の副業をしている場合は、それぞれの副業の所得を合計して20万円を超えると確定申告が必要です。たとえば、プログラミングの副業で年間所得が15万円、YouTubeの動画配信で年間所得が10万円の場合は、副業の所得額が25万円となるため確定申告が必要です。
収入と所得の違いって?
たとえば、本業の年収が500万円の人がハンドメイドアクセサリーを販売する副業をして30万円の収入を得た場合、ビーズなどの材料費が5万円かかったなら、所得は25万円です。このケースでは所得が20万円を超えるため確定申告が必要です。
本業と副業の収入が150万円以下で確定申告不要!
上記で、パートやアルバイトの副業の場合、副業の給与支給額が年間20万円を超えると確定申告が必要とお伝えしました。しかし、これには例外があり、以下の2つの条件を両方とも満たす場合は確定申告は不要となります。
・本業と副業の合計の給与収入から各種控除を引いて残った金額が150万円以下である
たとえば、本業の年収が120万円で、アルバイトの副業を行い年収30万円、各種控除の控除額が10万円の場合は、年間150万円以下の条件を満たします。アルバイトの給与からも税金が源泉徴収されている場合は確定申告は不要となります。
副業で20万円超稼いでいない人も確定申告でお得になる!
副業の所得が20万円を超えなかった人は確定申告をする必要はありません。
しかし、自身の判断で確定申告をすることで税金が安くなるケースもあります。
以下でどのような場合に確定申告で税金がお得になるのか解説します。
医療費控除など確定申告でのみ適用できる控除をうける
医療費控除のように確定申告でしか申告できない所得控除もあります。このような控除の適用条件を満たすときは、確定申告が不要の場合でも自身の判断で申告を行うことで税金が安くなります。
確定申告でのみ適用できる控除は以下の3種類があります。
・雑損控除
・寄付金控除
入院費用や家族の医療費、医薬品の購入費用も算入できますので、医療費の支払いが多かった年は控除の対象となるか確認してみるようにしましょう。
副業の所得が年間20万円を超えなかった年でも、上記の控除の条件を満たすときは、確定申告を行えば税金を安くすることができます。
パートやアルバイト先で源泉徴収されている
パートやアルバイトの副業をしている人は、複数の勤務先から給与を受け取っていることになります。この場合、年末調整をしていないパートやアルバイトの給与所得が年間20万円を超えると確定申告が義務となります。
一方で、副業の給与所得が年間20万円以下の場合は確定申告は義務ではなくなります。しかしこの場合でも確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
なぜなら、、、パートやアルバイトの勤務先では年末調整が行われないため、給与から天引きされた所得税に本来は適用できる所得控除が反映されていないからです。

本業と副業の両方の収入と源泉徴収額をもとに確定申告書を作成し、適用できる所得控除をすべて申告することで、払いすぎた税金が還付金として戻ってくる可能性があるってことだね!
副業が事業所得で青色申告している
事業所得に分類される副業をしている人で、青色申告を選択している場合は、確定申告を行うことで青色申告特別控除を受けられます。
青色申告の条件として、日々の取引の記帳を複式簿記で行い、詳細な帳簿を作成して申告する必要があります。
青色申告特別控除の控除額は最大65万円となり、控除額が大きいため確定申告を行うことで事業所得に課税される所得税や住民税を安くすることができます。
青色申告と白色申告の違いって?
確定申告での事業所得や不動産所得などの申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。それぞれ特徴やメリット、デメリットがあり、自分に合った方法を選択することができます。
青色申告では税務署での事前申請と複式簿記での帳簿作成を行うことで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。たとえば、副業の所得が年間100万円だった場合、青色申告特別控除を適用すると課税所得が35万円となりますので、大きな節税効果があります。
青色申告のその他のメリットとして、事業で赤字が出たときに翌年度以降に赤字を繰り越せることや、家族に給与を支払ったときにその給与を経費に計上できることがあります。青色申告は節税効果が高いため長期的に事業所得が発生する人におすすめです。
白色申告は、簡易的な帳簿で申告可能な方法です。簿記の専門知識が必要なく、事前に承認申請書を提出する必要もないため、初めて確定申告をする人におすすめです。ただし、青色申告特別控除や赤字の繰越などの制度は利用できません。
▼ 青色申告について詳しく知りたい方は↓
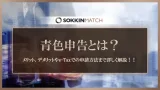
▼ 白色申告について詳しく知りたい方は↓

副業が事業所得で赤字になっている
事業所得に分類される副業を行っているときに、副業が赤字になっているときは確定申告をすることで節税が可能となります。副業の赤字を本業の所得と損益通算することで課税所得を減らすことができるからです。
たとえば、本業の所得が300万円のときに、副業で50万円の赤字となった場合は、「300万円 – 50万円 = 250万円」の計算により課税所得額が250万円となります。50万円減少した課税所得に税率を掛けて所得税額を計算するため税金が安くなります。
ただし、損益通算ができるのは事業所得に分類される副業です。雑所得に分類される副業では損益通算はできませんので注意が必要です。
住民税は副業で1円でも稼いでいる人は申告が必要
副業の所得が年間20万円以下となった年は確定申告の義務はなくなります。しかし、この場合でも住民税の申告は必要になりますので注意しましょう。
確定申告を行う場合は、税務署に申告した所得や所得控除の申告内容が自治体に連携されますので、個別に住民税の申告を行う必要はありません。しかし、確定申告を行わない場合は住民税が未申告のままになってしまうため、自治体で副業の所得を申告する必要があります。
手続き方法は、住民税申告書と本人確認書類、控除のための証明書などを準備して、住んでいる自治体の窓口で手続きを行う流れが一般的です。具体的な詳細は自治体によって異なる場合がありますので、ホームページなどで確認を行いましょう。

住民税の申告期限は確定申告と同じ3月15日までだよ!
扶養内で稼ぐならいくらまでOK?
ここからは、扶養内で稼ぐ際の金額条件について解説します。
扶養控除を適用するには所得の条件がありますので、扶養対象の親族の収入が一定を超えると扶養控除を受けることができなくなります。
また、納税者の配偶者(妻または夫)は配偶者控除または配偶者特別控除の対象となります。こちらも同様に所得の条件がありますので、控除の適用を受けたいときは配偶者の所得額に注意する必要があります。
以下で扶養内で稼げるのは具体的にいくらまでなのか解説します。
93万円の壁(住民税の壁)
住民税には、所得額に応じて課税される所得割と、所得にかかわらず一定額が課税される均等割があります。
このうち所得割については、給与収入が年間100万円を超えると課税されます。住民税は基礎控除額が45万円となり、給与所得控除の55万円との合計額は100万円となります。そのため、給与収入が100万円以下の場合は、基礎控除と給与所得控除の両方を適用すると課税所得が0円となり、住民税所得割が非課税となります。
住民税均等割については、93万円〜100万円の範囲で地域により非課税となる金額の基準が変わります。100万円以下で非課税となる場合が多いですが、具体的な金額は自治体のホームページなどで確認しましょう。
103万円の壁(所得税の壁)
この103万円の壁という制約は、扶養控除にも当てはまります。扶養控除の適用条件として、控除対象扶養親族の年間所得は48万円以下というルールになっています。
所得が48万円を超えてしまうと扶養控除の条件を満たさなくなり、控除を受けられなくなるため注意が必要です。扶養内で稼ぎたいときは、年間の所得が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)になるようにすれば、所得税が課税されず、扶養控除の適用を受けることができます。
106万円の壁(社会保険の壁)
一方で、収入が106万円を超えると、配偶者や親などの扶養から外れることになり、自分で何らかの社会保険に加入する必要があります。勤務先で社会保険に加入するか、または国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を自分で支払うことになります。
130万円の壁(社会保険の壁)
年間の収入が130万円を超えると、勤務先が従業員100人以下の企業であっても社会保険の対象となり、配偶者や親などの扶養から外れます。
自分で社会保険に加入する必要があるため、勤務先の給与から保険料が天引きされ、手取り額が減少することになります。
150万円の壁(配偶者特別控除の壁)
配偶者特別控除の控除額は配偶者の所得によって決まります。満額の控除を受けたいときは配偶者の給与収入は年間150万円以下にする必要があります。このラインを超えると配偶者特別控除の控除額が徐々に減少するため注意が必要です。
201.6万円の壁(配偶者特別控除の壁)
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得が増えるごとに減少していきます。最終的に、配偶者の年間の給与収入が201.6万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となります。
共働きとして配偶者の収入も増やしながら、配偶者特別控除も受けたい場合は、配偶者の収入は最大でも201.6万円以内におさえるようにしましょう。
副業でも消費税の申告が必要になる可能性も
インボイス制度が始まったことにより副業でも消費税の申告が必要になる可能性もあります。
個人の副業で消費税の申告が必要になるケースとしては、以下の2つがあります。
・適格請求書発行事業者として登録した場合
消費税の課税事業者になるのは売上1,000万円を超えた場合なので、副業の収入で消費税の申告が必要になるケースはあまりないでしょう。
しかし、インボイス事業者として登録を行った場合は、売上高に関係なく消費税の申告が必要です。よくあるケースとして、フリーランスとして副業案件を受注するときなどに、取引先から適格請求書の発行を求められることがあります。このような場合は、副業の収入が少額であっても消費税の申告と納税が必要となりますので注意しましょう。
確定申告の流れ
副業の所得が年間20万円を超えると、確定申告をする必要があります。
確定申告の手続きはどのように行えばよいのか、以下で具体的に解説します。
期間は毎年2月16日~3月15日
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までと定められています。この期間で税務署に確定申告書を提出し、所得税の納税も期限内にすませる必要があります。
ただし、例外として申告期限日が土曜日、日曜日、祝日になる場合は、その翌平日が期限日となります。

確定申告は期限に遅れないように行う必要がありますが、早すぎても手続きができないため、2月16日〜3月15日までの期間内で行いましょう!
1.帳簿の記帳
パートやアルバイト以外の副業をしている場合は、普段から収入や経費を記帳して帳簿を作成しておく必要があります。
帳簿をもとに副業の年間収入と経費の総額を計算し、副業の所得額を算出します。
確定申告の際に帳簿を税務署に提出する必要はありませんが、いつでも確認できるように保存しておく必要があります。経費の支払いを証明できるレシートなどもあわせて保存しておくようにしましょう。
2.必要書類を準備
次に、確定申告に必要な書類を準備しましょう。
所得の種類や申告する控除によっても変わりますが、以下の書類は必ず準備する必要があります。
・マイナンバーが分かるもの
・本人確認書類
上記に加えて、給与所得者は源泉徴収票や、所得控除を受けるための控除証明書も必要です。
個人事業やフリーランスは、収入や経費を記録した取引内容が記載された帳簿を準備します。青色申告を行う場合は貸借対照表や損益計算書を、白色申告では収支内訳書を準備する必要があります。
また、確定申告により税金の還付を受ける場合は、還付金の振込口座が分かる通帳なども準備しておきましょう。
3.確定申告書の作成
必要書類が準備できたら、源泉徴収票や帳簿に記録された金額をもとにして確定申告書を作成します。
申告書の作成は、大きく分けてパソコンを使う方法と紙の申告書に手書きで記入する方法の2通りがあります。
パソコンで作成すれば金額計算が自動で行われ、ミスがあった場合もすぐに訂正できるため便利です。パソコンでの申告書作成は、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用したり、確定申告ソフトやクラウド会計ソフトを使う方法があります。
4.確定申告書の提出
確定申告書を作成できたら、必要書類とともに税務署に提出し、納税額がある場合は期限内に納付すれば手続き完了です。
提出方法は以下の3つがあります。
・紙の申告書を郵送
・紙の申告書を税務署に持ち込む
紙の申告書を提出する場合、提出先は住んでいる場所を管轄する税務署となります。
e-Taxはパソコンで作成した申告書の電子データをインターネットで送信できますが、事前に利用者登録が必要です。

確定申告をしないとどうなる?
副業の所得が年間20万円を超えているのに確定申告をしなかった場合、本来納めるべき税金を納税していないことになります。
そのまま確定申告をしないままでいるとどうなるのかを以下で詳しく解説します
無申告加算税が課税される
確定申告が必要な人が期限内に申告を行わなかった場合、納めるべき所得税も納付していないことになります。この場合は無申告加算税が課税され、本来よりも高い税金を払うことになります。
無申告加算税の税率は、本来納める所得税の税額が50万円までの場合は15%、50万円超〜300万円までの部分は20%、300万円超の部分は30%です。所得税の税額が大きいほど無申告加算税の税額も大きくなります。
また、期限に遅れた後に、どのタイミングで申告と納税をするかによっても税率が変化します。申告期限が過ぎた後に税務署が調査を開始する前に自主的に申告した場合は、無申告加算税の税率が5%になります。また、税務署から調査の通知が届いてから実際に調査が始まる前に自主的に申告すると、税率が5%軽減されます。
延滞税が課税される
また、所得税の本来の納期限より遅れて納税すると延滞税も加算されます。延滞税は納付期限の翌日から実際に支払った日までの日数に応じて計算されます。
延滞税の原則の税率は、納期限から2ヶ月以内の期間は年7.3%、2ヶ月超の期間では年14.6%です。ただし、年度によって特例の税率が適用されることがあるため、実際の税率は国税庁のホームページなどで確認する必要があります。
所得税の納期限は通常は3月15日です。この納期限からの経過日数が大きくなるほど延滞税の税額も大きくなりますので注意が必要です。納期限から2ヶ月を経過すると延滞税の税率が大幅に上がりますので、万が一遅れたとしてもできるだけ早く納税することが大切です。
▼ もっと詳しく知りたい方は↓
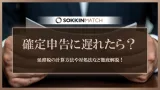
控除が受けられない
確定申告をしないと、本来受けられるはずの控除を適用できなくなるというデメリットもあります。
たとえば、医療費控除や寄付金控除、雑損控除、住宅ローン控除の初年度の手続きは年末調整では申告できず、確定申告をしなければ控除を受けることができません。控除を適用して税金が安くなる条件を満たしていても、確定申告をしないと税額を減らすことができないため注意が必要です。
人気のふるさと納税も所得税と住民税から控除を受けることができますが、確定申告で寄付金控除の申請が必要です。サラリーマン向けに「ふるさと納税のワンストップ特例制度」という仕組みがありますが、この特例に申し込んでいない人は確定申告をして寄付金控除の申請をする必要があります。
副業は1円でも稼ぐとバレる可能性がある!
勤務先の会社に副業のことを知られたくないという人もいるかもしれません。社内で副業のことを誰にも話さないよう気をつけていても、税金や社会保険料の変化でバレる可能性があるため注意が必要です。
隠している副業がバレる原因として多いのが、住民税や社会保険料の源泉徴収額の変化です。すでにお伝えしたように、副業で所得が発生すると、年間20万円を超える場合は確定申告が必要となり、年間20万円以下の場合でも住民税の申告が必要です。副業で所得が1円でも発生すると住民税や社会保険料が増えるため、勤務先の会社に通知が行くことでバレる可能性があります。
副業がバレるケースって?
住民税や社会保険以外にも副業がバレる原因は様々あります。
たとえば、副業の案件を獲得するためにSNSでやり取りしたり、ポートフォリオや成果物について情報発信しているのを会社の人に見られてバレる場合があります。SNSを利用するときは本人が特定できないようニックネームを使うなどするとよいでしょう。
会社の飲み会や喫煙所などの会話でうっかり副業のことを話してしまい、社内で噂になってバレてしまうというケースも考えられます。
その他に、飲食店やイベントスタッフなどのパートやアルバイトをしているところを同僚など勤務先の人物に偶然見られてしまうということもあるでしょう。
副業のことをできる限り知られたくないときは、勤務先で副業のことは話さないようにして、可能な限り在宅でできる副業を行うとバレにくくなります。
まとめ
この記事では、副業で確定申告が必要になる金額の条件や、住民税の申告、扶養内で稼げる金額などを詳しく解説しました。
年間を通して副業をすると、確定申告が必要となり、所得税や住民税の金額が増える可能性が高いです。事前に税金の仕組みや確定申告の手続き方法を知っておくとスムーズに副業ができるでしょう。
会社員の場合は、副業の所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。住民税については、副業で1円でも収入があると申告が必要となりますので注意しましょう。
なお、副業が勤務先にばれる原因として住民税の税額の変化があります。住民税の納税方法を普通徴収にすることでばれにくくなる場合があります。
扶養内で働きたいときは、年間の所得を48万円以内におさえる必要があります。アルバイトなど給与収入の場合は年間103万円以内が扶養内で稼げる範囲となります。
副業で個人事業を行う場合年間の売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の申告も行う必要があります。また、インボイス登録をした場合は売上高に関係なく消費税の申告が必要となりますので注意しましょう。
ぜひこの記事でまとめたことを参考にしていただき、自分に合った最適な副業を見つけてください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。