年末調整は1年間で源泉徴収された税金の過不足を調整する重要な手続きで、給与をもらっている会社員やアルバイトなどが対象者となります。
年末調整の手続きはいつ行い、いつの収入が対象なのかといった疑問も出てくると思います。書類の提出忘れや不備などで、いつまでなら修正できるか知りたいという人もいらっしゃるでしょう。

そこでこの記事では、年末調整のスケジュールや手続き方法、遅れてしまったときの対処方法などを解説します。年末調整によって還付金が受け取れるケースについても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
年末調整とは
年末調整とは、会社員やアルバイトなどの給与所得者が所得税を納税するための手続きです。
給与所得者は年間を通じて受け取っている給料から所得税が源泉徴収されています。勤務先の会社が給与から天引きして代わりに納税してくれますので、確定申告をしなくても所得税を納税することができます。
年末調整は給与から源泉徴収された税額の過不足を調整して正確な金額を計算するための手続きです。具体的には、所得控除を申告するための書類に記入して勤務先に提出することになります。

所得控除とは、親族や配偶者を扶養していたり、医療費の支払いが多かった人など、一定の条件を満たす人の税負担を軽減するための節税制度のことです。
年末調整はその名称のとおり毎年11月〜12月ごろの年末の時期に行われます。これは、納税者の所得額や申請できる所得控除などの詳細が、年末になってからでないと正確に判明しないからです。ただし、年の途中に退職する場合など、年末以外の時期に年末調整が行われることもあります。
年末調整は1月1日から12月31日までの収入が対象!
年末調整の対象となる収入は、その年の1月1日から12月31日までの期間に受け取る給料などの収入です。
年末調整を行う時点ではまだ12月分の給与が支給されていない場合が多いですが、最終的な金額の微調整が必要な場合は勤務先の会社が行います。
立場に応じた年末調整の対応方法
それでは実際に年末調整の手続きはどのように行うのか具体的に見ていきましょう。
会社側と従業員側、それぞれの立場での対応方法を解説します。
【年末調整】会社の対応
会社側が行う年末調整の手続きは、11月頃〜翌年1月31日までの時期に行われます。
手続きの流れをまとめると以下のようになります。
2.申告書の配布と回収
3.所得税を算出する
4.従業員に源泉徴収票を発行する
5.税務署に申告書類を提出する
以下でそれぞれの手順を具体的に解説します。
手順1 源泉徴収票の回収
従業員が年の途中で入社した場合で、今年のうちに別の会社で給与を受け取っている場合は、その会社が発行した源泉徴収票が必要です。源泉徴収票が必要になるケースとしては、他社から転職してきた従業員や、入社前にアルバイトをしていた場合などが考えられます。
源泉徴収票には従業員が前職で得た1年間の収入や源泉徴収税額などが記載されています。提出された源泉徴収票と年末調整の申告書類の両方をもとにして所得税の計算を行います。
手順2 申告書の配布・回収
次に、従業員に年末調整の申告書類を配布し、記入が終わったものを回収します。
年末調整で必要な書類は以下の4種類です。
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書
時期としては11月ごろに配布するのが一般的です。

最近では年末調整手続きをペーパーレス化する企業が増えており、パソコンやスマホで必要事項を入力し、申告書をデータとして回収するケースが多くなっています。
手順3 所得税を算出
回収した年末調整書類と、1年間で支給した給与や源泉徴収した税額をもとに所得税を算出します。

所得税の計算は以下の手順で行います。
2.給与所得 – 所得控除 = 課税所得
3.課税所得 × 税率 = 所得税額
4.所得税額 – 税額控除 = 所得税額
まず、支給した年間の給与や賞与などの合計金額から給与所得控除を差し引くと給与所得額が求められます。年末調整書類にその他の所得の記入があれば合算して所得額を求めることができます。
次に、年末調整書類で申告された所得控除を適用し、課税所得額を求めます。申告書類には従業員が計算した控除額などが記入されていますので、間違いがないか確認を行う必要があります!
最後に、課税所得額が算出できれば所得税率を掛けて所得税額を求め、復興特別所得税額を加算します。税額控除があれば控除額を差し引くと、所得税額が求められます。
手順4 源泉徴収票の発行
上記の計算で算出した所得税額と源泉徴収税額の差額を計算し、精算を行います。その後、源泉徴収票を発行して従業員に渡します。
源泉徴収票の発行時期は12月から翌年1月ごろになるのが一般的です。
手順5 申告書類の提出
社内での手続きが完了したら、税務署や市区町村に申告書類の提出を行います。
提出する書類は以下の4種類です。
・給与支払報告書
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・法定調書合計表(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)
【年末調整】従業員の対応

年末調整の従業員の対応は11月頃〜12月頃のスケジュールで行われます。
全体的な手順は以下のようになります。
1.源泉徴収票を提出する(必要な場合のみ) 2.申告書類の記入と提出 3.源泉徴収票を受け取る
それぞれの手順の具体的な手続き内容を見ていきましょう。
手順1 源泉徴収票の提出
転職などで1年間の間に複数の会社で勤務している場合、前職の退職時に源泉徴収票を受け取っています。そこには前職での給与の支給額や源泉徴収税額が記載されています。
これらの金額は年末調整の計算で使いますので、年末時点で在籍している会社に前職の会社の源泉徴収票を提出する必要があります。
手順2 申告書の記入
次に、勤務先の担当者から書類提出の案内が来たら、所得控除の申告書類に記入して提出します。
上記の会社側の対応の解説で記載した通り、年末調整の申告書類は4種類あります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養控除の申告書と、寡婦控除、ひとり親控除、障害者控除などの申告書を兼ねています。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、基礎控除や配偶者控除(配偶者特別控除)所得金額調整控除の申告を行います。
「給与所得者の保険料控除申告書」は、社会保険料や生命保険料、地震保険料を支払った人が記入して提出します。
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」は、住宅ローン控除の2年目以降の申請を行う人のみが提出します。
手順3 源泉徴収票の受領
書類の提出後、12月から翌年1月ごろになると会社から源泉徴収票が発行されます。
源泉徴収票では、年間の給与の支給額や源泉徴収税額、適用された控除や控除額などを確認できます。
年間の給与の支給額は「支払金額」の欄に記載されています。毎月の基本給に加えて賞与や残業代、手当なども含まれています。
1年間で会社から天引きされた税額は「源泉徴収税額」の欄に記載されています。年末調整で差額が精算され、過不足の調整は12月分または1月分の給与の支給時に行われるのが一般的です。

源泉徴収票を受領すれば従業員の年末調整手続きは完了となります。源泉徴収票は自分で確定申告をするときに必要になるほか、クレジットカードの審査などで年収証明書類として使えます。紛失しないよう大切に保管しておきましょう!
必要であれば確定申告を行おう!
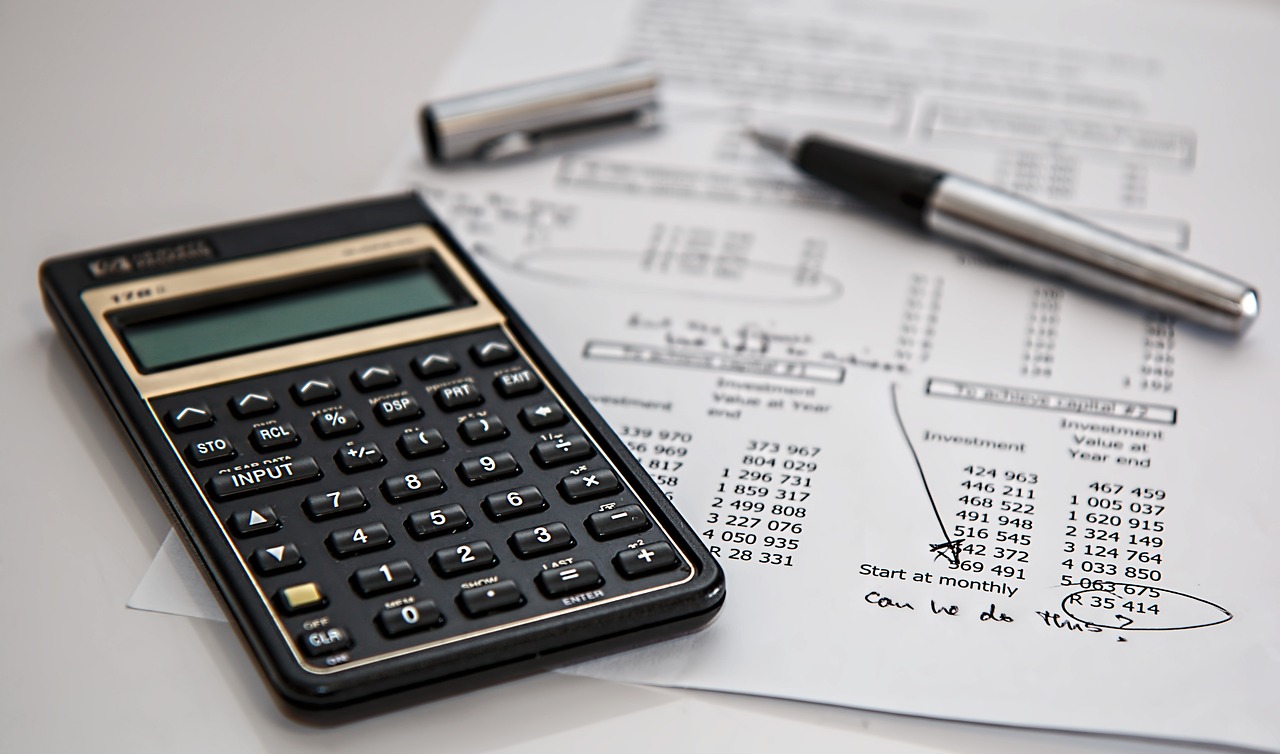
上記の手順で年末調整を行った場合でも、翌年に確定申告を行う必要があるケースもあります。
会社員が確定申告を行うケースには、年末調整とは別に確定申告をする義務がある場合と、確定申告をすることで税金がお得になる場合の2つのパターンがあります。
まず、年末調整とは別に確定申告をする義務があるのは以下のような人です。
・副業の所得が20万円を超えている人
・保険金など一時所得があった人
・アパート経営などで20万円を超える不動産所得がある人
・株などによる配当所得がある人
・ゴルフ会員権など譲渡所得がある人
・海外の口座で受け取った利子所得がある人
・退職などで年末調整を受けていない人
・転職前の収入を含めず年末調整を受けた人
・年末調整に誤りがあった人
基本的には、給与所得以外の所得が年間20万円を超えると、年末調整済でも確定申告が必要になります。また、勤務先の給与の年収が2,000万円を超える人も確定申告が必要です。
また、自身の判断で確定申告をすることで税金がお得になるのは以下のような人です。
・住宅ローン控除の初年度の申告をしたい人
・年末調整で申告できなかった控除がある人
・損益通算ができる状況にある人
・株やFXなどで損をした人
医療費控除のように年末調整では適用できない所得控除を受けるためには、確定申告が必要です。住宅ローン控除については、初年度のみ確定申告が必要です。
年末以外に行われる年末調整
通常は年末に行われる年末調整の手続きですが、様々な事情により年の途中で行われることもあります。
以下で年末以外の時期に年末調整が行われるケースについて解説します。
12月の給与等を受け取った後に退職した人
12月分の給与が支給された後に退職した人は、年末かどうかに関わらず、退職の時点で年末調整を受けます。
これは、すでに12月分の給与を受け取った場合は、仮に再就職したとしてもその年のうちに新しい給与を受け取る見込みがないからです。

年の途中で退職した場合は、別の会社に再就職して新たな給与を受け取る可能性があります。そのため、退職時点では源泉徴収票を受け取り、年末時点で在籍している会社で年末調整を受けることになります。
年の途中で退職し、給与の総額が103万円以下である人
年の途中で退職した場合であっても、その会社から受け取った給与の年間総額が103万円以下の場合は、退職時点で年末調整を行います。
これはパートタイマーや学生のアルバイト、単時間勤務の派遣社員などに当てはまるケースです。
心身の障害のために退職し、再就職の見通しがつかない人
退職の理由が心身の著しい障害のためで、その後年内の再就職の見通しがつかない人は、その会社を退職する時点で年末調整を受けます。
具体的な時期としては、最後の給料を受け取った時点で年末調整を行うことになっています。
死亡によって退職した人
納税者が死亡したことにより勤務先を退職した場合は、その年の死亡日までに支給された給与や賞与などの総額をもとに年末調整を行います。
ただし、死亡日以降に支給されることが決定されていた給与については、その人の所得ではなく、相続財産として扱われます。所得税の計算には含めないため、年末調整の計算から外れることになります。
海外勤務などの理由により非居住者となった人
海外勤務などの理由で非居住者となる人は、日本から海外へ行く前に年末調整を受ける必要があります。
所得税の計算においての「居住者」は、日本国内に住所を持っていて、1年以上日本に住んでる人のことを指します。この居住者の条件に当てはまる人以外は、日本人であっても「非居住者」となります。
海外に配属されて1年間以上外国に住む場合は非居住者になるため、海外に出発する日までに年末調整を受ける必要があります。
年末調整における各種申告書類の提出期限

ここからは、年末調整で提出する各種申告書類をいつまでに提出すればよいか、提出期限について見ていきましょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その年の最初の給与を受け取る前日までに勤務先に提出します。さらに、年末調整の時期に同じ書類に記入して提出することになります。
この書類では扶養控除の申告と、寡婦控除やひとり親控除、障害者控除、勤労学生控除の申告ができます。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
申告書類の名称の通り、基礎控除や配偶者控除、所得金額調整控除の申告をするための書類です。
基礎控除は全員が対象となりますので、この書類も必ず記入と提出が必要です。
基礎控除は所得額によって控除額が変わるため、勤務先の給与所得以外の所得の有無を記入します。
配偶者がいる人は配偶者の氏名や生年月日、配偶者の所得額を記入し、配偶者控除または配偶者特別控除の申告を行います。
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書では、社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除の申告ができます。さらに、iDeCoなどが対象となる小規模企業共済等掛金控除の申告もできます。
ただし、勤務先で加入している社会保険の自己負担分はすでに控除が適用されているため記入する必要はありません。家族の健康保険料を支払ったり、入社前に国民健康保険料などを支払っていた場合に記入します。
生命保険や地震保険の加入がない場合は空欄のまま提出します。

申告書類の記入時には、加入している保険会社や年金組織が発行する生命保険料控除証明書や国民年金保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金控除の証明書などを参照しながら正確な金額を記入する必要があります。これらの書類は年末調整の時期に合わせて10月下旬から11月ごろに届きますので大切に保管しておきましょう!
住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除申告書は、住宅ローン控除の2年目以降の申請を行うときに提出します。
確定申告をして住宅ローン控除初年度の申告を行うと、2年目以降分の住宅借入金等特別控除申告書が税務署から発行されます。書類を紛失しないよう保管し、年末調整の時期になったら記入して勤務先に提出する必要があります。
また、書類の記入は、住宅ローンの契約をしている金融機関が発行する年末残高証明書に記載された内容をもとに行います。住宅または土地の購入や増改築のための借入金の年末残高や連帯債務の割合、取得対価の額などを記入しましょう。
ちなみに、年末残高証明書は、通常は毎年10月上〜中旬頃に郵送で届きます。年末調整が終わった後も紛失しないよう大切に保管しておきましょう!
還付金を受け取れるケースって?

年末調整で所得控除を申告することで税金が安くなり、還付金を受け取れるケースがあります。
どのような場合に年末調整によって還付金が受け取れるのかを以下でまとめて解説します。
夫と離婚・死別した場合
夫と離婚または死別した場合は寡婦控除の対象となりますので年末調整で申告すれば還付金を受け取れます。
納税者本人の状況に応じて受けられる控除は12月31日時点での現況に合わせて決定されます。しかし、控除を申請するための「扶養控除等(異動)申告書」はその年の最初の給与の受取前に一度提出することになっています。そのため、寡婦控除の条件に該当しても、適用されていない金額計算で源泉徴収されているケースが多くなります。
ひとり親の場合
ひとり親に該当する人はひとり親控除の対象となります。ひとり親とは、同一生計の子がいる人のうち、現在婚姻関係にある人がいない人のことです。
ひとり親控除も上記の寡婦控除と同様に扶養控除等(異動)申告書で申告します。
その年の最初の給与を受け取る前の時点でひとり親に該当せず、年末時点で新たにひとり親の条件を満たす場合は還付金を受け取ることができます。
本人または家族が障害者の場合
本人または家族が障害者の場合は障害者控除の対象となります。

納税者本人が障害者であるケースだけでなく、家族が障害者の場合も適用可能です。控除額は障害者の区分や同居してるかどうかにより27万円〜最大75万円です。
こちらも寡婦控除やひとり親控除と同様に、年初の時点で該当せず、年末時点で新たに条件を満たした場合は還付金の対象となります。
扶養者が増えた場合
納税者が扶養する扶養親族の人数が増えた場合も還付金を受け取ることができます。
上記で何度か記載したのと同様に、年の途中で扶養親族の人数が増えた場合、扶養控除等(異動)申告書を年初に提出したときと比べて控除額が増えるからです。
扶養控除の控除額は毎年12月31日時点の扶養親族の人数で決まります。
たとえば、年の途中で子供が誕生日を迎えて16歳になり、扶養親族になるケースが考えられます。アルバイトで収入を稼いでいて扶養から外れていた子供が、アルバイトをやめて扶養親族になる場合もあるでしょう。
年度途中での入社で定額減税の対象外となっている場合
定額減税は、令和6年度に実施された1人あたり3万円の控除が受けられる減税制度です。年間の合計所得が1,805万円以下の人が対象で、税額が3万円減税されることで給与から引かれる源泉徴収税額が減るため、手取り額が増えます。
このようなケースでも、減税が受けられないわけではなく、年末調整で減税額を適用する仕組みになっています。年間の源泉徴収税額が本来の金額より大きくなるため、減税分をそのまま還付金として受け取ることができます。
結婚した場合
年の途中で結婚した場合、配偶者控除または配偶者特別控除が受けられるため、還付金を受け取れる可能性が高くなります。
配偶者控除は配偶者の年間所得額が48万円以下の場合に受けられる控除で、控除額は38万円です。
配偶者の所得が48万円を超える場合でも、133万円以下なら配偶者特別控除の対象となり、還付金を受け取れる可能性が高いです。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、加入者は年末調整で支払い額を記入して提出すれば還付金を受け取れます。
iDeCo(イデコ)とは、毎月掛金を積み立てて60歳以降になってから受け取る個人年金の制度です。

老後の資産形成をしながら節税をして還付金を受け取れるため、将来の年金額に不安がある人は検討してみるとよいでしょう。
住宅ローンを組んでいる場合
住宅ローンを組んでいる場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を申告することで還付金を受け取れます。
住宅ローン控除は、対象のマイホームの新築や増改築時に銀行などで住宅ローンを組んだ人が対象です。

最初の1年目は税務署で確定申告が必要で、還付金は税務署から振り込まれます。初年度の申告が終われば、2年目以降は毎年の年末調整で申告できます。
個人で社会保険料を払った場合
勤務先で加入する社会保険以外に個人で社会保険料を支払った場合は、年末調整で社会保険料控除の申告をすれば還付金が戻ってきます。
代表的なケースは以下の3つです。
・転職した人で、転職前の社会保険料を任意継続で支払っていた
・年末調整を受ける会社に入社する前に、国民健康保険や国民年金に加入していた
これらの保険料は年末調整で控除の対象となります。
生命保険や地震保険に加入している場合
生命保険や地震保険に加入している場合も、保険料の支払い額に応じて還付金を受け取れる場合があります。
生命保険料控除では、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った人が最大12万円の所得控除を受けられます。
地震保険料控除は地震保険料の支払額に応じて、最大5万円の控除を受けることができます。

保険会社が発行する控除証明書を大切に保管して、年末調整の書類に支払い額を忘れずに記入しましょう。
年末調整に間に合わなかったら?

事情があり年末調整の手続きが間に合わなかったということもあるでしょう。うっかり書類の提出を忘れてしまったり、後から申告漏れや間違いに気づくこともあります。このような場合にどう対処すればよいのかを以下で解説します。
▼ 年末調整が遅れた場合の対処法はこちらの記事で詳しく解説しています!

すみやかに会社に相談しよう
年末調整に間に合わなかったり、提出した書類の間違いに気づいたりしたときは、すみやかに会社の担当者に相談しましょう。手続きの進行状況にもよりますが、税務署に申告をしていない段階なら社内での手続きが間に合う場合があります。

いつまでなら間に合うかという点ですが、目安として会社から源泉徴収票が発行される前なら対応可能な場合が多いです。ただし、会社は1月31日までを期限として申告を行いますので、それより以前である必要があります。
年末調整を受けないデメリット
会社での手続きをあきらめて年末調整を受けなかった場合、以下のように様々なデメリットがありますので注意しましょう。
・所得税の過払い分が還付されない
・翌年の住民税が高くなる
会社から受け取っている給与から源泉徴収された税額には、本来受けられる所得控除が適用されていない場合があります。扶養控除などの申告は年末調整の書類で行いますが、年末調整を受けない場合は各種控除が受けられなくなってしまいます。
その結果、本来は12月分または1月分の給与に加算される形で還付金を受け取れるところが、年末調整を受けない場合は還付金がもらえなくなります。
確定申告を行うことで解決!
とはいえ、事情があってどうしても年末調整を受けられなかったというケースもあるでしょう。
上記で説明した年末調整を受けないデメリットを避けるには、翌年になってから自分で確定申告を行うことで解決することができます。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの日程で、前年の1月1日から12月31日までの所得税を計算して申告します。年末調整で申請する所得控除は、すべて確定申告でも申請できますので、年末調整を受けられなかったり不備があった場合は、税務署で確定申告を行いましょう。
確定申告の手続き方法は、以下の手順となります。
2.勤務先から受け取った源泉徴収票をもとに、所得や源泉徴収税額を入力する
3.申請したい所得控除の項目を入力する
4.e-Taxで送信する、または印刷して税務署に郵送で提出する
上記の手順は、年末調整を受けられなかった場合に最初から申告する場合にも使えますし、年末調整で不備や誤りがあった場合に修正する方法としても使えます。所得控除の適用により還付金が発生する場合は、約1〜2ヶ月後に税務署からの銀行振込などの方法で受け取ることができます。

このように、年末調整を受けられなかった場合でも確定申告を行えば税金を払いすぎることはなくなります。ただし、手続きの手間が増えてしまいますので、可能な限り勤務先での年末調整で手続きを完了させるようにしましょう!
まとめ
この記事では、年末調整のスケジュールや対象となる給与の期間、修正可能日などを解説しました。
年末調整は一般的には11月〜12月ごろにかけて行われ、1月1日から12月31日までの給与を対象としています。勤務先の担当者から必要書類について案内されたら、早めに記入と提出を行いましょう。
事情があって提出が間に合わなかったり不備に後から気付いた場合は、源泉徴収票の発行前なら社内で修正できる場合があります。また、社内での修正に間に合わなかった場合でも、翌年の3月15日までに確定申告を行うことで修正可能です。

年末調整を正しく行うことで還付金を受け取れる場合もあります。スケジュールに余裕を持って確実に手続きを行いましょう!
ぜひこの記事でまとめたことを参考にしていただき、年末調整の手続きで役立ててください!
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか



