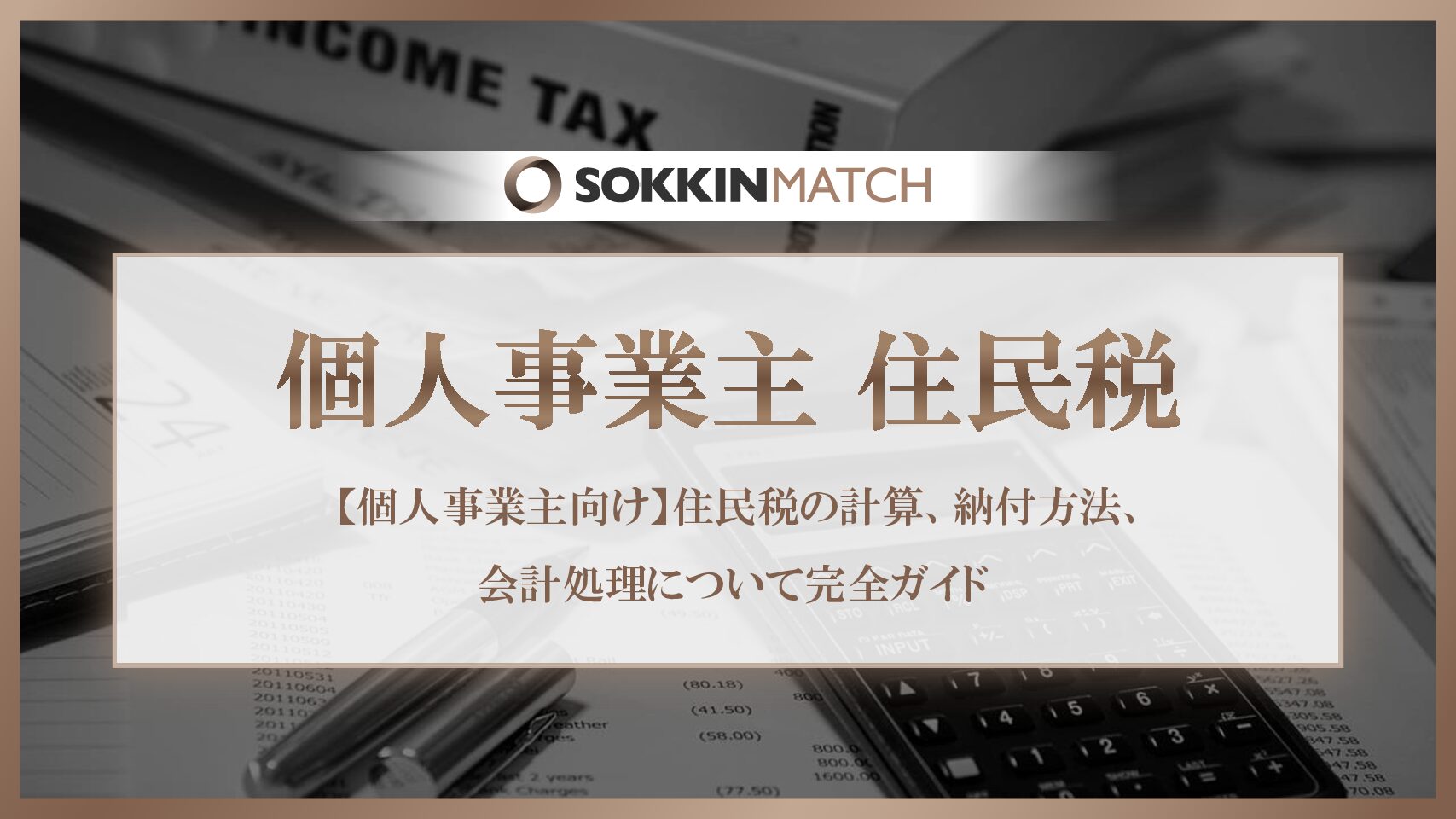個人事業主になるとさまざまな税金の納税義務が発生しますが、住民税もそのような税金のひとつです。
ただし、計算方法や納付のタイミングは所得税と異なり、会計処理などで混乱する方もいるのではないでしょうか。
本記事では住民税の計算方法・納付のタイミング・会計処理とあわせて、住民税の種類や非課税条件なども解説します。ぜひ最後までご覧いただき、住民税の知識を深めてください。
住民税はどんな税金?

住民税とは、地域で提供されている消防・救急・教育などの行政サービスの維持・運営のための財源確保を目的とした地方税です。
一定の年間所得がある地域住民やその地域で事業活動を行っている企業など、課税対象は広範囲にわたります。
住民税には個人住民税と法人住民税の2種類があり、その対象は以下のように定められています。
| 住民税の種類 | 対象者 |
| 個人住民税 | ・その年の1月1日時点でその地域に住所がある人 ・一定の年間所得がある人 |
| 法人住民税 | ・その地域に事務所などを有する法人 ・その地域で商売などをして事業収益を得ている法人 |
(参考:総務省|地方税制度|個人住民税、総務省|地方税制度|法人住民税)
個人事業主の場合、法人成りをしていないので個人住民税の対象です。
5つの住民税
「住民税」といっても具体的には以下の5種類があり、対象者・納税額などは同一ではありません
・所得割
・利子割
・配当割
・株式等譲渡所得割
上記5つの内容を確認していきましょう。
均等割
均等割とは一定年間所得がある人全員が負担する住民税のひとつであり、納税額は原則として以下の通りです。
| 税金の種類 | 区分 | 納税額 |
| 道府県民税 | 地方税 | 1,000円 |
| 市町村民税 | 地方税 | 3,000円 |
| 森林環境税 | 国税 | 1,000円 |
道府県民税・市町村民税の金額はあくまで原則納税額であり、各自治体の条例によって異なる金額設定が認められているので全国同額ではありません。
| 都道府県 | 市区町村 | 均等割 | 減額・超過の詳細 | |
| 都道府県 | 市区町村 | |||
| 岩手県 | - | 2,000円 | 3,000円 | いわての森林づくり県民税1,000円 |
| 宮城県 | - | 2,200円 | 3,000円 | みやぎ環境税1,200円 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 1,300円 | 3,900円 | 水源環境の保全・再生のため超過課税300円
横浜みどり税900円 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 1,500円 | 2,800円 | あいち森と緑づくり税500円
市民税減税-200円 |
上記は金額が異なる一部の自治体ですが、独自の条例によって納税額が異なっていることがわかります。
なお森林環境税は2024年度から新たに導入された国税であり、こちらは全国同額に設定されています。
所得割
所得割とは一定の年間所得額がある人を対象にその金額に応じて納税額が変動する住民税の一部で、税率は2種類から成り立っておりその内訳・割合は以下の通りです。
| 種類 | 税率 |
| 道府県民税 | 2% |
| 市町村民税 | 8% |
ただし所得割の税率も均等割同様に各自治体の条例によって異なる割合を定めることが認められており、全国同一ではありません。
| 都道府県 | 市区町村 | 所得割 | |
| 都道府県 | 市区町村 | ||
| 神奈川県 | - | 4.025% | 6% |
| 横浜市 | 2.025% | 8% | |
| 川崎市 | 2.025% | 8% | |
| 相模原市 | 2.025% | 8% | |
| 愛知県 | 名古屋市 | 2% | 7.7%(市民税減額) |
(2024年11月30日現在)
上記は、異なる税率が設定されている自治体の一部です。標準税率(10%)よりも高い割合が設定されているところもあれば、低く設定されている自治体もあります。
利子割
利子割とは、金融機関などの利子に対して課せられる税金のことです。
例えば銀行に預貯金をしている場合、年に1回の割合で利息が支払われます。あらかじめ定められた税率をかけた分が天引きされており、個人住民税のように納付書を金融機関等に持ち込んで納税する必要はありません。
なお、預貯金から天引きされる税金の内訳は以下の通りです。
| 区分 | 税率 |
| 利子割 | 5% |
| 所得割および復興特別所得税 | 15.315% |
課税対象は銀行・信用金庫などの預金利子や国債・地方債・社債の利子などであり、県民利子割や府民利子割と呼ばれることもあります。
配当割
配当割とは、上場株式との配当や割引債の償還差益に対して課せられる税金のことです。
課税対象は上場株式等の配当や特定口座外の割引債の償還差益となっており、株の配当や差益分を受け取る際に天引きされます。
納税額を算出するための税率・内訳は以下の通りです。
| 区分 | 税率 |
| 配当割 | 5% |
| 所得割および復興特別所得税 | 15.315% |

納税負担者は配当や償還差益を受け取る人ですが、納税は天引きした金融機関等であり、前述した利子割同様に個別での確定申告は必要ありません。
株式等譲渡所得割
株式等譲渡所得割とは、上場株式等の譲渡をした際に発生した利益に対して課せられる税金です。
この税金は一定の特定口座にて行われた譲渡取引の所得額などに課せられるものであり、株の譲渡利益などが支払われる際に事前に差し引かれます。
納税額を算出するための税率・内訳は以下の通りです。
| 区分 | 税率 |
| 株式等譲渡所得割 | 5% |
| 所得割および復興特別所得税 | 15.315% |
住民税の計算方法

住民税は所得割と均等割の2種類から成り立っており、均等割は納税額が一律なので計算する必要はありません。
一方の所得割は年間所得額に応じて納税額が変動するため計算しなければならず、均等割と比較すると算出方法が複雑です。
そこで先に所得割額を計算し、最後に均等割の金額を加算して最終的な納税額を算出します。
所得割の計算
所得割の計算手順は以下の通りです。
1.所得割の算出 2.課税所得額の算出 3.所得割額の算出
各手順の注意点等を解説するので、参考にしてください。
1.所得額の算出
所得額を算出する際の計算式は以下の通りです。
年間所得額=年間収入-経費・給与所得控除額
住民税は前年度の所得額をもとに計算するため、ここで算出する所得額は前年分であり、年間収入・経費も同様に前年の数字を用います。
なお「給与所得控除額」とは、サラリーマンなどの給与所得者に適用される経費です。原則として給与所得者は個人事業主のような経費計上が認められておらず、不公平感を解消するために給与所得控除が設けられています。
個人事業主の場合は事業収入を得るために直接関係のある支出を経費として計上して年間収入額からマイナスしますが、その際に経費として認められる主な例は以下の通りです。
・仕入費用 ・事業活動をする際に発生した交通費 ・事業用の備品 ・文房具の購入代 ・事務所の地代家賃 ・固定資産税 ・事務所の水道光熱費 ・電気代
2.課税所得額の算出
課税所得額を算出する際の計算式は以下の通りです。
課税所得額=年間所得額-所得控除
上記計算式の所得控除とは一定の要件を満たすことで年間所得額から差し引くことが可能な制度であり、以下のようなものがあげられます。
| 種類 | 要件 | 控除額 | ||
| 住民税 | 所得税 | |||
| 基礎控除 | 年末調整や確定申告対象者全員に適用 | 43万円 | 最高48万円 | |
| 扶養控除 | 配偶者以外の扶養家族がいる場合 | 最高45万円 | 最高63万円 | |
| 配偶者控除 | 配偶者がいる場合 | 最高38万円 | 最高48万円 | |
| 配偶者特別控除 | 33万円 | 最高38万円 | ||
| ひとり親控除 | 納税者本人がひとり親の場合 | 30万円 | 35万円 | |
(出典:個人住民税|暮らしと税金|東京都主税局)
3.所得割額の算出
所得割額を算出するための計算式は以下の通りです。
所得割額=課税所得額×税率(10%)-税額控除
上記計算式の税額控除とは、一定の要件を満たすことで納税額から直接控除できる制度であり、住民税の場合は以下の4種類が設けられています。
| 税額控除 | 概要 |
| 配当控除 | 総合課税の配当所得が一定金額ある場合 |
| 外国税額控除 | 外国所得において所得税・住民税に相当する課税があった場合 |
| 寄附金税額控除 | 自治体や一定の団体に2,000円超の寄附金を支払った場合 |
| 調整控除 | 所得税と住民税の控除額の差に基づく負担増の調整 |
(出典:個人住民税|暮らしと税金|東京都主税局)
なお上記4つ以外にも所得税で控除しきれなかった場合には住民税所得割額から控除される制度があり、その税額控除は以下の2つです。
・配当割額及び株式譲渡所得割額の控除 ・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
(出典:個人住民税|暮らしと税金|東京都主税局)

上記の2つは控除額に対して所得税が足りなかった場合のみ、住民税に適用される税額控除であり、控除額が残らなかった場合は適用されません。
住民税額の算出
最終的な住民税額を算出するための計算式は以下の通りです。
住民税額=所得割額+均等割額
均等割の金額は「均等割」の項目で紹介しましたが、原則納税額4,000円に森林環境税1,000を加算した5,000円であり、この金額を所得割額に加算して納税額が決定します。
住民税の納付方法
住民税の納付方法は以下の2通りです。
・特別徴収
上記2通りの納付方法や対象者や納付の仕方が異なります。それぞれ詳しく確認していくので、参考にしてください。
普通徴収
普通徴収とは、自治体から送付される納付書を使用して金融機関・コンビニなどで住民税を支払う方法です。
一般的に給与所得者や公的年金支給者以外であり、例えば個人事業主・フリーランス・自営業などが対象として含まれます。
6月・8月・10月・翌年1月の年4回にわけて支払う方法が一般的ですが、一括払いも可能です。送付される納付書には4回分と一括払いの両方が同封されているので、都合等にあわせて好きな方を選択しましょう。
特別徴収
特別徴収とは給与所得者・公的年金受給者を対象とした納税方法です。
所得税の源泉徴収義務がある事業者に勤務している給与所得者や公的年金受給者は住民税の特別徴収が義務付けられているため、原則として事業主・従業員等が自分の都合で特別徴収から普通徴収に切り替えることは認められていません。

住民税は毎月の給与から天引きされるため、払い忘れなどの防止に役立ちます。また前年の所得額をもとに決定された納税額を12回にわけて納付することから、負担額が少ないと感じる人もいるでしょう。
住民税の会計処理

個人事業主になるとさまざまな支出入の会計処理を行い、適切に帳簿に記録しなければなりません。
では、住民税を支払った際の会計処理はどのようにすればよいのでしょう。
経費計上の可否・仕訳の方法を解説するので参考にしてください。
住民税は経費計上できない
個人事業主になると、さまざまな支出の経費計上が可能です。ただし、経費として認められているのは事業収益に直接関係ある支出だけであり、プライベートな支出は計上できません。
個人事業主が納める住民税は、事業とは関係のない個人的な税金として扱われるため、経費には計上できません。
税金のなかには経費計上が可能なものもあり、その一例として以下のようなものがあげられます。
・個人事業税 ・法人事業税 ・固定資産税(事業用部のみ) ・自動車税(事業用のみ) ・消費税 ・印紙税
住民税の仕訳
個人事業主が支払う住民税はプライベートに区分されるため、経費としての計上はできません。本来はプライベートな支出を事業用の支出として会計処理する必要はありませんが、事業用預金から住民税を支払うこともあるかもしれません。その場合の仕訳は以下のように行います。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 |
金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 事業主貸 | 〇〇円 | 現金 | 〇〇円 |

事業用の現金・預金からプライベートな支出を支払った際には、「事業主貸」の勘定科目を使用してください。
なお前述で経費計上可能な税金を紹介しましたが、その場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | |
| 租税公課 | 〇〇円 | 現金 | 〇〇円 | 固定資産税 |
個人事業主にかかる税金
個人事業主にかかる税金は、住民税以外で以下のようなものがあげられます。
・所得税 ・消費税 ・個人事業税
それぞれの税金を詳しく確認していきましょう。
所得税
所得税とは事業活動を行った1年間の所得額に課せられる国税です。
個人事業主が事業所得を得た場合に用いる課税方式は総合課税であり、課税所得額によって税率と控除額が異なる累進課税制度で納税額を算出します。
課税方式には総合課税以外に分離課税があり、主な例は以下の通りです。
| 区分 | 内容 | 課税方式 | |
| 事業所得 | 商業・工業・自営業などの所得 | 総合 | |
| 事業で行う株式譲渡や先物取引の所得 | 申告分離 | ||
| 不動産所得 | 土地や建物、船舶などの貸付所得 | 総合 | |
| 利子所得 | 国外預金などの利子 | 総合 | |
| 特定公社債の利子など | 申告分離 | ||
| 預貯金利子など | 源泉分離 | ||
| 配当所得 | 法人余剰金配当金、投資信託の収益分配など | 総合 | |
| 上場株式等配当など | 申告分離 | ||
| 特定目的信託(私募のみ)の収益分配など | 源泉分離 | ||
| 給与所得 | 給料、賞与など | 総合 | |
| 雑所得 | 公的年金等 | 国民年金、厚生年金、確定拠出企業年金など | 総合 |
| その他 | 原稿料、講演料など | 総合 | |
| 業(事業以外)で行う株式譲渡所得など | 申告分離 | ||
(参考:所得の種類と課税方法|国税庁)

なお、納税する際には復興特別所得税が加算されます。2011年12月2日に東日本大震災の復興施策実施に必要な財源確保を目的に、2013年1〜2037年まで課税される税金です。
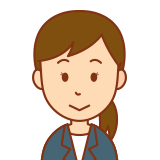
個人事業主の納期限は確定申告同様に原則として2月16日〜3月15日までであり、この期間中に申告から納税までを完了させなければなりません。
所得税の計算方法
所得税を算出する際の計算手順は以下の通りです。
| 手順 | 算出する金額 | 計算式 |
| 1 | 年間所得額 | 年間収入-経費・給与所得控除額 |
| 2 | 課税所得額 | 年間所得額-所得控除 |
| 3 | 基準所得税額 | 課税所得額×税率-控除額 |
| 4 | 所得税額 | 基準所得税額-税額控除 |
| 5 | 復興特別所得税額 | 基準所得税額×2.1% |
| 6 | 申告納税額 | 基準所得税額+復興特別所得税額 |
消費税
消費税とは、商品やサービスの消費に対して課される税金です。
消費税額=受取消費税額(課税売上高×税率)-支払済消費税(課税仕入高×税率)
ただしすべての事業者に納税の義務が発生するわけではなく、以下のような条件が定められています。
| 消費税の納税 | 名称 | 条件 |
| 必要 | 課税事業者 | ・課税売上高1,000万円超 ・適格請求書発行事業者登録済 ・前年1月1日~6月30日分の課税売上高1,000万円超 |
| 免除 | 免税事業者 | ・課税売上高1,000万円以下 ・適格請求書発行事業者未登録 ・前年1月1日~6月30日分の課税売上高1,000万円以下 |
インボイスってなに?
インボイス制度とは複数の税率でも正確に仕入税額控除が適用できる制度のことです。
正式名称は適格請求書等保存方式といい、適格請求書が発行されない取引では仕入税額控除は適用されません。
適格請求書を発行するには、以下の手順で税務署への事前登録が必要です。
1.「適格請求書発行事業者の登録申請書」を入手、作成。 2.「税務署への窓口提出」「インボイス登録センターへの郵送」「e-Tax申請」のいずれかで提出。 3.審査を経て登録。(税務署またはインボイス登録センター) 4.手続き完了通知受領。
個人事業税
個人事業税とは、フリーランスや個人事業主に納税義務が課せられている地方税のひとつです。
地方税法や自治体独自の条例で定められた業種に携わる人を対象としており、すべてのフリーランス・個人事業主に納税義務が発生するわけではありません。
例えば東京都の場合は、以下のように定められています。
| 事業種 | 税率 | 事業の種類 |
| 第1事業
(37事業) |
5% | 物品販売業、運送取扱業、飲食店業、請負業、運送業など |
| 第2事業
(3事業) |
4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3事業
(30事業) |
5% | 医業、歯科医業、士業、デザイン業、美容業、など |
| 3% | あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業事業、装蹄師業 |
住民税が非課税になるのはいくらから?
住民税はその地域に住んでいるまたは事務所を構えている場合に課せられる税金ですが、必ずしも納税義務が発生するわけではありません。
・合計所得額が自治体の条例の定める金額以下
・総所得額等が一定額以下
上記のケースに該当する場合は住民税が非課税になります。
それぞれのケースを詳しく解説するので、参考にしてください。
障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で合計所得金額が135万円以下
以下の条件に該当する場合は、所得割・均等割ともに非課税です。
1.障害者・未成年者・寡婦またはひとり親 2.前年の合計所得額135万円以下(給与所得のみの場合は204万4,000円以下)

例えばひとり親世帯で年間総収入額が145万円、経費20万円の場合の年間所得額を計算してみましょう。
145万円-20万円=125万円
年間所得額は125万円であることからボーダーラインに満たないので、所得割・均等割ともに課税対象から外れます。
合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下
各自治体では条例で合計所得額(損失の繰越控除前または分離譲渡所得の特別控除前)が一定金額以下の場合は、所得割・均等割ともに非課税になりますが、自治体によってボーダーラインは異なるので一律ではありません。
東京23区や川崎市の場合は、以下のように定められています。
| 条件 | 上限額 |
| 生計を同一にする配偶者・扶養親族がいる | 35万円×(本人・配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円 |
| 生計を同一にする配偶者・扶養親族がいない | 45万円以下 |
(出典:個人住民税|暮らしと税金|東京都主税局、川崎市 : 個人の市民税)
総所得金額等が一定の金額以下
所得割のみ非課税になる場合もあり、総所得金額等(損失の繰越控除後または分離譲渡所得の特別控除前)が一定の金額に満たない世帯が対象です。
ただし前述した所得割・均等割両方が非課税になる際のボーダーライン同様に、所得割のみが非課税になる金額も各自治体によって異なり、全国同一ではありません。
東京都や川崎市の場合は、以下のように定められています。
| 条件 | 上限額 |
| 生計を同一にする配偶者・扶養親族がいる | 35万円×(本人・配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円 |
| 生計を同一にする配偶者・扶養親族がいない | 45万円以下 |
(出典:個人住民税|暮らしと税金|東京都主税局、川崎市 : 個人の市民税)

上限額は自治体によって異なるので、市役所のホームページなどを確認してください。
まとめ
本記事では、個人事業主の住民税について解説しました。
住民税は所得割と均等割の2つから成り立っており、所得割は所得額によって異なるので計算しなければなりません。一方の均等割は各自治体によって金額が異なる可能性があるので、市役所のホームページなどで確認してください。

また、納期限についても各自治体によって異なる場合があります。納付書に納期限が明記されているので、確認してその期限までに納付しましょう。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか