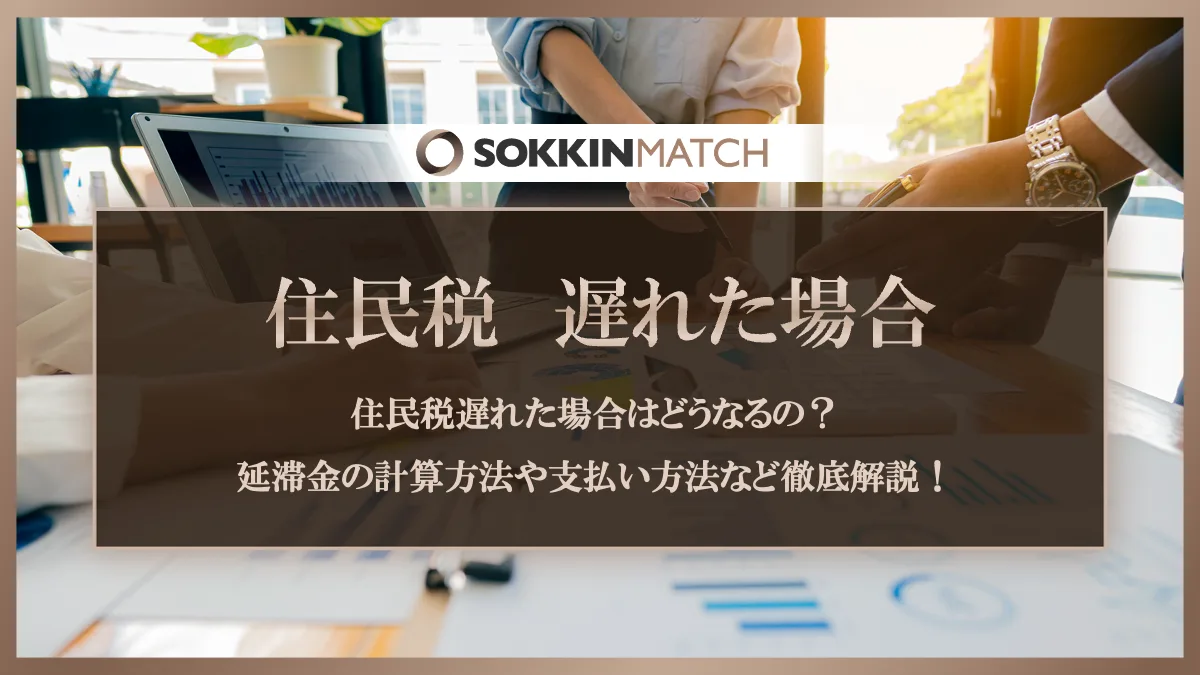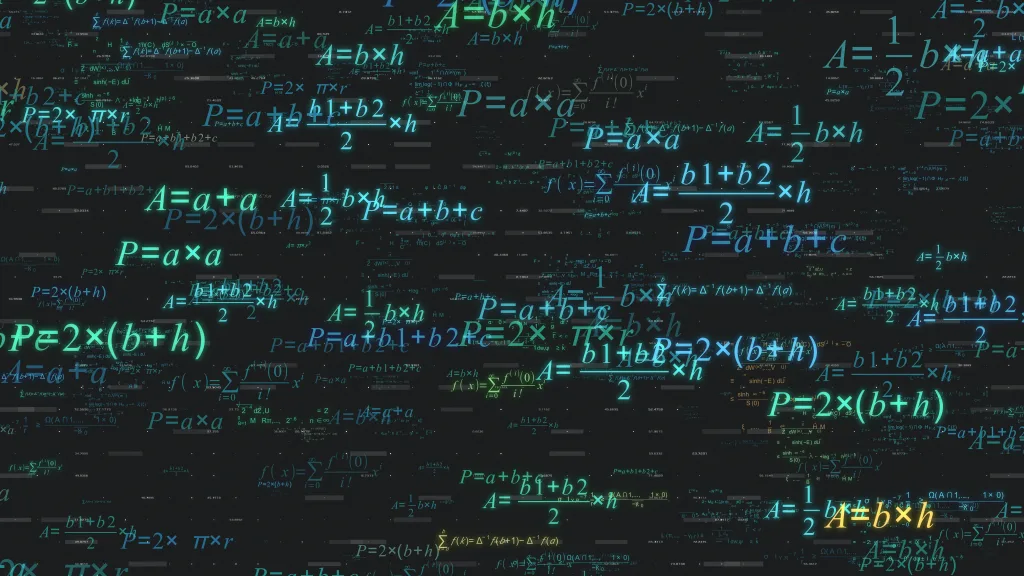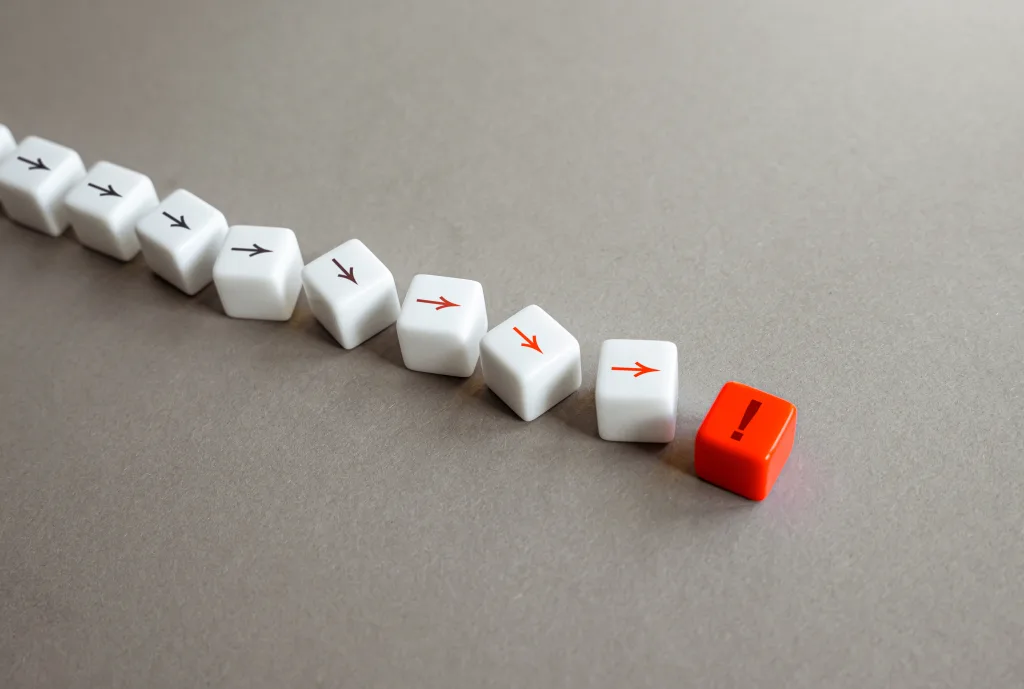会社員や個人事業主、フリーランス、副業で収入がある人など、何らかの方法で収入を得ると、稼いだ金額に応じた住民税を翌年に納税する必要があります。
会社員は税金が給与から源泉徴収されるため滞納の心配はありませんが、個人事業主など毎年確定申告を行っている人は注意が必要です。
住民税の支払いを忘れてしまうと、延滞金が発生したり、督促状や催告状が届くこともあります。

この記事では、住民税を滞納してしまうと何が起こるのか、延滞金の計算方法や滞納した税金の支払い方法を詳しく解説します。それに加えて、住民税の還付金が受け取れるケースについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
住民税滞納時の流れ
住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収とは、住民税が収入源から源泉徴収される徴収方法で、会社員などの給与所得者や年金受給者が対象です。給与や年金が支給される際に、前年の住民税を天引きした後の金額が振り込まれるため、滞納する心配はありません。
普通徴収は、住民税の納付書を使って窓口や口座振替などの方法で自分で納付する方法で、主に個人事業主やフリーランスが対象となります。普通徴収は住民税を支払う手続きを自分でする必要があるため、納付し忘れたり手持ちの資金が不足して納税できないといった事情により滞納してしまう場合があります。
普通徴収で住民税を一括納付する場合、納期限は毎年6月30日までとなります。年4回で分割納付する場合は、第1期が6月30日、第2期が8月31日、第3期が10月31日、第4期が翌年1月31日が納期限です。
もしこの納期限を過ぎても納税していない場合は、住民税を滞納したことになります。
▼ 住民税の支払い期間ややり方についてはこちら。

延滞金がかかる
住民税の納期限を経過して滞納状態になると、滞納の日数に応じた延滞金が発生します。
所得税などの国税を滞納した場合は「延滞税」が課税されますが、住民税は地方税のため「延滞金」と呼ばれます。
延滞金は滞納した税金の利息のようなもので、滞納者に対するペナルティの意味を持っています。期限までに納税した人との公平を保つために、納税が遅れた人には延滞金が加算され、本来の税額より多く支払うことになります。
延滞金は住民税の納税先である地方自治体に対して支払いを行います。滞納した税金を完納した後に自治体が延滞金の金額を計算し、延滞金の納付書が送付されます。
督促状が送付される
納期限を過ぎても納税されず滞納状態になると、まず督促状が送付されます。通常は本来の納期限を経過して1ヶ月程度で督促状が届きます。
督促状は未納となっていることの通知として送付され、未納の金額や納付期限などが記載されています。
催告書が送付される
督促状が送付されても滞納中の税金が納付されない場合、次に催告書が送付されます。
催告書には滞納中の税額や納付期限が記載され、納税できない特別な事情がある場合は自治体の担当者まで相談するように促す文面が記載されます。
催告書に記載された期限まで納付も相談もないときは、最終的に滞納処分が行われることになります。
催告書は「このまま滞納を続けると滞納処分が行われる」という最終的な通告として送付されます。
滞納処分
催告書が届いた後も滞納が続いた場合、強制的に徴収する手続きとなる滞納処分が執行されます。滞納処分では、給与や預金、不動産、生命保険などの差し押さえが行われます。
法律では督促状の送付から10日を経過しても納付されない場合は財産の差し押さえが開始されることになっています。実際の手続きでは財産の調査などが必要なため、1ヶ月〜数ヶ月程度かかることもあります。

たとえば、滞納処分で預金が差し押さえられた場合は、残高の引き出しができなくなり、強制的に滞納された税金の納税に充当されます。
このようなことにならないよう、万が一期限に遅れてしまった場合でも、できるだけ早く納税するようにしましょう。
延滞金の計算方法
延滞金の計算は以下の計算式で行います。
上記の計算式の中にある「日数A」は、納期限の翌日から1か月を経過するまでの日数です。「日数B」は、納期限の翌日から1ヶ月経過後から納税する日までの日数です。
延滞金の割合には、延滞期間によって納期限の翌日から1か月を経過するまでの割合(税率A)と、納期限の翌日から1ヶ月を経過した以後の割合(税率B)の2種類があります。そのため、それぞれの期間の延滞金を別々に計算して、合計する計算を行う必要があります。
延滞金の計算で小数点以下の端数が生じた場合は切り捨てします。合計の延滞金の金額から100円以下の端数を切り捨て、100円単位で請求されます。
延滞金の割合は延滞金特例基準割合によって決まりますので、年によって変わります。これまでの延滞金の割合を表にまとめると以下のようになります。
|
年度
|
期限から1ヶ月以内
|
期限経過後1ヶ月超
|
| 平成12年1月1日〜平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
| 平成14年1月1日〜平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
| 平成19年1月1日〜平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
| 平成20年1月1日〜平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
| 平成21年1月1日〜平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
| 平成22年1月1日〜平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
| 平成26年1月1日〜平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
| 平成27年1月1日〜平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
| 平成29年1月1日〜平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
| 平成30年1月1日〜令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
| 令和3年1月1日〜令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
| 令和4年1月1日〜令和7年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
1か月滞納した場合
それでは実際に延滞金の金額の計算を行ってみましょう。以下の条件で、5万円の税金を1ヶ月滞納した事例をシミュレーションしてみます。
・納付期限:2024年10月31日
・実際に納付をした日:2024年11月30日
・滞納日数:30日
この事例では納付期限が10月31日のため、延滞金はその翌日から納付される日まで(11月1日〜11月30日)の30日間で計算を行います。滞納期間が30日間のため、延滞金の割合は納期限から1ヶ月以内の税率のみが適用されます。
延滞金の計算式に数字を当てはめて計算すると以下のようになります。
延滞金の計算では小数点以下を切り捨てますので98円となります。延滞金の金額は100円未満を切り捨てるため、この事例では延滞金の金額は0円です。
なお、自治体によって異なる場合もありますが、延滞金の金額が1,000円未満の場合は請求されないことが多いです。

このように、延滞期間が短い場合は延滞金の金額も小さくなり、延滞金を支払わなくてもよい場合も多くなります。
3か月滞納した場合
次に、20万円の住民税を3ヶ月間滞納した場合を計算してみましょう。
・納付期限:2024年6月30日
・実際に納付をした日:2024年9月30日
・滞納日数:92日
まず、納期限の翌日から1ヶ月までの延滞金と、1ヶ月経過以後の延滞金をそれぞれ別に計算します。
・1ヶ月超過分の延滞金:20万円 × 8.7% × 61日 ÷ 365日 = 約2,907円
次に、2つの期間の延滞金を足して合計の延滞金を計算します。
延滞金の100円未満は切り捨てますので、この事例では3,300円の延滞金を支払う必要があります。
このように、延滞期間が長くなると延滞金の金額も大幅に増えるため注意が必要です。
▼ 給与所得者の住民税の計算方法についてはこちら。
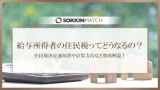
延滞金の支払い方法
住民税の普通徴収の支払いは、通常は住民税通知書と納付書が送付されますので、郵送で届いた納付書を使って行います。
住民税の支払い方法はその他にも様々な決済方法に対応しています。たとえば、東京都の住民税の納付方法は、以下の方法が使えます。
・口座振替
・スマートフォン決済アプリ
・ペイジー(Pay-easy)納付
・クレジットカード納付
・eLTAX電子納税
市区町村によっては上記の支払い方法のうち一部が利用できないこともあります。逆に、市区町村によっては他の支払い方法が利用できることもあります。
ただし、延滞金の支払いは通常の住民税の支払いとは異なりますので、利用できる支払い方法が少なくなります。
納付期限と取扱期限
滞納した住民税を支払う際には、まず住民税の納付書に記載されている納付期限と取扱期限を確認しましょう。
納付期限とは、住民税をこの日までに納税すべきという期限のことです。納付期限を経過すると、住民税を滞納したことになります。
取扱期限とは、その納付書を使って支払いができる期限のことです。取扱期限が経過した納付書は、金融機関に持参しても納税に使うことができません。この場合は自治体に問い合わせをして新しい納付書を発行してもらう必要があります。
コンビニ払いは基本できない
滞納した住民税や延滞金の支払いはコンビニ払いは基本的にはできない場合が多いです。
これは、コンビニ払いが利用できる取扱期限が税金の納期限と同じ日になっていることが多いからです。本来の納期限に間に合う場合は送られてきた納付書でコンビニ払いができますが、期限を過ぎるとコンビニ払いが利用できなくなります。
ただし、納期限経過後のコンビニ払いの扱いは自治体によって異なる場合がありますので、問い合わせをして確認するようにしましょう。
クレジットカード払いは各自治体に確認
多くの市区町村では住民税のクレジットカード払いが可能です。通常は市区町村のホームページや地方税お支払いサイトにアクセスして、オンラインでカード決済を行って納税します。
ただし、納付期限を過ぎた住民税や延滞金はクレジットカードで支払うことが出来る場合とできない場合があります。決済前に市区町村に問い合わせをして確認しましょう。
金融機関や市役所で納付しよう
上記のように、滞納した住民税や延滞金の支払いを行うときは、通常利用できる支払い方法が使えなくなる場合があります。そのため、基本的には市役所などの市区町村の窓口や金融機関で納付書を使用して支払う必要があります。
ただし銀行などの金融機関についても納期限が過ぎた納付書は使えない可能性もあります。期限に遅れた住民税や延滞金の支払いを確実に行うには、市区町村の窓口に納付書を持参して現金で直接納付するようにしましょう。
住民税の還付金を受け取れる場合は?
何らかの原因で住民税を払いすぎている場合は、還付金を受け取ることができます。
還付される場合は、払いすぎた税金の内訳や還付される理由などが記載された「過誤納通知書」が市区町村から送られてきます。
住民税の還付金が受け取れるのはどのような場合なのか、以下で考えられるケースを見ていきましょう。
医療費控除を受けた場合
医療費控除は、医療費や医薬品の購入費用を年間10万円以上支払った人が確定申告をすることで受けられる所得控除です。医療費としては病院の治療費や入院費用、通院のための交通費などが対象で、歯科での治療費用も含めることができます。
控除額は実際に支払った医療費の金額のうち、10万円を超える部分です。たとえば、医療費を50万円支払った場合は40万円の所得控除が受けられます。また、自分のための医療費だけでなく、家族のために支払った医療費も控除額に含めることができます。

年間の医療費が10万円以下の場合でも、医薬品を年間で12,000円以上購入していて、一定の条件を満たせばセルフメディケーション税制で控除を受けることができます。
確定申告で医療費控除を申請すると、税金の計算のもとになる課税所得の金額を減らすことができます。その結果住民税も安くなりますので、還付金を受け取れる場合があります。
寄付金控除(ふるさと納税)を受けた場合
国や地方自治体、公益法人などに寄付をした人は寄付金控除を受けることができます。自分が応援したい自治体に寄付をして返礼品を受け取れることで人気の高い「ふるさと納税」で寄付を行った場合も、寄付金控除の対象となります。
ふるさと納税を行ったときの住民税の控除額は以下の計算式で決まります。
・住民税からの控除額(特例分) = (寄付した金額 – 2,000円) × (100% – 10% – 所得税の税率 × 1.021%)
上記で計算した基本分と特例分の合計金額が翌年の住民税から控除されます。
雑損控除を受けた場合
雑損控除とは、災害の被害にあったり、盗難や横領で損害を受けたときに確定申告を行うことで所得控除が受けられる制度です。
たとえば、地震などの自然災害で生活に必要な資産や事業用の資産に損害を受けた場合に、保険金で補填された金額を差し引いてもまだ損害額が残る場合に、税負担を軽減することができます。
雑損控除の控除額は、以下の2つの計算で求めた金額のうち多い方の金額です。
・(災害関連支出の額 – 保険金などで補てんされた額) – 5万円
雑損控除の対象となる場合は確定申告で申請することで所得税と住民税が安くなるため、還付金を受け取れる可能性があります。
住宅ローン控除を受けた場合
住宅ローン控除は、納税者本人が住むための居住用住宅を新築したり、リフォームしたりする際に、返済期間10年以上の住宅ローンを組んだ場合に受けられる控除です。取得した住宅に入居してから最大13年間にわたって、年末時点の住宅ローン借入残高の0.7%に相当する額を税金から控除できます。
住宅ローン控除は、まず所得税から優先して控除を受けることができる制度です。ただし、その年の所得税額が住宅ローン控除の控除額を下回り、控除しきれなかった場合は、残りの金額は住民税から控除される仕組みになっています。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、会社員など給与所得者であっても初年度は確定申告での申請が必要です。初年度の手続きが終われば、2年目以降は年末調整で申告することができます。
年末調整で控除を申告し忘れた場合
会社員は毎年11月〜12月ごろに行う年末調整で所得控除の申告をしています。しかし、書類の記入忘れや控除を受けられることを知らなかったなどの理由で年末調整で控除を申告し忘れることもあるでしょう。
このようなときでも、後ほど自分で確定申告を行えば本来受けられる控除を適用することができます。年末調整で正しく控除の申請ができていない場合は税金を払いすぎていることになりますので、確定申告を行えば還付を受けることができます。
年末調整で申告できる控除の例としては、配偶者控除や扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除などの人的控除と、各種の保険料控除や小規模企業共済等掛金控除などの物的控除があります。
会社を退職した年に再就職しなかった場合
会社を退職した年に再就職しなかった場合も、そのままでは税金の払い過ぎになる可能性がありますので、確定申告をすれば還付金を受け取れる場合があります。
会社を年の途中で退職する場合、その後年内に別の会社で再就職をする見込みがないという例外的なケースを除いて、ほとんどの場合は退職時に年末調整を行いません。
その後、結果的に再就職しなかった場合は、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などの所得控除を申請しないまま税金を払うことになります。その結果、納税額が本来の税額より高くなる場合があります。
このような場合も、自分で確定申告をすることで、年末調整が行われなかったことにより受けられなかった所得控除を申告することができます。そうすると、課税される税額も本来の金額に修正されますので、税金を払いすぎている場合は還付を受けることができます。
還付は5年分さかのぼって請求できる!
上記で説明したような事情があり住民税を払いすぎている場合は、住民税の還付申告を行うことで還付金を受け取ることができます。
自治体のホームページで「過誤納金還付請求書」という様式をダウンロードして、記入して郵送などで提出することで還付申告ができます。
逆に考えると、住民税の還付は最大5年分までさかのぼって請求できます。何らかの事情で税金を払いすぎていることが判明したら、できるだけ早く還付の申告を行いましょう。
▼ 住民税の控除についてはこちら。

まとめ
この記事では、住民税の納税が遅れた場合の支払い方法や、延滞金の計算方法などを解説しました。
住民税の納税が遅れると、延滞金が加算され、本来の税額よりも高い金額を納税することになります。長期間にわたって滞納が続くと、督促状や催告状が送付され、財産の差し押さえを含む滞納処分が執行されますので注意が必要です。
滞納した住民税や延滞金の支払い方法は、コンビニ払いやクレジットカード払いが使えないことがあり、支払い方法も限定されてしまいます。
このように、住民税の納税が遅れるとさまざまなデメリットが生じるため、期限までに納付することが大切です。万が一遅れた場合も、できる限り早く納税するようにしましょう。

ぜひこの記事でまとめたことを参考にしていただき、住民税の納税手続きで役立ててください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。