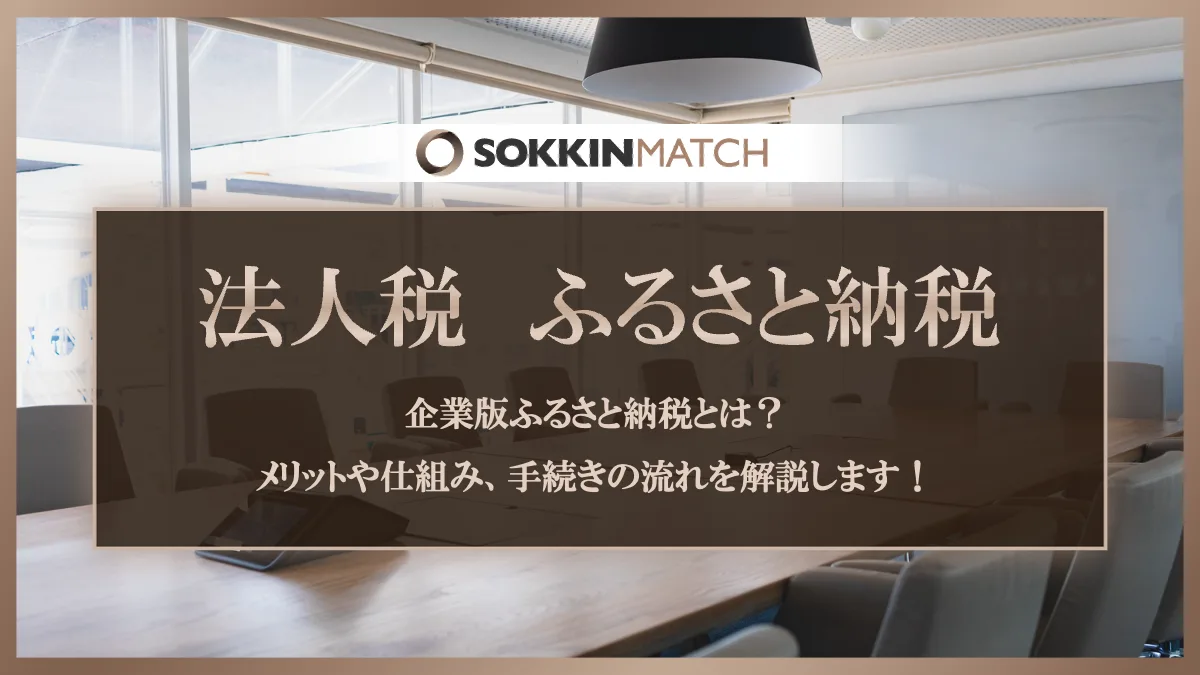2008年から運用が開始されているふるさと納税には、個人版と企業版があることをご存じでしょうか。個人版は所得税・住民税に対する節税対策が可能ですが、企業版は法人税の節税に特化しています。
会社員・フリーランスなどにはあまりなじみがない企業版ふるさと納税とは、どのような制度なのでしょう。

本記事では法人税に特化した企業版ふるさと納税の仕組み・手続きの流れとともに、メリットなども含めて解説します。
企業版ふるさと納税とは
2008年5月から運用がスタートしたふるさと納税には、個人版と企業版の2種類があります。個人版は所得税・住民税の節税対策に特化した内容である一方で、企業版は法人税の節税に特化している違いがあり、同じふるさと納税でもその中身は同一ではありません。
具体的な制度の中身・実績などを詳しく確認していきましょう。
▼ ふるさと納税の仕組みや控除の流れを知りたい方はこちら。

企業版ふるさと納税とはどういう制度?
企業版ふるさと納税とは、会社・企業が各自治体に寄附をすることで法人関連の税負担が軽減される制度のことです。
正式名称は「地方創生応援税制」であり、2008年5月に運用が開始された個人版ふるさと納税に対してその8年後の2016年に内閣府主導のもとで創設されました。
企業版ふるさと納税には、地方の人口減少に伴う地方事業の縮小を防ぐ目的があり、企業が各自治体に寄附を行うことで地域創成を活性化する狙いがあります。
企業版ふるさと納税の実績はどのくらい?
企業版ふるさと納税の実績について確認しましょう。
|
令和4年度
|
令和5年度
|
前年比
|
|
| 寄附件数 | 8,390件 | 14,022件 | 約1.4倍増加 |
| 寄附額 | 約341.0億円 | 約470.0億円 | 約1.7倍増加 |
| 寄附企業数 | 4,663社 | 7,680社 | 約1.6倍増加 |
| 受領地方公共団体数 | 1,276団体 | 1,462団体 | 約1.1倍増加 |
(抜粋:地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の令和5年度寄附実績について(概要)|内閣府)
上記のデータは2024年8月30日に内閣府地方創生推進事務局が発表した企業版ふるさと納税の「令和5年度寄附実績について」の概要であり、2022年と2023年のデータのみ抜粋して作成しました。
この制度の運用が開始されてから実績は増加しており、特に抜粋した2年間は増加率が大きくなっています。
長期的・短期的の両方の視点で見た場合でも、各自治体の成長率等に大きく貢献していることがわかるでしょう。
企業版ふるさと納税(人材派遣型)とは?
企業版ふるさと納税(人材派遣型)とは、企業が行う寄附金とあわせて寄附を行う企業の従業員を各自治体に派遣する制度のことです。

各自治体では社会的な少子化とあわせて、地方から都市部への人口流出も問題になっており、人材確保が困難な状況に陥っています。この状態を打開するために導入されているのが、企業版ふるさと納税(人材派遣型)です。
具体的な双方のメリットとして、以下のような点があげられます。
|
企業側
|
自治体側
|
| ・人件費の削減 ・各自治体とのパートナーシップ強化 ・人材育成が可能 |
・地方人口の増加 ・低コストでの人材採用が可能 ・優秀な人材の確保 |
企業側としては雇用している従業員を各自治体に派遣することで、給与などの人件費を自治体に負担してもらえると同時に、人材育成も実現可能です。
一方の各自治体にとっては優秀な人材を企業から派遣してもらえるため、即戦力として活躍してもらえるでしょう。また派遣された従業員は地方に根を下ろすことになるため、人口増加も期待できます。
企業版ふるさと納税の特別措置はいつまで続く?
企業版ふるさと納税の特別措置は2025年1月現在、令和6年度までです。
制度導入当時は2019年(令和元年度)までの特別措置として運用されていましたが、令和2年度の税制改正で適用期限が5年間延長され、令和6年度までに変更されました。
「個人版ふるさと納税」と「企業版ふるさと納税」何が違うの?
ふるさと納税には個人版と企業版がありますが、この2つの相違点を一覧表で確認しましょう。
|
相違点
|
企業
|
個人
|
| 所管省庁 | 内閣府 | 総務省 |
| 自己負担額 | 寄附額の1割 | 2,000円 |
| 返礼品の有無 | なし(禁止) | あり |
| 寄附先 | 本社を管轄する都道府県・市区町村以外 | 制限なし |
| 寄附額下限 | 10万円 | なし |
| 控除対象の税金 | 法人税、法人事業税、法人住民税 | 所得税、住民税 |
| 控除額の割合 | 最大9割(税額控除6割+損金算入3割) | ・所得税は総所得額の30%が上限 ・住民税は総所得額の40%が上限 |
同じふるさと納税ではありますが、所管する省庁が異なるため、返礼品の有無や控除対象となる税金の種類などにも相違があります。
なお「控除額の割合」については次の見出しで詳しく解説するので、あわせて参考にしてください。
▼ ふるさと納税の申告の仕方はこちら。

企業版ふるさと納税の仕組みである9割控除とは
企業版ふるさと納税の令和6年度時点での税額軽減は最大9割です。
制度が導入された時点では、税額控除3割に損金算入割を加算した最大6割が税額軽減の上限でした。
しかし令和2年度税制改正により、税額控除3割が2倍に引き上げられて6割に変更され、最大9割の控除が適用されます。

例えば、ある企業が特定の自治体に1,000万円のふるさと納税をしたとしましょう。控除額は寄附金の9割であることから、最大900万円分の法人税等が軽減されます。
実際にはこのような単純計算で算出されるわけではありませんが、イメージとしてはこのような控除であると考えてください。
企業版ふるさと納税の控除上限額はいくらまで?
税額控除は最大9割であると前見出しで解説しましたが、控除額には上限額が定められています。
企業版ふるさと納税の税額控除の対象となる税金の種類は「法人税」「法人事業税」「法人住民税」の3つであり、それぞれの上限額は以下の通りです。
|
税金の種類
|
原則
|
上限
|
|
| 法人税 | 国税 | ・寄附額の1割 ・法人住民税が4割に達しない場合は残額 |
法人税額の5% |
| 法人住民税 | 地方税 | 寄附額の4割 | 法人住民税法人税割の20% |
| 法人事業税 | 地方税 | 寄附額の2割 | 法人事業税の20% |
(出典:企業版ふるさと納税をぜひご活用ください! – 内閣府)
原則・条件ともに3つの税金は異なるので、この制度を利用する際は注意してください。
税制優遇措置を受けるための要件とは?
企業版ふるさと納税の税制優遇措置を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
・寄附に対する経済的利益の授与禁止
・本社が所在する地方公共団体以外の自治体が対象
・地方交付税不交付団体・地方活力向上地域以外の市区町村・首都圏整備法で定める地域以外
個人版とは異なり、企業版では寄附を行う際の自治体に制限が設けられています。寄附先がどこでもよいわけではない点に注意してください。
控除額を最大にするためには?
控除額を最大にするためには、所得金額に対してどれくらいの金額を寄付すればよいのでしょう。
以下の条件で所得税額1千万円〜5億円までをシミュレーションして、目安の金額を確認します。
2.資本金1億円以下
3.凍結決算を行っていない独立起業
4.標準課税率で計算
5.繰越欠損金は考慮せず
|
所得金額
|
寄附金予定上限額
|
自己負担額
|
自己負担割合
|
| 1千万円 | 103万円 | 415,772円 | 40.366% |
| 2千万円 | 206万円 | 831,543円 | |
| 3千万円 | 309万円 | 1,247,315円 | |
| 4千万円 | 412万円 | 1,663,087円 | |
| 5千万円 | 515万円 | 2,078,858円 | |
| 6千万円 | 618万円 | 2,494,630円 | |
| 7千万円 | 721万円 | 2,910,401円 | |
| 8千万円 | 824万円 | 3,326,173円 | |
| 9千万円 | 927万円 | 3,741,945円 | |
| 1億円 | 103万円 | 4,157,716円 | |
| 2億円 | 206万円 | 8,315,433円 | |
| 3億円 | 309万円 | 12,473,149円 | |
| 4億円 | 412万円 | 16,630,865円 | |
| 5億円 | 515万円 | 20,788,582円 |
上記一覧表を見るとわかりますが、自己負担割合は一律40.366%です。これは寄付金額に対して自己負担割合が4割になると、控除額が最大になるからです。
よって自己負担割合を40.366%に設定した場合の所得金額に対する寄附金の最大上限額は一覧表に掲載した金額が目安となります。
決算の時に控除の対象にするには?
決算時に控除の対象にするためには、決算最終日までに寄附金の決済が完了していることが前提です。
企業版ふるさと納税を行うメリットとは
企業版ふるさと納税を行うメリットを確認していきましょう。
企業のイメージアップが期待できる
企業版ふるさと納税を利用することで、以下のようなアピールが可能です。
・SDGs活動への取り組み
・地域に対する社会貢献
環境・社会全体への配慮を含めた取り組みを積極的に行っている点がアピールできるので、企業のイメージアップにつながるでしょう。
また積極的に参加することで企業の認知度を上げることにもつながり、効果的なPR戦略のひとつとしても期待できます。
さらに社会貢献を積極的に行っていることをアピールすることで取引先・金融機関からの好感度が高まり、新たな新規契約や有利な融資獲得も可能になるでしょう。
地方公共団体と良い関係を築ける
企業版ふるさと納税は、企業と各自治体のつながりを強化する点もメリットです。
寄附をきっかけにこれまで接点のなかった企業と自治体が連携することで、新製品の開発につながる可能性もあります。

例えばある企業は企業版ふるさと納税をきっかけに、対象となる自治体に特化した地域専用のアプリの開発を手がけました。
さらには人材派遣型を利用することで、従業員の社員教育につながった例もあります。
このようにこの制度を利用することで企業と各自治体が助け合える関係性が築ける点はメリットといえるでしょう。
地域資源を生かした新規事業を展開できる
地域資源を活かした新規事業展開が可能になる点もメリットです。
例えば、地元野菜を利用したレトルト食品・健康食品などの開発も可能でしょう。各自治体では、ほかの土地では生産が難しい野菜・果物などを栽培しているケースが多数あります。これらは知名度が低く、市場に出回らないことも多々あるため、企業が積極的にアピールすることで売上の増加につながるでしょう。
企業版ふるさと納税を行う時の注意点とは
企業版ふるさと納税を行う際の注意点を紹介します。
寄付額には要注意
企業版は個人版とは異なり、1回あたりの寄付金額が最低10万円と定められており、これを下回る金額は認められません。
一方、寄付金額の上限に規定は設けられていませんが、多額の寄付をすると対象年度の経営に影響を及ぼしてしまうリスクをはらんでいます。
適用対象外の地域があることにも注意
企業版ではふるさと納税を行う際の地域に制限が設けられており、以下に該当する地域は対象外です。
2.地方交付税の不交付団体である都道府県
3.地方交付税の不交付団体かつ地方拠点強化税制支援対象外地域の市町村
個人版とは異なり、どの自治体を選択しても対象になるわけではない点に注意しましょう。
内閣府から認定を受けてない事業も対象外
内閣府から認定を受けていない事業は、適用が認められません。その理由は企業版ふるさと納税の所管省庁が内閣府だからです。
個人版とは異なり企業版は内閣府主導のもとで実施されている制度であり、内閣府からの認定を受けている事業のみが対象として認められます。
仮に「地方創生プロジェクト」と名目を掲げていても、実際には内閣府の認定を受けていないケースもあるので、寄附を行う際には事前に確認しましょう。
企業版ふるさと納税の手続きの流れとは?
企業版ふるさと納税の手続きの流れは以下の通りです。
2.自治体に問い合わせ
3.必要書類の提出と寄附
4.受領証の受取と税額控除申請
各手順を詳しく確認していきましょう。
1.寄附先の選定をする
企業版は寄附が可能な自治体が限定されているため、慎重な選定が必要です。
地方創生推進事務局が運営する「企業版ふるさと納税ポータルサイト」にて、対象の寄附先を検索できるシステムが公開されています。「地域」「分野別」「キーワード」から検索が可能なので、目的等に合った寄附先を選定してください。
2.自治体へ直接問い合わせをする
寄附先が決まったら、次は自治体に寄附に関する問い合わせを行います。
原則として「企業版ふるさと納税ポータルサイト」に掲載されている自治体は寄附を随時受け付けていますが、突然現金を振り込まれたり送られたりしても自治体側は処理に困るでしょう。
3.必要書類の提出を行い、寄附をする
送金方法などの確認ができたら、必要書類を自治体に提出するとともに寄附を行います。
寄附金に関する申出書は、各自治体ホームページ内の関連ページにてダウンロードが可能です。例えば岩出市の場合はホームページ内の「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」のページ下部に寄附の手続き方法とあわせてPDF・WORDの申出書がダウンロードできるようになっています。
申出書以外にも提出書類がある場合は添付して提出し、寄附を行いましょう。
4.受領証を受け取り、税額控除の申請を行う
税額控除の申請を行う際には、寄附をした証明となる受領証が必要です。
必要書類の提出と寄附が完了したら、必ず自治体から受領証を受け取ってください。
企業版ふるさと納税に関するよくある質問
企業版ふるさと納税のよくある質問を紹介します。
返礼品は貰える?
企業版は個人版とは異なり、寄附を行っても返礼品はもらえません。税制優遇措置を受けるための要件のなかに、「寄附に対する経済的利益の授与禁止」が含まれているからです。
どの自治体に寄付が出来る?
企業版で寄附できる自治体には、一定の条件が設けられています。
どの企業でも税額控除を受けられる?
寄附を行う企業・会社側には特別な制限が設けられておらず、青色申告をしている企業であれば税額控除が受けられます。
国の補助金と併用することは可能?
企業版ふるさと納税は、以下のような国の補助金との併用が可能です。
・地方創生関係交付金
・農山漁村振興交付金
・過疎地域等自立活性化推進交付金
・自然環境整備交付金
(出典:地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について|内閣府地方創生推進事務局)
これらは一部であり、全部で80件の補助金・交付金との併用ができます。
まとめ
企業版ふるさと納税について解説しました。
ふるさと納税といっても個人版と企業版では所管省庁自体が異なるため、その運営方法などにも相違点が多数あります。

本記事で解説した内容を参考に企業版の知識・理解を深め、企業版ふるさと納税をご活用ください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。