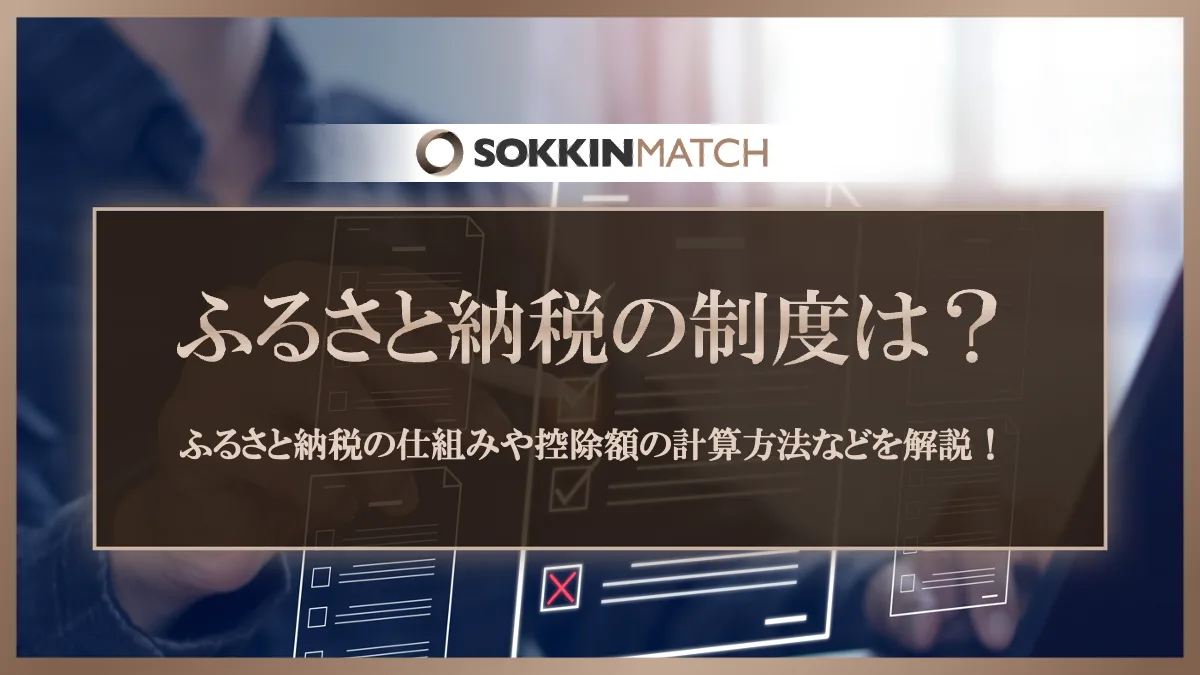所得税・住民税の節税対策の一環としても用いられることが多いふるさと納税は、2008年5月からスタートしました。さまざまな返礼品がもらえることもあり、この返礼品目当てで行っている人もいるでしょう。
しかしふるさと納税の仕組みや控除額の計算方法などがわからず、興味はあっても難しそうと不安・疑問を抱いている人もいるようです。

本記事ではふるさと納税の仕組み・控除額の計算方法などとあわせて、おすすめする人・しない人なども紹介します。
ふるさと納税とはどういう制度?
年末が近づくにつれてメディアなどで取り上げられることが多くなるふるさと納税ですが、そもそもどういう制度なのでしょう。
ふるさと納税そのものの仕組みとあわせて確認していきましょう。
応援したい自治体を選択して寄付できる制度
ふるさと納税とは、簡単に説明すると「応援したいと思う自治体を自分で選択して寄附する制度」です。
国内では地方の人口流出に伴い税収が減少する一方で、大都市では人口増加とともに税収が多くなる現象が起きています。この税収格差を小さくしようと考え出されたのがふるさと納税であり、2008年5月からスタートしました。
ふるさと納税は寄附制度のひとつであることから、利用者は寄附をしたい自治体を自分で選択して任意の金額を寄附できます。寄附をしたことで返礼品として地元の名産品が手に入る点も、この制度の魅力のひとつといえるでしょう。
またふるさと納税は確定申告を行うことで、所得税・住民税の節税対策としても利用可能です。
ふるさと納税の仕組みとは?
ふるさと納税は誰でも好きな自治体を選択して任意の金額を寄附できる制度で、寄附の金額に応じて寄附金控除の利用が可能です。
ただし控除が適用される金額は無制限ではなく、寄附金の合計額から2,000円をマイナスした金額が控除額として差し引かれます。

ふるさと納税での控除額に上限は設定されているんですか?

上限は設定されていますが、この金額は家族構成・年間所得額によって変動します。
例えば年間所得額300万円であっても、家族構成が独身と納税者を含む4人家族の場合では、ふるさと納税で適用される控除額は異なります。
ふるさと納税が可能な各サイトでは控除上限額をシミュレーションできるシステムが用意されており、年収・家族構成などの条件を入力・選択することで容易に上限額を確認することが可能です。
なお控除額の上限については後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。
ふるさと納税のメリット
ふるさと納税の主なメリットとして、以下の3つがあげられます。
・返礼品
・税金控除
それぞれのメリットを確認していきましょう。
寄付金の使い道が選べる
ふるさと納税のメリットとして、寄附金の用途選択が可能な点があげられます。
ふるさと納税で選択できる項目は、寄附する自治体・金額だけではありません。各自治体では寄附金の使用目的が明確化されており、興味・関心のある分野を選択できる点もメリットのひとつです。
例えば震災の復興支援として使用して欲しい場合は、使用目的で復興支援を選択して任意の金額を寄付すれば、ライフライン復興工事などに使用されるでしょう。

「寄附金がどのように使用されているのかわからない」「ほかのことには使用されたくない」と考える人にとっても、ふるさと納税は便利な制度といえます。
返礼品がもらえる
返礼品がもらえる点も、ふるさと納税のメリットのひとつです。
各自治体では寄付金額に応じてさまざまな返礼品を用意しており、利用者はその選択ができるように設定されています。
例えばふるさと納税の自治体として北海道夕張市を選択した場合には、返礼品のなかに夕張メロンをはじめとする特産品が含まれており、寄付金額に応じて選択が可能です。
返礼品は寄付金額の3割以内であることが多く、金額が多くなればそれだけ返礼品の選択肢が増加します。
例えばふるさと納税で7万円を寄付すると2.1万円相当の返礼品が表示され、そのなかから好きなものを選択できる仕組みです。
税金が控除される
所得税・住民税が控除される点も、ふるさと納税のメリットです。しかし無制限に控除されるわけではなく、納税者の年間所得額・家族構成によって上限が設けられているので注意してください。
またふるさと納税の控除は「所得税→住民税」の順番で実施されますが、なかには「所得税の控除は不要」「住民税だけ控除して欲しい」という人もいるかもしれません。その際にはワンストップ特例制度を利用しましょう。この制度を選択すると所得税分も含めた全額が住民税に適用されます。
なお実際の計算方法については、本記事で後ほど紹介します。
税金の控除額はどのくらい?
ふるさと納税を行うことで控除される金額は、実際に寄付した総額から2,000円を差し引いた金額です。
例えばふるさと納税で3万円を寄付した場合、2,000円を差し引いた2.8万円が所得税・住民税から控除されます。なお、所得税・住民税の控除されるタイミングは異なるので注意してください。
|
税金
|
控除されるタイミング
|
例(2020年にふるさと納税を行った場合)
|
| 所得税 | 本年度分 | 2020年度分として支払う所得税 |
| 住民税 | 翌年度分 | 2021年度分として支払う住民税 |
なおふるさと納税の控除制度にはワンストップ特例制度が設けられていますが、これは所得税の控除分も含めて住民税から控除する制度のことです。
先ほどの例を用いた場合、2.8万円が控除額として設定されますが、ワンストップ特例の使用未使用によって以下のように異なります。
|
ワンストップ特例
|
確定申告(特例未使用)
|
| 2.8万円全額を住民税から控除 | ・2.8万円の範囲内で所得税の還付 ・残額分を住民税から控除 |
控除される金額には上限がある
ふるさと納税で控除可能な金額には上限が設けられていますが、年収・家族構成によって異なり、一律ではありません。
その他の控除(配偶者控除・扶養控除等)の適用を考慮せず、自己負担額2,000円を指し日束場合の年収・家族構成による控除額の上限は以下の通りです。
|
年収
|
単身または夫婦
|
夫婦と子供(1人)
|
| 150万円 | 8,000円 | 0円 |
| 200万円 | 1.5万円 | 0円 |
| 300万円 | 2.8万円 | 1万円 |
| 400万円 | 4.2万円 | 2.5万円 |
| 500万円 | 6.1万円 | 3.9万円 |
| 600万円 | 7.7万円 | 5.9万円 |
| 700万円 | 10.8万円 | 7.7万円 |
| 800万円 | 13万円 | 10.9万円 |
| 900万円 | 15.3万円 | 13万円 |
| 1,000万円 | 18万円 | 15.4万円 |
| 1,500万円 | 38.7万円 | 36.5万円 |
| 2,000万円 | 55.3万円 | 53万円 |
| 3,000万円 | 105.2万円 | 102.6万円 |
| 5,000万円 | 207.4万円 | 204.3万円 |
| 1億円 | 433万円 | 429.9万円 |
(参考:ふるさと納税とは?仕組みとやり方を初心者向けにわかりやすく図解で解説|ふるさとチョイス)
上記一覧表の上限額はあくまで目安であり、控除制度の適用・扶養家族の人数によってこれらの金額は下がります。
ふるさと納税に対応しているサイトでは控除額上限のシミュレーションシステムを公開しているので、利用する前に上限額の確認を行ってください。
控除額の計算方法
ふるさと納税の控除額は、以下の3段階で計算されます。
2.住民税(基本分)
3.住民税(特例分)
上記の計算方法の手順は確定申告を選択した場合であり、ワンストップ特例を選択すると「1」を除いた「2」「3」のみです。
・年間所得総額:800万円
・控除上限額(目安):130万円
※寄附金は上限額全額とする
ここでは確定申告を行った場合で上記3つの計算方法を上記の条件にあてはめて確認していきましょう。
所得税の還付額
所得税の還付額を算出する際の計算式は、以下の通りです。
上記計算式の所得税の税率には、国税庁の「No.2260 所得税の税率」にて公開されている税率を使用します。今回の例では年間所得総額が800万円なので、所得税率は23%です。
所得税の還付額は298,540円と算出されました。
住民税(基本分)の控除額
住民税(基本分)の控除額を算出する際に用いる計算式は、以下の通りです。
今回の条件では上限額130万円全額を寄付しているので、この金額を上記の計算式にあてはめて算出します。
住民税のなかでも基本分の控除額は129,800円となりました。
住民税(特例分)の控除額
住民税(特例分)の控除額を算出する際には、以下の2つの計算式を用います。
2.(住民税所得割額)× 20%
「1」で算出した金額が住民税所得割の2割を超える場合には、「2」の計算式で特例分を計算し直して算出された金額を控除しなければなりません。
今回の例では住民税所得割の2割を超えないと仮定してシミュレーションしてみましょう。
上記の計算式から算出された特例分は、869,660円です。
控除額を計算するときの注意点
前項目で控除額の計算方法をシミュレーションしましたが、条件ではほかの控除制度の適用は含んでいません。
実際に所得税・住民税を計算する際にはあらかじめ設けられている控除制度を適用することから年間所得額は低くなり、ふるさと納税の控除上限額も下がります。
所得税・住民税にはさまざまな控除制度が設けられていますが、そのなかでも医療費控除・住宅ローン控除に注目してそれぞれの控除を適用する際の注意点を確認していきましょう。
医療費控除を受ける場合
所得税・住民税の計算をする際、医療費控除の適用を受ける人もいるかもしれません。
医療費控除とは、納税者本人または生計を同一とする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を200万円を上限に控除できる制度です。納税者本人だけではなく扶養している家族分も控除額に含まれることから、適用可能な納税者は多いでしょう。
控除額は実際に支払った医療費全額から受け取った保険金や10万円(所得額200万円以下の場合は所得額の5%)を差し引いた金額であり、支払済医療費によっては高額になる可能性があります。
ふるさと納税と医療費控除の併用は可能ですが、ふるさと納税の控除限度額は医療費控除などの控除を適用させた後の金額で決定するため、上限が想定よりも低くなるかもしれません。

医療費控除の適用を受ける予定がある場合は、ふるさと納税上限額のシミュレーション機能に医療費控除などの設定が可能なものを利用したほうがよいでしょう。
▼ 確定申告での医療費控除の申請方法はこちら。

住宅ローン控除を受ける場合
住宅ローン控除の適用を受ける際にも、ふるさと納税の控除上限額に影響します。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して家屋の購入・新築・増改築などをした場合に適用できる控除制度です。
住宅ローン控除は対象が家屋であることから控除額が大きくなりやすく、所得税だけでは控除しきれなかった分については住民税の控除にも適用されます。
住宅ローン控除の金額にもよりますが、状況によっては所得税・住民税の納税額がともに0円になる可能性もあり、ふるさと納税の控除が受けられない可能性は否定できません。ただし住民税の納税額が残っている場合には、ふるさと納税の控除額は自動的に住民税に充てられます。
住宅ローン控除とふるさと納税の控除の併用を行いたい場合は、それぞれの控除額などを確認しておくことが重要といえるでしょう。
ふるさと納税での注意点
ふるさと納税での注意点をいくつか紹介します。
ふるさと納税はあくまで税金の控除
ふるさと納税はあくまで税金の控除制度であり、還付金を受け取るためのものではありません。
所得税の場合、給与所得者は年末調整によって勤務先が申告・納税を行っていることから確定申告を行えば所得税の超過分を還付金として受取可能です。
しかし住民税の場合は翌年分の納税額から控除されるため、すでに支払った住民税が戻ってくるわけではありません。
手元の資金に余裕があるときに行う
ふるさと納税は資金に余裕がある際に行いましょう。
ふるさと納税は自治体に寄付をする行為であり、各サイトで返礼品を選択して受け取る際にはいったんお金を支払わなければなりません。
例えば1万円の返礼品を受け取る際にはいったん1万円を支払います。その後、確定申告等を行い、2,000円をマイナスした8,000円分が所得税または住民税の納税額から控除される仕組みです。
ふるさと納税の利用では、現実的な支出が伴う点を忘れないでください。
ふるさと納税をした方がいい人の特徴
ふるさと納税は誰でも手軽に各自治体に寄附ができる制度ではありますが、おすすめできる人には以下のような共通点があります。
・特定の自治体を応援したい場合
・欲しい返礼品がある場合
それぞれの特徴を確認していきましょう。
控除限度額が7,000円を超える人
ふるさと納税が可能な各サイトでは控除限度額のシミュレーションが公開されており、年間所得額・家族構成に応じた上限額を調べることが可能です。
この上限額が7,000円を超えた場合には、ふるさと納税で選択できる返礼品が寄付金額の3割を上回るので、損をすることはありません。
ただし控除限度額7,000円程度では選択できる返礼品の数が少なく、金銭的なメリットの享受も多くないでしょう。
決まった自治体を応援したい人
特定の自治体を応援したい人は、ふるさと納税をするとよいでしょう。
返礼品のなかには、寄附金の選択肢を限定したうえでの寄附ができるものもあります。子どものボランティア・震災の復興支援など、応援したい自治体で目的にあった使い道を選択して寄附すれば、その寄附金は意図した用途に回してもらえるでしょう。
ほしい返礼品がある方
欲しい返礼品がある場合は、ふるさと納税をおすすめします。
返礼品の選択肢のなかには通常では入手困難なものも多く含まれており、ふるさと納税をすれば比較的容易に手に入るでしょう。
ふるさと納税でしか入手できない限定品ともなると、寄附金の金額はそれなりに高く設定されています。しかし金銭的なメリットや節税対策とは切り離して返礼品目的で寄附を行う場合は、損をしたと感じることも少ないでしょう。
ふるさと納税をしない方がいい人の特徴
ふるさと納税をしたほうがいい人の特徴を紹介しましたが、反対にしないほうがいい人もいます。しないほうがいい人に共通する主な特徴は、以下の通りです。
・資金に余裕がない人
・手続きを面倒に感じる人
それぞれの特徴を確認していきましょう。
収入が少ない人
収入が少ない人はふるさと納税をおすすめしません。年間所得額が少ない場合、所得税・住民税の支払義務が免除される可能性があるからです。その場合、ふるさと納税の返礼品をお金を出して購入することにしかならないため、金銭面でのメリットが享受できません。
また仮に所得税・住民税の支払義務が発生する年間所得額であったとしても、選択できる返礼品が限られてしまい、通常で購入したほうが特になる可能性もあります。
資金に余裕がない人
資金に余裕がない人も、ふるさと納税はやめておいたほうがよいでしょう。
ふるさと納税の注意点でも解説しましたが、この制度はあくまで各自治体に寄附をすることが目的であり、いったん支出しなければなりません。
正しい手続きをすれば所得税の還付金や住民税の納税額減額などで寄附金の一部は戻されますが、2,000円は自己負担です。
ふるさと納税は強制的なものではなく、資金にゆとりのある人が手軽に寄附ができる制度である点を考慮してください。
手続きが面倒な人
手続きを面倒に感じる人は、ふるさと納税はやめておいたほうがよいでしょう。
ふるさと納税にはワンストップ特例と確定申告の2種類がありますが、いずれも正しい手続き・申告を行わなければ税金の控除が行われません。
「会社の年末調整しか受けたことがない」「確定申告をしたことがない」などに該当する場合、手続きの方法が理解できずに誤った内容で申告をして控除が認められない可能性もあります。
節税対策として利用されることも多いふるさと納税ですが、その手続きは決して簡単なものではないので、面倒に感じる人・慣れない人はおすすめしません。
よくある質問
ふるさと納税に関するよくある質問を確認していきましょう。
税金の控除を受けるためには?
ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、ワンストップ特例と確定申告のいずれかを選択しなければなりません。
ワンストップ特例を利用する場合の主な手順は以下の通りです。
・ふるさと納税を行う自治体に「ワンストップ特例制度の申請書」を提出
・翌年度分の住民税の納税額から控除
ただしこの特例を利用する際には以下の条件を満たさなければなりません。
・年間の寄附金先が5自治体以下
・寄附した翌年1月10日までに申請書を提出
いずれかひとつでも該当しない場合は確定申告が必要なので注意してください。
確定申告でふるさと納税の控除を受ける場合の手順は以下の通りです。
・ふるさと納税を実施
・確定申告を行う
・ふるさと納税を実施した年度分の所得税を控除または還付
・翌年度分の住民税の納税額から控除
確定申告の期限は原則として2月16日〜3月15日までなので、この法定期限内に申告書を提出しましょう。
▼ 確定申告のやり方について詳しく知りたい方はこちら。

税金の控除が適応される時期は?
税金の控除が適用されるタイミングは、所得税・住民税によって以下のように異なります。
・住民税:翌年度分
例えば2021年12月31日までにふるさと納税を行ったとしましょう。所得税は2021年度分から控除されるため、年末調整などで先に支払っている場合は還付されます。
一方の住民税は2022年6月から支払う住民税納税額から控除されるため、還付金は発生しません。
まとめ
ふるさと納税について解説しました。
誰でも手軽に好きな自治体に寄附ができる制度ではありますが、控除の適用を受ける際には正しい手続きを行わなければなりません。

また年間所得額・家族構成によっては必ずしも得をするわけではないので、その点も注意して利用するかしないかを判断しましょう。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。