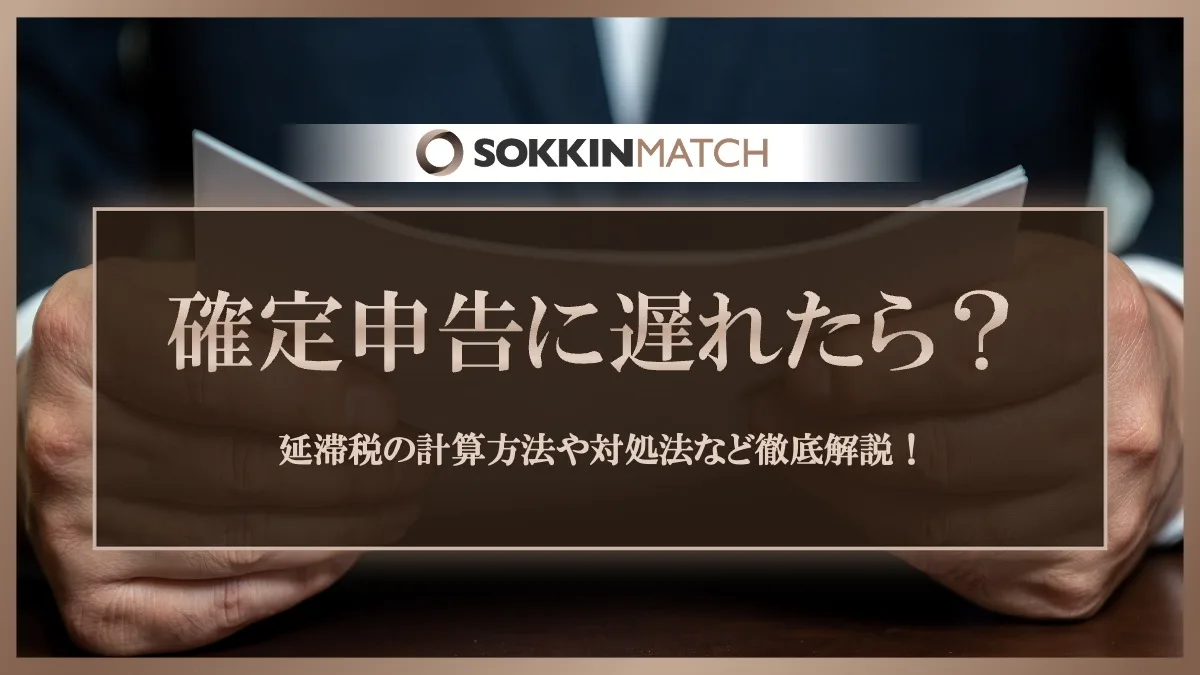確定申告は毎年ほぼ同時期に期間が決められており、その期間内に申告と納税の両方を完了させなければなりません。
しかし「確定申告を忘れていた」「特別な事情で期限内に申告できなかった」という場合、どのように対応すればよいのでしょう。

本記事では、確定申告が遅れた場合の対処法・ペナルティ・延滞税の計算方法などを解説します。最後までご覧いただき、期限内に確定申告をする重要性や対処法の理解・知識を深めてください。
期間は毎年2月16日~3月15日
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日〜3月15日までの1カ月間です。ただし2月16日や3月15日が土日に重なった場合、翌平日にずれ込みます。
申告期間は単に確定申告の申請書を作成して提出するだけではなく、所得税の納付もしなければなりません。提出して完了ではないので、注意してください。
なお申告書等の提出方法は、以下の通りです。
・税務署の窓口
・郵送
・時間外収受箱
e-Taxは24時間365日対応可能であることから、税務署の開庁日時に縛られたくない場合には利便性が高いでしょう。
確定申告に遅れた時のペナルティ
確定申告が遅れた場合、以下のようなペナルティが発生します。
・無申告加算税
・青色申告特別控除額の引き下げ
それぞれのペナルティを解説するので、参考にしてください。
延滞税が課せられる
延滞税とは、法定期限内に税金を納付しなかった場合に発生する罰金です。
確定申告の期限は所得税の申告だけではなく、納税額が発生する場合には納付も完了しなければなりません。確定申告が必要であるにもかかわらず期限内に行わなかった場合には納税も遅れることになるため、必然的に延滞税も発生します。
延滞税を算出する際に使用する税率は以下の通りです。
|
完納時期
|
原則税率(年率)
|
| 2カ月以内 | 7.3% |
| 2カ月超 | 14.6% |
法定期限の翌日を起算日として2カ月を境に、上記のように原則税率が変わります。
なお、延滞税を求める計算式は以下の通りです。
上記の計算式で算出された金額の1万円未満は切り捨てと定められており、1万円以下の場合は課税されません。
無申告加算税が課科せられる
無申告加算税とは、法定期限内に確定申告が必要であるにもかかわらず行わなかった場合に発生する罰金です。
財務省では罰金が発生する具体的な要件として、以下のような点を挙げています。
・期限後申告
・期限後申告での修正・更正
・所得金額の決定
(参考:加算税の概要|財務省)
無申告加算税を算出する際に使用する税率は以下の通りです。
|
増差本税(納税額)
|
課税割合(税率)
|
| 50万円以下 | 15% |
| 50万円超300万円以下の部分 | 20% |
| 300万超の部分 | 30% |
(参考:加算税の概要|財務省)
加算税を計算する際の税率は納税額の枠によって上記のように異なっており、一律ではありません。
青色申告特別控除が10万円に引き下げられる
青色申告特別控除とは、確定申告で青色申告を行う事業者を対象にした特別控除です。
控除額は65万円・55万円・10万円の3つありますが、65万円と55万円のいずれかの控除を受ける際には国税庁にて定められている要件を満たさなければなりません。
この要件のなかに「法定期限内の申告」があり、確定申告が期限内にできずに遅れてしまうと10万円に引き下げられてしまいます。
白色申告にはこのようなメリットはないので、継続して事業活動を行う場合は青色申告を行ったほうがよいでしょう。
▼ 青色申告の申請方法が知りたい方はこちら。
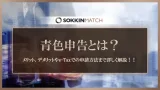
確定申告が遅れそうなときの対処法
確定申告が遅れそうなときは、以下のような方法がおすすめです。
・確定申告期限延長の申請
・延納の申請
各対処法の要件・手続きの方法などを解説するので、参考にしてください。
納税の猶予申請書を提出する
納期限までに国税の納付が難しい場合には、猶予申請書を提出して猶予制度の適用を受けることをおすすめします。
猶予制度は以下の要件に該当すると利用可能です。
・災害等による財産の消失
・納税者本人または生計を同一とする配偶者やその他の親族が病気を発症
・やむを得ない休廃業
(参考:猶予の申請の手引|税務署)
納税の猶予制度を受けるためには、税務署に必要書類を提出しなければなりません。
・猶予該当の事実を証明する書類などを用意
・税務署に申請書を含む必要書類を提出
・税務署にて提出書類をもとに審査
・申請者に猶予通知書を送付
(参考:猶予の申請の手引|税務署)
ただし申請書や事実を証明する書類などを税務署に提出したからといって、必ず猶予が認められるわけではありません。上記の手順は許可された場合であり、不許可の場合はその旨を知らせる通知書が届きます。
確定申告期限延長を申請する
確定申告期限延長とは、以下に該当する理由により期限内申告が困難になった納税者の救済措置です。
・人為的な災害
・自己に帰さないやむを得ない事実
延長を申請する際は、以下の手順で行います。
2. 申請書に必要事項を記入
3. 管轄する税務署に提出
上記は紙の申請書で申請する場合の手順であり、e-Taxでも申請可能です。
延長が認められた場合には無申告加算税などは発生しませんが、延長期間の利子税は納付しなければなりません。
延納を申請する
延納とは、所得税の納付が困難と事前にわかっている場合に利用可能な制度です。
確定申告を行う際に作成する申告書の第一表には「延納の届出」という欄が設けられています。
|
項目名(項目番号)
|
記入内容
|
| 申告期限までに納付する金額(64) | 納期限内に納付する金額を明記 |
| 延納届出金額(65) | 延納したい納税額を明記 |
なお期限後に確定申告をする際にも申請書を提出するので、上記の一覧表の項目に必要事項を記入しましょう。
ただしこの制度を利用する際には、以下の点に注意してください。
・延滞期間中は利子税が発生する(7.3%または特例基準割合のいずれか)
少なくとも納期限内に納税額の半分は納付しなければならず、それ以下の金額は認められません。
また、延滞中は原則税率7.3%または特例基準割合のいずれかの税率をかけた利子税が発生します。利子税は自分で計算する必要はなく、税務署から利子税分の納付書が届くので金融機関等に納付しましょう。
確定申告期限後の修正も罰則対象
期限後申告で罰則が課せられるのは、初回分だけではありません。
例えば法定期限内に申告・納税ともに完了させていたとしましょう。期限後に申告に誤りがあることが判明して修正した場合、その内容によっては罰則が課せられます。
また、納税額が発生する場合と還付金が発生する場合とでは手続きの方法が異なる点も注意しておいたほうがよいでしょう。
税額の過少申告・過大申告の修正方法と罰則について解説するので、参考にしてください。
税額の過少申告の場合
税額が本来の納税額よりも少なかった場合は過少申告となり、以下の手順で修正申請を行います。
2. 第一表の「〇〇年分」に修正する年度、「〇〇申告書」は「修正申告書」と明記
3. 「種類」の欄は「修正」に丸印
4. 正しい金額で申告書を作成
5. 「修正申告」欄の「修正前第3期分の税額(53)」に修正する前の申告税額を記入
6. 「修正申告」欄の「第3期分の税額の増加額(54)」に本来の納税額と(53)の差額を記入
7. 第二表の「特例適用条文等」の欄に修正申告発生理由を明記
上記手順5〜7は、最初に作成した内容と異なる部分です。正しい金額で再作成したうえで、5〜7の項目にも追記してください。
なお過少申告をすると原則として延滞税とあわせて、「過少申告加算税」または「重加算税」が課せられます。
それぞれの罰金について、詳しく確認していきましょう。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告・納税した税金の金額が本来の税額よりも少なかった場合に課せられる罰金です。
加算税を計算する際に使用する税率は、以下の2通りあります。
|
条件
|
税率(年率)
|
| 原則 | 10% |
| 期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分 | 15% |
ただし、本来の納税額よりも少なく申告したからといって必ず過少申告加算税が課せられるわけではありません。以下の要件を満たす場合には、免税または減税対象です。
|
要件
|
税率(年率)
|
| 税務調査前の自主的なものであり、更正を予知しない修正申告の場合 | 課税対象外 |
| 税務調査を受けたうえでの期限後修正申告であり、更正を予知しないもの | ・原則は5%
・期限内申告額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10% |
さらに無申告加算税の金額が5,000円未満の場合は、切り捨て処理することが国税通則法(第119条4項)に明記されています。よって4,999円以下の場合は加算されません。
重加算税
重加算税とは、意図的な隠ぺい・仮装が認められる場合に課せられる罰金であり、さまざまな種類がある加算税のなかでは最も重い罰則です。
重加算税はほかの加算税に代えて課せられる罰則であり、その加算税によって使用する税率が以下のように異なります。
|
加算税
|
税率(年率)
|
| 過少申告加算税 | 35% |
| 無申告加算税 | 40% |
(出典:加算税の概要|財務省)
本来なら上記の加算税であっても、状況等が悪質と税務署によって判断された場合には重加算税として各税率をかけて計算した罰金が課せられるので注意してください。
税額の過大申告の場合
本来の納税額よりも申告額が多かった場合は過大申告となり、以下の手順で更正の請求を行います。
2.更正の請求の根拠となる証明書類の準備
3.本人確認書類のコピーを添えて税務署へ提出
先述した過少申告との違いは、過大申告の修正で行う更正の請求では新たに確定申告書類を作成しない点です。
期限内に過大申告の修正を行う場合は、正しい内容で申告書類を作成して提出すれば完了しますが、期限後の更正の請求では申告書を作り直す必要はありません。「1」の請求書が代わりになるからです。
還付申告と更正の請求
納めすぎていた税金を返金してもらう手続きには「還付申告」と「更正の請求」の2種類がありますが、これらは厳密には同一ではありません。
|
請求方法
|
対象
|
| 還付申告 | 確定申告義務がない場合 |
| 更正の請求 | 確定申告と納税を完了させた場合 |
更正の請求方法等については先述したので、還付申告の方法などを確認していきましょう。
還付申告
還付申告とは、確定申告の義務がない人が超過分の税金を還付してもらう際に行う手続きです。
還付申告を行う際には以下の必要書類を準備して作成しなければなりません。
・控除証明書
・本人確認書類
確定申告と同様の申告書作成・添付書類の準備などの手続きを行うことが原則です。
還付の時期については、提出方法や申請する時期によって以下のように異なります。
|
手続き方法
|
確定申告期間中
|
確定申告期間外
|
| e-Tax | 3週間程度 | 3週間程度 |
| 紙媒体(窓口提出・郵送) | 1~1カ月半 | 1~2カ月程度 |
更正の請求同様に還付申告の期間に縛りはありませんが、還付発生年の翌年1月1日を起算日として5年以内に行わなければなりません。
▼ 確定申告の還付金について詳しく知りたい方はこちら。

消費税の確定申告
課税事業者は所得税とあわせて消費税の確定申告も必要です。課税事業者とは消費税の納税義務が発生する法人・事業主のことであり、具体的な要件は以下のように定められています。
・特定基準期間の売上高が1,000万円以上
・適格請求書発行事業者の登録済
なお課税基準期間と特定基準期間は法人・個人事業主によって以下のように異なり、同一ではありません。
|
意味
|
個人事業主
|
法人
|
|
|
基準期間
|
課税事業者・免税事業者・簡易課税制度の適用の可否などを判断する期間のこと | 前々年1月1日~12月31日 | 前々事業年度(1月1日~12月31日または4月1日~3月31日) |
|
特定期間
|
「平成23年度税制改正:で新たに創設された納税義務判定の期間 | 前年1月1日~6月30日 | その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間 |
(出典:消費税課税事業者届出書|国税庁、特定期間の判定|国税庁)
申告期限
消費税の申告期限は、個人事業主と法人で以下のように異なります。
|
区分
|
申告期限
|
| 個人事業主 | 課税期間翌年の3月31日 |
| 法人 | 課税期間終了日翌日から2カ月以内 |
個人事業主は明確に申告期限が定められていますが、法人の期限はあいまいであるため、不自然に感じる人もいるかもしれません。これは課税期間が異なるからであり、個人事業主は1月1日〜12月31日です。
一方の法人は課税期間が1月1日〜12月31日のところもあれば4月1日〜翌年3月31日のところもあり、同一ではありません。そのため申告期限を個人事業主のように限定することが難しいことから、課税期間終了日翌日から2カ月以内としています。
必要書類
消費税の還付金を受け取る際に必要な書類は、以下の通りです。
|
必要書類
|
内容
|
| 消費税及地方消費税の確定申告書 | 消費税用の確定申告書 |
| 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書 | 課税売上高・課税仕入税額などを記載 |
| 消費税の還付申告に関する明細書 | ・還付申告理由 ・取引先ごとの売上、仕入の明細など |
それぞれの必要書類の記入方法を解説するので、参考にしてください。
▼ 消費税の還付金についてより詳しく知りたい方はこちら。

1.確定申告書の記入
確定申告書には、事業者の基本情報と計算した消費税の金額などを記載します。
還付申告の場合は確定申告書第一表の「消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額(26)」の欄に記入する金額の前に「-(マイナス)」をつけることを忘れないでください。
また第一表の「還付を受けようとする金融機関等」に、還付金を振り込むための金融機関情報を明記します。
銀行・信用金庫などへの振込を希望する場合は、金融機関名と本店・支店・出張所などの名称を明記し、「預金」と「口座番号」にも必要事項を記入します。
ゆうちょ銀行を希望する場合は、「ゆうちょ銀行の貯金記号番号」と「郵便局名称等」の各項目に記入しましょう。
2.明細書の記入
「消費税の還付申告に関する明細書」は還付を受ける際に重要な書類であり、必ず必要事項を記入して提出しなければなりません。
「還付申告となった主な理由」には主な選択項目が2つありますが、いずれにも該当しない場合は「その他」に丸印をつけてカッコ内に具体的な内容を明記します。
「課税売上等にかかる事項」の「(1)主な課税資産の譲渡等」には、すべての内容を明記する必要はありません。明細書にも書かれていますが、取引金額が100万円以上の上位5積までの取引を金額が高い順に記載します。
「課税仕入れにかかる事項」の「(1)仕入金額等の明細」には所得区分に該当する欄に仕入金額や必要経費などの金額を記載しますが、事業所得・不動産所得のいずれにも該当しない場合は「所得」のみが書かれた欄を利用してください。その際「所得」のうえにどのような所得なのかも、忘れず記入しましょう。
詳しい書き方は、国税庁が「消費税の還付申告に関する明細書の記載例」を法人用と個人事業主用の2種類にわけて公開しています。実際に金額が入った記載例を公開しているので、こちらを参考にしてください。
kojin_youshiki3.計算表の記入
「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」は、課税・免税のそれぞれの売上高などから課税売上割合や控除対象仕入税額を計算するための申告書です。
計算する際には1円未満の端数が出る可能性がありますが、これらはすべて切り捨てて計算します。
(1)~(26)の各項目に該当する場合にそれぞれ金額を記入しますが、仕入れ対価の返還(値引き、割引など)があった場合は「課税仕入れにかかる支払対価の額(税込)(9)」と「特定課税仕入れにかかる支払対価の額(11)」に返還した分をマイナスした金額を記載しましょう。
計算表を作成する際の注意点などは、国税庁の「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」に添付されている「記載要領等」を確認してください。
2-34.税務機関に提出
前述した3つの書類作成が完了したら、以下のいずれかの方法で税務署へ提出します。
|
提出方法
|
内容
|
| 税務署へ直接提出 | ・管轄する税務署へ持参 ・開庁日時に注意 |
| 税務署へ郵送 | ・管轄する税務署あてに郵送 ・郵便代がかかる点に注意 ・提出期限ぎりぎりに郵送すると間に合わない可能性有 |
| e-Taxによる電子提出 | ・事前に利用者識別番号や暗証番号等の取得が必要 ・確定申告書等作成コーナーや申告書類作成ソフトなどを利用した場合に便利 |
確定申告期限後の提出と納付
法定期限後の確定申告に関連する書類の提出・納付は、期限内と同様です。
ただし期限後に申告書類等を提出しても、その方法によっては期限内提出として処理されるかもしれません。
期限後の提出・納付の方法や注意点などを解説するので、参考にしてください。
3月16日税務署開庁時間までに時間外収受益箱に提出する
全国の税務署には「時間外収受箱」が設置されており、開庁日時以外に申告書類等を提出する場合はこのBOXに投函します。
時間外収受箱に提出すると翌日3月16日の回収までは期限内として認められるので、申告義務のある人が期限後申告した場合に課せられる無申告加算税の対象にはなりません。
納税額によっては延滞税もかからない可能性もありますが、実際に計算してみないとわからないので発生することを想定しておいたほうがよいかもしれません。
3月15日の23時59分までにe-Taxで提出する
税務署の窓口提出期限は3月15日17時までですが、e-Taxの場合は23時59分まで期限内提出が可能です。
例えば「税務署の開庁時間(17時)までに窓口提出が難しい」「郵送では明らかに間に合わない」などのケースに該当する場合は、e-Taxで提出するとよいでしょう。
ただしe-Tax提出には事前に登録・準備などが必要であり、誰でも可能な方法ではありません。
税務署の窓口で提出しよう!
税務署の窓口で提出する場合は、開庁日時にあわせなければなりません。開庁日時は平日8時30分〜17時までです。法定申告期限を過ぎても提出は受け付けてもらえますが、土日祝は閉庁しているので注意してください。
期限後に申告書・添付書類などを窓口に提出する場合、納付もしなければなりません。期限後提出の納期限は、提出した当日に自動設定されるからです。
国税庁では延滞税の計算ツールのみ「延滞税の計算方法」にて公開しているので、これを利用するとよいでしょう。
▼ 無申告加算税の仕組みについては、こちら。

郵送やe-taxで提出する場合は注意が必要
郵送で提出する場合は、申告書・添付書類などを同封して管轄する税務署あてに送付します。
一方のe-Taxの提出方法は、オフラインソフト・オンライン・スマホアプリのいずれかから電子保存した申請書・添付書類を送信すれば完了です。
まとめ
確定申告が遅れた場合の延滞税や対処法などを解説しました。
確定申告には法定期限が設けられており、この期間内に申告・納税の両方を完了させることが原則です。遅れると延滞税・加算税・控除額の減額など、さまざまなペナルティが科せられます。
本記事を参考に対処法なども念頭におきつつ、期限内に済ませることを心がけてください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。