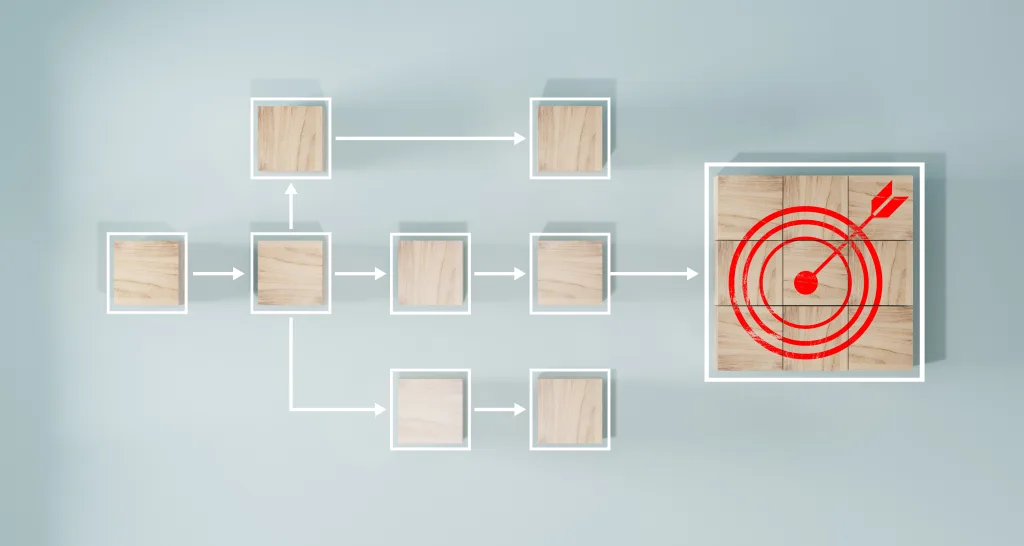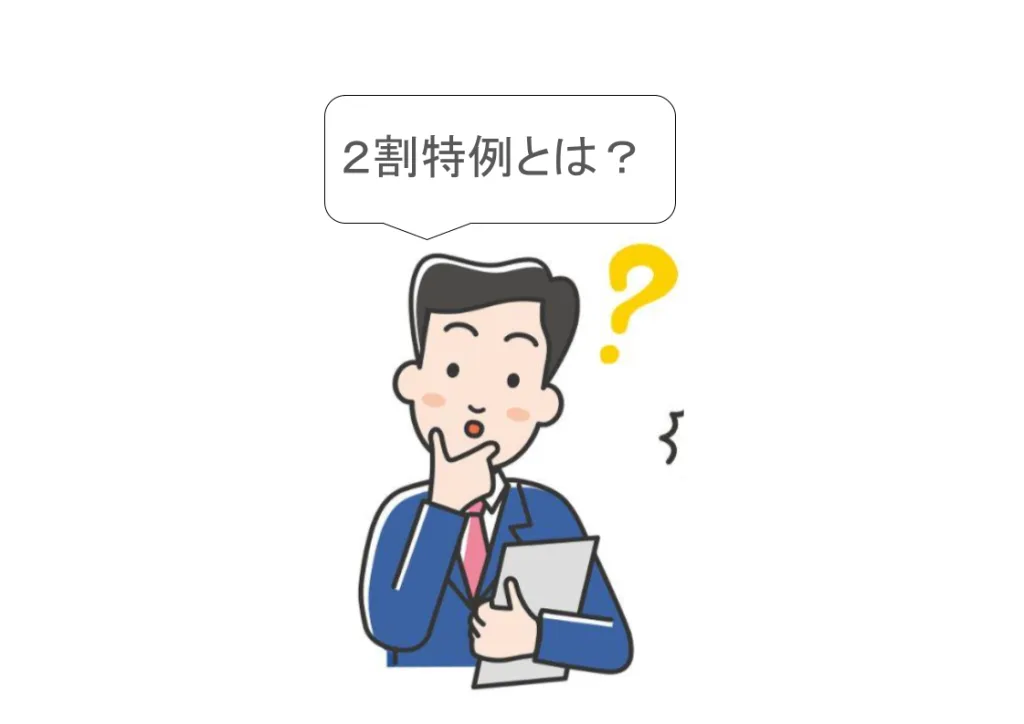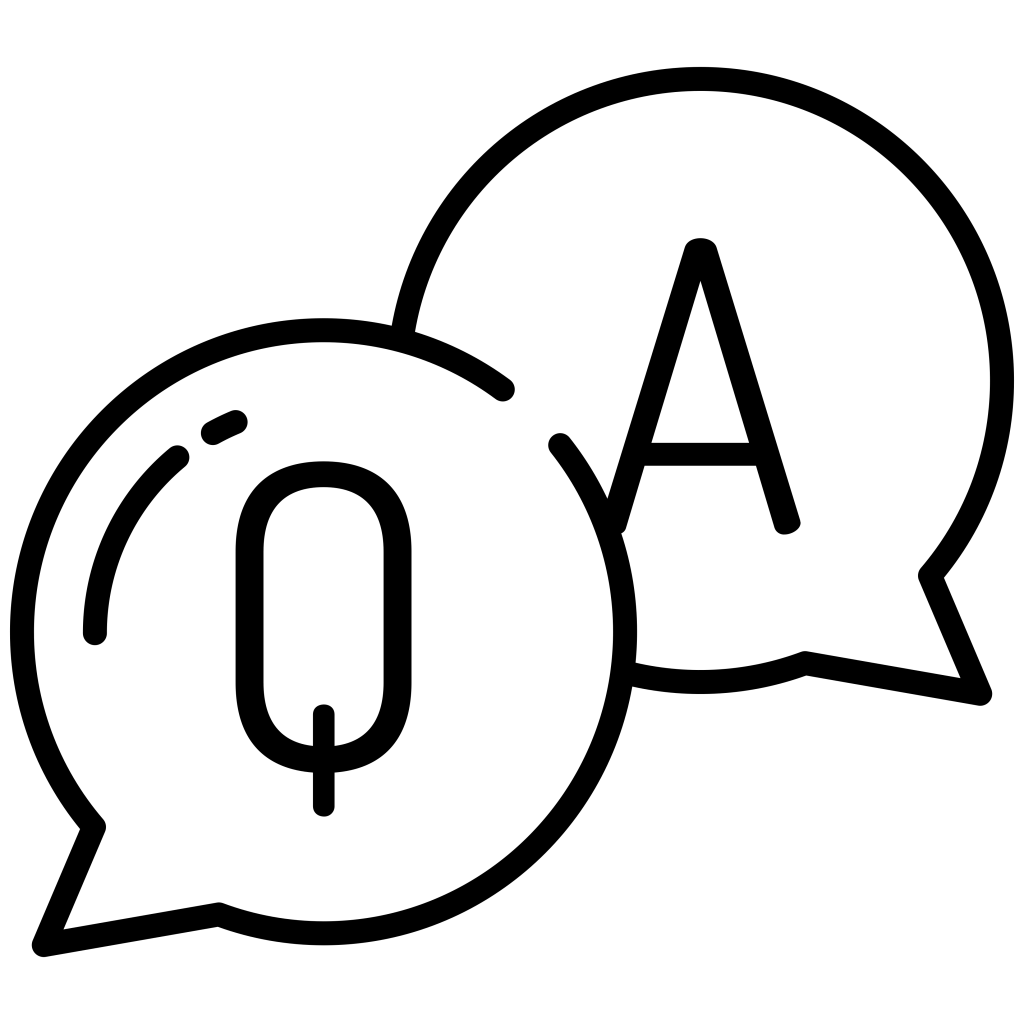標準税率と軽減税率の2通りによる消費税の運用開始を受けて、インボイス制度がスタートしました。
メディアではインボイス制度が開始されるためにさまざまなところで影響があると報道していたため、なかには確定申告にも影響があるのではと不安を抱えている人もいるかもしれません。インボイス制度の導入に伴い、確定申告には何らかの影響を受けるのでしょうか。

本記事ではインボイス制度全般とあわせて、白色申告・青色申告や消費税の確定申告も解説します。インボイス制度による影響の範囲・内容の知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)に基づいて消費税を計算する仕入税額控除の方法です。
仕入税額控除とは消費税の確定申告時に適用される控除制度であり、この制度の適用を受けることで納税額が抑えられます。消費税の申告・納税義務が発生する事業者にとっては、重要な節税対策のひとつといえる控除制度です。
インボイス制度の導入により、仕入税額控除の適用条件が変更になりました。簡単に解説するとインボイス(適格請求書)が発行された取引のみが仕入税額控除の対象です。しかしインボイス(適格請求書)として認められる請求書は、以下の項目を掲載していなければなりません。
・税額ごとの適用税率および合計額
・税額ごとの合計消費税額等
上記3つの項目が明記された請求書のみに仕入税額控除の適用範囲が限定された制度をインボイス制度といいます。
▼ インボイス制度について詳しく知りたい方はこちら。

インボイス制度によって消費税の確定申告が変わる
インボイス制度の導入に伴い、大きく変更されたのは消費税の確定申告です。
インボイス制度に基づく適格請求書は課税事業者しか発行できません。課税事業者は消費税の申告・納税が必要な事業者であることから、必然的に消費税の確定申告が必須です。
なお確定申告には消費税以外に所得税もありますが、こちらは年間所得総額に課せられる税金のための申告・納税であり、関係ありません。
消費税の課税事業者への影響
インボイス制度の導入は、消費税の申告・納税義務が発生する課税事業者に影響を及ぼしますが、すべての課税事業者に対して影響があるわけではありません。
計算方法には簡易課税と本則課税の2種類がありますが、影響があるのは本則課税を導入している事業者です。
本則課税によって消費税の経理処理をしている場合、適格請求書(インボイス)以外の請求書・領収書は仕入税額控除の対象になりません。
2.特定期間の課税売上高5,000万円以下
上記条件の基準期間・特定期間は事業形態によって以下のように異なります。
|
事業形態
|
基準期間
|
特定期間
|
| 個人事業主 | 対象年の前々年 | 対象年前年の1~6月 |
| 法人 | 対象事業年度の前々事業年度 | 対象事業年度の前事業年度の上半期 |
消費税の免税事業者への影響
消費税免税事業者のインボイス制度導入による影響はありません。免税事業者は消費税の確定申告・納税の義務が発生しないからです。
ただし取引先によっては仕入税額控除の対象から外れてしまうため、取引終了の申し出があるかもしれません。仕入税額控除の対象外になると取引先の負担額が大きくなってしまうため、取引終了または課税事業者への変更依頼をされる可能性があります。
免税事業者から課税事業者になった場合
インボイス制度導入に伴って免税事業者から課税事業者になった場合、消費税の申告・納税義務の対象です。
原則として消費税の計算方法は本則課税・簡易課税のいずれかですが、インボイス制度導入による新規課税事業者については以下の要件を満たすことで2割特例が適用されます。
・2023年10月1日以降に新規課税対象事業者
・2021年分および2022年4月~6月の課税売上高が1,000万円以下
・課税期間短縮適用外
・一般課税および簡易課税の申告対象外
(参考:インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート|国税庁)

上記の要件をすべて満たした場合にのみ適用が認められており、売上税額の20%に軽減される一時的な特例措置です。
課税事業主と免税事業主の違い
課税事業者と免税事業者の主な違いを一覧表にして確認してみましょう。
|
事業者
|
概要
|
| 課税事業者 | ・基準期間または特定期間内の課税売上高1,000万円以上 ・消費税の申告や納税義務が発生 ・インボイス(適格請求書)の発行が可能 |
| 免税事業者 | ・基準期間と特定期間いずれも課税売上高1,000万円未満 ・消費税の申告や納税義務が不要 ・インボイス(適格請求書)の発行不可 |
インボイス制度で個人事業主(フリーランス)が知っておくべき白色申告と青色申告とは?
個人事業主(フリーランス)として年間所得が一定額を超えると、所得税の確定申告が必要です。この確定申告には青色・白色の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
インボイス制度は消費税に関連した制度であることから、所得税における確定申告には直接影響がありません。

しかし、なかには所得税の確定申告と消費税の確定申告を混同する人もいるようなので、ここでは白色申告・青色申告について触れておきましょう。
白色申告とは?
白色申告とは確定申告の方法のひとつで、青色申告の承認を受けていない場合は自動的に白色申告に分類されます。
なお確定申告時に必要な提出書類は以下の通りです。
・収支内訳書
・第三表(譲渡所得がある場合のみ)
「収支内訳書」はインボイス制度の導入に伴い、「仕入金額の明細」という項目が追加されており、様式が変更されました。
白色申告で確定申告を行っていた場合は、収支内訳書の様式が変更されている点に留意してください。
白色申告のメリット
白色申告の主なメリットは以下の通りです。
・シンプルな申告手続き
白色申告を用いる場合、記帳は簡易簿記が認められています。帳簿に明記する内容・項目は「取引年月日」「勘定科目」「金額」のみであり、複式簿記のように借方・貸方にわけて記帳する必要はありません。
白色申告のデメリット
白色申告のデメリットは以下の通りです。
・青色事業専従差給与の制度なし
・純損失の繰越・繰戻不可
・少額減価償却資産の特例なし
・貸倒引当金の一括計上不可
白色申告のデメリットの代表としてあげられるのは、特別控除がない点でしょう。青色申告の場合は特別控除が設けられており、青色申告を選択するだけで一定金額が年間所得額から控除されます。白色申告にこのような制度がない点は、さまざまなデメリットのなかでも代表的なものといえるでしょう。
また、純損失の繰越・繰戻ができない点もデメリットです。損失分は対象年でしか処理できないため、赤字決算の翌年に利益が出たとしても相殺できません。節税対策ができないので、デメリットに感じる人がいるでしょう。
▼ 白色申告のメリット、申請方法について詳しく知りたい方はこちら。

青色申告とは?
青色申告とは、個人事業主・フリーランス・法人など本格的に事業活動をしている場合に用いられることが多い確定申告の方法のひとつです。
その理由は白色申告と比較して青色申告のほうがメリットが多いからです。
継続して事業活動を行っていくことは、それだけ年間所得額が大きい点があげられます。所得税は年間総所得額に比例して増加するため、所得額が増えれば納税額も比例して高額になり、支払いが困難になるなどの状況が起こるかもしれません。
可能な限り納税額を抑えたいと思う人は一定数存在しており、青色申告はその節税対策の一環として適用できる制度・特例などが用意されています。
具体的にどのようなメリットがあるのか、デメリットとあわせて以下の見出しで確認していきましょう。
青色申告メリット
青色申告の主なメリットは以下の通りです。
・赤字の繰越・繰戻が可能
・青色事業専従者給与の制度あり
・少額減価償却資産の一括計上が可能
・貸倒引当金の一括計上が可能
青色申告の代表的なメリットとしてあげられるのは「青色申告特別控除」であり、10万円・55万円・65万円の3パターンが用意されています。
55万円・65万円の控除適用を受ける際にはe-Tax申請必須や帳簿の電子保存など、細かな条件が設けられており、それらをすべて満たさなければ認められません。しかし10万円控除は青色申告を行えば自動的に適用されるため、お得な制度といえるでしょう。
それ以外にも赤字の繰越・繰戻ができる点もメリットとしてあげられます。

赤字決算の翌年の収益が黒字だった場合、前年の赤字分を黒字分と相殺できるので年間総所得額を抑えることが可能です。年間総所得額が低くなれば比例して所得税の納税額も抑えられるので、節税対策として役立ちます。
青色申告のデメリット
青色申告の主なデメリットは、主に以下の2つです。
・複式簿記による記帳が必須
青色申告を行う際には、管轄する税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。青色申告を行う年の3月15日までに提出すれば適用されるので、確定申告の書類とあわせて提出しましょう。
また青色申告特別控除のなかでも55万円または65万円の適用を受ける場合は、複式簿記による記帳が必須条件です。複式簿記は借方・貸方にわけた記帳方法であり、貸借対照表や損益計算書も作成しなければなりません。簿記・経理などの知識に乏しい場合は、これらの記帳・作成に困難を感じる人もいるでしょう。
▼ 白色申告のメリット、申請方法について詳しく知りたい方はこちら。
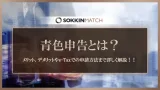
白色・青色申告の際に生じる個人事業主への影響
白色・青色申告ともに個人事業主におけるインボイス制度導入の影響を確認していきましょう。
免税事業者のインボイス制度対応による手取り収入の減少
免税事業者の場合、インボイス制度の導入に伴って収入が減少する可能性があります。その理由は課税事業者への変更に伴い、消費税の申告・納税義務が発生するからです。
インボイス(適格請求書)を発行するためには、課税事業者へ変更するとともに適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。課税事業者は必然的に消費税の申告・納税義務が発生するため、これまで受取済消費税を収入の一部として計上できていた免税事業者は収入が減少してしまいます。
免税事業者の場合、仕事の受注が減少してしまうリスクがある
免税事業者のままで事業活動を継続すると、仕事の受注が減少するリスクが高まるので注意が必要です。
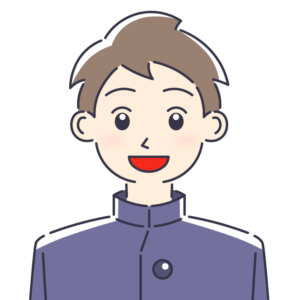
なんで仕事の受注が減少するリスクが高まるんですか?

免税事業者のままではインボイスの発行は認められず、仕事を依頼する側にとっては仕入税額控除の対象外の取引であることから消費税の納税額が高くなってしまいます。なので対象外との取引を控える企業が増えていきますよね。

だから、免税事業者のままでは仕事の受注量が減少してしまうかもしれないんですね!
インボイス制度の導入に伴い、仕入税額控除の適用がインボイスのみに制限されたため、仕事を依頼する側は受注者側にインボイス(適格請求書)を発行してもらわなければなりません。しかしインボイスを発行するためには課税事業者へ変更とインボイス(適格請求書)発行事業者への登録が必要です。
事務作業にかかる時間が増加する
経理事務作業に要する時間が増加する点も、インボイス制度導入による影響のひとつとしてあげられます。インボイス(適格請求書)として認められるための必須項目を、請求書内に記載する必要があるからです。
インボイスにはあらかじめ記載項目が定められており、それらを的確に遵守した内容の請求書を作成しなければなりません。
白色申告・青色申告をする際に個人事業主が行うインボイス制度への対処とは
個人事業主がインボイス制度の導入に向けて必要と考えられる対処法を紹介します。
免税事業者は取引先(買い手側)と受注価格を決定する
免税事業者のままで事業活動を継続する場合は、取引先と受注価格の相談をしてください。
取引先によってはインボイス制度への対応をしなくても良いというところもあります。その場合、免税事業者のままで継続する代わりに受注価格が下げられる可能性はゼロではありません。受注価格を下げることで、取引先における消費税の納税額が抑えられるからです。
消費税分をマイナスした受注価格に引き下げられることで免税事業者の売上は下がってしまいますが、課税事業者への変更とどちらがよいのか検討する必要があるでしょう。
課税事業者はインボイス制度への対応を進める手順
課税事業者だからといって、必ずしもインボイス制度への対応が必要なわけではありません。課税事業者のなかには、インボイスの発行手続きの煩雑さから対応しきれないと考える個人事業主もいるでしょう。
発行事業者登録はe-Taxでも可能であり、IT導入補助金としてインボイス制度に対応した会計ソフトなどの購入に対して補助金性も設けられているので、これらを活用して対応を考えてみてください。
インボイス制度での消費税確定申告の流れ
インボイス制度における消費税の確定申告の流れを確認していきましょう。
1.取引関連資料の準備
対象年の全取引における関連資料を準備します。
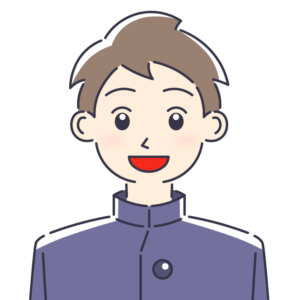
もし免税事業者から課税事業者に変更した場合にはどうすればいいでしょうか?

消費税の納税額が発生する取引と発生しない取引にわけてください。例えば2023年10月1日の導入に伴って課税事業者に変更すると、2023年9月30日以前の取引については消費税の申告・納税が発生しません。
そのため、申告・納税義務が発生する2023年10月1日以降とそれ以前に取引関連資料をわける必要があります。
また取引先のなかには免税事業者と課税事業者があり、仕入税額控除の対象になるのは課税事業者のみであることから、これらについても税額を計算する前にわけておかなければなりません。
2.消費税額の算出
取引関連資料の準備が完了したら、次に消費税額を算出します。
消費税は標準税率(10%)と軽減税率(8%)の2通りで運用されているので、それぞれの税率にわけて税額を算出しましょう。
3.消費税申告書の作成
消費税額の計算ができたら、申告書を作成します。
申告書の作成方法は課税方式によって異なり、すべての事業者で一律ではありません。詳しい作成方法は後述するので、そちらを参考にしてください。
4.消費税申告書の提出と納税
申告書の提出・納税は、事業形態によって以下のように異なります。
|
事業形態
|
提出・納税時期
|
| 個人事業主 | 課税期間の翌年3月31日まで |
| 法人 | 課税期間最終日翌日から2カ月以内 |
また個人事業主・法人に限らず前期消費税額が48万円を超えると、税額にあわせて中間申告が必要です。
|
前期消費税額
|
提出・納税回数
|
時期
|
| 48万円超400万円以下 | 年1回 | 各中間申告対象期間末日の翌日を起算日として2カ月以内 |
| 400万円超4,800万円以下 | 年3回 | |
| 4,800万円超 | 年11回 | 「No.6609 中間申告の方法」を参照 |
中間申告対象期間とは、例えば1月1日~12月31日までが事業年度である個人事業主の対象期間は1月1日~6月末日までであり、7月1日~8月31日までに申告・納税をしなければなりません。
消費税申告書の作り方
消費税納税額の計算方法は、簡易課税と本則課税で異なります。
以下の条件におけるそれぞれの計算方法を確認していきましょう。
年間総仕入高(税込):1,100万円
消費税率:標準税率10%(国税分7.8%、地方税分2.2%)
みなし仕入率:60%
簡易課税のとき
簡易課税とは、対象年の前々年度における課税売上高5,000万円以下の場合に適用可能な制度です。税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、「みなし仕入率」を使用した納税額の計算ができます。
「みなし仕入率」は事業区分によって異なり、すべての事業に対して一律ではありません。国税庁の「No.6509 簡易課税制度の事業区分」にて事業区分に対する税率や事業例が記載されているので、確認してください。
| 1 | 売上分の消費税額(国税分) | 3,000万円×7.8%=234万円 |
| 2 | 仕入分の消費税額(国税分) | 3,000万円×7.8%×60%=187.2万円 |
| 3 | 消費税の国税分 | 234万円-187.2万円=46.8万円 |
| 4 | 消費税の地方税分 | 46.8万円×22/78=13.2万円 |
消費税の納税額は60万円と算出されました。
本則課税のとき
本則課税とは、売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税をマイナスして計算する方式のことです。
| 1 | 売上分の預り消費税額(国税分) | 3,000万円×7.8%=234万円 |
| 2 | 仕入分の支払済消費税額(国税分) | 1,100円×7.8/110=78万円 |
| 3 | 消費税額(国税分) | 234万円-78万円=156万円 |
| 4 | 消費税額(地方税分) | 156万円×22/78=44万円 |
本則課税を用いた場合の消費税の納税額は200万円と算出されました。
消費税確定申告による特例
消費税の計算方法は、原則として簡易課税と本則課税の2種類のいずれかです。しかし特定の条件を満たすことで2割特例の利用が可能です。
2割特例とは
免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった場合に一定期間の売上消費税額を2割減額する経過措置であり、以下のように定められています。
・2023年10月1日以降に新規課税対象事業者
・2021年分および2022年4月~6月の課税売上高が1,000万円以下
・課税期間短縮適用外
・一般課税および簡易課税の申告対象外
(参考:インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート|国税庁)
上記の要件はすべて満たさなければなりません。
適用期間は2023年10月1日〜2026年9月30日まで限定的な特例制度なので注意してください。
所得税の確定申告に与える影響とは?
インボイス制度の導入による所得税の確定申告に与える直接的な影響はありません。
しかし課税事業者の場合は消費税分の確定申告を考慮しなければならず、それに対応した帳簿方法などの見直しが必要でしょう。
簡易課税のとき
免税事業者がインボイス制度の導入に伴って課税事業者に変更し、簡易課税の適用を受ける場合には帳簿の記載方法を見直さなければなりません。課税事業者になったことで、これまで免除されていた消費税の申告・納税が必要になるからです。
簡易課税での経理方式には以下の2通りがあり、経理処理の方法も異なります。
|
経理方式
|
概要
|
処理方法
|
|
| 税抜経理方式 | 売上分の消費税 | 「仮受消費税等」の勘定科目を使用 | 消費税額=仮受消費税等-仮払消費税等 |
| 仕入分の消費税 | 「仮払消費税等」の勘定項目を使用 | ||
| 税込経理方式 | 売上分の消費税 | 収入・収益計上 | ・納税額は必要経費もしくは損金処理 ・還付金は雑収入として処理 |
| 仕入分の消費税 | 経費・費用計上 | ||
(出典:No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理|国税庁、No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理|国税庁)
方式は事業者側にゆだねられているので、処理しやすいと感じる方式を選択してください。
本則課税のとき
本則課税で消費税の処理を行う場合、免税事業者取引分については期間限定で仕入税額控除の適用が可能です。
|
期間
|
割合
|
| 2023年10月1日~2026年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日~2027年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
(参照:5 経過措置|国税庁)
2024年現在、上記の期間を過ぎた免税事業者取引分については適用されなくなるので注意してください。
免税事業者のとき
免税事業者を継続する場合は、消費税・所得税ともに申告・納税における影響はありません。
ただし「白色・青色申告の際に生じる個人事業主への影響」で紹介した取引上のリスクが発生する可能性が高いので注意しましょう。
インボイス制度で無申告はバレる?
インボイス制度では事前に課税事業者・インボイス(適格請求書)発行事業者としての登録が必要であるため、消費税の無申告をすると税務署に知られてしまいます。課税異業者・発行事業者として登録するということは、消費税の申告・納税義務は必ず発生するからです。
無申告個人事業主はインボイス制度の影響はどのようなものがあるのか
課税事業者であるにもかかわらず、無申告を行ってきた個人事業主の場合、インボイス制度でどのような影響を受けるか考えてみます。
インボイス(適格請求書)を発行するためには、登録事業者として税務署に登録申請を行い、登録番号を発行してもらわなければなりません。申請の際には申告書類などを税務署に提出しますが、その場ですぐに登録番号が発行されるわけではなく、税務署にて調査が行われます。
無申告の形跡があると疑われると税務調査が行われ、得られた証拠をもとに追徴課税のような罰金が課せられるでしょう。
無申告加算税の増加
無申告加算税とは、期間内に確定申告をしなかった場合に課せられる罰金です。財務省が公表している具体的な課税要件は、以下のように規定しています。
・期限後の申告や決定について、修正申告や更正があった場合
(出典:加算税の概要|財務省)
加算税を算出する際の税率は増差本税の金額によって異なり、以下の通りです。
|
増差本税額
|
税率(年率)
|
| 50万円以下 | 15% |
| 50万円超300万円以下の部分 | 20% |
| 300万円超の部分 | 30% |
(出典:加算税の概要|財務省)
また税務署で「意図的な隠ぺい等が認められる」と判断された場合は、40%の重加算税が課せられる可能性があるので注意してください。
インボイス制度についてよくある質問
インボイス制度におけるよくある質問を確認していきましょう。
個人事業主がインボイス制度に対応しないとどうなりますか?
個人事業主がインボイス制度に対応しない場合、取引数・年間総売上などが減少する可能性があります。取引先側で仕入税額控除の適用が受けられなくなるからです。
「免税事業者のインボイス制度対応による手取り収入の減少」の項目にて解説しているので、こちらを参考にしてください。
インボイス制度とはどのような制度ですか?
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)に基づいて消費税を計算する仕入税額控除の方法です。
▼ インボイス制度について詳しく知りたい方はこちら。

2割特例とは何ですか?
免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった場合に一定期間の売上消費税額を2割減額する経過措置です。
まとめ
インボイス制度における確定申告の影響を解説しました。
確定申告には所得税と消費税の2種類がありますが、インボイス制度の影響を受けるのは消費税の確定申告です。所得税の確定申告は直接的な影響を受けませんが、帳簿の記載方法については変更を余儀なくされる場合があるので注意してください。
本記事を参考にインボイス制度と確定申告の関係性の理解・知識を深め、適切に対応しましょう。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。