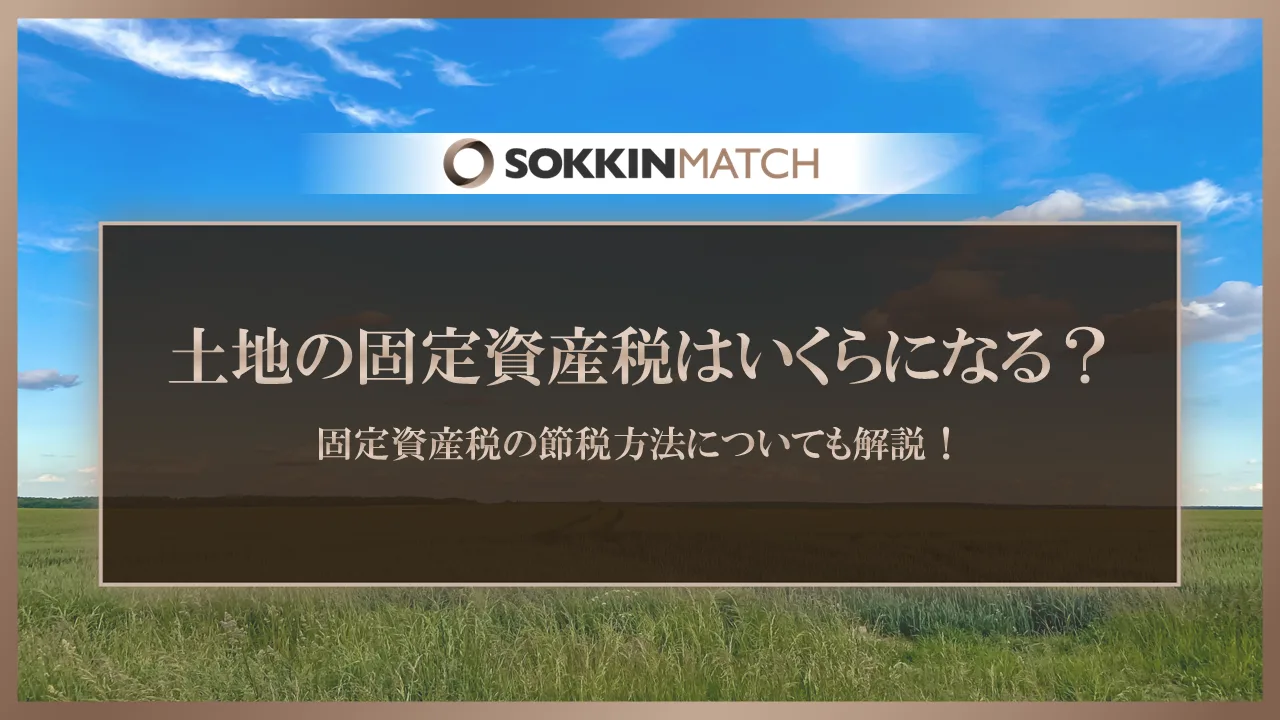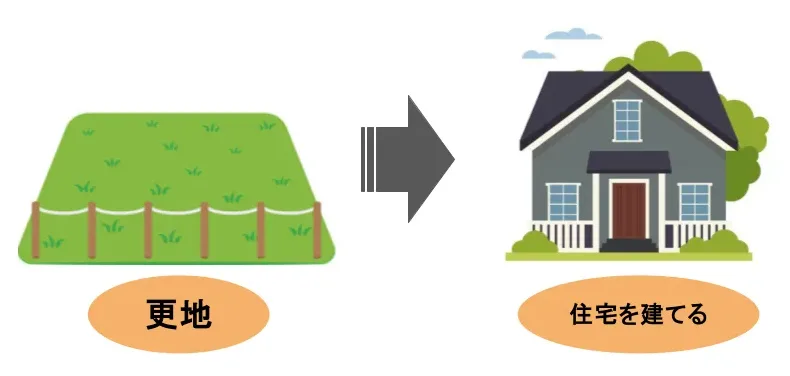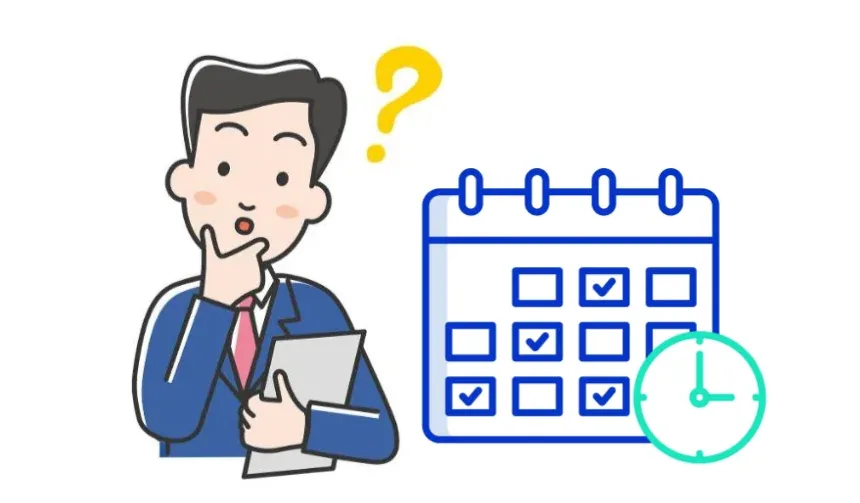個人で土地を保有していると毎年納税の義務が発生する固定資産税ですが、納税額はどのように算出・決定されているのかご存じでしょうか。
また固定資産税には別途都市計画税が含まれている場合もあり、有無については納税通知書などを確認するとわかります。この固定資産税と都市計画税の違いについて、疑問を抱いている人もいるでしょう。
本記事では固定資産税の納税額決定にかかる土地の評価方法や計算の仕方とあわせて、都市計画税についても解説します。
固定資産税とは
固定資産税とは、1月1日時点で以下に掲げる固定資産を所有している場合に課せられる税金です。
| 固定資産 | 主な内容・例 |
| 土地 | 住宅地、山林、田畑、牧場、原野、鉱泉地(温泉など)、池沼など |
| 家屋 | 住宅、店舗、工場、倉庫など |
| 償却資産 | 会社や事業主が所有する建造物(フェンス、陳列棚など)、飛行機、船、車両運搬具(鉄道、トロッコを含む)、備品(パソコンなど) |
納税額を計算する際には原則として標準税率(1.4%)をかけて算出しますが、各自治体の条例によって変更が認められているため、税率は統一されていません。
▼固定資産税についてもっと知りたい方はこちら

都市計画税との違い
都市計画税とは、以下に掲げる都市計画を行っている地域に土地・家屋を所有している際に課税される税金です。
| 主な事業 | 種類 | 内容・例 |
| 都市計画事業 | 交通 | 道路(高速道路を含む)、都市高速鉄道、駐車場など |
| 公共施設 | 公園、墓地など | |
| 生活 | 水道、ガス、ゴミ処理場、下水など | |
| 市街地開発事業 | 新住宅市街地開発 | 土地の買収、造成、建物の建設など |
| 工業団地造成 | 工業団地用の土地の買収、公共施設の整備など | |
| 市街地再開発 | 建物の建て替え、対象地域の整備など | |
| 土地区画整備事業 | ・公共施設の整備改善 ・宅地利用の増進 ・土地区画の変更 ・新公共施設の設置と建設 |
|
固定資産税がすべての土地・家屋等に課せられる税金であるのに対し、都市計画税は特定の地域に存在する土地・家屋に課せられます。
また都市計画税の課税は各自治体の判断にゆだねられているため、上記に掲げる事業計画が実施されているからといって必ず課税されるとは限りません。
土地の固定資産税の計算方法
土地の固定資産税納税額の計算方法は、以下の通りです。
納税額は課税標準額に標準税率をかけて算出しますが、この税率は「固定資産税とは」でも解説したように各自治体の条例によって変更が認められているため、一律ではありません。住んでいる地域の税率は自治体のホームページや納税通知書等に明記されているので、確認してください。
固定資産税評価額とは
固定資産税の納税額を計算するうえで欠かせないのが固定資産税評価額です。
固定資産税評価額とは土地・建物などの価値をベースに自治体が評価および決定した金額のことで、各自治体が作成・保管する固定資産課税台帳に登録されています。
評価額の決定方法は土地・家屋・償却資産によって異なり、同一ではありません。土地の場合は利用目的によっても評価方法が違っており、宅地の場合は公示価格の7割をめどに決定します。
固定資産税評価額の評価替えとは
固定資産税評価額は、半永久的に同一金額で台帳に登録されているわけではありません。
土地を例にあげると近隣の都市開発などで価格が高騰や下落が発生する可能性はゼロではなく、適正な時価にて課税価格を算出しなければならないことから、このような価格変動を反映させることが重要です。
税負担の平等性を保つという意味でも定期的に土地・家屋などの固定資産は評価額の見直しが行われており、これを評価替えといいます。
なお固定資産税評価額の評価替えについては、土地・家屋の量が膨大であることから3年ごとに実施されており、毎年行われているわけではありません。
固定資産税評価額と課税標準額との違い
課税標準額とは、対象の土地・家屋などに一定の税率をかけて算出する金額のことです。
基本的には前項目で解説した固定資産税評価額と同一金額になりますが、課税標準額には特例および調整措置が適用される場合があります。このような措置が適用されると課税標準額は評価額よりも低い金額になることがあるため、必ずしも同一とは限りません。
土地の固定資産税の計算手順
土地の固定資産税納税額を算出する際の計算手順は、以下の通りです。
- 固定資産税評価額の算出
- 課税標準額の算出
- 納税額を算出
各手順をさらに詳しく解説するので、参考にしてください。
1.固定資産税評価額を求める
納税額の算出をするためには、固定資産税評価額を算出しなければなりません。
- 実際の評価額の確認
- 固定資産絵税路線価から算出
- 時価から算出
上記3つの固定資産税評価額の算出方法を確認していきましょう。
実際の固定資産税評価額を調べる
固定資産税評価額の基本的な算出方法は、実際の評価額を確認することです。
土地を保有していると毎年5〜7月に納税通知書と納付書が自治体から送付されます。このうち納税通知書には課税明細書が添付されており、「価格」欄に記載されている金額が実際の固定資産税評価額です。
仮に納税通知書・課税明細書を紛失した場合には、各自治体にて固定資産税評価額証明書を取得するか固定資産課税台帳を閲覧して調べましょう。
固定資産税路線価から求める
固定資産税路線価から評価額を求める方法もあります。
固定資産税路線価は、一般社団法人資産評価システム研究センターが運営する「全国地価マップ」から検索が可能です。路線価掲載マップには「固定資産税路線価等」「相続税路線価等」「地価公示・地価調査」の3種類がありますが、「固定資産税路線価等」のマップを使用して路線価を調べます。
詳細情報に表示される価格は1平方メートル当たりなので、その金額に面積をかけて評価額を算出してください。
時価から求める
固定資産税評価額は時価から算出することも可能です。
時価は実際に不動産会社などで取引されている金額であり、一般人が正確な価格を知ることは困難でしょう。複数の不動産会社を訪れて周辺の売買価格を調べれば、おおよその時価がわかります。
なお固定資産税評価額は時価の7割が基準なので、実際の売買価格の7割を目安として算出してください。
2.課税標準額を求める
課税標準額は固定資産税評価額をベースに算出します。ただし、土地の状態・用途などによって標準額の計算方法が異なるので注意してください。
なお土地には30万円の免税点が設けられており、課税標準額が免税点未満の場合は固定資産税はかかりません。
ここでは更地・住宅あり・農地の3パターンの標準額の求め方を紹介します。
更地の場合
更地とは、土地に建造物等が何もない状態の土地のことです。
土地の用途・状態にはいくつかの種類がありますが、そのなかでも更地は固定資産税がもっとも高い状態といえます。その理由は、負担調整措置の対象外だからです。
よって更地の課税標準額は、固定資産税評価額の金額がそのまま適用されます。
住宅が建っている土地の場合
土地に住宅が建っている場合は、土地区分のなかでも住宅用地に分類されることから負担調整措置の対象です。
課税標準額は、小規模住宅用地・一般住宅用地および負担水準によって以下のように異なります。
| 負担水準 | 土地区分 | 課税標準額 |
| 100%以上 | 小規模住宅用地 | 固定資産税評価額×1/6 |
| 一般住宅用地 | 固定資産税評価額×1/3 | |
| 100%未満 | 小規模住宅用地 | 前年度課税標準額+(固定資産税評価額×1/6×5%) |
| 一般住宅用地 | 前年度課税標準額+(固定資産税評価額×1/3×5%) |
なお負担水準は小規模住宅用地・一般住宅用地によって算出方法が以下のように異なり、同一ではありません。
| 土地区分 | 負担水準の計算方法 |
| 小規模住宅用地 | 前年度課税標準額/(本年度固定資産税評価額×1/6) |
| 一般住宅用地 | 前年度課税標準額/(本年度固定資産税評価額×1/3) |
農地の場合
農地の場合の課税標準額は、以下の計算式で算出します。
| 負担水準 | 課税標準額 |
| 100%以上 | 固定資産税評価額×1/3 |
| 100%未満 | 前年度課税標準額+(固定資産税評価額×1/3+5%) |
なお負担水準を算出する計算式は、以下の通りです。
負担調整措置とは
更地・住宅あり・農地それぞれの課税標準額の計算方法を解説しましたが、そのなかで負担調整措置についても軽く触れました。
負担調整措置とは、宅地等の固定資産の課税を公平にするために標準額の急激な上昇を抑える目的で導入された制度です。この措置制度の適用可否を決定する際には、以下の計算式で算出される負担水準を基準にします。
上記計算式で求められた負担水準が100%未満の場合は、負担調整措置の対象となるので課税標準額は低くなります。
3.課税標準額×税率をする
納税額を算出する際の計算式は、以下の通りです。
上記計算式では標準税率(1.4%)を使用していますが、この税率は各自治体の条例によって変更が認められています。そのため、高いところもあれば低いところもあり、一律ではありません。
土地の固定資産税の節税方法
土地の固定資産税の節税対策を紹介します。
更地を農地にする
更地の状態で土地を保有している場合は、農地にして節税対策をする方法がおすすめです。
土地は更地・宅地・農地に区分されますが、更地よりも宅地または農地として利用したほうが固定資産税は安くなり、さらに一般的には宅地よりも農地のほうがさらに低く設定されています。
ただし更地から農地へ転用する場合、自治体によって規模・農作物の数などに条件・制限が設けられており、それをクリアしなければ農地として認めてもらえません。
また、登記簿の地目も「宅地」から「畑」への変更が必要になるので忘れないでください。
住宅を建てる
土地に住宅を建てることも、固定資産税の節税対策としておすすめします。住宅を建てることで土地区分が住宅用地に分類され、特例措置が適用されるからです。
特例措置を適用した場合の課税標準額は「住宅が経っている土地の場合」にて解説しましたが、固定資産税評価額よりも金額が低くなるので、それをベースに算出される固定資産税納税額は安くなります。
土地の情報を再度確認する
土地の情報を再確認することも、節税対策のひとつです。
固定資産税評価額を算出する際の土地の面積は、登記簿上に記されている数字を使用します。しかし時代の流れとともに測量方法などに変更が加えられ、実測値のほうが小さい可能性もゼロではありません。
納税額の計算では実測値のほうが優先されるため、自治体に申し出ることで払い過ぎを防止できます。
土地の固定資産税が上がる理由
土地の固定資産税は上がることもあれば下がることもあり、永年一定ではありません。
では、納税額が変動するのでしょう。ここでは特に固定資産税が上がる理由に注目して解説します。
空き家を放置している
土地に住宅が建っていても、空き家のまま放置していると固定資産税が高くなるので注意してください。
空き家に関するさまざまな問題の解決策のひとつとして「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年2月26日に施行されました。この法律を受け、各自治体から特定空き家等に認定されると住宅用地の特例制度の適用外となり、固定資産税が高くなります。
減額措置が適用されなくなった
減額措置が適用されなくなったことも、固定資産税が高くなる原因のひとつです。
土地には更地・宅地・農地の大まかな区分があり、このなかで宅地・農地にはそれぞれ特例制度が設けられています。しかし宅地・農地として利用していた土地を更地にすると、特例制度の適用外となり、結果として固定資産税が上がります。
土地の価値が上がった
場所にもよりますが、土地の価値が上がることも固定資産税が上がる原因です。
例えば都市開発が進み、マンション・大型商業施設が複数建設されたとしましょう。開発はその土地の需要の高まりを期待して行われることであり、需要が高まれば必然的に土地の価値も高くなります。
土地の価値の上昇は固定資産税にも反映され、納税額が高くなるのです。
負担調整措置が取られていた
負担調整措置の適用も固定資産税の納税額が高くなる理由です。
負担調整措置については「負担調整措置とは」で解説しましたが、これは段階的に納税額が上がっていく特例制度であることから、毎年納税額は高くなります。
本来の納税額に達するまで毎年金額が見直されるので、固定資産税が高くなることは仕方がないといえるでしょう。
土地の固定資産税のシミュレーション
土地の固定資産税の解説をしてきましたが、実際の数字を当てはめてみないとわかりにくいと感じる人もいるかもしれません。
「あなたの固定資産税はいくら?計算方法やシミュレーション例を紹介します!」では、一軒家と新築マンションの場合の納税額を実際の数字を使用してシミュレーションしています。
本記事とあわせてこちらの記事も参考にしてください。
固定資産税の支払いについて
固定資産税の支払いについて解説します。
支払い期限はいつまで?
支払期限はおおむね4月または5月・7月・12月・2月のそれぞれ末日ですが、各自治体によって設定が可能であることから一律ではありません。
| 自治体 | 納期 | |||
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
| 東京都中央区 | 2024年7月1日 | 2024年9月30日 | 2024年12月27日 | 2025年2月28日 |
| 石川県金沢市 | 4月30日 | 7月31日 | 12月28日 | 2月末日 |
| 大阪府和泉市 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
さらに毎年変更する自治体もあるので、詳しい支払期限は納付書または各自治体に確認してください。
支払い方法について
固定資産税の支払方法は現金・口座振替が基本ですが、自治体によっては以下のような支払い方法に対応している場合もあります。
- クレジットカード
- スマートフォンアプリ決済
- ページ―
- 電子マネー
上記4つの支払方法は対応している自治体が限られており、必ず選択できるわけではありません。
選択可能な支払方法は納付書等に明記されているので、そちらを確認してください。
支払い期限を過ぎた場合について
固定資産税には納期限が設けられていますが、この期限を過ぎた場合には延滞金が加算されます。
| 期限 | 原則(年率) | 特例基準割合(年率) |
| 1カ月以内 | 7.3% | 延滞金特例基準割合+1% |
| 1カ月超 | 14.6% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
納期限翌日を起算日として1カ月を境に税率が変わりますが、使用される税率は原則と特例基準割合を比較して低いほうです。
特例基準割合は毎年変更されるので、各自治体のホームページを確認してください。
▼固定資産税の支払いについてもっと知りたい方はこちら

まとめ
土地の固定資産税について解説しました。
土地の区分等によって納税額が変わる固定資産税ですが、特例制度を活用することで節税対策が可能です。
本記事で紹介した固定資産税の計算方法・節税対策等を参考にして固定資産税の知識・理解を深め、定められた納期限内に納税を完了するようにしてください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。