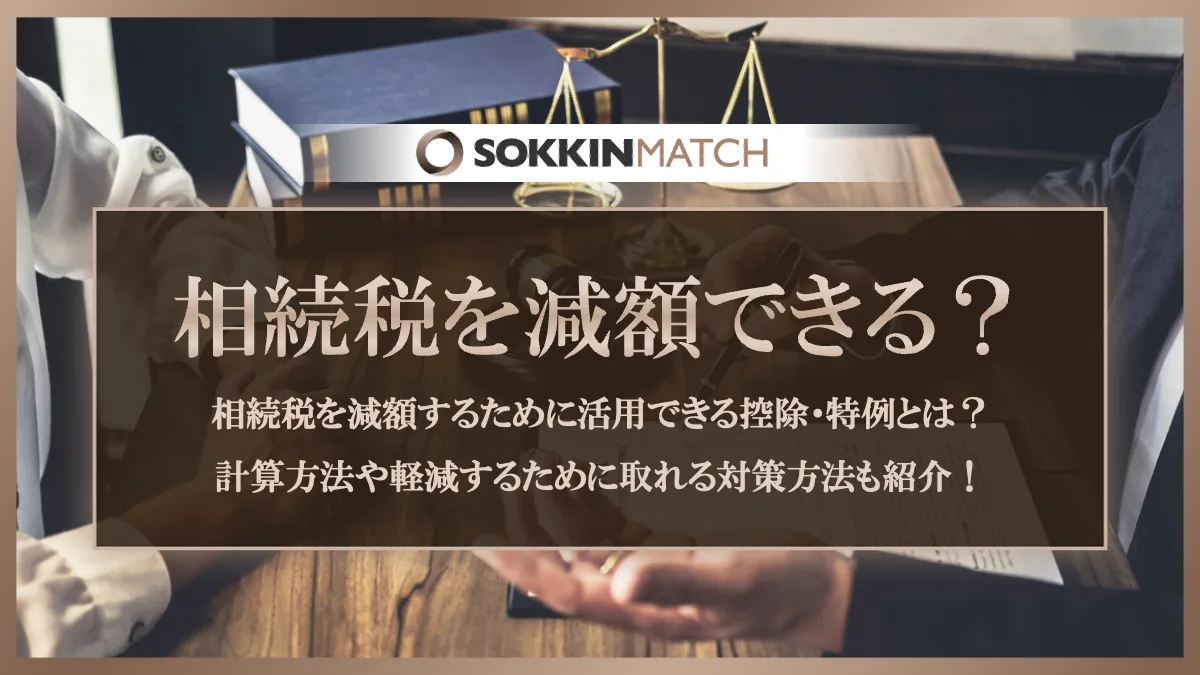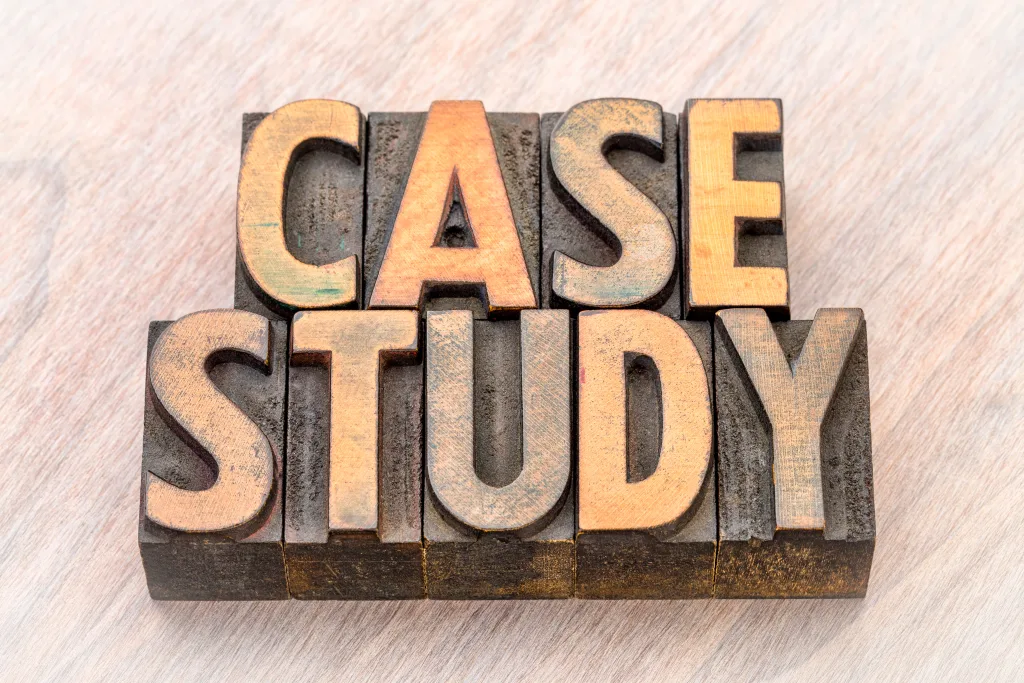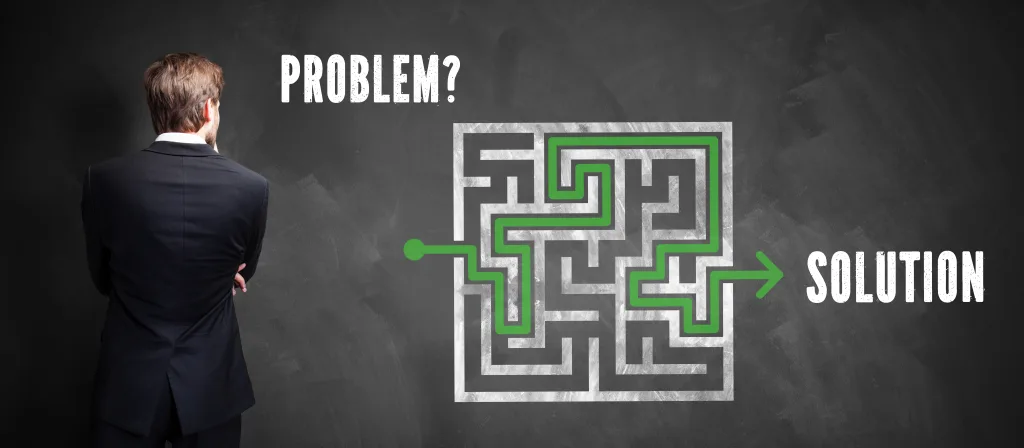遺産を相続すると相続税が課税されるのは知っているけど、実際にどのくらいかかるのか、どうすれば負担を軽減できるのか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
相続税の計算方法は複雑なところもありますが、事前に知識を身に付けておくことで税額を大きく軽減できる可能性もあります。

この記事では、相続税を減額できる控除や特例などの制度について詳しく解説します。相続税の基本的な計算方法や、負担を軽減する対策方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
相続税の対象内外の財産, 費用について
まずは、どのような財産に相続税が課税されるのか、基本的な部分からおさらいしましょう。
相続税の対象内外の財産を知っておくことで、節税の対策方法も理解しやすくなります。
課税の対象となる財産
相続税の課税対象となる財産は以下のような財産です。
2.みなし相続財産
3.相続人が被相続人から暦年課税で贈与を受けた財産
4.相続時精算課税制度適用財産
本来の相続財産とは、被相続人が所有していた財産のことで、預金や現金、土地や建物などの不動産、有価証券などが含まれます。その他に、貸付金やゴルフ会員権、著作権や特許権のような金銭的な利益につながるものも対象です。
みなし相続財産とは、生命保険の保険金や死亡退職金などが当てはまります。
相続人が被相続人から贈与を受けた財産のうち、相続開始以前の7年間の贈与額を相続財産に算入します。以前は3年間でしたが、税制改正により現在は7年間に変更になっています。

相続人が被相続人から受けた贈与のうち、相続時精算課税制度を適用していた財産は、贈与時の価格で相続税の課税対象となります。相続時精算課税制度とは、子や孫に対して2,500万円まで非課税で贈与を行い、相続発生時に相続税として一括で納税する制度です。
相続税の課税対象外となる財産
被相続人の財産のうち、以下のものは相続税の課税対象外となります。
2.相続税の対象財産から控除できるもの
3.相続財産の価額から控除できるもの
祭祀財産(さいしざいさん)とは、仏壇や仏具、神棚、墓地、墓碑などが当てはまります。
相続税の対象財産から控除できるものとは、みなし相続財産の非課税枠のことで、「法定相続人数 × 500万円」の金額が課税対象外となります。

たとえば、死亡保険金が2,000万円で法定相続人数が3人の場合、相続税の課税対象は500万円で、1,500万円は課税対象外となります。死亡保険金と死亡退職金の両方がある場合、それぞれから上記の金額を控除できます。
相続財産の価格から控除できるものとは、債務などのマイナスの遺産と葬式費用です。
債務とは、たとえば借金や未納の税金、家賃などの未払金などのことです。葬儀費用は、葬祭業者や寺などに支払う葬儀費用やお通夜のために支出した費用を課税財産から差し引くことができます。ただし、香典返しや墓地の費用は控除対象外となります。
▼ 相続税の申告の仕方はこちら。
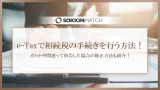
相続税を減らすために活用できる特例や控除の例
それでは、具体的に相続税を減らす方法を見ていきましょう。
以下で相続税を減らすために活用できる特例や控除を8つまとめて紹介します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、土地を相続するときに利用できる特例です。持家が建っている土地だけでなく、事業をしていた土地や貸付している土地も対象となります。
小規模宅地には以下の3種類の特例があります。
|
利用区分
|
減額割合
|
| 特定住居用宅地等(被相続人が住んでいた住宅の宅地) | 330㎡までの部分を80%減額 |
| 特定事業用宅地等(被相続人が事業で使っていた土地) | 400㎡までの部分を80%減額 |
| 貸付事業用宅地等(被相続人が貸付していた土地) | 200㎡までの部分を50%減額 |
このように、土地の相続税の課税価格を最大80%減らすことができます。土地の利用区分は、相続開始直前の利用状況によって判断されます。
土地は高額になることが多いため、相続税を軽減するために重要な特例です。
基礎控除
相続税の基礎控除は、課税対象財産の計算時に法定相続人の人数に応じて差し引くことができる控除です。
基礎控除額の計算式は以下のように決まっています。
たとえば、法定相続人が4人の場合の基礎控除額は以下のとおりです。
このように、法定相続人の人数が多いほど基礎控除額が大きくなり、相続税額が安くなります。
基礎控除額が遺産総額より大きい場合は、相続税が非課税となり、申告や納税の義務もなくなります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者(妻または夫)が財産を相続するときは配偶者の税額軽減(配偶者控除)の対象となります。
配偶者の税額軽減の控除額は以下の2つのうち大きい方の金額です。
・法定相続分相当額
このように、配偶者の税額軽減は控除額が大きいため、相続税が大幅に軽減されます。
未成年者控除
相続人が未成年の場合は、相続人の年齢に応じて以下の控除額が適用されます。
年齢は月単位を切り捨てして年単位で計算します。たとえば、15歳と6ヶ月の人は15歳として以下のように計算します。
そのため、相続人の年齢が低いほど控除額が大きくなり、税額が低くなります。
未成年者が受け取る相続財産の金額が控除額を下回る場合、残りの控除額は扶養義務者の税額から控除できます。
障害者控除
障害者控除は、相続人が障害者で年齢が85歳未満のときに適用可能な控除です。
控除額は以下の計算式で、年齢に応じて決まります。
未成年者控除と同様に、年齢のうち1年未満は切り捨てします。
また、控除額が相続額を上回り控除しきれなかった場合に、残りを扶養義務者から控除できるのも未成年者控除と同様です。
相次相続控除
相次相続控除は、相続が開始される前の10年間で被相続人が相続税を納税しているときに、一定の金額を控除できる制度です。
控除の名称からも分かるとおり、短期間で相次いで相続が発生したときの負担を軽減する控除です。
相次相続控除を受けるには以下の3つの条件を満たす必要があります。
2.今回の相続開始前の10年以内に開始した相続で、被相続人が財産を取得している
3.その相続で、被相続人が相続税を納税している
被相続人の相続人であることが条件のため、相続放棄や相続権を失った人は対象外です。また、今回の相続の被相続人が、前回の相続で財産を取得して、そのときに相続税を納税していることが条件となります。
相次相続控除の控除額は、被相続人が前回の相続で納税した相続税額を1年あたり10%ずつ減額した金額です。以下で控除額の計算式を国税庁ホームページから引用します。
A × C / (B – A) × D / C × (10 – E) /10 = 各相続人の相次相続控除額
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税の適用を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額(注)-債務および葬式費用の金額(以下、同じです。))
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切捨てます。)
引用:相次相続控除│国税庁
上記のように、前回の相続から今回の相続までの期間が短いほど控除額が大きくなります。
贈与税額控除
贈与税額控除は、相続人が被相続人から生前に贈与を受けており、贈与税を納税している場合に受けられる控除です。
相続税の課税財産額の計算ルールでは、被相続人が相続開始前の7年間で相続人に贈与した財産も課税対象に含めることになっています。
このような二重課税を防ぐために、相続税の納税額から、過去に納税した贈与税と同額を控除できるようになっています。
暦年課税分の贈与税額控除
上記の贈与税額控除のことを「暦年課税分の贈与税額控除」と呼ぶこともあります。
贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。このうち暦年課税は1月1日~12月31日の期間で1年間に贈与された合計額をもとに贈与税を計算する方式です。
どちらの方式で贈与税を納税した場合でも、その後に相続が開始した場合には、贈与税額控除を受けることができます。暦年課税で納税した贈与税額相当分を控除するときに「暦年課税分の贈与税額控除」という言葉が使われます。
▼ 相続税の控除について詳しく知りたい方はこちら。

相続税の計算方法
ここからは、相続税の計算方法について見ていきましょう。
計算方法が分かれば事前にどの程度の税額になるか判断することができます。
相続税の計算方法の全体の流れは以下のようになっています。
2.課税遺産総額を算出する
3.法定相続分に従って仮の課税遺産額を法定相続人ごとに求める
4.相続税の総額を実際の割合に応じて各人に割り振る
5.各種控除や加算を行う
以下でそれぞれの手順について具体的に解説します。
課税価格を算出する
まず課税価格の算出を行います。
課税価格とは、簡単に表すとプラスの遺産からマイナスの遺産を差し引いて残った価格のことです。
基本的な計算式は以下のようになります。
みなし相続財産とは、生命保険の保険金や死亡退職金などのことです。
債務にはローンなどの借入金や未納の税金などが含まれます。また、相続人が支払った葬儀の費用も債務に含めて良いことになっています。
課税遺産総額を算出する(課税価格から基礎控除額を差し引く)
次に、課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
基礎控除額は、法定相続人の人数によって以下の式で計算します。
たとえば、課税価格が8,000万円で法定相続人の人数が2人の場合、以下の計算になります。
・課税遺産総額 = 8,000万円 – 4,200万円 = 3,800万円
法定相続分に従って仮の相続税額を法定相続人ごとに求める
課税遺産総額が計算できたら、法定相続分に従って仮の課税遺産額を法定相続人ごとに求めます。
そして、仮の課税遺産額にもとづいて、各法定相続人の仮の相続税額を計算しま
法定相続分に従って仮の相続税額を法定相続人ごとに求める
課税遺産総額が計算できたら、法定相続分に従って仮の課税遺産額を法定相続人ごとに求めます。
そして、仮の課税遺産額にもとづいて、各法定相続人の仮の相続税額を計算します。
相続税の税率は累進課税のため、相続額が大きいときは計算が複雑になります。税額計算は国税庁ホームページに掲載されている「相続税の速算表」を使うと簡単に計算できます。
以下に相続税の速算表を課税遺産額1億円までの部分について引用します。
|
法定相続分に応ずる取得金額
|
税率
|
控除額
|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
出典:国税庁ホームページ
たとえば法定相続分に応じて取得する財産額が2,000万円の場合、表の上から2番目に当てはめて以下の計算を行います。
上記のような計算を法定相続人ごとに行い、すべての法定相続人の仮の相続税額を合計すると、相続税の総額が求められます。
相続税の総額を実際の割合に応じて各人に割り振る
次に、上記で計算した相続税の総額を、実際の相続割合に応じて各相続人に割り振ります。
実際の相続割合は遺言書や遺産分割協議などにより自由に決めることができます。
各種控除や加算を行う
最後に、相続人の立場や相続時の状況により控除や特例、加算を適用すれば、最終的な税額が求められます。
相続税の計算で利用できる控除や特例については、この記事の上記で紹介していますので参考にしてください。たとえば、配偶者が相続するときは配偶者控除、未成年が相続するときは未成年控除を適用可能です。
加算については、配偶者や1親等以外の人が相続した際に2割加算されるルールがあります。
相続税を軽減するために取れる対策
ここからは、相続税を軽減するために取れる対策として、以下の3つを紹介します。
・財産の組み換え
・財産の分割方法
控除や特例を活用すること以外にも、これらの方法を事前に準備をすることで税額の負担を軽減できる場合があります。
以下でそれぞれの対策方法を具体的に解説します。
生前贈与を活用し財産を移転する
1つめは、生前贈与を活用して財産を移転する方法です。これは、贈与税の年間110万円の基礎控除を活用して毎年少額ずつ財産を移転することで、相続税の課税額を減らすというものです。
贈与税の課税制度は暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、どちらか一方を選択することができます。
このうち、暦年課税で贈与を行う場合、年間110万円までは贈与税がかからず、110万円を超えた部分に対して10%〜55%の税率で課税されます。そこで、110万円以内の贈与を複数年かけて行うことで、贈与税と相続税を負担せずに財産を移転することができます。
財産を組み換え相続税評価額を圧縮する
これは、財産の組み換えにより相続税の課税価格を減少させる方法です。
以下のような財産の組み換え方法が考えられます。
・生命保険の非課税枠を活用する

たとえば、建物が建っていない更地を所有している場合は、費用を借入れしてアパートや事業用の建物を建築し、不動産収入を得るという方法が考えられます。
更地のまま土地を所有していると、評価額にそのまま相続税が課税されることになります。そこで、新築した建物と土地の合計評価額から、新築費用として借入れする債務を引いた金額が、もとの土地の評価額より小さくなるようにすれば、相続税評価額を圧縮できます。
財産の分割の仕方を工夫し税額を軽減する
配偶者には課税相続額から最低1億6,000万円が控除される配偶者の税額の軽減制度があります。この制度を活用して財産の分割方法を工夫することでトータルの相続税額を軽減できる場合があります。
この方法は、一次相続と二次相続の2回の相続が発生することを考えて相続税額の試算を行い、税額が軽減される財産の分割方法を工夫することが重要です。
たとえば、課税遺産総額が1億6,000万円のケースで、配偶者と子供2人での財産分割方法を3パターンで試算してみると、目安として以下のようになります。
|
財産の分割方法
|
配偶者の相続税額
|
子の相続税額の目安
|
|
| A | 配偶者:1億6,000万円 子:0円 |
0円 | 0円 |
| B | 配偶者:0円 子:各8,000万円 × 2人 |
0円 | 1,700万円 |
| C | 配偶者:8,000万円 子:各4,000万円 × 2人 |
0円 | 850万円 |
|
子の相続額
|
二次相続の相続税額の目安
|
一次相続と二次相続の合計
|
|
| A | 各8,000万円 × 2人 | 2,100万円 | 2,100万円 |
| B | 0円 | 0円 | 1,700万円 |
| C | 各4,000万円 × 2人 | 450万円 | 1,300万円 |
このように、財産の分割方法によってトータルでの相続税額(一次相続と二次相続の相続税の合計額)に差が出ます。
税額が安くなる分割方法は相続財産の総額や相続人の構成などで変わります。また、適用可能な控除の種類や控除額も相続が発生するときの状況で変わります。いろいろなパターンで試算を行い、分割方法を検討することで相続税の総額を軽減できる場合があります。
まとめ
この記事では、相続税の計算方法や負担を軽減するための控除や特例、節税対策について解説しました。
相続税の税額を減らすには、課税対象となる財産の判断基準や、控除・特例について知識を身に付けることが重要です。それに加えて、生前贈与や財産の分割など、負担を軽減できる対策を検討するのも効果的です。
まずは控除できる項目や利用できる特例をしっかりと確認し、少しでも税額を減らせるようにしましょう。

ぜひこの記事でお伝えしたことを参考にしていただき、相続税の手続きで役立ててください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか