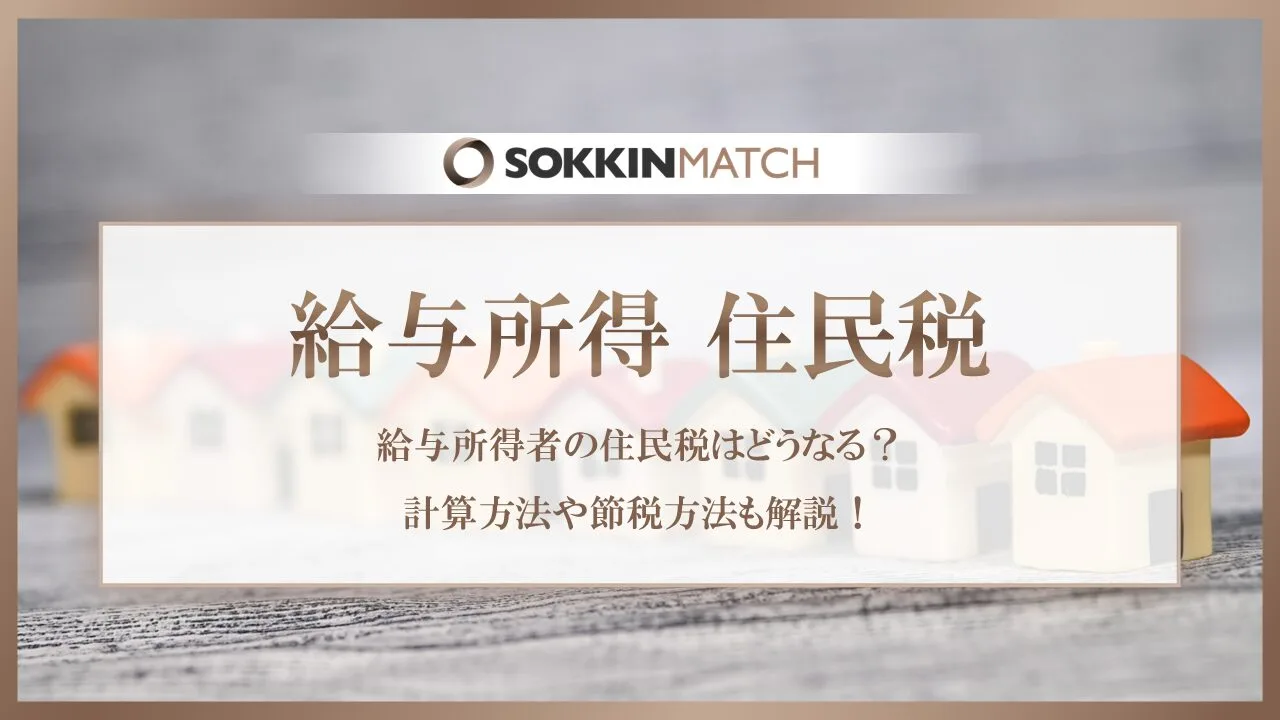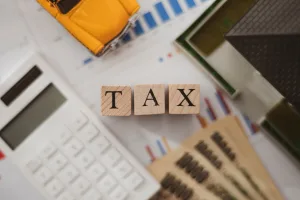一定の所得がある場合に課せられる住民税は、給与所得者も課税対象です。
しかし会社員と個人事業主とでは徴収方法が異なっており、個人事業主から給与所得者に働き方を変更した際には戸惑うこともあるかもしれません。
住民税とは
住民税とは、地域で提供されている行政サービスの維持・運営のために必要な費用を公平に分担する地方税です。
学校教育・上下水道の維持管理・道路の整備・ゴミ処理・公共施設など、これらの行政サービスを運営するためには費用が必要ですが、国・自治体だけが負担しているわけではありません。
国・自治体単位だけでは到底まかないきれるものではなく、地域に在住してさまざまな行政サービスの提供を受けている住民にも負担してもらうことを目的に徴収されています。
働き方によって徴収方法は変化する
住民税の徴収方法は、以下の2通りです。
・普通徴収
上記2つはそれぞれ徴収方法だけではなく、対象者も異なります。原則として働き方によっていずれかの徴収方法が強制的に決められますが、例外もあるので一概にはいえません。
それぞれの徴収方法を詳しく解説するので、参考にしてください。
特別徴収とは
特別徴収とは、会社員などの給与所得者や年金受給者を対象とした徴収方法です。
「会社・企業から毎月決まった給与を受け取っている」「毎月公的年金が支給されている」のいずれかに該当する場合は、原則として特別徴収すると定められており、選択できません。
徴収方法は1年分の納税額を12カ月で割った金額を毎月の給与・公的年金支給額から天引きします。そのため1回に支払う金額は少なく、負担になると感じる人は少ないでしょう。さらに納税額が自動的にマイナスされて納付されるので、納期限忘れなどのうっかりミスも防げます。

ただし強制的な徴収方法なので、次に紹介する普通徴収への自主的な切り替えができません。自分で計画的に納税したいなどの理由がある場合は、納付方法が選択できないことをデメリットに感じてしまう人もいるでしょう。
普通徴収とは
普通徴収とは、自営業・個人事業主・派遣社員といった特別徴収されない人を対象にした徴収方法です。
自宅に納付書が送られてくるので、納付書に明記されている納期限までに金融機関などで納めます。
普通徴収の場合は納付書を使用して自分のタイミングで納付できることから、収入などの都合で自主的に計画を立てて納付したい人にはメリットです。
ただし納税額は1年分を4回にわけて支払う形式が取られており、1回分の納付額は特別徴収額と比較すると高い金額になります。1年分の総額にもよりますが、納税額によっては4回の分割払いでも支払いが難しいと感じることもあるかもしれません。
また自治体にもよりますが、口座引落が選択できない可能性もあり、その場合は納期限までに忘れず支払わなければなりません。

このように特別徴収と比べて1回の支払額が高い点や、納税期限まで忘れずに自分で支払わなければならない点はデメリットと言えますね!
住民税の納付額の計算方法
住民税は所得割と均等割の2つから成り立っており、納税額を求める際にはそれぞれの計算式などが異なります。
所得割と均等割の概要・計算方法を詳しく解説するので、参考にしてください。
所得割とは
所得割は、前年の所得額によって納税額が変わる変動制です。
所得割は以下の計算式で求められます。
所得控除や税額控除は、要件を満たすことで適用される控除制度です。それぞれの控除制度については後述するので、そちらを参考にしてください。
なお上記計算式の税率は10%としていますが、都道府県(4%)と市区町村(6%)を合計した割合であり、自治体によって税率が異なるので一律ではありません。
以下は2024年11月25日現在の税率の一覧表です。税制改正や自治体の条例が変更になると変わる可能性があるので注意してください。
|
都道府県
|
市区町村
|
所得割
|
|
| 都道府県 | 市区町村 | ||
| 北海道 | 札幌市 | 2% | 8% |
| 宮城県 | 仙台市 | 2% | 8% |
| 千葉県 | 千葉市 | 2% | 8% |
| 神奈川県 | - | 4.025% | 6% |
| 横浜市 | 2.025% | 8% | |
| 川崎市 | 2.025% | 8% | |
| 相模原市 | 2.025% | 8% | |
| 愛知県 | 名古屋市 | 2% | 7.7%(市民税減税) |
(2024年11月16日現在)
標準税率とは異なる税率が設定されているのは基本的には政令指定都市であり、都道府県8%と市区町村2%です。
しかし神奈川県と愛知県名古屋市は、異なる税率が設定されています。税率は各自治体の条例によって自由に決定できることから、ほかとは異なる税率が設定されているのです。
均等割とは
均等割とは、一定の所得がある人を対象に自治体であらかじめ決められた納税額を全員で負担する住民税です。
均等割も所得割同様に都道府県と市区町村の2種類から成り立っており、基本的には以下のように金額が定められています。
| 金額 | |
| 都道府県 | 1,000円 |
| 市区町村 | 3,000円 |
| 森林環境税 | 1,000円 |
| 合計 | 1,000円+3,000円+1,000円=5,000円 |
ただし自治体によって環境税や県民税などが設定されており、納税額が異なっているのが現状です。
|
都道府県
|
市区町村
|
均等割 |
減額・超過の詳細
|
|
| 都道府県 | 市区町村 | |||
| 岩手県 | - | 2,000円 | 3,000円 | いわての森林づくり県民税1,000円 |
| 宮城県 | - | 2,200円 | 3,000円 | みやぎ環境税1,200円 |
| 神奈川県 | - | 1,300円 | 3,000円 | 水源環境の保全・再生のため超過課税300円 |
| 横浜市 | 1,300円 | 3,900円 | 水源環境の保全・再生のため超過課税300円 横浜みどり税900円 |
|
| 愛知県 | - | 1,500円 | 3,000円 | あいち森と緑づくり税500円 |
| 名古屋市 | 1,500円 | 2,800円 | あいち森と緑づくり税500円 市民税減税-200円 |
|
上記は自治体独自の条例に基づいて原則とは異なる均等割の金額を設定している地域の一部であり、上記以外に国税である森林環境税1,000円が加算されます。
定額減税とは
定額減税とは、住民税課税世帯を対象にした2024年度限定の特別減税のことです。
| 対象者 | 減税額 |
| 納税者本人 | 1万円 |
| 生計を同一とする配偶者または扶養親族 | 1万円/1人につき |
例えば配偶者と子3人の家族の場合、住民税の減税額は以下の通りです。
1万円(納税者本人)+1万円(配偶者)+1万円×3人(子)=5万円
減税のタイミングは2024年度分の住民税総額から減税額を差し引き、残りの金額を11カ月分に分割して7月〜翌年5月まで支払います。

給与所得者は勤務先で定額減税を適用されてから毎月徴収する金額を決定するので、個別に各自治体に対して手続きを行う必要はありません!
所得控除と税額控除の相違点
所得割の計算式で紹介した所得控除と税額控除は、いずれも住民税の納税額を算出する際に適用する控除制度です。しかし、同じ控除制度でも詳細等は以下のように異なります。
|
所得控除
|
税額控除
|
|
|
概要
|
年間所得額に応じて控除額を決定 | 所得割額から一定の金額を控除 |
|
控除対象
|
年間所得額 | 所得割額 |
|
種類
|
・基礎控除 ・扶養控除 ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 ・障害者控除 ・ひとり親控除 ・寡婦控除 ・勤労学生控除 ・雑損控除 ・医療費控除 ・社会保険料控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 |
・調整控除 ・外国税額控除 ・配当控除 ・住宅ローン控除 ・寄附金税額控除 ・配当割額控除 ・株式等譲渡所得割額控除 |
▼ 控除制度の詳細等についてはコチラから


住民税の納税額を確認する方法
住民税の納税額は自分で計算することも可能ですが、慣れていないと計算間違いをする可能性があります。
正確な納税額を確認する際には、住民税決定通知書の確認がおすすめです。通知書の届く時期などを解説するので、参考にしてください。
住民税決定通知書とは
住民税決定通知書とは、前年分の所得額に応じて算出した住民税の納税額を通知する書類のことです。
原則として通知書は納付書とともに毎年5〜6月頃に各自治体から納税者のもとに送付されますが、特別徴収の場合は会社・企業に届きます。
会社・企業は特別徴収対象の従業員の納税額を毎月の給料から徴収し、代わりに納税しなければなりません。納税義務者は各従業員ですが、実際の納税作業は会社・企業が行うので通知書は勤務先に送付されるのです。会社・企業には一覧表示された通知書と個別の通知書の2種類が届き、従業員は勤務先から個別の通知書を受け取ります。
特別徴収用と普通徴収用では様式や見た目が若干異なりますが、明記されている内容に違いはありません。
住民税の計算例
給与所得者の住民税を、実際の数字を入れてシミュレーションしてみましょう。
| 条件 | 年収:350万円 所得控除:基礎控除のみ 税額控除:なし 使用する税率等:標準 |
| 年間所得額 | 350万円-55万円(給与所得控除)=295万円 (参考:No.1410 給与所得控除|国税庁) |
| 課税所得額 | 295万円-43万円(基礎控除)=252万円 (参考:個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局) |
| 所得割額 | 252万円×10%=25.2万円 |
| 均等割額 | 1,000円+3,000円+1,000円=5,000円 |
| 住民税額 | 25.2万円+5,000円=25.7万円 |
配偶者控除や扶養控除といったさまざまな控除制度の適用が可能であれば、さらに納税額は下がります。
住民税を納税するタイミング
住民税を納税するタイミングは徴収方法や状況などによって異なり、同一ではありません。
・特別徴収
・海外滞在の納税義務者
・退職後の納税義務者
・公的年金受給者
上記5つのパターン別に納税のタイミングを解説するので、参考にしてください。
普通徴収の場合
普通徴収の場合、毎年6月頃に各自治体から納税者のもとに納付書が送付されます。納付期限はおおむね6月末・8月末・10月末・翌年1月末の年4回ですが、自治体によっては7月1日・9月2日・10月末・翌年1月末に定められていることもあり、一律ではありません。
正確な納期限は納付書に記されているので、必ずその期日を確認してください。
特別徴収の場合
特別徴収の場合、納税通知書の項目で解説したように決定した納税額がわかるのは5〜6月頃です。その後、勤務先で年間納税額を12カ月分にわけて毎月の給料から天引きされます。
よって、納税のタイミングは6月〜翌年5月までの1年間です。
自分で金融機関などの窓口にて納付する必要はありませんが、1年間の天引きは毎年6月からスタートして翌年5月までかかっている点に注意してください。
海外に滞在していて納税が必要な場合
海外に滞在していても住所が日本国内にある場合は、住民税を納税しなければなりません。
納税通知書や納付書は毎年6月頃に日本国内の住所に送付されるため、海外に滞在している場合は自治体からの郵便物に注意してください。
納期は、普通徴収の場合と変わりません。海外での滞在期間のほうが長い場合は、4回分の納税額をまとめて支払うことも可能です。

ただし、海外在住者の場合だと、住民税の納税義務は発生しません。
退職した後、納税が必要な場合
退職後に納税が必要な場合は、退職の時期やその後の再就職の有無などによって以下のように異なります。
|
ケース
|
納税のタイミング・方法
|
| 退職と同時期に再就職 | 再就職先で特別徴収 |
| 6月~12月に退職後、再就職なし | ・原則は普通徴収 ・希望すれば一括徴収も可能 |
| 1月~5月に退職後、再就職なし | 前職にて一括徴収 |
退職と同時期に再就職するケースでは、再就職先での特別徴収希望を前職に伝えなければなりません。前職は、再就職先に「給与所得者異動届出書」を作成して送付しなければならないからです。

同時期に再就職する際には、忘れず特別徴収の有無を前職に伝えましょう!
公的年金受給者で納税が必要な場合
公的年金受給者の場合は、毎月の年金支給額から天引きされる特別徴収です。
住民税の納税額が確定した後、自宅には納税通知書のみが送付されて納付書は同封されません。
給与所得者同様に1年分の納税額を12カ月分にわけ、6月支給分から翌年5月分まで天引きされます。
住民税の負担を軽減させる方法
住民税の負担額を軽減させる方法として、以下の3つがおすすめです。
・非課税条件の確認
・年間医療費の確認
ぞれぞれの軽減方法を紹介するので、参考にしてください。
ふるさと納税を活用する
住民税の負担額を軽減させる方法として、ふるさと納税はおすすめです。
ふるさと納税とは、地方と大都市の税収格差問題の改善目的で2008年5月にスタートしました。ふるさと納税を活用するメリットは以下の通りです。
・返礼品
・所得税と住民税の両方を控除

所得税・住民税の控訴だけでなく、返礼品がもらえるのは最大のメリットだね!

また、ふるさと納税は所得税だけでなく、住民税も寄附金から2,000円を差し引いた全額が控除されます!
非課税になる条件を確認する
住民税は一定の条件を満たすと非課税になるため、その条件を確認することもひとつの方法です。
|
非課税パターン
|
条件
|
| 所得割のみ | 【生計を同一とする配偶者や扶養親族がいる場合】 35万円×本人・配偶者・扶養親族の総人数+42万円 【配偶者も扶養親族もいない場合】 35万円 |
| 所得割と均等割 | ・生活保護を受給者 ・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年総所得額135万円以下 |
上記の一覧表の条件は一部であり、自治体によって独自の非課税条件が設定されていることもあります。
年間の医療費を確認する
年間の医療費を確認することもおすすめします。その理由は、所得控除の医療費控除が利用できる可能性があるからです。
医療費控除とは納税者や生計を同一とする家族の支払った医療費を年間所得額から差し引くことが可能であり、住民税の場合は所得割を算出する際に適用します。
|
年間所得
|
計算式
|
| 200万円以上 | 医療費控除額=年間医療費-10万円-保険金など |
| 200万円未満 | 医療費控除額=年間医療費-(年間所得額×5%)-保険金など |
住民税を納税する際の注意点
住民税を納税する際の注意点として、以下のようなものがあげられます。
・自治体によって異なる税率
・住民税滞納は罰則対象
各注意点を解説するので、参考にしてください。
ふるさと納税は寄付金控除として扱う
ふるさと納税は寄附金控除の一種であり、上限額の超過分は控除できません。
自治体によって税率が異なる
住民税を算出する際の税率は標準税率10%が定められていますが、この税率を使用しなければならないわけではありません。
税率は各自治体の条例によって独自に設定することが可能となっており、異なる場合があります。
本記事の「所得税とは」にて、標準税率とは異なる税率が用いられている自治体を一部一覧表で紹介しました。
引越しをする際には異なる税率によって以前よりも納税額が高くなったり低くなったりする可能性があるので、確認してください。
住民税の滞納は罰則の対象になる
住民税が特別徴収される場合は問題ありませんが、普通徴収の場合には納期を忘れて滞納してしまう可能性があります。その場合は延滞金の罰則対象になるので、注意してください。
なお、延滞金は以下のように計算されます。
なお延滞税を計算する際の税率は延滞期間によって異なり、その利率は以下の通りです。
|
延滞期間
|
年利率
|
| 2カ月以内 | 7.3%と「特定基準割合+1%」を比較して低いほう |
| 2カ月超 | 14.6%または「特定基準割合+7.3%」を比較して低いほう |
特定基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利の前々年10月〜前年9月までの平均に1%を加算した割合のことで、国内銀行の貸し出し約定平均金利の平均値は財務大臣が告示します。
延滞期間が長くなるほど延滞税は高くなるので、早めに納税したほうが良いでしょう。
まとめ
給与所得者の住民税を解説しました。
給与所得者の場合、原則として納税額は毎月の給料から天引きされる特別徴収なので納付忘れの心配はありません。しかし退職後に再就職をしない場合は自分で納付しなければならないので、忘れないようにしましょう。
また住民税は節税が可能なので、本記事で紹介した対策方法なども参考に知識を深めてください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のトップマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。