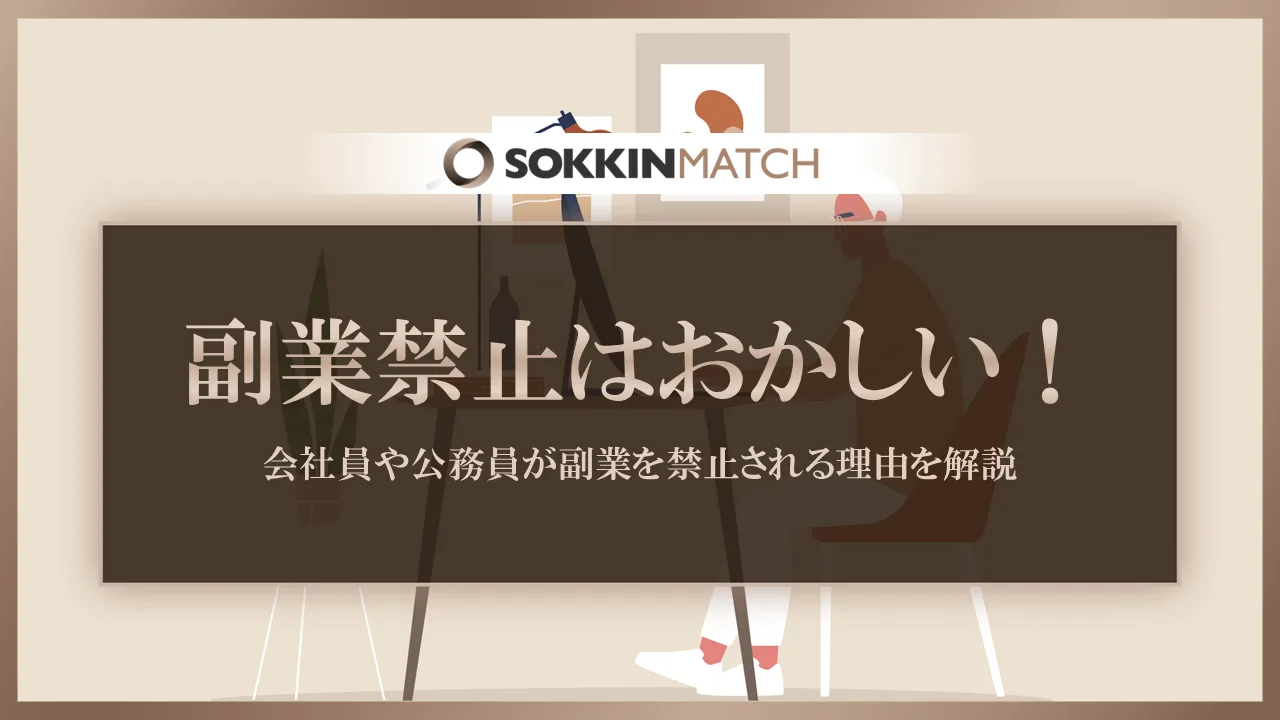厚生労働省が副業・兼業に関するガイドラインを発表したことで、公的には副業が解禁になりました。しかし企業・職種によっては副業を禁止しているところもあり、すべてで解禁になっているわけではありません。
このような現状に「おかしい」と感じている人も少なからずいるようです。
▼ 副業について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
副業を禁止にする理由
2018年のモデル就業規則改定を受けて、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成・発表しました。この発表は副業・兼業を行うことを国が推奨することを意味しており、本来なら本業とは別の収入源を持つことは会社・企業からも推奨されるはずです。
しかし現実にはそのようなことにはなっておらず、就業規則によって副業・兼業を禁止している企業・会社も少なくありません。
経団連が2020年に実施した副業・兼業の施策導入調査では、副業・兼業を認めている企業は22%にとどまる結果となりました。これは7~8割程度の会社・企業は、認めていないことを意味しています。
国としては認めているにもかかわらず、企業・会社側が禁止にしている現状に「おかしい」と感じるのは無理ないといえるでしょう。勤務先の就業規則や方針に不満を抱き、転職・退職を考える人もいるかもしれません。
ではなぜ国の方針に反して企業・会社では禁止にしているのでしょうか。その背景には以下のような理由があげられます。
・情報漏洩のリスク
・利益相反
・転職・独立の原因
会社・企業側がどのような理由・原因を考慮して禁止にしているのか、上記4つを詳しく確認していきましょう。
本業をおろそかにする可能性があるから
副業を禁止している理由として、本業がおろそかになる可能性があげられます。
例えば、副業で受注した仕事の進捗状況が予定よりも遅れたとしましょう。納品に間に合わせるために睡眠時間を削って副業時間に充てていると、寝不足になって集中力が低下するなどの支障をきたします。
集中力が低下すると本業の仕事の精度が下がり、ミスが多くなったり就業中に居眠りをしたりするかもしれません。仕事の完成度が低下すると顧客に迷惑をかけることになるなど、本業側としては迷惑をこうむります。
毎月給料を支払っているからにはきっちり仕事をして欲しいと思うのは当然であり、おろそかになる可能性を懸念して副業を禁止にしている可能性があります。
社外秘の漏洩リスクがある
情報漏洩のリスクが高くなることも、禁止にしている原因のひとつです。
例えば、本業に関連した仕事を副業として受注したとしましょう。本業で独自に編み出した方法で副業の仕事をこなした場合、その手法がライバル社に漏洩してしまう可能性があります。
仕事をこなしていると気づきにくいこともありますが、各会社では独自の手法・方法を開発してマニュアル化しているケースが多く、これらを他社に漏らすようなことをしてはなりません。会社としては他社に漏洩してしまうと損害を被ることになるからです。
また本業で扱っている個人情報・機密情報を、うっかり副業のクライアントに漏らしてしまうといったことも考えられます。その場合に本業が受けるダメージ・被害は計り知れません。
このようなリスクを未然に防ぐ意味で、副業を禁止している会社・企業もあります。
利益相反につながるから
利益相反の可能性が高まる点も、副業を禁止する理由です。
本業と同業種の副業を始めた場合、副業で取引しているクライアントが実は本業のライバル会社である可能性があります。そのことを知らずに副業での成果を上げると、本業側は売上・契約数などでライバル会社に抜かれてしまうかもしれません。これが利益相反です。
本業の勤務先側から見れば毎月給料を支払っている社員が、わずかな報酬を得るためにライバル社の売上・業績向上に加担しているわけで、推奨できることではありません。
このような状態を未然に防ぐために、副業を禁止している企業・会社もあるのです。
転職や独立を考える要因となる
転職・独立を防ぎたいと考えて、会社・企業が副業を禁止しているケースもあります。
会社・企業側としては優秀な従業員を雇用することは売上・業績の向上につながるので、可能な限り長く勤めて欲しいと思うのは当然でしょう。
しかし副業を許可してしまうと、それがきっかけで転職・独立を考える従業員が増えるかもしれません。
また一人前の従業員として活躍してもらうために、会社・企業は時間とコストをかけています。ようやく優秀な従業員として活躍できるまでに成長したのに、副業での仕事のほうが魅力的に感じて退職することもあるでしょう。
優秀な従業員が副業をきっかけに退職してしまうと、会社としては大損です。
そのような可能性を少しでもゼロにするためには本業に集中してもらう必要があり、副業を禁止していることもあります。
公務員は副業が禁止されている?
国は副業・兼業のガイドラインを作成して、推奨する方向に転換しました。会社・企業によってはさまざまな理由から就業規則で禁じているところもありますが、国として推奨している以上はこのような状況も少しずつ変わっていくでしょう。
しかしその一方で公務員は、副業が禁止されています。その理由について解説するので、参考にしてください。
営利企業の役員、自営
公務員には国家公務員法という独自の法律が適用されており、公務員として仕事に従事するからにはこの法律を遵守しなければなりません。
この国家公務員法第103条の「私企業からの隔離」において、副業を禁止する内容が明記されています。文章自体が難しいと感じる人もいるかもしれませんが、わかりやすく言い換えると営利目的での企業運営は禁止です。
ただし、事前に許可を得ている場合に限り認めるとしています。副業の許可を得るためには人事院の承認を得なければならないので、一般企業に比べるとハードルは高いといえるでしょう。
公務員が遵守しなければならない法律上では原則として営利企業の自営は禁止されているので、結果として副業ができないのが現状です。
報酬を得る一定の副業
公務員に対して独自に制定されている国家公務員法で禁止しているのは、営利目的の企業運営だけではありません。
国家公務員法第104条の「他の事業又は事務の関与制限」では、企業運営以外の副業に関する禁止事項も明記されています。こちらも法令であることから、言い回しが難しいと感じる人もいるかもしれません。わかりやすい表現方法に言い換えると、営利企業以外でも職員が公務員以外の報酬以外で労働の対価を受け取ることは禁止です。
例えば、懸賞金などで一時的に得た収益に関しては問題ありません。しかしアルバイト・パートのような労働の対価として報酬を得ることは原則として認められないということです。
ただし事前に所轄庁の長と内閣総理大臣から事前に許可を得ている場合は、例外として認められます。
地方公務員も同じ!
ここまで国家公務員を前提に話を進めてきましたが、公務員には地方公務員もあり国家公務員だけではありません。
地方公務員の場合は地方公務員法という法律が制定されており、仕事に従事する際はこの法律を順守することが原則です。
なお地方公務員法では第38条「営利企業への従事等の制限」にて、副業を禁止する内容が明記されています。国家公務員法同様に、営利目的の企業運営とあわせて公務員以外の労働の対価を得ることも禁止です。
地方公務員は国家公務員と採用の方法・条件などは異なりますが、公務員である以上は原則として副業は認められていません。
ただし事前に人事委員会から許可を得ていれば副業が認められます。この点も国家公務員法と同様です。
公務員が副業を禁止されている理由
厚生労働省がガイドラインを作成してまで副業を推奨するなか、なぜ公務員は副業を禁止しているのでしょうか。その理由は、公務員全体のイメージ・信用を損なう可能性があるからです。
2018年1月に厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定・公表していますが、その一方で総務省は、2025年9月に「地方公務員の兼業について」を公開しました。
このなかの「許可基準の認定について」にて、国家公務員としての信用・不名誉となる恐れを理由に副業は原則として認められないとしています。国家公務員と明記されていますが、地方公務員にも同様の理由が適用されており、公務員として副業は原則認めないということです。
公務員は一般企業に勤務する会社員とは異なり、国民全体に対して奉仕する立場にあります。営利目的とした企業運営や事業所得を得る行為はその企業・会社・個人など限られた範囲での奉仕に値するものであり、国民全体を対象としているとはいえません。
公務員の立場・役割を背景に考えた場合、副業は公務員としての本質から外れる行為であるといえます。このような観点から国家公務員・地方公務員を問わず、公務員という職に従事する限りは原則として副業が禁止されているのです。
▼ 副業を始めたい公務員の方は、こちらの記事をチェック

副業は推奨されつつある!
厚生労働省が策定・公表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業禁止に関する規定が削除されました。これは国として副業を認めたことを意味しています。
また働き方改革・コロナ禍などの影響もあり、仕事の仕方・勤務スタイルなどが多様化しつつあるのが現状です。完全リモートワークでの仕事・案件も増えつつあり、これらの多くは勤務時間に縛られることがありません。
このような背景から、国・社会全体として副業は推奨されつつあります。
一方で企業・会社で見た場合には就業規則で禁止しているところが多数あり、国・社会全体の流れに沿っているとは言い難いでしょう。
ただし副業が明確に認められたのは、2018年以降のことです。セキュリティ・環境整備などで対応しきれず、副業を推奨したくてもできない現状を抱えている企業・会社もあります。
公務員については本質が民間企業の会社員とは異なるため、全面解禁になることは難しいかもしれません。
しかし民間企業は環境整備の問題が大半を占めていることから、次第に解禁になるところも増えていくでしょう。
副業禁止に疑問を持ったらどうすべき?
副業禁止に疑問・不満を感じた場合の行動として、以下のようなものがあげられます。
・本職に内緒で副業開始
・本業を退職
なぜ副業をしたいと思うのか考えてみてください。
「なんとなく」「知り合いが副業をしているから」などに該当する場合は、副業に対しての熱意が高いとはいえません。よって副業を断念して本業に専念することをおすすめします。
「本業の収入だけでは足りない」などの経済的理由がある場合は、本業に内緒で副業を始めてもよいでしょう。ただしその場合は、就業規則に反した行動を取っていることを忘れないでください。バレた場合には何らかの罰則があるかもしれないことも覚悟しておきましょう。
スキルアップ・将来的な独立を視野に入れている場合は、思い切って退職してみてはいかがでしょうか。副業可能な同業種への転職やフリーランスとして活動する方法があります。
このように現状・動機によって行動は変わるので、まずは原因を考えてみてください。
一度、副業を始める直前まで進んでみよう!
副業を始める直前まで進んでみることもおすすめです。特に動機ははっきりしているけれどいまいち踏ん切りがつかない場合には、副業開始直前まで準備を進めて覚悟・意志の強さを確かめてみるとよいでしょう。具体的には以下のような準備方法がおすすめです。
・副業として始めた場合の相場などを調査する
・必要なスキル・実績などを確認する
・副業エージェントに登録・相談してみる
上記は副業を始める前の準備であり、実際に仕事・案件を受注するわけではありません。
例えば、本業と同業種で副業を始めるとしましょう。副業は実力重視であることが多く、スキル・実績が不十分では仕事・案件が受注できない可能性があります。また、依頼主のなかには副業案件として発注している場合もあり、本業とは異なる価格が設定されていることも少なくありません。
このように本業とは業務形態も異なるので、副業としての情報・データを徹底的に集める必要があります。
これらの準備をしている間に、覚悟・意志の強さが明確になってくるでしょう。本気で副業を続けていく覚悟があるのかを自分に問う意味でも、直前まで準備を進めてみてください。
副業と認定されにくい仕事
副業といっても職種・業種に明確な枠組み・規定はありません。そのため、一見副業とはいえないようなものでも副業とされることもあります。
副業と認定されにくい仕事を紹介しますが、広い意味と捉えてさまざまなもの具体例をあげて解説するので、参考にしてください。
フリマアプリ
フリマアプリは、副業として認定されにくい仕事としておすすめです。
本来のフリマアプリは不用品を売買するために開発・運営されているアプリであり、小売業などの商売目的ではありません。
読まなくなった本・着なくなった古着などをフリマアプリで販売し、誰かが購入すれば設定した価格を収入として得られます。このサイクルを繰り返し続けていれば、1カ月単位でそれなりのまとまった収入になるかもしれません。
しかしあくまで不用品をフリマアプリを利用して売買しただけであり、ネットショップのように商売目的で行ったわけではありません。
このような理由から、会社に知られたとしても副業と認定されにくい可能性が高いといえます。
せどり
せどりも状況によっては副業と認定されにくい仕事です。
せどりとは売却目的の商品を仕入れて利益を上乗せした金額で売却することであり、ネットショップの運営と少し似ているところがあります。
なぜせどりが状況によっては副業と認定されにくいのかというと、販売する商品のなかには不用品も含まれるからです。
せどり初心者に推奨されている方法として、不用品の売却があります。購入したけれどいらなくなったもの・自室を圧迫している使用しなくなったものを、フリマアプリなどを利用して売却する方法です。仕入れにお金をかけずにせどりの練習が可能であり、不用品の処分もできます。
せどり目的で商品を仕入れた際にも、「本当は自分で使うつもりだった」と理由を述べられる程度の個数を購入して利益を上乗せした金額で売却すれば、副業として認定される可能性は低くなるでしょう。
趣味の作品を販売する
趣味で作ったものを販売する方法も、副業と認定されにくい仕事のひとつです。
例えばビーズ手芸が趣味の人が、オリジナルのアクセサリーを複数制作したとしましょう。自分で身につけるにも限界があるため、フリマアプリを利用して制作したものを販売して収入を得ました。
作品を販売して収益を得ているのですから、一見副業と認定されそうです。しかし実際には手芸という趣味の一環として販売して収益を得たと判断されることが多く、副業であると認定されることは少ないでしょう。
ただし、大量生産して毎月多額の収入を得ている場合は、その限りではありません。
また、本業がデザインに関連した仕事である場合は、勤務先とは別のルートでデザインしたものを販売したと判断されて副業認定される可能性はあります。
執筆業
執筆業は副業として認定されにくい仕事というよりは、バレにくい仕事といえるかもしれません。
副業を禁止している会社・企業であっても、インターネットの普及に伴い、個人でブログを立ち上げている人は一定数存在します。そのブログを見た人が「単発で投稿して欲しい」と依頼してくる可能性はゼロではありません。その際に原稿代として報酬を受け取ったとしても、明確に副業とは言いにくいでしょう。
また執筆業は顔出しをしないケースが多く、副業として仕事・案件を受注してもバレにくいのが特徴です。さらに本名を出す必要もなく、ペンネームのような匿名を使った執筆活動ができます。
このような点から認定されにくいというよりはバレにくい仕事といえるでしょう。
投資
副業として投資をしていた場合、勤務先から副業と認定される可能性は少ないでしょう。投資は資金運用と言い換えることが可能だからです。
資金運用の代表的なものとしてNISAがあげられますが、これも言い換えるなら投資のひとつのスタイルであり、副業として認めた場合は加入できません。しかし副業を禁止している企業・会社のなかには、NISAのような確定拠出年金を積極的に進めるところもあります。
一方、FXや仮想通貨なども投資の一部ですが、こちらはギャンブル的な要素が強く、副業として考えにくいでしょう。
副業という明確な定義・規定はありませんが、投資は一般的に副業と考えられるものとは性質が異なっていることから、対象外として扱っている企業・会社が多いのが現状です。
▼ 副業禁止に抵触しにくい副業はこちら!

副業はバレるの?
本業の会社に黙っていたのに、なぜか副業していることが知られているということがあります。
なぜ知られてしまうのか疑問に感じる人もいるでしょう。その原因と対処法を解説するので、参考にしてください。
マイナンバーからはバレない!
勤務先の年末調整時には申請書類にマイナンバーの記載が必要です。
このマイナンバーから副業をしていることが知られてしまうかもしれないと不安を抱えている人もいるようですが、そのようなことはありません。
マイナンバーの本来の目的は行政関連の事務作業の効率化を図るためであり、紐づけられている個人情報を民間企業が知ることは不可能です。
また反対に行政から勤務先に、マイナンバーに紐づけられた個人情報を通知することもありません。
マイナンバーは原則として行政上の手続きのために使用されるものであり、その内容・情報の開示請求は認められていないことから、副業していることが知られる可能性もないのです。
開業届ではバレない!
開業届を提出することで、会社に副業を知られてしまうかもと不安になる人もいるでしょう。しかし開業届を提出したからといって、副業が会社に知られることはありません。開業届を提出しても、税務署が勤務先に連絡することはないからです。
そもそも本業を持つ会社員が副業をする際、開業届を提出する必要はありません。個人事業主として事業を開始した際には、所得税法で1カ月以内の提出が定められています。しかしこの場合でも提出しなかったからといって罰則が課せられるわけではなく、会社員として副業する際も同様です。
開業届をもとに税務署が勤務先に連絡をする可能性はありませんが、不安に感じる場合は開業届を提出しないこともひとつの方法といえます。
会社の同僚からバレる
会社に副業がバレる原因にはさまざまなケースが考えられますが、そのなかでも多いのが同僚です。
プライベートな会話のなかで副業について触れてしまうと、悪気がなくてもそのことは会社中に広まってしまう可能性があります。また、同僚との会話をほかの誰かに聞かれてしまうこともあるでしょう。
知られたくないのであれば、同僚・先輩・後輩など会社の関係者には話さないことです。自ら離さなければ、副業をしていることを誰かに知られるリスクは軽減されます。本気で会社に知られたくないと思うのなら、社内・会社関係者の会話には細心の注意を払いましょう。
SNSの投稿でバレる
SNSの投稿でバレる可能性もゼロではありません。
SNSは匿名で投稿することが多いため、ここから副業していることを会社に知られることはないと思っている人もいるでしょう。
しかし投稿内容から見る人が見ればわかってしまうことは多く、勤務先での出来事を配信しているSNSアカウントで副業のことも投稿してしまうとバレてしまいます。
アカウントが本名ではないからといって、油断するのは危険です。勘の鋭い人なら、投稿内容からそのアカウントが誰のものなのかわかることがあります。
副業をする際には、仕事の受注やポートフォリオとしてSNSを利用することもあるでしょう。その場合は普段使用しているアカウントとは別に副業用として作成し、くれぐれも本業に関する投稿はしないように注意してください。
余談ですが、アカウントを間違えないようにも注意してください。よっぽどフォロワーが多くなければ、それによって問題が起こる可能性は低いですが、注意するに越したことはありません。
年末調整の控除申告書に副業の所得を記入してバレる
年末調整の控除申請書に自分で記入してバレることもあります。
毎年10月頃から順次手続きが始まり、勤務先から対象である従業員に申請書が配られます。この申請書には勤務先とは別のを書く欄が設けられており、会社から支給される給与・賞与以外の収入の申告が可能です。
申請書に副業分の収入を記入すれば控除申告などの手続きをまとめてしてもらえるので、後日確定申告をする必要はありません。しかし、副業をしていることは会社にバレてしまいます。

副業していることを知られたくない場合は、副業分の収入については自分で確定申告を行うようにしましょう。
住民税が高くなりバレる
住民税の金額からバレる可能性もあります。
給与所得者は原則として、住民税は特別徴収で納税します。特別徴収とは住民税の徴収方法のひとつで、毎月支給される給与から1年分の住民税を天引きします。徴収した住民税は会社・企業が代わりに納税してくれるので、従業員は自分で納める必要がありません。
住民税は前年の年間所得額から計算して算出しますが、副業分の収入がプラスされていると納税額が高くなるのでバレる可能性があります。
副業の収入が事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかに該当する場合、確定申告時に普通徴収を選択すれば副業分にかかる住民税は納付書での納税が可能です。
会社に副業していることを知られたくない場合は、副業分の所得については自分で確定申告をして普通徴収を選択しておきましょう。
▼ 副業がバレるケースとその対策についてはコチラ!

副業がバレたらどうなる?
副業は本来ならば国が推奨していることから、行っても罰則が課せられることはありません。
しかし会社・企業によっては就業規則で禁じている場合があり、その際には違反時のペナルティも明記されています。就業規則に反して副業を行った場合に課せられるペナルティの例は、以下の通りです。
・降格
・出勤停止
なかには、懲戒解雇などの厳しいペナルティが明記されていることもあるので注意してください。
就業規則は、誰もが確認できるように公開されています。副業の可否とともにペナルティについても事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
▼ 副業禁止を違反したときの対応についてはコチラ!

副業した時の残業ってどう変わるの?
労働基準法では、原則として労働時間は1日8時間及び週40時間に規定されており、これを超える場合は時間外労働として割増料金が発生します。
例えば本業の勤務時間が1日8時間だったとしましょう。副業で別の仕事をする場合には、労働時間はすべて時間外労働扱いになり、割増料金が発生します。
副業として飲食店でのホールスタッフやキッチンスタッフをした場合、そこでの勤務時間はすべて時間外労働であることから、雇用主は割増料金を支払わなければなりません。
ただし、副業先にあらかじめ本業があることを伝えておくと、36協定を締結することになるでしょう。
36協定とは法定労働時間を超えて勤務する場合に、上限時間を定めておく取り決めのことです。締結すると、1カ月100時間未満または複数月の場合は平均80時間以内の規定が追加されます。
この考え方は、あくまで企業・会社などと雇用契約を結んで副業を行う場合です。

例えばフリーランスとして副業を行う場合、クライアントと雇用契約を締結するわけではありません。よって労働時間に関する規定は適用されなくなり、副業に充てている時間の通算も不要です。
まとめ
副業禁止について解説しました。
国の方針としては副業を推奨していますが、公務員や一部の企業・会社では禁止にしているのが現状です。禁止にする背景にはさまざまな理由があり、規定・就業規則等を覆すことは難しいでしょう。
企業側には企業側の理由があるので、納得できない場合は副業を何故したいのかという理由を考えてみてください。理由・原因を考えることで、今後どのように行動すべきかも見えてくるでしょう。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか