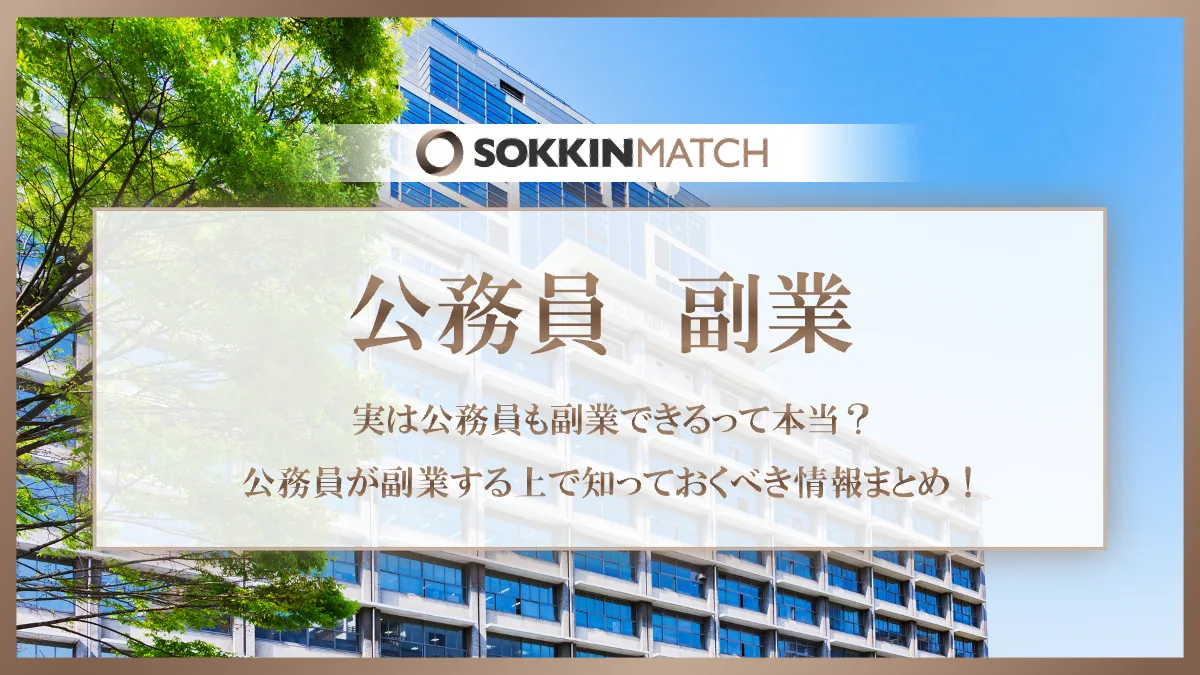2018年1月より、国は労働者の副業・兼業を推進する方向に舵を切りました。厚生労働省からもこれらを推奨するガイドラインが発表されたため、さまざまな企業・会社で副業を解禁するところが増加傾向にあります。
しかしその一方で、公務員は原則として副業禁止です。一般の企業と比較して副業ができない状況に窮屈さを感じている人もいるでしょう。
▼ 副業について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
公務員が副業をしていけない理由
2018年1月以降、一般企業では副業・兼業を認める動きが活発化しています。そのなかで一見、逆行しているように見えるのが公務員です。
法律上は副業・兼業をしても罰則が与えられませんが、公務員に限っては原則禁止されています。なぜ公務員は、一般企業で認められている副業・兼業ができないのでしょうか。
その理由は、公務員が国家公務員法および地方公務員法の遵守が原則だからです。それぞれの副業における規定について、詳しく確認していきましょう。
▼ 副業禁止の理由について詳しく知りたい方はこちら

国家公務員法における規定
この法律内における副業・兼業に関する条例は、第103条および第104条に明記されています。
|
国家公務員法
|
概要
|
罰則
|
| 第103条 | 営利企業の役員の職を兼ねる立場、または自ら営利企業を営んではならない | 有 |
| 第104条 | 営利企業以外のあらゆる事業・事務の報酬を得る兼業は原則禁止 | 無(懲戒処分あり) |
(参考:国家公務員の兼業について(概要)|内閣官房内閣人事局)
なお、事前に人事院・所轄庁から許可されていれば罰則の対象にはなりません。
地方公務員法における規定
副業・兼業に関する規定は第38条に明記されており、許可なく以下に掲げる行為を行うことは禁じられています。
2. 自ら営利企業を営むこと
3. 報酬を得て事業又は事務に従事すること
(出典:地方公務員の兼業について|総務省)
ただし事前に人事委員会より許可されている場合は、副業・兼業が可能です。
公務員の副業が認められた実例について
公務員は原則として、副業・兼業が法律によって禁止されています。例外として、事前に人事院などから許可を得た場合には可能です。
一見、人事院などに許可を依頼しても認められそうにないと感じる人もいるかもしれません。しかし一定の条件を満たせば許可されるケースもあり、副業が認められたケースもあります。
その条件と実際の具体例を確認してきましょう。
公務員の副業が認められる条件とは?
公務員には国家公務員と地方公務員の2種類があり、いずれもそれぞれの法律によって副業・兼業をしてはならないことが原則です。ただし、以下の条件を満たせば、副業が認められる可能性があります。
|
公務員
|
副業条件
|
| 国家公務員 | ・副業又は兼業先が非営利団体 ・社会通念上相当だと認められる金額を超えない報酬 ・勤務時間外(重複は禁止) ・人事院の許可を得た場合のみ |
| 地方公務員 | ・原則としてはあらゆる副業や兼業は禁止 ・任命権者によって認められた場合のみ可能 |
一見、国家公務員のほうが副業・兼業に関する条件が緩いと感じるかもしれません。しかし、副業条件のなかに「人事院の許可を得た場合のみ」とあり、許可が得られなければ副業・兼業はできません。
簡単にいうと、国家公務員も地方公務員も人事院・任命権者によって認められた場合のみに限られています。
公務員の副業が解禁された例にはどんなものがある?
なおここで紹介する具体例は、いずれも前述した条件および許可が得られていることが前提です。
国家公務員の副業が過去認められた例
2019年10月から認定NPO法人フローレンスという団体が、内閣府および厚生労働省に勤務する国家公務員の兼業者の受け入れを開始しました。
認められた背景として、以下のような点があげられます。
・認定NPO法人としての活動実績あり
・認定NPO法人が刑罰などの処分を受けていないこと
・副業および兼任者は経営上の責任者ではないこと
・副業する事業及び事務が公務の信用を傷つけないこと
以上の条件から、人事院から認められて副業をするに至りました。
都道府県職員の副業が過去認められた例
長野県では2018年に長野県にて社会貢献職員応援制度を導入し、多くの職員が副業に取り組める環境を整えています。
この制度を利用して長野県の職員は、農事組合の活動に参加して副業をスタートさせました。具体的な活動として、山菜収穫・草刈りなどを行っています。
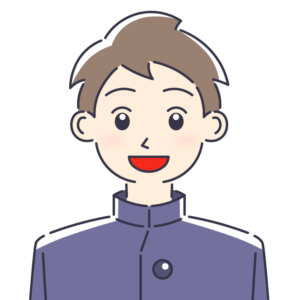
地元に密着した副業を行うことで地域住民と交流する機会が増えたよ!

さらに高齢化による人手不足問題の解消にもつながりました。
市区町村職員の副業が過去認められた例
茨城県鹿嶋市では、キャリアコンサルタントの副業をしている職員がいました。
市区町村職員としての勤務時間外を活用して、大学生を中心に就活・キャリアに関するサポートを行うことが主な業務内容です。就活イベントのスタッフとして活動することもあり、来場者から寄せられるさまざまな相談を聞いてアドバイスをしていました。
公務員ができる副業まとめ!
ここからは、公務員でもできる副業を紹介していきます。ただし、さまざまな条件を満たさなければならない点には注意が必要です。
不動産投資
公務員の場合の不動産投資は、不動産賃貸として家賃収入を得る場合に副業が可能です。具体的には以下の条件が定められており、満たす場合は事前の許可は必要ありません。
・土地は10件未満
・駐車場は機械設備なしかつ駐車台数10代未満
・娯楽・遊戯設備および旅館・ホテルは禁止
・年間の賃貸収入額500万円未満
(参考:人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)
家業の手伝い
家業の手伝いは、無報酬の場合に限り許可なしでの副業が可能です。報酬が発生しない点から、副業とはいえないと感じる人もいるかもしれません。公務員のなかには実家で工場を営んでいるなどさまざまなケースがあり、休日に手伝う可能性はゼロではありません。その場合、国家公務員であれば無報酬に限り承認なしで副業が可能です。
ただし、わずかでも報酬が発生する場合には、人事院の承認が必要になるので注意しましょう。
NPO法人
国家公務員法・地方公務員法のいずれにも規定されている「営利目的」ではないことから、副業での活動が可能です。
ただし非営利活動法人であっても、以下の条件を満たしたうえで事前に人事院・上司の許可を得なければなりません。
・兼業先は非営利団体のみ
・社会通念上相当額の報酬
総務省が公開している「地方公務員の社会貢献活動に関する事業について」によると、兵庫県神戸市・山形県新庄市・佐賀県佐賀市などでは、独自の許可基準や制度を設けて積極的なバックアップを行っています。

自治体によっては地域貢献を目的とした制度が設けられていることもあり、このような制度を利用すれば許可を得やすいでしょう。
投資(株式、仮想通貨、NFT等)
株式・仮装通貨・NFTなどの投資は、公務員であっても副業として許可なく始められます。このような投資は資産運用のひとつであり、報酬を得る副業とは異なると考えられているからです。
ただし公務員としての勤務時間中に投資に関する取引を行った場合は、業務時間と重複していることから罰則対象になる可能性があります。
また公務員としての立場上、投資に関する未公開情報を得る機会があるかもしれません。そのような情報をもとに売買取引を行うとインサイダー取引と判断され、法律で罰せられるので注意してください。
アンケートモニター
アンケートモニターで得られる報酬は大きくなく、スマートフォンを活用してスキマ時間に稼げます。
このような稼ぎ方はあくまで節約術のひとつに分類されており、営利目的の副業に該当しないことから事前に許可を得る必要はありません。
フリマ出品
フリマ出品は本来の目的が不用品の販売であり、営利目的ではありません。そのため、公務員がフリマアプリ・サイトに不用品を出品して利益を得ても、整理整頓の一種として認識されます。あくまで不要になったものをフリマで売るというスタンスのもとで行う場合は、事前に許可することなく副業が可能です。
ただし転売目的・仕入を伴う場合には営利目的として認識され、公務員はできません。また転売目的の場合は公務員としての信頼も失う可能性があるため、罰則対象になる可能性があります。
小規模農家
自給自足目的の小規模農家の場合、公務員の副業が可能です。また、人事院・上司への事前許可も必要ありません。
あくまで自給自足であり、栽培したものはすべて自身・家族などで消費することが前提です。親戚・友人などに無料で配ることも認められています。
しかし「余った」「消費しきれない」といった理由から道の駅などで販売すると営利目的になるので、認められません。
執筆活動
執筆活動は、職務に影響しない範囲内で認められている副業です。職務に影響しない具体的な範囲内とは以下の通りです。
・営利目的ではない謝礼
・本職とは無関係の内容
公務員の副業として上記に該当する場合には執筆活動が認められますが、事前に人事院・上司などからの許可を得なければなりません。
また仮に執筆したものを販売した場合は、印税が発生します。この印税は謝礼ではなく報酬にあたり、営利目的での収入に該当するので受け取れません。
さらに執筆した内容が本職の守秘義務や信用失墜行為にあたる場合は活動できなくなるばかりか、罰則が課せられる可能性があります。謝礼が発生しない執筆活動であっても、守秘義務および信用失墜行為に触れる内容は禁止なので注意しましょう。
公務員が副業する時に避けるべき職種は?
公務員が副業する際に避けるべき職種として、以下のようなものがあげられます。
・データ入力
・アフィリエイト・YouTube
上記3つはなぜ避けたほうがよいのか、その理由を確認していきましょう。
イラストレーター
公務員が副業として避けるべき職種として、イラストレーターがあります。その理由は、作成したイラストを販売する際には、営利目的に該当するからです。
趣味で作成したイラストをSNSなどで無料で配布したり、ほかの誰かが作成したイラストと交換したりする際には該当しません。これらのケースでは、報酬が発生しないからです。
公務員は原則として、営利目的の報酬を受け取る行為は禁止です。自分で作成したオリジナルイラストをSNS・専門サイトで販売して収入を得た場合には営利目的の副業に分類されます。このような行為は公務員の原則に反することなので、知られると罰則の対象になるかもしれません。
データ入力
データ入力は、具体的な仕事内容によっては認められないかもしれません。具体的には以下のような内容がグレーゾーンにあたります。
・公益性が認められない内容
反対に以下のような内容であれば、人事院・上司に事前に相談すれば認められるかもしれません。
・報酬が発生しないデータ入力
ただし省庁・自治体によっては、データ入力そのものが認められない副業に分類されていることもあります。
データ入力は仕事の内容によっては手軽であり、業務時間を圧迫しない最適な副業に感じることもあるでしょう。しかし、報酬が発生するという点で限りなく黒に近いグレーゾーンであるため、許可なく受注して報酬を受け取ってしまうと罰則の対象になる可能性があります。
アフィリエイト・YouTube
アフィリエイト・YouTubeは、公務員が副業として認められる可能性が低い副業といえるでしょう。
これは成果報酬型ビジネスであり、発生する報酬は営利目的であることから公務員の副業としては認められません。
YouTubeは動画を配信することでフォロワー・閲覧者数を増やし、その人数や再生回数などで報酬を得る方法です。具体的な収益化の方法として、インプレッション型・投げ銭のほかに特定のサイトに誘導して商品購入・サービス利用に促すアフィリエイトがあります。これらの方法で得た報酬は営利目的にあたることから、アフィリエイト同様に公務員では禁止行為です。

いずれも報酬を得た場合には国家公務員法・地方公務員法に反するので、副業の職種として避けたほうがよいでしょう。
公務員の副業がばれてしまう主な理由とは?
公務員の副業がばれてしまう主な理由として、以下のようなケースがあげられます。
・確定申告
・社内の噂
それぞれのケースを詳しく確認していきましょう。
住民税の変化でバレる
副業をしていることが知られてしまうケースとして、住民税の変化があげられます。公務員の住民税は原則として、毎月支払われる給料からの特別徴収だからです。
住民税には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。
特別徴収の場合、納税決定通知書は徴収する企業・省庁・各自治体などに送付されます。住民税は原則として1年間の所得額に応じて決定されるため、納税額が著しく高くなっていると副業していることがばれてしまうのです。
確定申告でバレる
確定申告でばれてしまうケースもあります。確定申告でばれてしまうケースとは、副業で赤字が出た場合に行う赤字申告です。
赤字申告を行うと年間所得額が減少します。住民税は年間所得額をもとに計算されるため、年間所得額が減少すれば住民税の納税額も少なくなるでしょう。本来支払うべき納税額と比較して著しく減少している場合は、副業を疑われる可能性があります。
赤字申告を行ったからといって、必ずしも住民税額の減少で副業がばれるわけではありません。赤字の金額が少なければ住民税の変動も少なくなるので、ばれるリスクは軽減します。
社内の噂でバレる
社内の噂でばれるケースも無視できません。
先輩・同僚・後輩のなかには、内緒で副業をすることを快く思っていない人もいます。そのような人に直接副業を話をしなくても、どこで聞いているかわかりません。通りがかりに副業の話を聞いて人事院・上司などに告げ口をされる可能性があります。
また、話を聞いた人たちが悪気なくほかの人にしゃべってしまうかもしれません。人伝に広まる噂のスピードは想像している以上に早く、人事院・上司の耳に入ってしまうまであっという間です。

このように意図しない場所で噂話が広がり、その結果として副業がばれてしまうケースは多々ありますので気をつけましょう。
バレないようにするための方法
副業がばれないようにするためには、どうすればよいのでしょう。具体的には以下の2つの方法をおすすめします。
・SNSに注意する
それぞれのばれないようにする方法を紹介するので、参考にしてください。
社内のメンバーには話さない
副業していることを知られたくない場合は、自分から話さないことです。
仲の良い人であったとしても、副業に対して快く思っていないかもしれません。勤務先で副業・兼業を禁止している場合はなおさらです。
話した相手が実は副業をしたくても禁止されているからという理由で我慢している場合、副業している話を聞かされるとどんな思いをするでしょう。「ずるい」「自慢話のように聞こえる」と思われるかもしれません。
このような思いを抱いてしまうと我慢できず、人事・上司に話してしまう可能性があります。
また社内で副業の話をした場合には、意図しない誰かが近くで偶然聞いてしまうかもしれません。
これらに共通する原因は、自ら職場で副業の話をした点です。話さなければ副業している事実は誰も知らないので、勤務先にバレるリスクも軽減されるでしょう。
SNSで個人を特定される情報をあげない
SNSにも注意が必要です。SNSで公開した情報で個人が特定され、勤務先に副業がばれてしまう可能性があるからです。
Instagram・XのようなSNSは誰でも利用できるサービスであり、公開した情報はどんな人が見ているかわかりません。
たとえば、Xにて身分は隠した状態で、食事の写真を公開したり、出先の写真をアップしたり、仕事の愚痴や、副業のことを呟いたりしたとしましょう。バレるわけがないと思うかもしれませんが、全然バレます。小さな情報も積み重なると大きな情報となり、個人を特定されるリスクが高くなるのです。
副業でSNSを利用することはあると思いますが、個人を特定されるような情報は投稿しないこと、どうしても投稿したい場合は、日付をズラすなど、工夫すると良いでしょう。
公務員の副業がバレてしまった!一体どうなる?
公務員では原則として営利目的での副業は禁止されています。にもかかわらず人事院・上司への事前相談なく副業を行い、その事実が知られてしまった場合にはどのようなことが起こるのでしょうか?具体的には、以下のような罰則が課せられる可能性があります。
|
処分
|
内容
|
| 免職 | 職を失う処分 |
| 停職 | ・一定期間欠勤扱いとする処分 ・主な期間は数週間以上 |
| 減給 | 給料の減額処分 |
| 戒告 | 副業を行った本人の責任を確認したうえで注意する処分 |
上記の一覧表は一番上がもっとも重く、一番下がもっとも軽い罰則です。
公務員は国民への奉仕の精神が職務の根底にあり、営利目的での副業は禁止されています。すべての副業が禁止されているわけではなく、事前に相談すれば認められるケースもあるのが現状です。
公務員の副業の今後について
公務員の副業については、さまざまな議論・意見が交わされています。2018年1月に厚生労働省が副業・兼業に関するガイドラインを発表したことで、国全体としては副業・兼業を推奨する方向に進み始めました。
そのようななかで公務員だけは現状があまり変わっておらず、逆行していると感じる人も少なくありません。公務員の職務は奉仕の精神が前提となっているため、副業・兼業を解禁することに抵抗を感じる人たちもいるからでしょう。
しかし副業・兼業に対して厳しいといえる公務員の現状は、変わりつつあります。2025年には地方公務員の副業・兼業に対して「見直しが必要である」として、柔軟な姿勢が垣間見えた発言もありました。
まとめ
公務員の副業について解説しました。
公務員の副業・兼業に対する現状は、一般企業と比較すると難しいと言わざるを得ません。しかし、あらかじめ報告・相談すれば認められるケースもあります。

副業を始めたい場合は、事前に相談するなど正しい手順で行うようにしてください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか