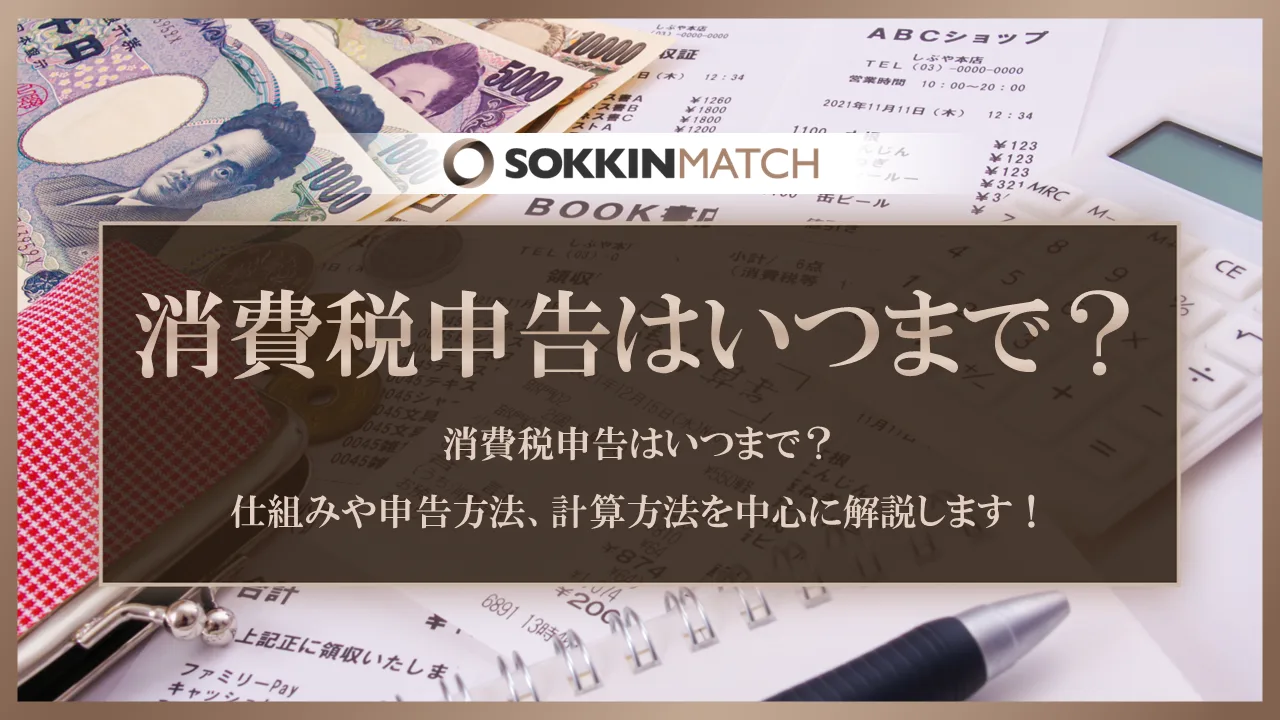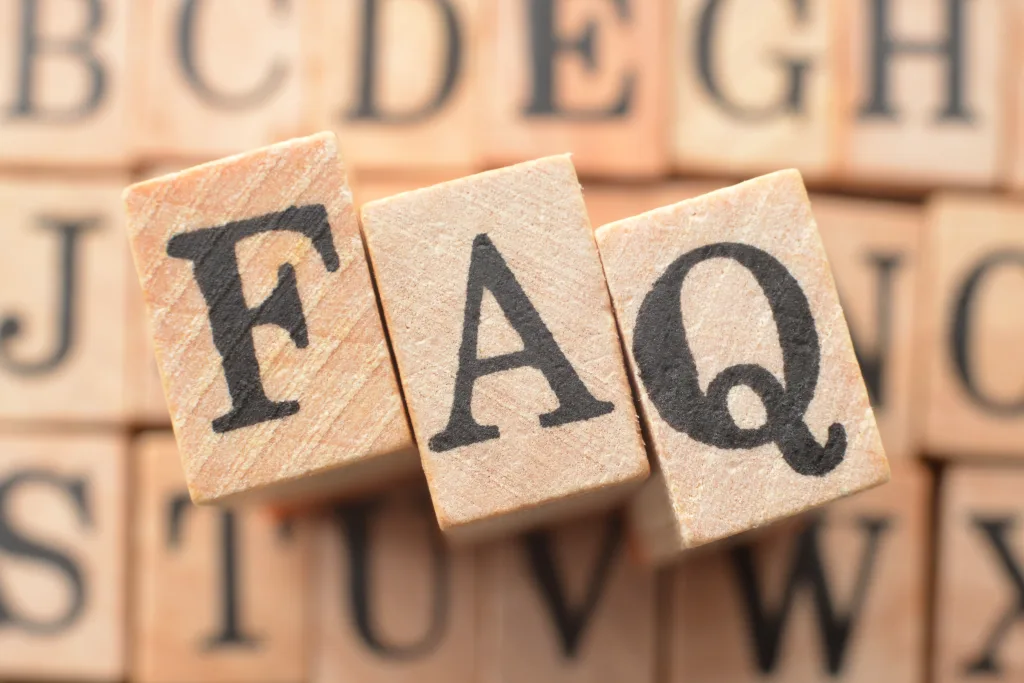インボイス制度の導入に伴い、免税事業者のなかには課税事業者に変更した人もいるかもしれません。その際に納税義務が発生する消費税ですが、法定申告期限・納期限内に手続きを行わなければペナルティが科せられます。
初めて消費税の申告・納税を行う場合には、期限・税金の計算方法などがわからないこともあるでしょう。
本記事では消費税申告全般を解説します。消費税の知識・理解を深めて正しい手続きで申告・納税を行いましょう。
課税事業者が行う消費税申告とは
課税事業者は、年間の売上総額が一定の金額を超えると消費税申告をしなければなりません。
消費税はほぼすべての商品・サービスに課せられており、購入・利用する際に支払われる代金に含まれています。
2024年現在、消費税は標準税率(10%)と軽減税率(8%)の2パターンで運用されていますが、申告する際にはそれぞれの税率ごとで分けて計算する必要があります。
なお後述しますが、消費税の申告・納期限はあらかじめ決められており、その期間内に申告・納税の両方を完了させなければなりません。
事業者は消費者の代わりに消費税申告を行う
消費税は間接税に分類されますが、これは納税義務者と申告義務者が異なるからです。
消費税の納税義務は消費者にありますが、実際に申告・納税の手続きは事業者が行います。消費者は申告・納期限内に手続きをする代わりに、商品の購入やサービス利用時に消費税もあわせて支払い、手続きを事業者にゆだねているのです。
売買取引で消費税を受け取った事業者は、あくまで納税額を預かっている形になるので、消費者の代わりに申告の手続きを行います。このとき、事業者は別の事業者などから商品を購入したりサービスを利用したりしているかもしれません。その場合は、取引で支払った消費税を受け取った消費税から差し引いて申告します。
詳しい計算方法については後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。
消費税申告の対象者とは
商品・サービスの取引を行う際には、ほとんどのケースで消費税が発生します。しかし、事業者は必ずしも申告・納税の義務が発生するわけではありません。
消費税の申告義務が発生する課税事業者と、義務が発生しない免税事業者それぞれの条件を確認していきましょう。
課税事業者になる場合
国税庁では、消費税の課税事業者になる条件として以下の4つをあげています。
2. 基準期間の課税売上高1,000万円以下かつ「消費税課税事業者選択届出書」提出済
3. 特定期間の課税売上高1,000万円超
4. インボイス発行事業者の登録済
(出典:【消費税及び地方消費税の申告等】|国税庁)
なお上記条件の「基準期間」と「特定期間」は個人事業主と法人で異なり、同一ではありません。
| 事業形態 | 基準期間 | 特定期間 |
| 個人事業主 | 前々年1月1日~12月31日 | 前年1月1日~6月30日 |
| 法人 | 前々年の事業年度 | 前年の事業開始日以降6カ月間 |
4つの条件のいずれか1つでも該当する場合は自動的に課税事業者となり、消費税申告の対象者です。
免税事業者になる場合
免税事業者になるには、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
課税事業者の場合は、条件のうちいずれかひとつでも該当していれば消費税の申告義務が発生します。
しかし免税事業者の場合、上記3つすべての条件を満たすことで申告・納税が免除されるので注意してください。例えば課税売上高が1,000万円以下であったとしても、適格請求書発行事業者に登録していると申告・納税を行わなけばなりません。
▼ 個人事業主である場合の消費税の計算方法はどうなるか?について知っておきたい方はぜひ

インボイス制度による影響
インボイス制度の導入により、免税事業者が自主的に課税事業者に登録する傾向が強まっています。免税事業者のままでは取引をしてもらえない可能性があるからです。
課税事業者は免税事業者と取引をすると、インボイスを発行してもらえないので損をします。
例えば課税事業者が税込7.7万円で購入した商品を、税込8.8万円で販売したとしましょう。仕入先がインボイス発行事業者だった場合、仕入時に7,000円の消費税を支払ったことを証明する請求書が発行されるので、納税額は8,000円から7,000円を差し引いた1,000円です。
しかし仕入先が免税事業者の場合、インボイスが発行できないので仕入値が7.7万円と認識されてしまいます。仕入時に支払った7,000円は消費税として認められないため、課税事業者が支払う消費税は8,000円です。
このように免税事業者と取引をすると課税事業者は損をするので、免税事業者は取引先が減少する可能性があります。
消費税の申告期限と納付期限はいつまで?
消費税の申告・納期限は事業形態によって決算月が異なるため、一律ではありません。また前期分の消費税納税額によって期限だけではなく、申告回数も異なります。
そこで前期の消費税納税額ごとの期限を一覧表で確認してみましょう。
| 決算月 | 中間申告・納付 | |||
| 前期消費税額 | 48万円超400万円以下 | 400万円超4,800万円以下 | 4,800万円超 | |
| 申告回数 | 年1回 | 年3回 | 左記の期日で年11回 | |
| 1月 | 9月30日 | 12月31日 | 6月30日 | |
| 2月 | 10月31日 | 1月31日 | 7月31日 | |
| 3月 | 11月30日 | 2月末日 | 8月31日 | |
| 4月 | 12月31日 | 3月31日 | 9月30日 | |
| 5月 | 1月31日 | 4月30日 | 10月31日 | |
| 6月 | 2月末日 | 5月31日 | 11月30日 | |
| 7月 | 3月31日 | 6月30日 | 12月31日 | |
| 8月 | 4月30日 | 7月31日 | 1月31日 | |
| 9月 | 5月31日 | 8月31日 | 2月末日 | |
| 10月 | 6月30日 | 9月30日 | 3月31日 | |
| 11月 | 7月31日 | 10月31日 | 4月30日 | |
| 12月 | 8月31日 | 11月30日 | 5月31 | |
なお前事業年度の消費税納税額が48万円以下の事業者は、中間申告の義務は発生しません。
申告期限は延長できる
前項目で中間申告の期限を紹介しましたが、原則としてその期限までに申告・納税ともに完了させなければなりません。
しかし法人は法人税の申告期限延長の申告を行い、その適用を受けている場合に限って消費税も期限延長が可能です。「消費税申告期限延長届出書」を管轄する税務署に提出すると、1カ月延長されます。
ただし延長が認められているのは申告期限のみであり、納期限の延長はされません。消費税の納税額には「利子税」が加算されるので注意してください。
消費税の期限後申告のペナルティ
消費税は法定期限が定められており、その期限内に申告・納税をしなければなりません。期限後に申告・納税を行った場合には、以下のようなペナルティが発生します。
・過少申告加算税
・不納付加算税
・重加算税
・延滞税
それぞれの内容・税率などを確認していきましょう。
無申告加算税
無申告加算税とは、期間内に確定申告をしなかった場合に課せられる罰金です。財務省が公表している具体的な課税要件は、以下のように規定しています。
2. 期限後の申告や決定について、修正申告や更正があった場合
(出典:加算税の概要|財務省)
加算税を算出する際の税率は増差本税の金額によって異なり、以下の通りです。
| 増差本税額 | 税率(年率) |
| 50万円以下 | 15% |
| 50万円超300万円以下の部分 | 20% |
| 300万円超の部分 | 30% |
(出典:加算税の概要|財務省)
ただし、期限内に確定申告を行わなかったからといって必ずしも無申告課税が課せられるわけではありません。「正当な理由が認められる」「予知しない修正申告や期限後申告」などの場合は、5%または免除されます。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告・納税した税金の金額が本来の税額よりも少なかった場合に課せられる罰金です。
加算税を計算する際に使用する税率は、以下の2通りあります。
| 条件 | 税率(年率) |
| 原則 | 10% |
| 期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分 | 15% |
ただし、本来の納税額よりも少なく申告したからといって必ず過少申告加算税が課せられるわけではありません。以下の要件を満たしていると認められる場合は、課税対象外です。
原則として自主的に修正を行った場合には、課税対象外になる可能性があります。
重加算税
重加算税とは、意図的な隠ぺい・仮装が認められる場合に課せられる罰金であり、さまざまな種類がある加算税のなかでは最も重い罰則です。
重加算税はほかの加算税に代えて課せられる罰則であり、その加算税によって使用する税率が以下のように異なります。
| 加算税 | 税率(年率) |
| 過少申告加算税 | 35% |
| 無申告加算税 | 40% |
(出典:加算税の概要|財務省)
延滞税
延滞税とは、法定期限内に税金を納付しなかった場合に発生する罰金です。
確定申告の期限は所得税の申告だけではなく、納税額が発生する場合には納付も完了しなければなりません。確定申告が必要であるにもかかわらず期限内に行わなかった場合には納税も遅れることになるため、必然的に延滞税も発生します。
| 納期限翌日から完納まで | 延滞税の割合 | |
| 2カ月以内 | 原則 | 7.3% |
| 現行 | 延滞税特例基準割合+1% | |
| 2カ月超 | 原則 | 14.6% |
| 現行 | 延滞税特例基準割合+7.3% | |
(出典:No.9205 延滞税について|国税庁)
なお、現行税率は毎年変動するので前年と同じ数字とは限りません。
消費税の計算方法
消費税の計算方法には、一般(原則)課税と簡易課税の2種類があります。
それぞれの計算式・算出方法などを確認していきましょう。
一般課税の計算方法
一般課税方式とは、売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税をマイナスして計算する方式のことです。
この方法は納税額を算出する際の基本的な計算式であることから、「本則課税」「原則課税」とも呼ばれています。
一見単純な計算方法に思えますが、実際の取引では課税・非課税・不課税・免税の4種類があり、これらを適切に区別して会計処理をしなければ正確な納税額は算出できません。
簡易課税の計算方法
簡易課税方式とは、以下のように簡単な計算式を用いて納税額を算出する方法です。
上記の計算式に使用する「みなし仕入率」とは事業区分によって定められている税率のことで、以下のように定められています。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
| 第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業) |
| 第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
| 第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く |
| 第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業など。
なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業。 |
| 第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除く |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業 |
消費税の軽減税率はいつまで?
軽減税率とは、2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられると同時に導入された制度です。
2019年9月までの消費税は一律8%でしたが、10月の消費税10%引き上げ時に一部の品目については8%に据え置かれることになりました。その結果、現在は8%と10%が混在する複数税率で消費税は運営されています。
2つの消費税率が混同していることから「消費税」という表現ではどちらを指しているのかわかりません。そこで原則税率の10%は「標準税率」といい、一部の品目が対象の8%は「軽減税率」と表現して区別しています。
終了時期は未定
軽減税率は一時的に導入されたものではないため、終了時期は未定です。
すべての商品・サービスを一律10%に引き上げてしまうと低所得者の悪影響・消費活動の落ち込みなどが懸念されたことから、生活必需品などに対しては軽減税率を適用したという背景があります。
多くの国民の生活に配慮した制度という一面もあることから、消費税全体の引き下げが行われない限りはこのまま継続されたほうがよいといえるでしょう。
軽減税率導入によって起こる事業者への影響
軽減税率導入によって事業に起こる影響について確認していきましょう。
経理処理の複雑化
軽減税率導入前、消費税の経理処理は一律で問題ありませんでした。例えば8%の一律だった場合、事業用として購入した商品・利用サービスなどにかかる消費税はすべて8%であり、分ける必要はありません。
しかし軽減税率導入後は8%と10%に分けて申請しなければならず、日頃から区別できるような経理処理が必要です。
例えば売上にかかる消費税を処理する場合、10%と8%にそれぞれ分けて仕訳をしなければなりません。また軽減税率(8%)対象のものはそれとわかる記載も必要であるため、導入前と比較して経理処理が複雑になったといえるでしょう。
軽減税率対象と対象外を区別できるレシートが必要
軽減税率導入後には、対象品目の区別ができるレシートを発行しなければなりません。
特に飲食店の場合、テイクアウトは8%が適用されますが、イートインの場合は10%を適用して消費税が計算されます。この区別をレシート上で明確に記す必要があり、その印字が自動で行われるシステム・レジの導入が必要不可欠です。
なぜレシートに区別できる印字が必要なのか、疑問に感じる人もいるかもしれません。商品購入・サービス利用などで発行されるレシートは消費税申告の際の必要書類として有効であり、正しく印字されていなければ申告時の証明書類としての役目を果たしません。
レシートは消費者にとっての単なる確認用紙だけではなく、申告の際の添付書類として使用されることもあるため、区別できる印字をしなければならないのです。
よくある質問
消費税におけるよくある質問と、その回答を確認していきましょう。
2025年の消費税の確定申告期限はいつまで??
消費税の確定申告の法定申告期限は、原則として3月31日までです。しかし最終日が土日と重なった場合には、翌平日にずれ込みます。
2025年は3月31日が月曜日であることから、通例通りのスケジュールです。
もし仮に3月31日が土曜日・日曜日と重なっていた場合は、月曜にまで延長されるのでカレンダーを確認してください。

上記の部分において要注意である確認事項があります!
それは、消費税と所得税でそれぞれ確定申告の期間が異なるということです。

それは、ぜひここで知りたい情報ですね!
教えてください!

消費税の確定申告における法定申告期限は、原則として3月31日までです。
一方で、所得税の確定申告における法定申告期限及び、期間は原則として、2月17日から3月17日です!
上記の事に留意して、申告を進めていきましょう!
軽減税率の目的とは
軽減税率が導入された目的は「終了時期は未定」で解説しましたが、国民の生活への圧迫を軽減させるためです。
具体的には低所得者への負担軽減ですが、実際には低所得者に限定されているわけではなく、国民全体が軽減税率の恩恵を受けているといえるでしょう。
▼ 軽減税率に関する有益な情報や意外な仕組みついて見てみたい、という方はぜひ

消費税率の今後は?
消費税率は今後どのように推移するのか、気になる人もいるかもしれません。
2019年の時点でIMF(国際通貨基金)は日本に対して、2030年までに15%、2050年までに20%まで引き上げるようにと勧告していました。しかしその後、コロナウイルスなど世界中を揺るがす大きな事象が発生し、その影響は世界経済にも影響を及ぼしています。
IMF(国際通貨基金)の勧告は2019年と古いものであることから、2030年までに15%まで引き上げられるかどうかは現時点ではわかりません。世界的な物価高などを背景に下がる可能性もゼロではなく、明確に予測を立てることは困難でしょう。
どのような推移をたどるにしても国から事前に正式な発表があるはずなので、定期的にニュースなどを確認してください。
税の申告が遅れてしまったときどうすればいいの?
法定期限後に税の申告をした場合、「消費税の期限後申告のペナルティ」で紹介した加算税の対象です。
ただし「申告理由に正当性がある」「税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告した」などに該当する場合は、加算税が免除されたり計算時に使用する税率が低くなったりする可能性があります。
申告が遅れれば遅れるほど加算税・延滞税は高くなるので、早めに申告しましょう。
申告を間違えてしまったら
申告内容を間違えた場合は、速やかに訂正を行ってください。
法定期限内に間違いに気づいた場合は、訂正申告で対応します。訂正申告とは、正しい金額で申告書を作成して再提出する方法です。このとき、申告書上部の空欄に全壊申告した年月日を赤字で記載しておきましょう。
期限後に間違いに気づいた場合は、申告した金額と本来の納税額の差額によって以下のように異なります。
| 訂正方法 | 概要 |
| 更正の請求 | ・本来の納税額よりも申告金額が高かった場合 ・申告年の翌年を起算日として5年まで |
| 修正申告 | ・本来の納税額よりも申告金額が低かった場合 ・延滞税等が発生 |
まとめ
消費税の申告について解説しました。
消費税は2通りで運営されていることから、申告書の作成等に複雑さを感じる人もいるかもしれません。しかし法定期限・納期限までに申告・納税を完了しなければペナルティが発生します。
本記事を参考に消費税の確定申告に関する知識・理解を深め、スムーズに手続きができるようにマスターしてください。
▼ 消費税に関する控除や仕組みについてさらに知りたい!という方はぜひ

副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。