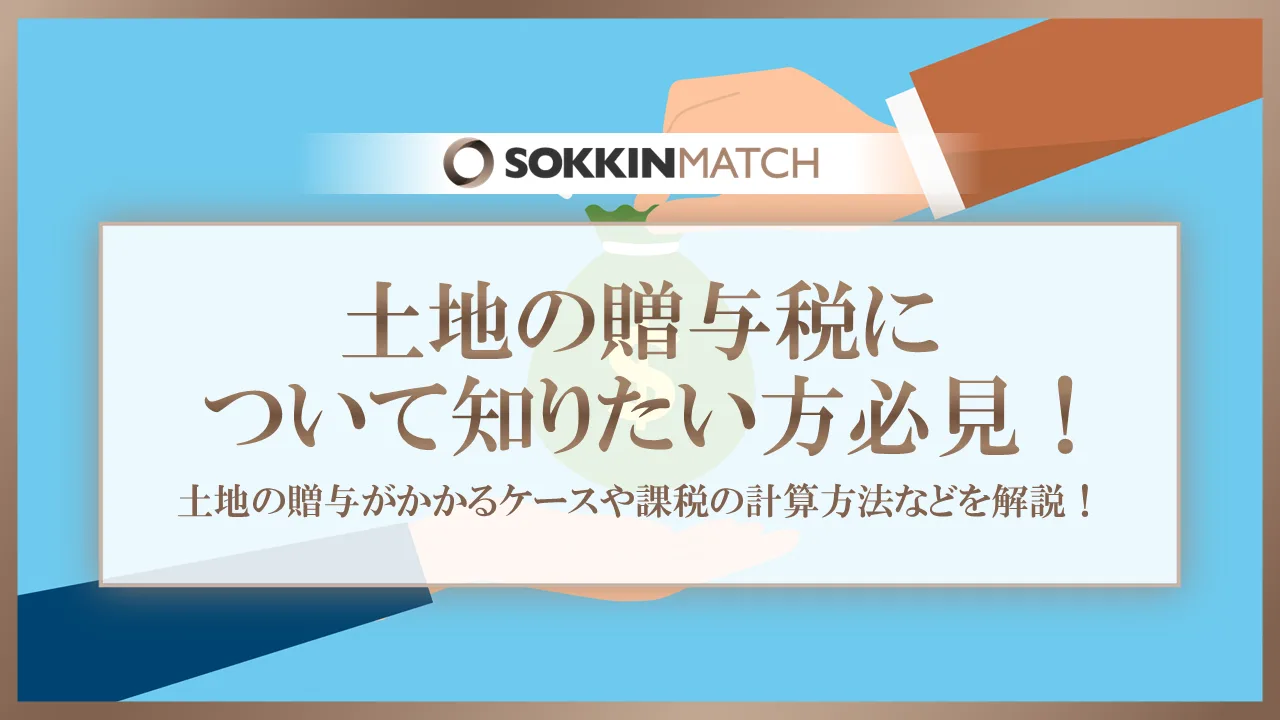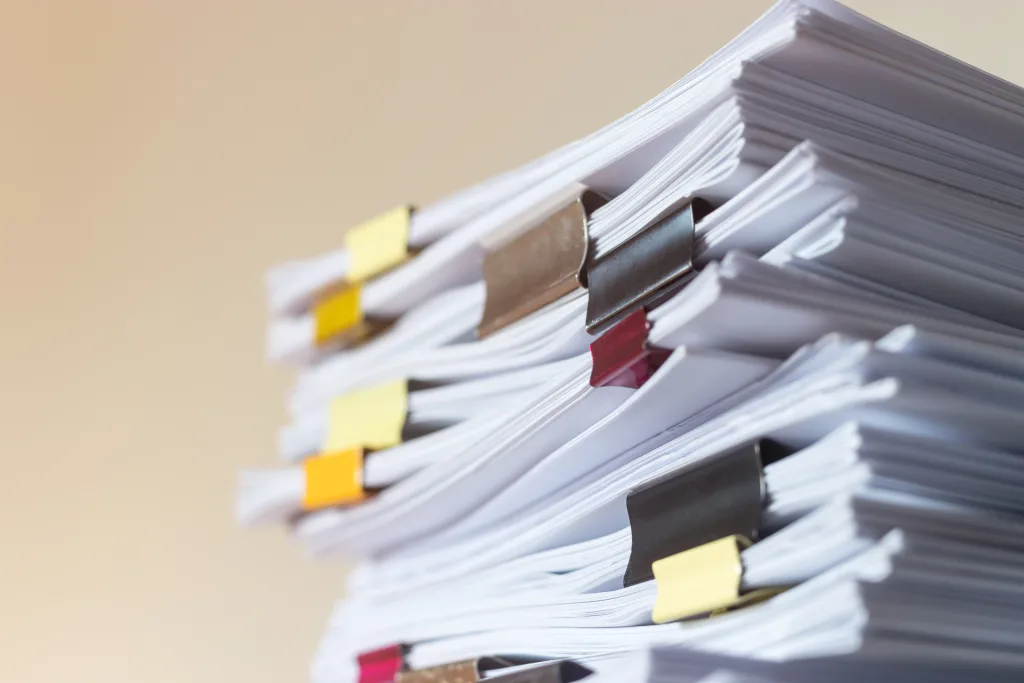親や親族などから土地の贈与を受ける人や、贈与を検討中の人にとって気になるのが、土地の贈与税ではないでしょうか?
「そもそもどのようなケースで贈与税がかかるの?」「税額の計算方法は?」「申告時の注意点は?」など、様々な疑問が出てくるでしょう。
贈与税の仕組みや計算方法を知らないままでいると、後になって予想外の負担が発生することもあります。
贈与税とは
財産を贈与する人が「贈与者」、贈与を受ける人が「受贈者」と呼ばれ、この2者が意思を持って金銭や土地などを引き継ぐことを贈与と呼びます。
贈与される財産は現金や預金など金銭だけでなく、土地や建物、有価証券や自動車なども対象です。
毎年1月1日〜12月31日までの期間に贈与を受けた財産が110万円を超えると、その超えた部分に贈与税がかかります。
贈与税が課税される場合は、財産を受け取った受贈者が翌年の2月1日〜3月15日までを期限として贈与税の申告書を提出し、納税する必要があります。
土地の贈与がかかるケース
まず、土地の贈与税が課税されるのはどのようなときなのか、贈与税がかかるケースについて見ていきましょう。
親族など関係なく土地名義を変更したとき
土地を所有している人から別の人へ、土地の名義を無償で変更したときは、土地を贈与したことになり贈与税の対象になります。
血縁関係がない人同士だけでなく、親から子への名義変更など、たとえ親族間であったとしても贈与税が課税されます。贈与者と受贈者との関係性にかかわらず、無償で名義変更をすると贈与税が課税されますので注意が必要です。
親族間での贈与では控除が適用されるなどの状況で贈与税の税額が安くなることはあります。しかし、たとえ親から子への名義変更であっても課税対象となることには変わりないため注意しましょう。
土地の共有持分を変更したとき
もともとそれぞれの持分で共有所有している土地について、無償で共有割合を変更した場合、持分が増えた人に贈与税が課税されます。
土地の財産価値は土地の広さによって増加しますので、共有している土地の持分が増えると、所有する財産が増えたことになるからです。
無償で共有持分が変更された場合は、財産の一部を贈与したとみなされるため、贈与税がかかります。
土地を著しく低い価格で譲り受けたとき
土地を著しく低い価格で譲り受けたときは、対価を支払っている場合でも贈与税の課税対象となります。
このようなケースでは、対価として支払った金額と本来の時価の差額に対して贈与税が課税されます。

もし5,000万円の土地を500万円で購入できたらどうなると思いますか?

すごくお得ですね!

でも、その4,500万円の差額は「もらった」とみなされて贈与税の対象になるんですよ。
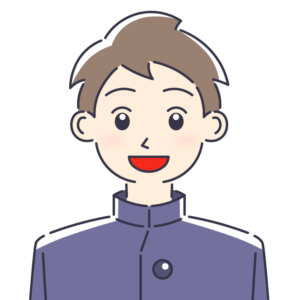
ただの安い買い物じゃないんですね…。
土地の譲渡で著しく低い価格と判断されないためには、一般的な目安として土地の時価の80%以上の価格なら問題ないとされています。ただし、明確な数字が示されているわけではありませんので、税理士などの専門家へ相談するようにしましょう。
共有の土地の分筆をしたとき
複数人で共有している土地を分筆した結果、分筆前に比べて土地の評価額が増えた場合、その増加分の土地を贈与したという扱いになります。
分筆とは、登記簿の上で1つの土地を、複数の土地に分けて登記し直すことを指します。

たとえば、評価額2,000万円の土地をAさんとBさんが3:1の割合で共有していたとします。
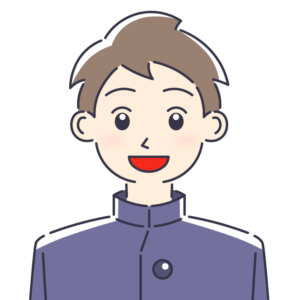
ということは、Aさんが1,500万円分、Bさんが500万円分を持っているんですね。

そうですね。その土地を1:1の割合で分筆すると、AさんもBさんも1,000万円ずつの土地を持つことになりますよね?

あれ?Bさんの財産が500万円増えました?

そうなると、BさんはAさんから500万円分の土地を「もらった」とみなされて、贈与税の対象になるんですよ。

分筆の仕方によっては、贈与税が発生するんですね!
負担付贈与をしたとき
土地を負担付贈与をしたときは、土地の本来の時価から負担分の差額に対して贈与税が課税されます。
負担付贈与とは、財産を無償で渡す代わりに受贈者に何らかの債務を負担させる形態での贈与のことです。
たとえば、土地を無償で贈与する代わりに、その半分のスペースを使わせてもらうという条件の場合は、負担付贈与となります。
負担付贈与では、土地の本来の取引価格から、受贈者が負担する債務の金額を差し引いた残りが課税対象です。
受贈者が負担する債務の分だけ贈与税が安くなりますが、土地の時価と負担分の差額に贈与税がかかりますので注意が必要です。
土地の贈与には2つの課税方法が存在する
土地の贈与には以下の2つの課税方法が存在します。
・相続時精算課税制度
以下でそれぞれどのような課税方法なのか見ていきましょう。
暦年課税制度
暦年課税制度では、毎年1月1日〜12月31日の期間で年間に贈与した財産の合計額に対して課税されます。贈与税の基本的な課税方式となり、事前に何も申請していない人は自動的に暦年課税が適用されます。
暦年課税制度では毎年110万円の基礎控除額があり、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が非課税となります。
そのため、年間110万円以下に分割して少額ずつ贈与することで、贈与税非課税で贈与しながら、将来の相続税の負担を軽減することができます。
ただし、暦年課税で贈与を行ってから7年を経過しないうちに相続が発生した場合は、相続税の計算時に相続財産に含める必要があります。
親から子への贈与など、受贈者が将来相続人になる可能性が高い場合は、下で説明する相続時精算課税制度と比較してどちらを選択するか検討するようにしましょう。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の親または祖父母から、20歳以上の子または孫に贈与を行うときに選択できる課税方式です。
相続時精算課税を選択すると、累積の贈与額が2,500万円までは贈与税がかからなくなります。その代わりに、将来相続が発生したときに相続税として課税されることになります。
また、令和6年度の改正で110万円の基礎控除額が適用されることになり、年間110万円までは累積の贈与額に含めなくてよいことになっています。
ただし、相続時精算課税で贈与した財産は期間に関係なく相続時の計算に含める必要があります。一方で、暦年課税では死亡日以前7年間より前の贈与は相続財産に含める必要がありません。将来いつ相続が発生するかによって税額に違いが出る場合があります。
一度相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻せませんので、慎重に検討するようにしましょう。
暦年課税制度と相続時精算課税制度の計算方法
ここでは、暦年課税制度と相続時精算課税制度それぞれの贈与税の計算方法について解説します。
暦年課税制度の計算
暦年課税では1年間の贈与の合計額から基礎控除額を差し引き、残った金額に税率をかけて税額を計算します。
計算式は以下のようになります。
暦年課税制度では毎年110万円の基礎控除枠があります。そのため、年間で贈与を受けた合計額が110万円以下の場合は、課税対象額が0円となるため贈与税がかかりません。
年間の贈与額が110万円を超える場合は、贈与を受けた合計額から-110万円の計算を行い、残った部分に税率を掛けて税額を計算します。
贈与税の税率は以下の2種類があります。
・特例贈与財産を贈与した場合の特例税率
特例贈与財産の贈与での特例税率は、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合に適用されます。
特例贈与財産以外の財産はすべて一般贈与財産となり、一般税率が適用されます。
2種類のいずれの税率も、贈与される財産の価格が大きくなるほど、贈与税の税率も高くなっていく累進課税となっています。
具体的な税率については、以下に国税庁ホームページに掲載されているそれぞれの税率の速算表を引用します。
- 一般贈与財産を贈与した場合の一般税率
|
基礎控除後の課税価格
|
200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 |
|
税率
|
10% | 15% | 20% | 30% |
|
控除額
|
ー | 10万円 | 25万円 | 65万円 |
|
基礎控除後の課税価格
|
1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
|
税率
|
40% | 45% | 50% | 55% |
|
控除額
|
125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
- 特例贈与財産を贈与した場合の特例税率
|
基礎控除後の課税価格
|
200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 |
|
税率
|
10% | 15% | 20% | 30% |
|
控除額
|
ー | 10万円 | 30万円 | 90万円 |
|
基礎控除後の課税価格
|
1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
|
税率
|
40% | 45% | 50% | 55% |
|
控除額
|
190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
出典:国税庁ホームページ
上記のように、親から子、祖父母から孫など、特例贈与財産を贈与した場合の特例税率の方が税率が低くなります。
暦年課税制度の注意点
暦年課税では1年間の贈与額の合計に対して累進課税の税率で贈与税が課税されます。土地の価格は高額になることが多く、贈与税の負担も重くなるため注意が必要です。
相続時精算課税でも相続時に税金がかかりますが、相続財産を支払いに充てることができるため、納税者の負担は軽く感じられる場合が多いです。
国税の納付は一括納付が原則なので、事前にどのくらいの贈与税がかかるのか大まかに計算しておくことが重要です。
また、暦年課税では毎年110万円の基礎控除があります。毎年基礎控除の範囲内で少額ずつ贈与すると贈与税がかからなくなりますが、状況によっては定期贈与とみなされる場合もあります。
定期贈与とは、一定期間にわたって一定額ずつ贈与するという契約のことです。たとえば、100万円の贈与を5年間にわたって毎年行うようなケースでは、500万円の贈与があらかじめ決まっていたものとして贈与税が課税される場合がありますので注意が必要です。
相続時精算課税制度の計算
相続時精算課税制度の適用を受けるときは、累積の特別控除枠が2,500万円あります。毎年の贈与額を累積していき、2,500万円に達するまでは贈与税が非課税となります。その代わりに、相続が発生したときに相続税として税額を計算して納税することになります。
さらに、2024年からは相続時精算課税にも基礎控除の110万円が新設され、年間110万円までは累積2,500万円の計算に含めなくてもよいことになっています。
相続時精算課税では、この特別控除枠の2,500万円を超えた部分に一律20%の税率で贈与税が課税されます。
計算式にすると以下のようになります。
このように、暦年課税と比較して税率が低いというメリットがあります。
特別控除枠を超えた部分は上記の計算により贈与時に贈与税を納税しますが、相続が開始されたときに相続税額を計算し、贈与税額と相続税額の差額が生じた場合は、還付を受けるまたは納付を行い精算することになります。
相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税制度の注意点として、暦年課税とどちらかしか選べないという点があります。
相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までの期間に税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出します。一度この届出書を提出して相続時精算課税制度の適用を受けると、その後は暦年課税に戻せなくなります。
相続時精算課税と暦年課税で、相続税も含めた合計の税負担に違いが出る場合がありますので、税理士などに相談しながら慎重に検討することが重要です。
また、相続時精算課税で贈与した財産は、相続税の計算時に、贈与した時点の価格で課税価格を計算します。今後値下がりしていく土地を相続時精算課税で贈与すると、値下がり前の高い価格をもとに相続税が課税されるため注意が必要です。
贈与の際の土地の評価額の計算方法
土地の贈与税の計算では、土地の評価額に税率を掛けて税額を求めます。
土地の評価額の計算方法には以下の2種類があります。
・倍率方式
以下でこれら2つの計算方法について解説します。
路線価方式
路線価方式とは、路線価が定められている地域で適用される評価額の計算方法です。
路線価とは、その地域の道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格を千円単位で表示する価格のことです。
路線価方式では、その地域の路線価を基準として、対象の土地の形状や広さなどにより補正した価格を算出します。
路線価を調べたいときは、国税庁ホームページの「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、財産評価基準を知りたい年度と地域を選択することで簡単に調べることができます。必要に応じて確認しておくようにしましょう。
参考リンク:財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
倍率方式
路線価が定められていない地域では、倍率方式で評価額を計算します。
倍率方式では土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて求めます。贈与する土地の種類によって計算に使う倍率が変わります。
固定資産税評価額は、各自治体が固定資産税を課税するために決めている価格です。具体的な評価額価格は各自治体の窓口(都税事務所や市・区役所など)で確認することができます。
▼ 贈与税の計算方法の詳細についてはコチラ!

土地の贈与税の節税方法
ここからは、土地の贈与税の負担を軽減できる節税方法について解説します。
暦年課税の基礎控除を利用する
暦年課税には毎年110万円までの基礎控除があります。この仕組みを活用することで、贈与税の負担を減らして土地を贈与することができます。
たとえば、1,500万円の土地を贈与するときは、年間100万円程度に分割して15年間かけて贈与すれば、非課税で贈与できます。
少しずつ贈与する方法としては、共有持分を設定して、受贈者の持分を1年間で100万円程度ずつ増やしていくという方法が考えられます。
ただし、毎年同じ金額を同じ時期に繰り返し贈与すると、定期贈与とみなされて基礎控除が適用できないこともあるため注意が必要です。
税理士など専門家に相談しながら、贈与契約書を作成するなどして少しずつ贈与を行えば、毎年の基礎控除枠を活用して節税をすることができます。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度を利用すれば、110万円の基礎控除に加えて累積2,500万円までの贈与は贈与税が課税されなくなります。評価額の高い土地を暦年課税で贈与すると翌年の贈与税が高額になるため、相続時精算課税を利用して負担を軽減することができます。
ただし、贈与税が非課税となる2,500万円分の財産についても、最終的に相続が発生する際には相続税の課税対象となります。特別控除枠2,500万円分の税金を払わなくてよくなるわけではありませんので注意が必要です。
それでも、相続税は預金や現金などの相続財産を資金として支払えますので、納税者の負担は軽くなります。すぐに支払うべき贈与税を節税できるという意味で、相続時精算課税の利用を検討してみるとよいでしょう。
贈与税の配偶者控除(おしどり控除)を利用する
夫婦間で土地の贈与をするときは、贈与税の配偶者控除を利用することで大幅な節税が可能です。この制度は、通称として「おしどり贈与」と呼ばれています。
おしどり控除を適用するための条件は、結婚してから20年以上が経過していることと、自宅のための宅地の贈与で、居住用不動産の取得に伴う土地の贈与である必要があります。
特例の条件を満たせば、通常の基礎控除110万円に加えて、最大2,000万円まで非課税で土地を贈与することができます。
親の土地を一部無料で借りる
親の土地の一部を子が使用したい場合は、土地の贈与をする代わりに土地の一部を無料で借りるという方法があります。
土地の一部を借りるときは、通常は土地の所有者に対して金銭を支払います。しかし、所有者が親の場合は無料で借りることができるでしょう。
無料で土地を借りることを使用貸借と呼びますが、親子間の使用貸借では贈与税が課税されることはありません。
土地を借りるだけなら名義変更や共有持分の設定や変更をしないため、贈与税を課税されずに土地を使用できることになります。
貸家建付地にすることで相続税評価額を下げて節税する
土地を貸家建付地に変更すれば、相続税評価額が下がるため課税される税金も安くなります。
貸家建付地とは、賃貸アパートや貸家といった賃貸物件が建っている土地のことです。
貸家建付地は、建物を住宅として入居者に貸すことから、所有者が土地を自由に使ったり譲渡したりできなくなります。土地の所有権を持ちながら様々な制限があるため、相続税評価額も安くなります。
当面は受贈者が自分の用途で使う予定がない土地は、貸家建付地に変更してから贈与することで、贈与税を節税することができます。
住宅取得等資金贈与の特例を利用する
住宅取得等資金贈与の特例を利用することで、最大1,000万円までの贈与を非課税にすることができます。
住宅取得等資金贈与の特例は、直系尊属(父母や祖父母など)から、自分が住むための住宅の購入費用や建築費用の贈与を受けたときに適用されます。
基本的には建物を対象とした特例ですが、住宅とともに取得する土地や、住宅の増改築に伴って取得する土地にも、条件を満たせば適用することができます。
親や祖父母が資金を贈与して、贈与を受ける子や孫がその資金をもとに住宅と土地を取得する際に利用できる節税方法です。
▼ 贈与税の節税方法についての詳細はコチラ!

▼ 効果的な法人の節税対策はコチラ!

土地の贈与税申告時に必要な書類
ここからは、土地の贈与税を申告する際に必要になる書類について見ていきましょう。
贈与税の申告書
贈与税の申告書は主に以下の3種類があります。
・申告書第1表の2(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)
・申告書第2表(相続時精算課税の計算明細書)
上記のうち、「申告書第1表」は贈与税の申告で基本となる様式で、全員が提出する必要があります。残りの2種類については、制度の適用を受ける人のみが提出します。
「申告書第1表の2」は、住宅取得等資金の非課税の適用を受けるための申告書です。この制度の適用を受けるためには、「申告書第1表」と「申告書第1表の2」の合計2つの申告書を作成して税務署に提出します。
同様に、「申告書第2表」は相続時精算課税制度の適用を受ける人が提出する書類です。
贈与税の配偶者控除(おしどり控除)を利用する場合の書類
贈与税の配偶者控除(おしどり控除)を利用する場合は、贈与税の申告書に加えて以下の書類を提出します。
・受贈者の戸籍の附票の写し
・贈与の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書
・受贈者の住民票の写し
上記の書類で受贈者が配偶者であることが確認され、控除の対象となることを証明できます。
戸籍や住民票に関する書類は住んでいる自治体で発行を受けることができます。
相続時精算課税制度の適用を受ける場合の書類
最大2,610万円までの贈与で贈与税が非課税になる相続時精算課税制度の適用を受けたいときは、贈与税の申告書に加えて以下の証明書類を提出します。
・受贈者や贈与者の戸籍謄本または抄本(受贈者の氏名、生年月日、贈与者との関係が記載されたもの)
・受贈者の戸籍の附票の写しなど(受贈者が20歳になったとき以降の住所が記載されたもの)
・贈与者の住民票の写しなど
・贈与者の戸籍の附票の写しなど(贈与者が60歳になったとき以後の住所が記載されたもの)
相続時精算課税制度の条件として、贈与者が60歳以上で、受贈者の親または祖父母であることが必要です。受贈者だけでなく贈与者の証明書類も準備する必要がありますので注意しましょう。
土地の贈与税について相談するなら税務署か税理士どっちがいい?
土地の贈与税について不明点があるときは専門家に相談することが大切です。
相談する先としては、贈与税の納税先である税務署に直接不明点を質問したり、税理士に相談する方法が考えられます。
どちらの方法で相談するのがよいかはケースにより異なりますので、以下でメリットやデメリットを解説します。
税務署なら無料で相談できる
まず税務署に相談するメリットやデメリットについて解説します。
税務署は手続きの進め方に関する相談を無料でできるのが特徴です。
税務署に相談するメリット
税務署では、贈与税を含む国税の申告方法や税額の計算方法について、面談での相談や電話相談が可能です。
税務署での相談は費用を請求されませんので、無料で気軽に相談できるところがメリットです。
税務署に相談するデメリット
ただし、税務署での相談は一般的な内容しか回答してもらえないため注意が必要です。また、いかに税金を安くするかといった節税について相談することはできません。
税務署は土日祝日はお休みとなり、平日の日中しか営業していないため、仕事がある人などは相談できるタイミングがない場合もあります。
税理士なら節税もできる
次に、税理士に相談するメリットやデメリットについて見ていきましょう。
税理士のメリットとして、節税の話題もじっくりと相談できるという点があります。
税理士に相談するメリット
税理士に相談するメリットとして大きいのが、複雑な手続きが必要な申告を代理してもらうことができる点です。土地や不動産の贈与は金額が大きくなり、必要書類の準備も大変なので、専門家に任せることができれば心強いでしょう。
税理士に相談すれば一般的な手続き方法だけでなく、個別のケースごとの節税について相談することもできます。土地の現金での贈与税の比較や、贈与税と相続税の比較など、いかに税負担を軽減するかというポイントもじっくりと相談できます。
税理士に相談するデメリット
税理士に相談するデメリットは税理士に支払う報酬に費用がかかる点です。
特に、手続きを代理してもらう場合は贈与する財産の金額に応じた費用がかかりますので注意が必要です。
申告方法や計算方法の質問だけなら市区町村などで行われる無料相談を活用するのもひとつの方法です。
税務署か税理士に相談する際のポイント
このように、税務署に相談する場合と税理士に相談する場合で、それぞれメリットやデメリットがあります。
贈与を行うときの状況や相談したい内容で、どちらに相談するか決めましょう。
税務署に相談した方がいい場合
税務署に相談した方がいい場合は、単純に手続き方法や税額の計算方法が分からないというケースです。
窓口で手続き方法の説明を受けたり、電話での相談は無料で受けられます。自分で申告手続きをする際に簡単な不明点があるだけのときは、高額な税理士費用を払うよりも税務署に相談した方がよいでしょう。
税理士に相談した方がいい場合
税理士に相談した方がいい場合は、贈与税が高額になることが予想されるため、節税をしたいときです。
税理士の費用はかかりますが、それを上回る節税効果が得られれば、トータルの出費が安くなることが期待できます。
必要に応じて手続きの一部を任せれば申告ミスのリスクも減り、手続きに要する時間も短くなるでしょう。
土地を贈与する際の注意点
最後に、土地を贈与する際に気を付けたい3つの注意点について解説します。
親族でも贈与税は発生する点
土地の贈与税は、親から子への贈与のように、親族への贈与であったとしても発生する税金です。
親族なら税金の負担なく自由に土地を引き継げるというわけではありませんので注意が必要です。
ただし、配偶者控除や相続時精算課税など、親族であることで利用できる制度も多くあります。
また、土地の大きさや評価額なども贈与税がかかるかどうかに大きく影響します。判断が難しいときは税理士など専門家への相談を検討しましょう。
贈与税が非課税でも不動産取得税や登録免許税がかかる
土地を贈与するときに課税される税金は贈与税だけではありません。以下の2つの税金もかかります。
・登録免許税
不動産取得税は土地・建物などの不動産を取得した人に課税される税金で、2026年3月31日までは「土地の評価額 × 1/2 × 3%」の計算式で税額が決まります。
登録免許税は土地の名義を変更する際に「土地の評価額 × 2%」の税額が課税されます。
節税方法などを活用して贈与税が非課税になったとしても、上記の2つの税金は課税されるため注意が必要です。
死亡日以前3~7年間の贈与は相続財産に加算する
親から子へなど親族間で土地の贈与を行い、贈与税の課税方式で暦年課税を選択する場合は、将来の相続にも注意が必要です。
相続税の計算時に、死亡日以前の3〜7年間に行った贈与は、相続財産に加算しなければならないというルールがあるからです。
2023年までは死亡日以前の3年間が対象でしたが、2024年以降は7年間に変更されています。
近い将来に相続が発生する可能性があるときは、相続税の計算や相続時精算課税での贈与も含めて検討するようにしましょう。
まとめ
この記事では土地の贈与税について、基礎知識や税額の計算方法、注意点などを解説しました。
贈与税について理解を深めることで、予想外の税負担を避けつつ、安心して贈与を行うことができます。
贈与税の負担が高額になることが予想される場合は、税理士などの専門家に節税方法も含めて相談するようにしましょう。
ぜひこの記事でまとめたことを参考にしていただき、スムーズに土地の贈与を進められるようにしてください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか