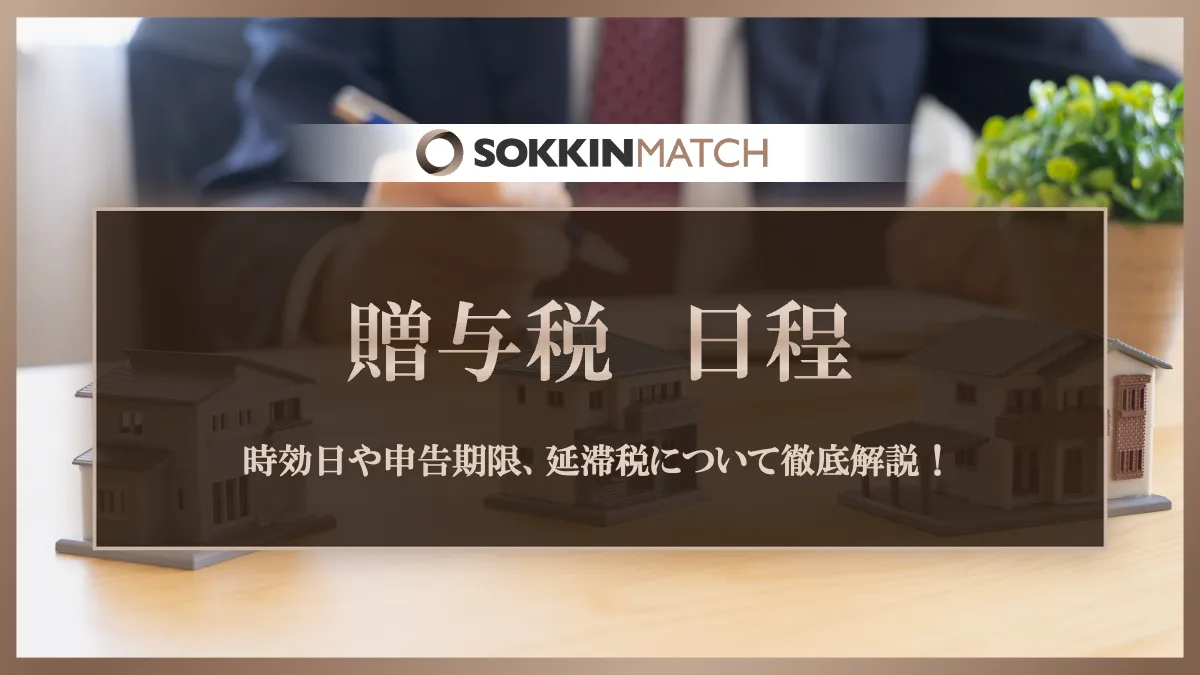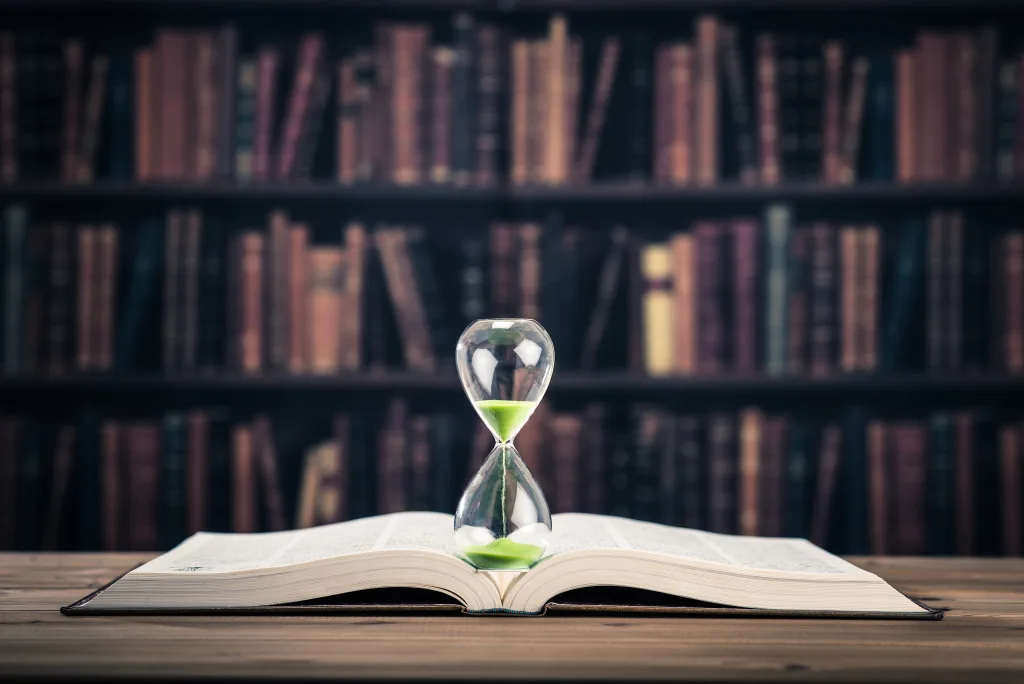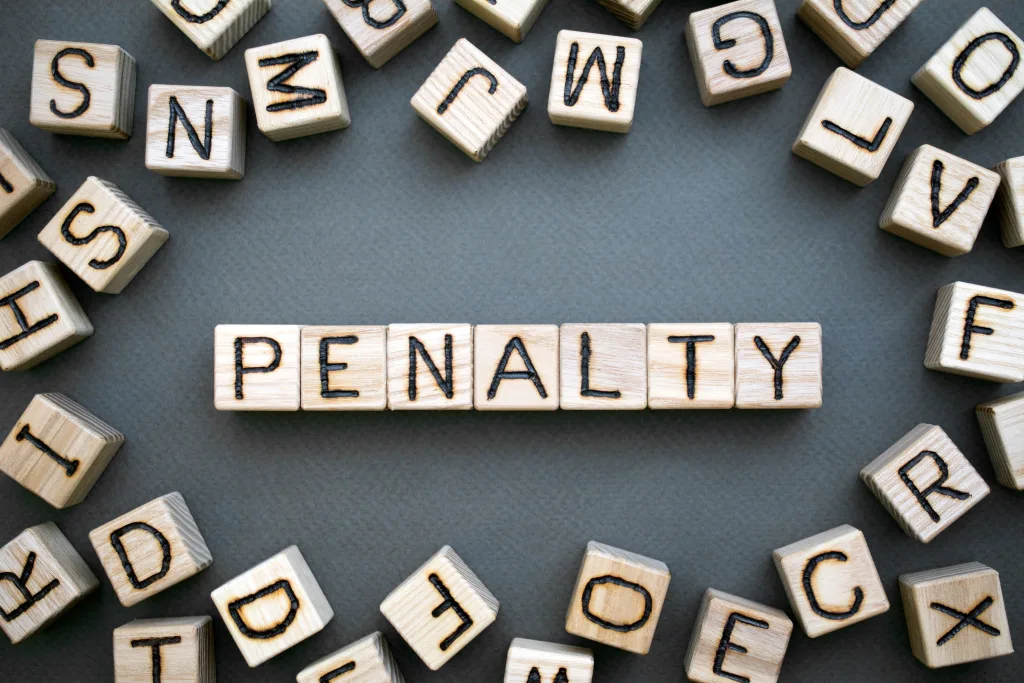相続税の節税対策として生前贈与を行うケースがありますが、贈与を受けた側は一定の条件を満たした場合に贈与税の納税義務が発生します。
贈与税には申告する際の法定期限と納税する際の納期限が設けられており、これらの期限までに申告・納税を完了しなければなりません。もし完了しない場合は延滞税が発生する可能性があるので注意してください。

本記事では、贈与税の申告期限・延滞税・時効について解説します。贈与税の申告・納税する可能性がある場合は、ぜひ参考にしてください。
贈与を受けた翌年の3月15日までに申告しよう!
贈与税の課税方式には「暦年課税方式」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。
暦年課税方式とは、1月1日〜12月31日までの1年間に受けた贈与額の総額に応じて贈与税が課税される方式のことです。ただし必ずしも課税されるわけではなく、1年間の総額が110万円以下の場合は申告・納税はともに発生しません。言い換えるなら、年間贈与総額が110万円を超えた場合には申告・納税が必要です。
また贈与される総額が一定金額を超えなければ贈与税が発生しない制度もあり、これを相続時精算課税制度といいます。限度額・税額計算の際に使用する税率については後述しますが、選択した場合には申告・納税が必要です。
このように課税方式には2種類の方法が設けられていますが、いずれも贈与税の納税義務が発生した場合には2月1日〜3月15日までに申告・納税ともに完了させなければなりません。
この期限は法定期限と納期限の両方を兼ねているため、申告のみを期限内に行って納税を忘れていた場合には延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。詳しいペナルティについては後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。
贈与税の申告義務があるケース
贈与税の申告義務があるケースを、暦年課税と相続時精算課税制度に分けて確認してみましょう。
暦年課税方式の場合、1年間に受けた贈与総額が110万円を超えた場合には申告・納税義務が発生します。

例えば1月1日〜12月31日までで現金200万円の贈与を受けた場合、控除額を差し引いた90万円に対して贈与税が発生するので、申告・納税ともに行わなければなりません。
相続時精算課税制度の場合は、年間に関係なく総額が2,500万円までは非課税対象です。しかし選択初回時と一定額以上の贈与を受けた際には、2,500万円を超えていなくても確定申告はしなければなりません。
110万円を超える贈与を受け取った場合
暦年課税方式の場合、年間贈与額が110万円を超えると申告・納税が必要ですが、納税額の算出に使用する計算の手順と式は以下の通りです。
2.贈与税=課税価格×税率-控除額
「2」の式で使用する税率と控除額は、課税価格と贈与財産の種類によって以下のように異なります。
【特例贈与財産】
|
基礎控除後の課税価格
|
200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
|
税率
|
10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
|
控除額
|
- | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
(出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁)
特例贈与財産とは直系尊属(祖父母から孫、父母から子など)による財産贈与のことであり、受贈者(孫や子)は成人していなければなりません。
【一般贈与財産】
|
基礎控除後の課税価格
|
200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
|
税率
|
10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
|
控除額
|
- | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
(出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁)
一般贈与財産とは特例贈与財産に該当しない場合の財産贈与のことで、兄弟間や夫婦間がこれにあたります。また親から子へ贈与財産は子が未成年者なら一般贈与財産に分類され、特例贈与財産の対象にはなりません。
相続時精算課税制度を利用する場合
相続時精算課税制度を利用する際には、初回時に贈与税の申告が必要です。贈与税の確定申告書類に「相続時精算課税選択届出書」を添付して税務署に提出します。
初回時に届出書の提出を伴う確定申告を行った後は、以下のいずれかのケースに該当する場合にのみ申告しなければなりません。
・贈与総額が限度額(2,500万円)を超えた場合
限度額(2,500万円)を超えた際に贈与税額を計算する際には、以下の計算式を使用します。
2,500万円を超えると、それ以降は贈与額に対して一律20%の税金が課せられ、基礎控除(110万円)の適用もされません。
またこの制度の適用を受けて贈与税が免税された財産については、贈与者が故人となった際に、贈与された時期の財産価額として相続財産に加算されて相続税の計算が行われます。
贈与税の申告が免除されるケース
贈与税の申告が免除されるケースは、主に以下の通りです。
2.生活費・教育費・お祝い金としての贈与
3.受贈者が贈与の事実を知らない場合
4.教育資金一括贈与の非課税制度を利用
5.結婚・腰建て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度利用
6.おしどり贈与の適用
7.住宅取得等資金の非課税制度を利用
8.特定障害者への贈与
残りの2〜8のケースについて、詳しく確認していきましょう。
生活費や教育費、お祝い金を贈与された場合
扶養義務者から生活費や教育費を目的として贈与されるものやお祝い金は、課税対象にはなりません。認められる主な範囲は以下の通りです。
| 主な例・範囲 | |
|
生活費
|
・日常生活に必要な費用 ・病院での治療代 ・養育費 など |
|
教育費
|
・学費 ・教材費 ・文房具の購入代 など |
|
お祝い金
|
・結婚のお祝い金 ・就職祝金 など |
生活費・教育費で課税対象外になるのはあくまで上記として認められる範囲内であり、名目上はこれらであっても預金や不動産などの購入に充てると贈与税の課税対象です。
贈与を受けた者が贈与の事実を知らない場合
受贈者が贈与されたことを知らない場合も、贈与税申告の免除対象です。
贈与とは贈与者と受贈者の間で財産を贈与するという明確な意思表示がなければ成立しているとは認められません。

具体的な例として、贈与に関する契約書が作成されていた場合が該当します。

贈与者が受贈者に相談なく受贈者の名義で口座を開設して預金をしていた場合はどうなるんですか?

「贈与の事実を知らないケース」に当てはまるため、申告が免除される可能性が高いでしょう。
教育資金一括贈与の非課税制度を利用した場合
以下の条件を満たすことを前提に教育資金として財産の贈与を受けた場合も、非課税です。
・受贈者は30歳未満の子または孫
・金融機関を介しての受け取り
・上限は1,500万円まで(学校以外の場合は500万円まで)
・2019年4月以降は受贈者の前年合計所得額が1,000万円以下
・2026年3月末までが対象
・受贈者の対象年齢までに使い切らなければならない
(出典:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|税務署)
上記の条件はすべて満たさなければならず、どれかひとつでも満たしていない場合は課税対象になります。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度を利用した場合
以下の要件を満たすことを前提に、結婚や子育ての資金目的で贈与された財産に関しては非課税対象です。
・受贈者は18歳以上50歳未満
・金融機関を介しての受け取り
・上限は1,000万円まで(結婚費用の場合は300万円まで)
・受贈者の前年総所得額が1,000万円以下
・結婚・子育て資金管理契約終了までに使い切らなければならない
(出典:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁)
おしどり贈与された場合
おしどり贈与とは以下の要件を満たせば、居住目的の不動産そのものまたはそのための資金2,000万円までが非課税になる制度です。
・居住用不動産またはその取得資金のいずれか
・居住用不動産が国内の家屋またはその敷地(借地権含む)
・贈与年の翌年3月15日までに、贈与された居住不動産または金銭で取得した居住不動産に居住、かつその後も居住継続見込み
・同配偶者から夫婦間居住不動産贈与の特例が未適用
・一定の書類を添付して贈与税申告
(出典:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁)
住宅取得等資金の非課税制度を利用した場合
子または孫が住宅を購入する際、資金援助を目的として財産を贈与する場合に適用される非課税制度です。以下の要件を満たすことで最大1,000万円までが課税対象から外れます。
・省エネ等住宅は1,000万円までだが、それ以外は500万円まで
・贈与される側の所得金額が最大2,000万円未満
・子や孫の配偶者は対象外
・贈与税の非課税対象でも申告が必要
(出典:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁)
この制度は条件が多く、上記にあげているものは一部です。受贈者の要件とあわせて住宅に関する要件も細かく設定されており、適用を受ける際には国税庁のホームページにて事前に確認しておいたほうが良いでしょう。対象のサイトは出典のリンク先に設定しているので、ご確認ください。
特定障害者への贈与の場合
特定障害者の生活費などを目的とした贈与財産は、以下の要件を満たすことで贈与税の納税義務が発生しません。
・信託会社を通じて贈与
・特別障害者の場合は上限6,000万円まで
・特別障害者以外の障害者のうち精神障害の方は上限3,000万円まで
(出典:障害者と税|国税庁)
なお、特定障害者とは以下に該当する人のことです。
2.特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある場合
(参考:障害者と税|国税庁)
▼ 贈与税の節税方法について知りたい方はこちら。

贈与税の時効は6年、故意的な場合は7年
贈与税は原則として申告期限内に申告・納税を完了させなければならず、期限を過ぎても支払義務があるにもかかわらず申告・納税しない場合は、加算税などのペナルティが科せられます。
ただし贈与税には時効が設けられており、その期限は原則6年です。この期限は「生活が困窮して支払いが難しい」「自然災害に見舞われた」「贈与されていたことを知らなかった」など正当性があると認められた場合の期間であり、脱税のような悪質と判断された場合には7年に延長されます。
時効の起算日は翌年3月16日
贈与税の時効は、確定申告の法定期限である3月15日の翌日3月16日からカウントします。
例えば、2010年4月2日に生前贈与を受けたとしましょう。この分の贈与税に関する確定申告・納税は翌年2月16日〜3月15日の法定期限内に行わなければなりません。時効のカウントは翌年2011年3月16日から始まり、通常なら6年後の2017年3月15日に時効成立です。
贈与税の時効が成立しているか注意が必要
贈与税には通常なら6年、悪質なものと判断された場合には7年の時効が設けられていますが、実際に時効が成立しているかどうかはわかりません。その理由として、以下のようなケースがあげられます。
・贈与が成立した証拠が必要
・意図的な時効成立待ちは不成立
それぞれのケースについて確認していきましょう。
不動産贈与の時効は登記の完了時点が起算日となる場合がある
不動産贈与の場合、時効のカウントが登記時点からスタートされることがあるので注意してください。
例えば10年前に贈与されていた土地を、受贈者の他界をきっかけに名義変更したとしましょう。名義が変更された事実は法務局から税務署に共有されるので、贈与があった事実が知られてしまいます。
贈与が成立した証拠が必要となる可能性がある
贈与税の時効は贈与の事実があったことが前提となっており、その事実が証明できない場合は贈与税の納税義務が発生しないので時効も成立しません。
例えば贈与者が受贈者の知らないところで受贈者のために、財産を金融機関の口座などに預金していたとしましょう。受贈者はその事実を知りませんし、贈与契約書も作成されていません。
このようなケースでは贈与税ではなく、贈与者が故人となった後に相続税が発生する可能性が高いでしょう。
故意的に時効を待った場合は成立しない場合も
意図的に時効を待ったと判断された場合は、時効が成立しない可能性があります。
例えば、生前贈与として高額な骨とう品を贈与されたとしましょう。受贈者は時効成立後に、贈与された骨とう品を売却しました。
贈与税の納付の遅れに対するペナルティ
相続税の納付が遅れると、以下のようなペナルティが科せられる可能性があるので注意してください。
2.無申告加算税
3.重加算税
4.過少申告加算税
それぞれのペナルティについて確認していきましょう。
延滞税
延滞税とは、法定期限内に税金を納付しなかった場合に発生する罰金です。
確定申告の期限は所得税の申告だけではなく、納税額が発生する場合には納付も完了しなければなりません。確定申告が必要であるにもかかわらず期限内に行わなかった場合には納税も遅れることになるため、必然的に延滞税も発生します。
延滞税を算出する際に使用する税率は以下の通りです。
|
完納時期
|
原則税率(年率)
|
| 2カ月以内 | 7.3% |
| 2カ月超 | 14.6% |
法定期限の翌日を起算日として2カ月を境に、上記のように原則税率が変わります。
延滞税の税率
前述で延滞税の税率について触れましたが、紹介した数字は原則税率と呼ばれているものです。しかし、実際の延滞税算出時には原則税率とは別の現行税率を使用することがあります。
原則税率と現行税率を比較した一覧表で確認してみましょう。
|
納期限翌日から完納まで
|
延滞税の割合
|
|
| 2カ月以内 | 原則 | 7.3% |
| 現行 | 延滞税特例基準割合+1% | |
| 2カ月超 | 原則 | 14.6% |
| 現行 | 延滞税特例基準割合+7.3% | |
(出典:No.9205 延滞税について|国税庁)
特例基準割合とは銀行の平均金利を12で割ったものに1%を加えたものであり、延滞税を計算するうえで使用する税率は本則と現行のいずれか低いほうとされています。
なお、現行税率は毎年変動するので前年と同じ数字とは限りません。
延滞税の計算方法
延滞税を算出する際に使用する計算式は、以下の通りです。
上記計算式の「延滞税の割合」には、「延滞税の税率」で紹介した原則税率と現行税率のいずれか低いほうを用います。原則税率は法改正等がない限り変更されませんが、現行税率は毎年基準となる特例基準割合が変わるため変動します。税率を計算する際には国税庁のホームページを確認のうえ、最新の税率を使用するようにしてください。
なお国税庁の「延滞税の計算方法」では、自動で納税額が算出できるシミュレーションシステムを公開中です。最新の税率で自動計算されるため、誤って古い税率を使用するリスクは顕現されるでしょう。
無申告加算税
無申告加算税とは、期間内に確定申告をしなかった場合に課せられる罰金です。財務省が公表している具体的な課税要件は、以下のように規定しています。
・期限後の申告や決定について、修正申告や更正があった場合
(出典:加算税の概要|財務省)
加算税を算出する際の税率は増差本税の金額によって異なり、以下の通りです。
|
増差本税額
|
税率(年率)
|
| 50万円以下 | 15% |
| 50万円超300万円以下の部分 | 20% |
| 300万円超の部分 | 30% |
(出典:加算税の概要|財務省)
重加算税
重加算税とは、意図的な隠ぺい・仮装が認められる場合に課せられる罰金であり、さまざまな種類がある加算税のなかでは最も重い罰則です。
重加算税はほかの加算税に代えて課せられる罰則であり、その加算税によって使用する税率が以下のように異なります。
|
加算税
|
税率(年率)
|
| 過少申告加算税 | 35% |
| 無申告加算税 | 40% |
(出典:加算税の概要|財務省)
過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告・納税した税金の金額が本来の税額よりも少なかった場合に課せられる罰金です。
加算税を計算する際に使用する税率は、以下の2通りあります。
|
条件
|
税率(年率)
|
| 原則 | 10% |
| 期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分 | 15% |
ただし、本来の納税額よりも少なく申告したからといって必ず過少申告加算税が課せられるわけではありません。以下の要件を満たしていると認められる場合は、課税対象外です。
・更正を予知しない修正申告の場合
原則として自主的に修正を行った場合には、課税対象外になる可能性があります。
▼ 贈与税の計算法などを詳しく知りたい方はこちら。

贈与を取り消した場合は6年以内なら返金される
受けた贈与を取り消した場合には、納税済みの贈与税が返金される場合があり、これを更正の請求といいます。
更正の請求の有効期限は法定申告期限最終日を起算日として6年間と定められており、その期間内ならいつでも申告が可能です。
更正の請求を行う際には国税庁の「贈与税の更正の請求書(令和4年分以降)の様式」から最新の請求書をダウンロードして必要事項を記入し、請求理由の根拠となる証明書類を添付して税務署へ提出します。
取消し又は解除されるケース
贈与の取消しまたは解除される主なケースは以下の通りです。
|
ケース
|
概要
|
| 詐欺または強迫など | 相手に騙された、または相手から暴力・脅迫を受けた場合 |
| 夫婦間の契約 | 経済力などから判断して贈与回避として認められない場合 |
| 未成年者の行為 | 未成年者や成年被後見人が単独で贈与を行った場合 |
上記のケースに該当する場合は、贈与があったとしても取消・解除される可能性があります。
まとめ
贈与税の申告日・納税日などを解説しました。
贈与税には法定申告期限・納期限があり、この期間を過ぎると延滞税などのペナルティが発生します。

ペナルティが発生すると本来の納税額に罰金がプラスされて高額になるので、定められた期限内に申告・納税の両方を行ってください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか