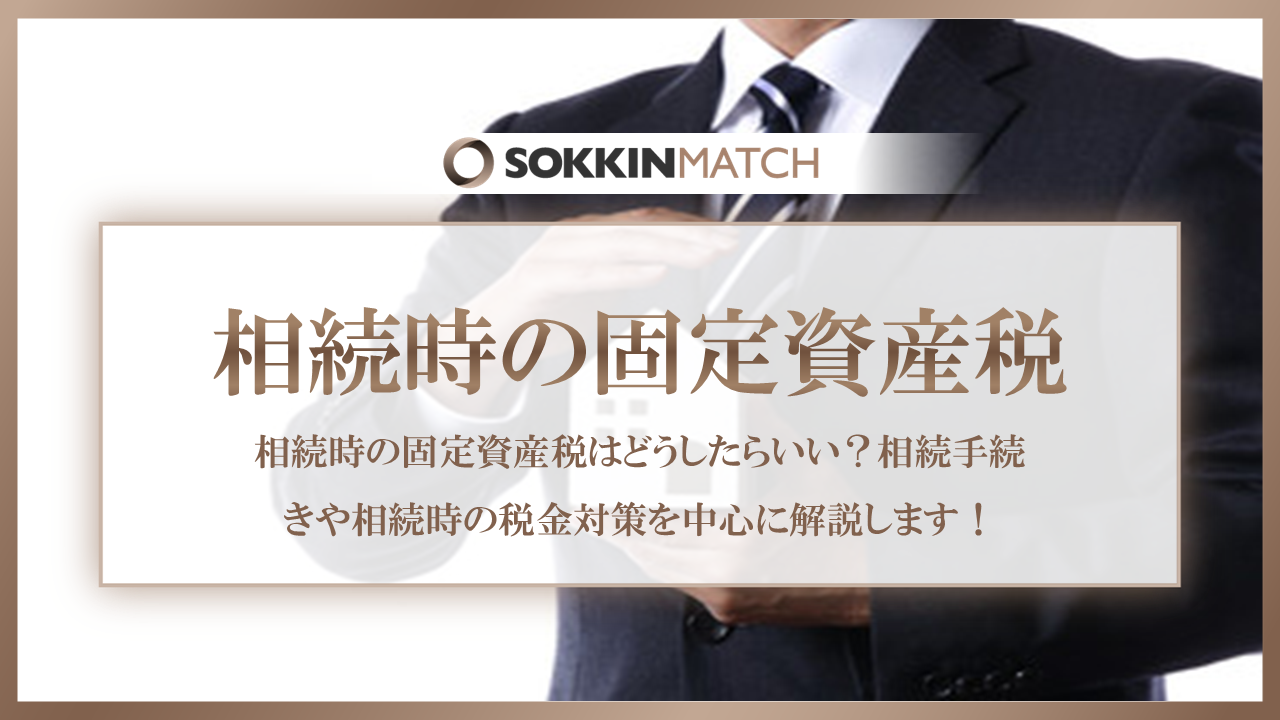相続時の固定資産税はどうしたらいい?相続手続きや相続時の税金対策を中心に解説します!
相続する遺産は現金・預貯金は、貴金属類などだけではありません。土地・家屋などの不動産を相続することもありますが、この場合に問題になるのが固定資産税です。
相続した土地・家屋などの固定資産税は、どのように手続きすれば良いのでしょう。
本記事では相続時の固定資産税の手続き・計算方法とあわせて、税金対策も紹介します。不動産などを相続する可能性がある人は、ぜひ参考にしてください。
固定資産税とは

相続時の固定資産税の手続きや計算方法・税金対策などを解説する前に、固定資産税そのものの知識・理解を深めたほうが良いでしょう。
固定資産税とはどのような税金でどんなものが対象になるのかを解説するので、参考にしてください。
▼ 固定資産税についてさらに詳しく知りたい方はこちらをクリック!

そもそも固定資産税とはどんなもの?
固定資産税とは、固定資産に課せられる地方税の一種です。納税者は固定資産の所有者であり、毎年一定の時期になると自治体から送付書が送られてくるので、それを利用して定められた納税額を納めなければなりません。
また、固定資産税のなかには都市計画税が含まれるケースもあります。
都市計画税とは、都市計画や土地区画事業の対象となっている市街化区域内に固定資産を保有している場合に課せられる地方税です。ただしこの税金は各自治体の判断にゆだねられており、すべての市街化区域で徴収されるわけではありません。
固定資産税の対象になるものは何がある?
固定資産税の対象になるものは3つに大別され、その区分とそれぞれの具体例は以下の通りです。
| 対象区分 | 主な例 |
| 土地 | 宅地、田畑、山林、牧場、原野など |
| 家屋 | 住宅、店舗、倉庫、工場など |
| 償却資産 | 運搬具(車、バイクなど)、備品(パソコン、事務机など)、事業者所有の構造物(フェンスなど)、飛行機、船など |
上記一覧表の償却資産については「地方税法第341条の4」にて、具体的に以下のように定められています。
- 土地および家屋以外の事業用の資産(無形減価償却資産以外)
- 減価償却費等が法人税法や所得税法に基づく損金または経費
- 取得価額が10万円以上
- 自動車税種別割対象並びに原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車以外
償却資産はイメージが湧きにくい人もいるかもしれませんが、取得価額が10万円以上かつ耐用年数1年以上のものと覚えておくとよいでしょう。
固定資産税の計算方法はどうやる?
固定資産税の納税額を求める際の計算式は、以下の通りです。
| 区分 | 計算式 |
| 固定資産税 | 課税標準額×1.4%(標準税率) |
| 都市計画税 | 課税標準額×0.3%(制限税率) |
市街化区域以外に固定資産を保有している場合は固定資産税の計算式で求められる納税額のみですが、市街化区域に保有している場合は都市計画税もあわせて納税しなければなりません。その場合は上記の都市計画税の計算式を用いて納税額を算出した後、固定資産税に合算して納付書が作成されます。
都市計画税課税対象地域に課税標準額1,500万円の土地を持っていた場合の納税額をシミュレーションしてみましょう。
| 固定資産税 | 1,500万円×1.4%=21万円 |
| 都市計画税 | 1,500万円×0.3%=4.5万円 |
| 納税額 | 21万円+4.5万円=25.5万円 |
▼固定資産税の計算についてさらに知りたい方はこちらをクリック!

相続時、固定資産税の納税者は誰になる?

遺産を相続する際には土地や建物などの固定資産も含まれますが、これらには固定資産税が課税されています。

相続時に納税者は誰になるんだろう?

相続したタイミングで納税額が完済されているケースは少ないから、支払金額が残っていることのほうが多いよ!誰が相続時に固定資産税を納税するのか確認するから、見てみてね!
1月1日の時点
固定資産税の納税者は、原則として賦課期日である1月1日時点での固定資産所有者です。
そのため、仮に1月1日に所有者が亡くなったとしても固定資産税の納税義務は故人に発生します。
1月1日以降に所有者が亡くなった場合は、「相続人代表者指定届出書」に必要事項を明記して自治体に提出してください。この書類は所有者の死亡届出を提出すると自治体から送付されてきますが、各自治体のホームページからダウンロードも可能です。相続人代表者の本人確認書類とともに提出すれば、納付書は代表者のもとに送られてきます。
相続が発生する前の時点
相続が発生する前の時点で所有者が亡くなった場合、固定資産税の納税者は原則として故人です。
しかし納付時期によっては納税義務もあわせて相続する可能性があるので、一概にはいえません。
固定資産税は、4回の分割と1年分をまとめて支払う一括払いの選択が可能です。納付書が届いた時点で所有者がまとめて一括払いを選択していれば固定資産税はすでに支払済なので、納税者は故人のままで変更はありません。
ただし分割払いを選択していた場合は納税額が残っているため、相続人は固定資産とあわせて残額分の納税義務も相続します。
相続発生後、不動産の相続人が決まっていない場合
相続発生後に不動産相続人が決まっていない場合の固定資産税は、相続人全員が分担して支払わなければなりません。遺産分割の処理・手続きが完了していない相続財産は、相続人全員が共有しているという考えがあるからです。
実際には話し合いで代表者が納税することが多いようですが、納税義務は相続人全員に発生しています。
納付書や評価証明書の送付先は1月1日時点での固定資産所有者宛てであり、納税する人の手元には届きません。
相続発生後、不動産の相続人が決まっている場合
相続発生後に不動産の相続人が決まっている場合は、相続人が不動産とともに納税義務も相続します。そのため、固定資産税の納税は相続人が行わなければなりません。
不動産の相続人が決定すると相続登記の所有者名義変更が必要になりますが、この手続きが賦課期日(1月1日)までに完了しない場合は、「固定資産現所有者申告書」を自治体に提出してください。
ただし、賦課期日(1月1日)までに所有者の名義変更が完了する場合は不要です。例えば該当する固定資産の納税額を一括払いしている場合は、次の賦課期日までに所有者の名義変更を完了すれば「固定資産現所有者申告書」の提出は必要ありません。
【具体例】被相続人が9月に亡くなった場合は?
被相続人が9月に亡くなった場合、固定資産税はどうなるのか考えてみましょう。
固定資産税の納期は自治体にもよりますが、4月・7月・12月・翌年2月と仮定します。被相続人が年4回の分割払いで納税していた場合、12月分と翌年2月分が未払になっているので相続人が負担しなければなりません。誰が固定資産を相続するのか決まっていない場合は、全相続人で負担して支払ってください。
一方、被相続人が一括払いをしていた場合は当該年の固定資産税は9月の時点で全額分の支払いが完了しています。そのため、その年分の固定資産税の納税義務は発生しません。ただし、翌年分の固定資産税については相続人に納税義務が発生します。
相続時の固定資産税はいくらになる?

不動産などを相続したときの固定資産税は、いくらになるのでしょうか。
固定資産税の金額や正確な納税額を確認する方法などを解説するので、参考にしてください。
時期によって固定資産税は変わる
所有者が故人となった固定資産にかかる納税額は、亡くなった時期によって異なります。その理由は前項目の具体例でも解説しましたが、それまで所有者だった被相続人が納税している可能性が高いからです。
所有者が1月や2月など固定資産税の納付書が届く前に亡くなった場合は、その年の納税額がすべて残っている状態なので相続人は全額を負担しなければなりません。
しかし納付書が手元に届いてから所有者が亡くなった場合、年4回の分割払いのうち何回分かは支払われており、相続人は残額を支払うことになります。
また、固定資産税は一括納付も可能です。所有者が手元に納付書が届いた時点で一括納付を選択しているとすでに全額納付済なので、相続人にその年分の納税義務は発生しません。
このように、相続時の固定資産税は3つのパターンがあるので注意してください。
正確な納税額を確認する方法
納付書は所有者に届くため、相続後に正確な納税額を把握することが困難な場合もあります。所有者と同居していたり納付書の確認を普段からしていたりする場合は正確な納税額がわかるかもしれませんが、そのようなパターンに該当するケースはあまり多くありません。
固定資産税は地方税のひとつであり、毎年各自治体が納税額を算出して納付書を送付しています。誤った金額を納付すると延滞金などの罰則対象になる可能性もあるので、正確な納税額を把握しなければなりません。
そこで正確な納税額の確認方法を紹介するので、参考にしてください。
役所から届く納税通知書を見て確認する
一番良い方法は、役所から届く納税通知書を確認することです。
納税通知書とは、納税額・納付時期などを知らせるもので各自治体から送付されます。この通知書には固定資産税・都市計画税などの正確な金額が明記されているので、納税額を把握する際には大いに役立つ書類です。
ただし納税通知書は、納付書とともに固定資産の所有者に送付されます。
例えば所有者がこれらの書類をどこに保管しているのかわからない場合は、実家などを徹底的に探さなければなりません。短時間で見つかれば良いですが、どれだけ探しても見つからない場合は納期限までに納付が間に合わない可能性も考えられます。
「被相続人と同居している」「納付書などの保管場所を把握している」などに該当する場合はこの方法をおすすめしますが、該当しない場合は次に紹介する方法で確認しましょう。
役所で固定資産税の証明書を取得して確認する
役所で固定資産税公課証明書を取得することも、おすすめの方法です。
前項目で紹介した納付通知書が探しても見つからない場合は、以下の手順で証明書を取得してください。
| 申請書の入手 | ・「固定資産税証明書等交付申請書」 ・各自治体のホームページなどから入手 |
| 必要書類の準備 | ・戸籍謄本 ・除籍謄本 ・相続人の本人確認書類 |
| 申請書・必要書類の提出 | ・各自治体または市税事務所に提出 ・住宅家屋証明は市税事務所のみ |
固定資産税に関連する証明書は公課証明書以外にも「固定資産税評価証明書」「課税台帳記載事項証明書」「名寄帳」などがありますが、固定資産税・都市計画税の納税額を知りたい場合は公課証明書を取得してください。
各自治体の窓口で事業等を説明すると、どのような証明書を取得すれば良いか教えてもらえます。証明書を取得する前に、窓口で相談してみることもひとつの方法でしょう。
固定資産税の評価額から税額を計算して確認する
固定資産税の評価額から税額を計算する方法もありますが、正確な納税額を把握するという観点からおすすめしません。誤った金額を納税すると、延滞金などの罰則が課せられる可能性があるからです。
「概算を知りたい」「どれくらいの金額を用意すれば良いのか把握して起きた」などに該当する場合は、以下の計算式を使用して算出してください。
納税額=評価額×税率
評価額とは固定資産におけるその時の価額であり、購入した際の金額ではありません。評価額の確認方法として、固定資産評価証明書の取得や市区町村で管理されている固定資産台帳を利用します。
また税率は標準税率1.4%を使用しますが、各自治体の条例によって税率が異なる場合があり、一律ではありません。使用している税率は、各自治体のホームページなどで確認できます。
固定資産税の相続手続きはどのように行えばいい?

固定資産税の相続手続きは、以下のような手順で行うのが一般的です。
- 納税額の確認
- 不動産登記簿の名義変更
- 現所有者申告
それぞれの手続き内容を解説するので、参考にしてください。
1.納税額を確認する
相続時の固定資産手続きをするためには、納付すべき正確な金額を確認することが重要です。
納税額の確認方法は、「正確な納税額を確認する方法」で紹介した「納付書での確認」または「固定資産税公課証明書の取得」のいずれかを選択してください。
前項目では、評価額から自分で計算する方法も紹介しています。しかし慣れていないと計算ミスなどをする可能性が高く、正確性という点でおすすめしません。
2.不動産登記簿の名義変更を行う
次に不動産登記簿の名義変更を行います。
実は、不動産登記簿の名義変更に法的な義務も期限もありません。しかし変更しておかないと「不動産売却ができない」「知らない間に団参社所有になっていた」などの問題が発生するリスクが高まります。
また固定資産税の納付書や納付通知書は所有者に送付されますが、所有者が他界した後に名義変更されていない場合は各自治体で独自に代表者等を設定して送付することが可能です。不動産を相続していないのに納付書だけが手元に届く、といった事態を引き起こしかねないので名義変更は行っておきましょう。
なお名義変更の手順は以下の通りです。
- 必要書類の準備
- 登記申請書作成
- 法務局で登記申請
- 法務局から書類を受領
登記簿の名義変更を行う際には、以下の書類を準備しなければなりません。
• 各相続人の戸籍謄本
• 不動産相続人の住民票
• 被相続人(前所有者)の住民票除票もしくは戸籍附票
• 遺産分割協議書(法定相続以外の割合で相続する場合)
• 各相続人の印鑑証明書(遺産分割を行った場合)
• 固定資産評価証明書
なお戸籍関係は、事前に相続関連の戸籍をすべてそろえて法務局に確認してもらうことで「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえます。この書類を作成しておくと、登記簿の名義変更以外に金融機関の口座解約手続きなど幅広く利用が可能なので便利です。
法定相続情報一覧図の写し発行を希望する場合は、必要書類・手続き方法などを各法務局に問い合わせしてください。
3.現所有者の申告を行う
現所有者申告は、不動産登記簿の名義変更ができない場合に行う手続きです。この手続きを行っておくと固定資産税の納税義務者が変更になり、納付通知書や納付書が現所有者のもとに送付されます。
現所有者申告を行う際に必要となる書類は、自治体によって異なるので同一ではありません。ここでは東京都を例にして紹介します。
| 区分 | 必要書類 |
| 基本書類 | ・申告者全員の住民票または戸籍除票の写し ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで確認できるもの) |
| 遺産分割未完了 | ・申告者全員の戸籍謄本 ・先順位法定相続人がいないことを証明できる書類(法定相続人が第2または第3順位の場合) |
| 遺産分割協議書あり | ・遺産分割協議書および法定相続人全員の印鑑登録証明書 ・法定相続人全員の戸籍謄本 ・先順位法定相続人がいないことを証明できる書類(法定相続人が第2または第3順位の場合) |
| 遺言書あり | 遺言書 |
(出典:現所有者申告のご案内| 東京都主税局)
手続きに必要な書類を正確に知りたい場合は、各自治体へ問い合わせてください。
相続時に行うべき固定資産税の税金対策とは?

相続する固定資産に未払い分の税金がある場合は、その税金も相続しなければなりません。この支払済固定資産税は、以下の方法で税金対策に活用できます。
- 債務控除の利用
- 必要経費計上
各税金対策を掘り下げて解説するので、参考にしてください。
債務控除を利用する
債務控除とは、相続した財産の価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引くことです。債務控除を行うことで相続税を算出する際の課税価格が減少し、相続税の節税対策ができます。
債務控除に該当する範囲は、以下の通りです。
| 債務区分 | 主な内容 |
| 債務 | ・第三者(金融機関)などの借入金や連帯債務 ・租税公課(所得税、住民税、固定資産税など) ・未払医療費 ・未払公共料金 ・その他の未払金(クレジットカード未決済分など) |
| 葬儀費用 | ・通夜や告別式の費用 ・葬儀関連の料理代 ・火葬料、埋葬料、納骨料、遺体搬送料 ・お布施、読経料、戒名料 など |
(参考:No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁)
固定資産税は債務のなかの租税公課に含まれており、被相続人の未払分を支払った場合にはその全額を債務控除として相続した金額から差し引きます。
必要経費として計上する
相続した固定資産が事業用の場合は必要経費として計上することで、節税対策が可能です。
ただし事業用固定資産を相続し、固定資産税を支払ったからといって必ずしも経費計上できるわけではありません。
- 準確定申告時
- 納税通知書受取済
準確定申告とは、年途中での相続発生時に1月1日から相続発生日までの所得額を相続発生翌日を起算日として4カ月以内に申告する方法です。
また、相続発生日までに納税通知書を受け取っている場合のみに限定されています。
例えば被相続人が11月に亡くなり、同月中に2回分(12月と翌年2月)の固定資産税未払の不動産を相続したとしましょう。11月に相続が発生した時点で納税通知書は受取済であることから、2回分の固定資産税の支払金額は経費計上が可能です。
しかし被相続人が1月中に他界して同月中に不動産を相続した場合、納税通知書は4月〜6月に送付されることから手元に届いていません。このケースでは「納税通知書受取済」に該当しないため、経費計上は不可です。
必要経費として計上できるかどうかは、相続した固定資産が事業用であることと相続した時点で納税通知書が届いているかの2つで左右されるので注意してください。
▼相続税の税率について詳しく知りたい方はこちらをクリック!

相続時の固定資産税が大きすぎる場合のオススメ対処法

不動産などの固定資産を相続した際、固定資産税が大きく過ぎることもあります。そのような場合は無理して税金を納めるのではなく、以下の対処法を検討してみてはいかがでしょうか。
- 不動産売却
- 役所・税理士・不動産会社に相談
- 相続放棄
それぞれの対処法を紹介するので、参考にしてください。
相続した不動産の売却を検討する
相続した不動産を売却すれば、課税対象がなくなるので固定資産税は発生しません。
ただし売却する際には以下の点に注意してください。
- 共有名義の場合は共有者全員の同意が必要
- 不動産売却益には所得税・住民税が発生
単独名義の場合は問題ありませんが、共有名義の場合は共有者全員の同意が必要であり、勝手に売却できません。
また売却した際には売却益が発生しますが、これには所得税(最大30.63%)と住民税(最大9%)がかかります。
固定資産税はなくなりますが、そのほかの税金が発生する点を考慮してください。
役所や税理士、不動産会社に相談する
役所・税理士・不動産会社に相談することもひとつの方法です。
例えば相続した土地と家屋に住み続ける場合には、前項目で紹介した不動産売却を行うと住む場所がなくなってしまうのでできません。
そのような場合は役所・税理士・不動産会社に相談すると、よい方法をアドバイスしてもらえます。

固定資産税は、自治体に認められれば更なる分納や1年間の支払猶予なども可能です。家を担保にしたリースバックといった方法もあるので、プロに相談してみましょう。
相続放棄を検討する
状況によっては、相続放棄も考えてみてはいかがでしょうか。
例えば不便な場所にある土地・家屋や被相続人に多額の負債があるといったケースでは、固定資産を相続すると負担が大きくなります。相続そのものを放棄してしまえば、不動産にかかる固定資産税の納税義務は発生しません。
ただし以下の点に注意してください。
- 検討期間は相続開始から3カ月以内
- そのほかの相続財産もすべて放棄対象
- 取り消し困難
相続時の固定資産税についてのよくある質問

相続時の固定資産税について、よくある質問とその回答を紹介します。
固定資産税の支払期限はいつ?
固定資産税の支払期限は、各自治体によって定められているので全国一律ではありません。6月・9月・12月・翌年2月の各月末の月末に設定されていることが多く見受けられますが、一概にいえないので各自治体に確認してください。
なお、支払期限を超過すると以下の税率で延滞金が課せられます。
| 延滞期間 | 税率(年率) |
| 支払期日翌日から1カ月以内 | 最大7.3% |
| 支払期日翌日から1カ月超 | 最大14.6% |
長期放置は財産差し押さえが実行されることもあるので、注意してください。
固定資産税の相続順位は?
固定資産税の相続順位は原則として遺言書に明記されているとおりですが、遺言書がない場合は以下のような順番で相続します。
| 順番 | 対象 |
| 常時 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子または孫 |
| 第2順位 | 父母または祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹または甥姪 |
債務控除以外に相続時に使える控除はある?
相続した不動産に適用できる控除制度は、債務控除だけではありません。以下のような控除制度も利用すると、固定資産税の負担額が抑えられるかもしれないので検討をおすすめします。
| 特例制度 | 内容 |
| 小規模宅地の特例 | 生活基盤となる土地・家屋を相続したが、相続税が高額で住めない場合 |
| 農地等の納税猶予の特例 | 被相続人が農業を営んでいた場合にその農地等を相続すると適用可能 |
上記2つの特例制度は当サイトで相続税の控除制度を紹介した記事にて詳しく解説・紹介しているので、あわせてそちらも参考にしてください。
相続時に必要な「固定資産税の課税明細書」はどう読めばいい?

不動産などの固定資産を相続する際には「固定資産税(都市計画税)の課税明細書」が必要です。しかしこの明細書はどのような書類なのでしょうか。
固定資産税の課税明細書について、申告に必要な情報とあわせて解説します。
そもそも固定資産税の課税明細書とはどんなもの?
固定資産税の課税明細書とは、1月1日時点で所有している土地・家屋の詳細を記載したものです。課税明細書には、主に以下のような内容が明記されています。
- 所在番地
- 現況地目・家屋の種類
- 課税地積や床面積
- 価格
- 税相当額
- 納付相当額
など
(参考:名古屋市:Q.固定資産税・都市計画税の課税明細書について知りたい。(暮らしの情報))
この明細書は相続税を申告する際に、土地の面積・評価額などを確認・計算する際に参考にするものです。
明細書の見方や必要な情報は次の項目で解説するので、あわせて参考にしてください。
課税明細書で申告に必要な情報は?
相続税の申告をする際に課税明細書の抑えるべきポイントを紹介します。
| 項目 | 内容・概要 |
| 「土地の所在」の「現況地積」 | ・現在の土地の面積 ・土地の評価額を算出する際に使用 |
| 「家屋の所在」の「価格」 | ・一棟全体の価格 ・家屋の評価額 |
課税明細書はさまざまな項目に金額などが記載されていますが、相続税の申告時に必要な情報は上記の2つのみです。
なお土地の評価額は、上記の現況地積に国税庁が公開・運営している「財産評価基準書」の路線価をかけて算出します。
家屋は計算する必要がなく、「家屋の所在」の「価格」に明記されている金額を使用してください。
まとめ
相続時の固定資産税を解説しました。
相続時の固定資産にどれくらいの税金が課せられているのか、また納税額の残高がどれくらいあるのかは意外とわからないものです。
相続した際の固定資産税の確認の仕方や手続き方法とあわせて節税対策なども紹介しているので、本記事を参考にして知識・理解を深めつつ、的確な方法で対処してください。
SOKKIN MATCHとは
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。