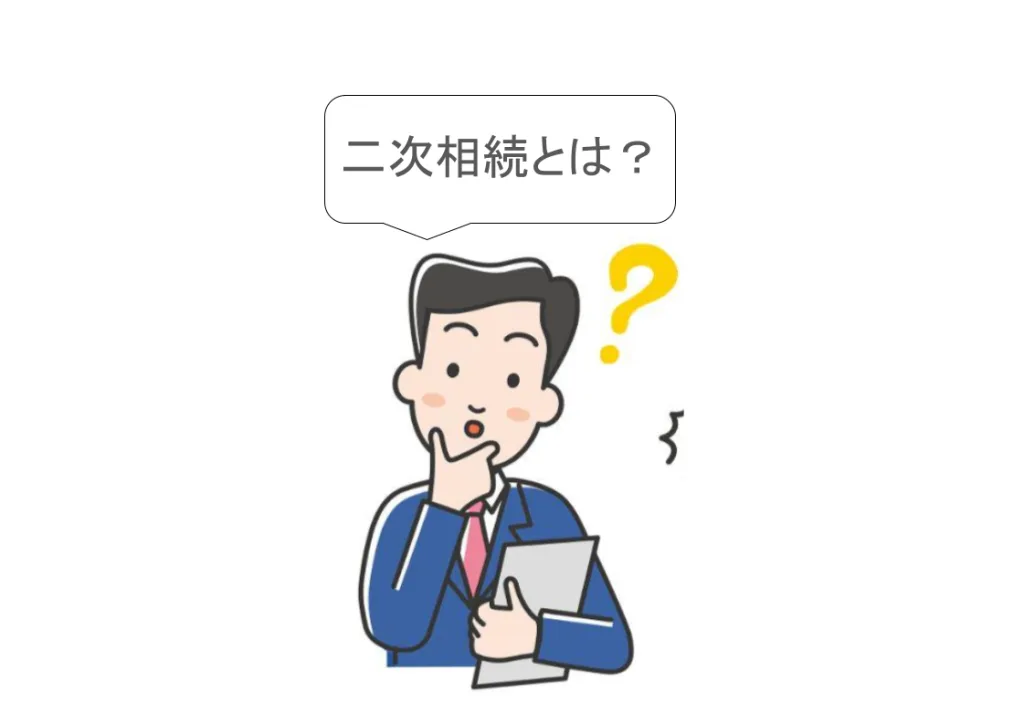故人の遺産を相続するとその相続額に応じて申告・納税の義務が発生する相続税ですが、申告期限は短く設定されており、税金関連の事務作業に慣れていない場合には困難に感じることもあるでしょう。
またすべての相続財産が課税対象になるわけではなく、納税額を計算する際にはこれらの分類も正確に行わなければなりません。

本記事では相続税の計算方法・申告の流れとともに、早見表も紹介します。今後遺産を相続する予定がある人や相続税についての知識・理解を深めたい人は、ぜひ参考にしてください。
そもそも相続税とは?
相続税とは、故人から財産を引き継いだ際にその財産の総額に応じて加算される税金のことです。
相続税は生家の経済状況の格差を縮小し、相続財産の一部を国に納税することで社会貢献につなげることで資産を再分配する目的として導入されました。
生まれながらの経済格差の縮小を本来の目的として導入した税金であることから、相続した財産の金額が大きくなればそれに比例して相続税の納税額も高くなるよう設定されています。
▼ 相続税がいくらから発生するのかはこちらで解説。

相続税の対象になる財産とならない財産とは?
相続税は受け継いだ財産に応じて課せられる税金ではありますが、すべての財産に対してかかるわけではありません。
相続税の対象の財産と対象外の財産をそれぞれ確認していきましょう。
相続税の対象になる財産
国税庁では、相続税の対象になる財産として以下のようなものをあげています。
・預貯金
・有価証券
・宝石
・土地
・家屋
・貸付金
・特許権
・著作権
上記のなかには金銭的な見積もりが可能なものも含まれており、「貸付金」「特許権」「著作権」などは経済的価値があると判断されることから課税対象です。
また上記以外にも国税庁では以下のような財産も対象としています。
2.被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、非上場会社の株式、事業用資産など
3.教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理財産
4.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
5.相続や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間内
6.被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
7.相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
8.特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
相続税の対象にならない財産
一方、相続税の対象外として認められている財産について、国税庁では以下のようなものをあげています。
2.宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4.相続によって取得したとみなされる生命保険金または退職手当金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
6.相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
相続税の申告がいる場合といらない場合とは?
課税対象の財産を相続しても、相続税の申告が必要なケースと不要なケースがあります。
どのような条件下で申告の有無を判断するのか、必要・不要それぞれにわけて確認していきましょう。
相続税の申告がいる場合とは
相続税は原則として、受け継いだ財産の取得価額の合計額が基礎控除額を超える場合に申告しなければなりません。
ただし上記の条件を満たさない場合でも、以下のケースに該当する場合は申告が必要です。
2.小規模宅地等の特例を受ける場合
3.農地の納税猶予特例を受ける場合
4.相続財産の寄附金非課税特例を受ける場合
上記4つはいずれも相続税の納税義務は発生しませんが、各特例の適用を受ける条件として申告が義務付けられています。「1」「2」の税額控除制度については後述しますが、利用する際には申告をしなければならない点に注意してください。
相続税の申告がいらない場合とは
相続した財産の取得価額の合計額が基礎控除額を下回る場合は、課税対象額が0円になるので申告は不要です。
また上記の条件で計算した課税対象額が1円以上であっても、以下の条件に当てはまる場合は申告義務は発生しません。
2.未成年者控除の適用を受けて0円になる場合
3.相次相続控除の適用を受けて0円になる場合
上記3つの控除制度については後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。
▼ 相続税の確定申告が遅れた場合についてはこちらで解説。

相続税早見表で概算額を素早くチェック!
相続税の計算は複雑であるため、概算だけが知りたい場合には自分で計算することを面倒に感じる人もいるでしょう。
そこで相続人が配偶者と子どもの場合と、子どものみの場合とにわけてそれぞれの概算を一覧表で示しました。あくまで概算であり、控除制度などを適用すると金額は変わります。正確な数字ではなく、目安としての金額である点に注意してください。
相続人が配偶者と子どもの場合の早見表
相続人が配偶者と子どもの場合の早見表は以下の通りです。
・配偶者控除の適用あり
・その他の控除制度の適用なし
|
課税価格
|
子ども
|
|||
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | - | - |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | - |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
| 4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 | 5,500万円 |
| 6億円 | 9,855万円 | 8,680万円 | 7,838万円 | 7,375万円 |
| 7億円 | 1億2,250万円 | 1億870万円 | 9,885万円 | 9,300万円 |
| 8億円 | 1億4,750万円 | 1億3,120万円 | 1億2,135万円 | 1億1,300万円 |
| 9億円 | 1億7,250万円 | 1億5,435万円 | 1億4,385万円 | 1億3,400万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
なお、上記の条件下のもとでは5,000万円以上から相続税が発生するので、それ以下の課税価格については作成していません。
相続人が子どものみの場合の早見表
相続人が子どものみの場合、課税価格に対する相続税は以下のような概算になります。
|
課税価格
|
子ども
|
|||
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
| 4,000万円 | 40万円 | - | - | - |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | - |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 320万円 | 320万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
| 6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 | 1億6,980万円 | 1億5,040万円 |
| 7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 2億1,240万円 | 1億9,040万円 |
| 8億円 | 3億4,820万円 | 2億9,500万円 | 2億5,740万円 | 2億3,040万円 |
| 9億円 | 4億320万円 | 3億4,500万円 | 3億240万円 | 2億7,270万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 9億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
(控除制度の適用なし)
相続税の計算方法や流れとは?
相続税を計算する際の主な流れは以下の通りです。
2.階税遺産総額を計算
3.相続税の総額を計算
4.相続税の総額を按分して税額控除を適用
それぞれの計算手順を詳しく確認していきましょう。
1.課税対象となる遺産の総額を計算する
相続税を計算するためには、課税対象の遺産総額を算出しなければなりません。
相続財産のなかには課税対象になるものと対象外のものとがあるので、目録などを作成して明確に分けてておきましょう。
なお対象・対象外の財産については「相続税の対象になる財産とならない財産」ですでに紹介しているので、そちらを参考にしてください。
2.課税遺産総額を計算する
課税遺産総額とは、「1」で算出した遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額です。
なお相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
法定相続人とは遺産を相続する人数のことであり、基礎控除額は法定相続人の人数によって高くなる仕組みです。
例えば法定相続人が配偶者と子ども3人の場合、基礎控除額は以下のように算出されます。
「1」で算出した遺産総額から上記の控除額を差し引いた金額が、課税遺産総額です。
3.相続税の総額を計算する
課税遺産総額が計算できたら、法定相続人の割合に応じて相続したものと仮定して相続税を計算します。
例えば配偶者と子ども3人の場合、全員が相続放棄をせずに財産を引き継いだ場合の割合は以下の通りです。
・子ども:配偶者が相続した残り2分の1を3等分
課税相続額が6,000万円だった場合、配偶者は3,000万円を相続し、子ども3人は1,000万円ずつ相続することになります。
この金額を以下の計算式にあてはめてそれぞれの相続税を計算しますが、計算式に使用する「税率」「控除額」は国税庁が公表している「相続税の速算表」を参考にするため、一律ではありません。
上記の計算式で算出した相続税の税額を最後に合算して、総額を算出します。
4.相続税の総額を按分し、各種税金控除の計算をする
実際に財産を相続する際には法定相続人の割合であるとは限りません。そこで、相続税の総額を実際の相続割合で按分して、税額控除を適用して最終的な納税額を算出します。
なお相続税で利用可能な主な控除制度は以下の通りです。
・未成年者の税額控除
・障害者の税額控除
・小規模宅地の特例
・相次相続控除
・贈与税額控除
それぞれの控除制度の適用要件や控除の割合などを確認していきましょう。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、被相続品の配偶者を対象に取得した症吽の遺産額が以下の金額のいずれか多い金額までは非課税対象になる制度です。
・配偶者の法定相続分相当額
ただしこの制度の適用を受ける際には、以下の条件を満たしていなければなりません。
・申告期限までに遺産分割を完了
・申告書を提出

内縁関係・事実婚などは認められないので、注意してください。また相続税が発生しない場合でも相続が発生した翌日から10カ月以内に申告書の提出をしなければなりません。
未成年者の税額控除
未成年者の税額控除とは、以下の要件に当てはまる場合に適用される制度です。
・相続した時点での年齢が18歳未満である人
・法定相続人である人
この制度の適用を受けるためには、上記3つすべての要件を満たさなければなりません。
なお、控除額は以下の計算式で算出します。
年齢は満年齢でカウントすることが原則となっており、例えば相続時点での年齢が15歳7カ月だった場合は15歳でカウントします。
障害者の税額控除
障害者の税額控除とは、満85歳以下の障害者を対象に相続税から一定額を差し引く制度のことです。
この制度の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
・障害者である人(一般・特例いずれも含む)
・法定相続人である人
(出典:No.4167 障害者の税額控除|国税庁)
なお控除額の計算式は一般障害者と特別障害者で以下のように異なります。
・特別障害者:20万円×(85歳-相続した時点での年齢)
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、相続した土地が居住用または事業用として使用している場合に適用される特例制度です。
利用区分によって適用される面積と減額割合は以下のように異なります。
|
利用区分
|
限度面積
|
減税割合
|
| 居住用 | 330平方メートル | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400平方メートル | 80% |
| 貸付事業用 | 200平方メートル | 50% |
(参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁)
相次相続控除
相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続が生じた場合に適用される税額軽減特例です。
この特例制度の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
2.相続開始前10年以内に開始した相続により相続人が財産を取得
3.相続開始前10年以内に開始した相続により取得した財産が課税対象
(出典:No.4168 相次相続控除|国税庁)
例えば父親が2017年に他界し、その際に配偶者である母親と子ども本人がそれぞれ父親の遺産を相続したとしましょう。3年後に母親が他界した場合、子どもは母親からの遺産を受け継ぐことになります。このときの相続財産が2017年に相続した財産であった場合は、この特例制度の対象です。
なお控除額を計算する際には、以下の計算式を用います。
贈与税額控除
贈与税額控除とは、支払済贈与税とこれから支払う相続税が二重課税にならないようにするための制度です。
生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2種類がありますが、それぞれに上限額が定められており、超えると金額に応じた贈与税を納税しなければなりません。
贈与税は相続税の代わりのような税金であることから、すでに贈与税を支払った財産・遺産については相続税が発生しないことが前提です。
なお贈与税額控除額は以下の計算式で算出します。
▼ 相続税の控除の種類について詳しく知りたい方はこちら、。

相続税の申告の仕方と納税の流れを紹介します!
相続税の申告・納税の流れは以下の通りです。
2.申告書の作成と提出
3.相続税の納税
上記の手順とともに法定期限と納期限についても確認していきましょう。
1.財産の評価して課税価格を計算する
相続税の申告をする際には、課税価格の計算をしなければなりません。
課税価格の計算方法については、「相続税の計算方法や流れとは」で解説しました。

ただし課税対象となる遺産の総額計算などは一般人には難しいこともあるため、「税金関連の知識に不安がある」「確定申告をしたことがない」などに該当する場合は、専門知識を有している人に依頼することをおすすめします。
2.申告書の作成して提出
課税価格の計算が完了した後は申告書の作成です。
国税庁の「B1-2 相続税の申告手続」では、最新の申告書の様式一覧が掲載されています。申請書の様式は毎年このページにて最新のものが掲載されるので、必ず新しいものをダウンロードして作成してください。
なお申請書の書き方もダウンロードが可能になっているので、これを参考にして作成しましょう。
作成した申告書は以下の方法で提出します。
・税務署へ郵送
・e-Taxを利用してオンライン送信
税務署の開庁時間は原則として平日8時半〜5時までとなっており、直接持参する際はこの時間帯に訪れるようにしましょう。
3.相続税の納税をする
申告書類の提出が完了したら、最後に相続税の納税です。国税庁では主に以下の方法での納付を推奨しています。
2.電子納税
金融機関または所轄税務署で納付する場合には、納付場所に納付書が用意されているので、必要事項を記入したうえで現金で窓口納付をしてください。
またe-Taxを利用した電子納税も可能です。インターネットがつながる環境なら自宅・職場など自由な場所から好きなタイミングで納付できます。納付方法はe-Taxのホームページにてご確認ください。
上記以外にもコンビニ納付・クレジットカードでの納付も可能です。コンビニ納付の場合は「G-2-6 コンビニ納付(QRコード)」を、クレジットカードで納付したい場合は「クレジットカード納付のQ&A」のサイトにて利用方法を確認してください。
相続税の申告期限と納税期限は?
相続税の申告期限と納税期限は、いずれも相続が発生した翌日を起算日として10カ月以内です。
10カ月を過ぎると延滞税などの追徴課税が加算されるので、早めに相続した遺産総額を算出して納税額を計算し、申告から納税まで行ってください。
相続税の手続きでe-Taxを利用したい方はこちら。
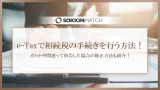
相続税の二次相続にも注意!
相続税における二次相続と注意点について解説します。
二次相続とは?
二次相続とは、一次相続の相続人であった配偶者が故人となった場合に発生する相続のことです。

例えば父親が他界した際に配偶者である母親と子ども2人が、父親の遺産を相続したとしましょう。これを一次相続といいます。その後、配偶者であった母親が他界してその遺産を子ども2人が相続しました。これが二次相続です。
二次相続を注意しなければならない理由とは?
二次相続で注意しなければならない理由として、以下のような点があげられます。
・相続人の減少
・小規模宅地等の特例が利用できない場合あり
それぞれの注意点を確認していきましょう。
配偶者の税額軽減がなくなるため
二次相続では配偶者の税額軽減が適用されません。
例えば父親が他界した場合に発生する遺産を相続する際には、配偶者である母親が存在しているので配偶者の税額軽減が適用されます。

しかし二次相続では配偶者であった母親が他界しているため、配偶者の税額軽減の要件は満たされておらず、適用されなくなるのです。
このことから相続税の金額が高くなる可能性があります。
相続人の数が異なるため
二次相続では法定相続人の人数が異なる点にも注意が必要です。
一次相続では、配偶者である母親も法定相続人に含まれていました。しかし二次相続では被相続人が母親であることから、法定相続人の人数は減少します。
法定相続人の人数が少なくなれば基礎控除額の金額も少なくなるので、相続税の納税額は反対に上がるでしょう。
小規模宅地等の特例が利用できない場合があるため
二次相続では、小規模宅地等の特例が利用できない可能性があるので注意してください。
この特例は、配偶者が小規模宅地を相続すると無条件で評価額の80%の税額軽減が適用されます。
しかし配偶者以外の親族が相続した場合、その住居に引き続き居住するなどの条件が追加され、適用要件が厳しくなるのです。

例えば二次相続での法定相続人の子どもが実家とは別の場所に居住していた場合、この特例は適用されません。
自分には難しいと感じたら専門家へご相談を!
相続税関連の相談は税理士と金融機関の2種類があります。
金融機関のなかには、簡単な相続税を試算したうえで対策もあわせて相談できるところがあり、このようなサービスを利用すると大まかな相続税の金額と具体的な対策が検討できるのでおすすめです。
一方の税理士は相続税にかかる全般の相談が可能であり、明確な遺産総額から相続税の計算まで行ってもらえます。依頼すれば申告書の作成や手続きなども依頼できるので、相続税だけではなく申告から納税のすべてにおいて不安を感じている人は相談するとよいでしょう。
まとめ
相続税全般の解説と、早見表の紹介をしました。
相続税は基本となる遺産総額の計算が複雑であり、さらに相続税の計算も決して簡単ではありません。また相続開始の翌日を起算日として10カ月以内に申告から納税前完了させなければならず、困難を感じる人もいるでしょう。

本記事では相続税全般について解説しましたが、「手に負えない」と感じた場合は専門家に依頼して正しい納税額で申告・納税されることをおすすめします。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか