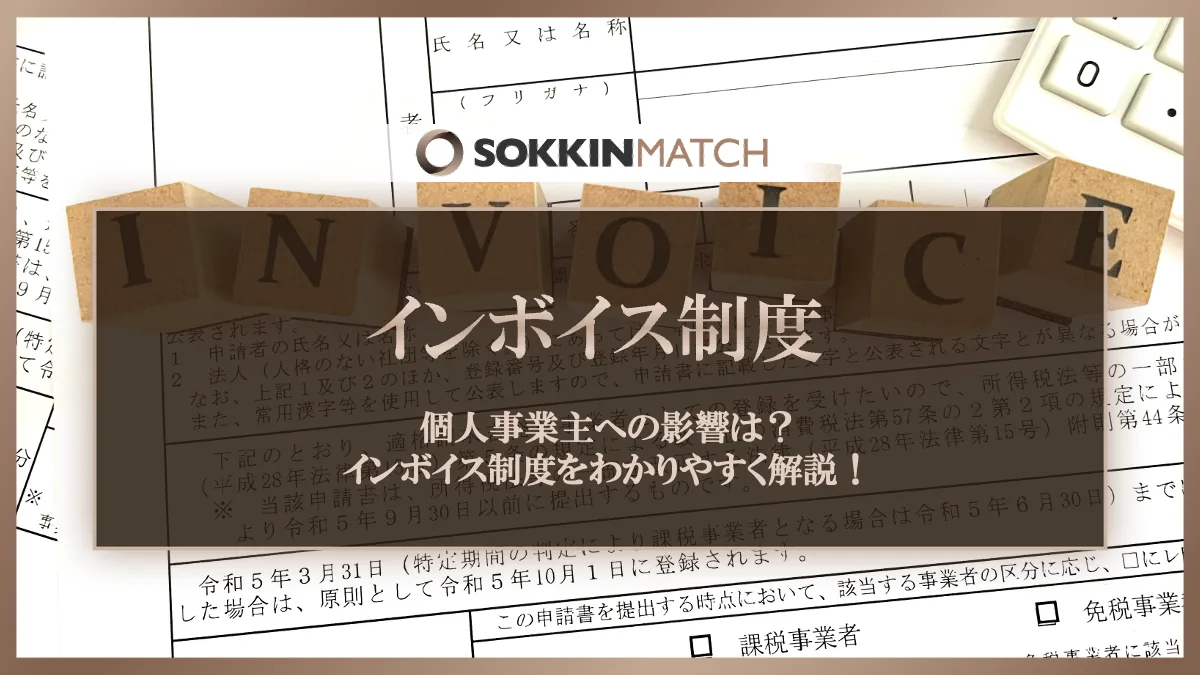2023年10月1日から始まったインボイス制度により、消費税における控除制度・請求書への記載事項などが変更されました。しかしこれまでの消費税に関する制度とは大きく内容が異なることから、混乱している人もいるでしょう。
インボイス制度は売り手・買い手の両方に影響があり、導入の有無によってもその対応方法が異なります。課税・免税のいずれも無視できない新制度です。
本記事では支援措置・個人事業主への影響も含めて、インボイス制度全般を解説します。ぜひ最後まで読んで、知識・理解を深めてください。
インボイス制度とは?
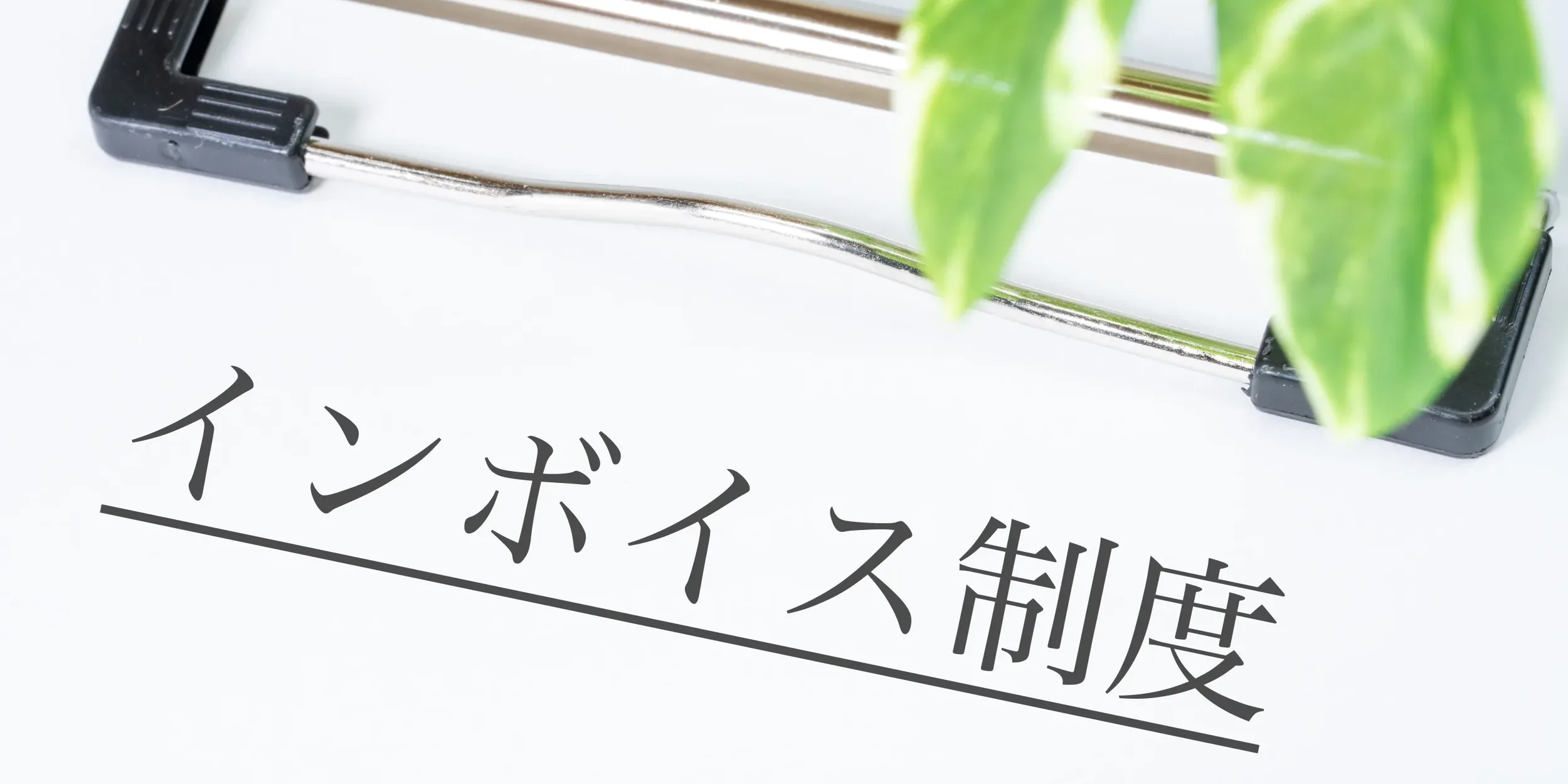
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を複数税率に対応させるための制度です。正式名称は「適格請求書保存方式」といい、名称に明記されている適格請求書を売り手が買い手に発行しなければなりません。
請求書には一定の記載要件が設けられており、それらが明記されていない場合はインボイスとして認められず、買い手は仕入税額控除の適用が受けられない仕組みです。
この請求書はどのような事業者でも発行できるものではなく、事前に発行事業者の登録を税務署に行う必要があります。登録申請で税務署から承認されれば発行が可能になりますが、発行事業者は課税事業者のみに限定されている点に注意が必要です。
インボイス制度導入による変更点
インボイス制度の導入によって変更となった点は以下の2つです。
・請求書の書式変更
それぞれの変更点を詳しく確認していきましょう。
仕入税額控除の適用要件が変更される
インボイス制度の導入による変更点のひとつは、仕入税額控除の適用要件です。控除の適用を受けるためには売り手から適格請求書を発行してもらう必要があります。
しかし、売り手から仕入税額控除が適用される請求書を受け取っていない場合は、売却時に得た消費税30円で申告・納税をしなければならず、消費税の二重払いが発生してしまいます。
買い手にとっては収入の減少にもつながることから、適格請求書の発行が認められていない発行登録事業者以外の事業者との取引については、何らかの条件・対処法を行わなければ損になるでしょう。
書式が区分請求書から適格請求書へ
インボイス制度導入における変更点として、請求書の書式もあげられます。
導入前は区分請求書の発行・受領・保存が認められており、仕入税額控除も適用されていました。
しかし制度導入後は適格請求書のみが控除対象であることから、それに対応した請求書を発行しなければなりません。
認められるためには、以下の項目の記載が必要です。
| 適格請求書 | 適格簡易請求書 |
| ・インボイス交付先の氏名または事業者名 ・売り手(自社)の氏名または事業者名および登録番号 ・取引年月日 ・取引内容(軽減税率対象品目である旨を記載) ・原則税率(10%)・軽減税率(8%)それぞれの対象対価の総額および適用税率 ・原則税率(10%)・軽減税率(8%)それぞれの消費税額等 |
・売り手(自社)の氏名または事業名および登録番号 ・取引年月日 ・取引内容(軽減税率対象品目である旨) ・適用税率または消費税額等のいずれか一方を記載 |
(出典:インボイス制度について|国税庁)
原則は適格請求書の内容ですが、以下の事業に該当する場合は適格簡易請求書の発行が認められています。
2. 飲食店業
3. 写真業
4. 旅行業
5. タクシー業
6. 駐車場業(不特定多数のものに限る)
7. その他(上記に準ずる、かつ不特定多数を対象とした事業)
(出典:適格簡易請求書の交付ができる事業|国税庁)
インボイス制度導入の目的
国税庁ではインボイス制度について、複数の税率に対して正確に納税できるように計算する仕組みと解説しています。
2019年10月1日より、消費税が8%から10%に引き上げられました。しかしすべての商品・サービスの消費税を引き上げると消費者への負担が大きくなり、購買率などに悪影響を及ぼすことが予想されたため、一部については8%に据え置かれています。
現在、消費税は標準税率10%と標準税率8%の2通りで運用されていますが、課税事業者は申告時に2種類の消費税率にわけて申告書類を作成しなければなりません。
これまで1種類で運用されていた消費税が、2種類になったことを受けて誤った金額を申請・納税する可能性があります。仮に誤った金額で申請・納税すると、罰金などの対象になるリスクが発生するため、正確に消費税を申請・納税できるインボイス制度が導入されました。
インボイス制度導入に関して必要な対応を立場別に解説

インボイス制度で必要な対応は売り手・買い手の立場によって異なります。
さらに課税・免税事業者によっても対応・検討要件・支援措置などが違うので、4つに大別して確認していきましょう。
売り手の課税事業者の場合
売り手の課税の場合における対応・検討・支援措置は、主に以下の通りです。
| 対応 | ・発行事業者登録 ・適格請求の発行と保存 ・インボイス制度に準ずる帳簿の作成と保存 |
| 検討要 | インボイス制度に対応した会計ソフトなどの導入 |
| 支援措置 | ・小規模事業者持続化補助金の増額 ・IT導入補助金 ・1万円未満の値引き・返品取引については適格返還請求書の発行不要 |
なかには人手不足や環境整備困難などから発行事業者登録を見合わせる事業者も存在しますが、その場合は支援措置の利用も検討してみてください。「小規模事業者持続化補助金の増額」や「IT導入補助金」は、適用条件を満たすことで補助金が支給されます。各リンク先に条件等が掲載されているので、確認してみてください。
買い手の課税事業者の場合
買い手の課税の場合、請求書はインボイス制度にのっとった書式でなければ仕入税額控除適用の対象外です。
しかしすべての取引先が適格請求書が発行可能な事業者であるとは限りません。免税事業者もあれば、課税事業者でありつつ人手不足などの理由から発行事業者に登録しないで事業を継続しているところもあるでしょう。
控除適用対象の請求書を発行してもらえない取引先が多ければ、その分消費税の納税額は高くなり、売上は下がってしまいます。事業所得に多大な影響を及ぼす可能性もあるので注意が必要です。
発行事業者・未発行事業者の割合を確認し、取引先に応じた対応が求められます。
取引先が課税事業者のケース
買い手が課税かつ取引先も同様に課税の場合における、主な対応・検討事項・支援措置は以下の通りです。
| 対応 | 適格請求書発行可否の確認 |
| 検討要 | ・受け取った適格請求書の保存方法 ・適格請求書とそれ以外の請求書の処理と保管方法 ・処理や保存方法の周知徹底(従業員がいる場合) |
| 支援措置 | ・IT導入補助金 ・1万円未満の値引き・返品取引については適格返還請求書の発行不要 |
取引先が課税事業者であっても、適格請求書の発行が可能とは限りません。社内等の事情により対応できないところもあるので、発行してもらえるのかどうか確認してください。
取引先が免税事業者のケース
買い手が課税かつ取引先が免税の場合、買い手側の消費税額算出方法によって対応が異なります。
| 簡易課税方式 | 一般課税方式 | |
| 対応 | 特になし | 取引額の交渉 |
| 検討 | 特になし | 簡易課税制度の導入 |
| 支援措置 | 特になし | 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置 |
買い手側の消費税額算出方法が簡易課税方式の場合は、売上税額から納税額を計算するので特に対応・検討が必要なものはありません。
なおインボイス制度の導入に伴い、免税事業者からの仕入に関しては経過措置が用意されています。詳しい内容については後述するので、そちらもあわせて参考にしてください。
売り手の免税事業者の場合
売り手が免税の場合、買い手が課税・免税のいずれに該当するのかで対応が変わります。買い手が課税だった場合、売り手はインボイス制度に則った書式の請求書を発行しなければ仕入税額控除の適用外となり、売上に大きな影響を及ぼすからです。
しかし免税事業者は発行が認められていません。発行事業者の登録が必要であり、登録対象は課税事業者のみです。よって必然的に課税事業者への変更を余儀なくされます。
課税事業者になれば消費税の申告・納税義務が発生することから、発行事業者登録の申告手続きを行うことに抵抗を覚える事業主もいるでしょう。
インボイス制度を導入するケース
インボイス制度を導入する場合に求められる対応・検討要件・支援措置は以下の通りです。
| 対応 | 適格請求書を発行するための事業者登録 |
| 検討要 | ・消費税額の計算や納税方法 ・インボイス制度に対応した会計ソフト等の導入 |
| 支援措置 | ・小規模事業者持続化補助金の増額 ・IT導入補助金 ・1万円未満の値引き・返品取引については適格返還請求書の発行不要 |
インボイス制度を導入する際には、管轄する税務署にて発行事業者登録をしなければなりません。申請から登録完了まで1カ月程度かかるので、導入する場合は早めに申請手続きを行いましょう。
インボイス制度を導入しないケース
インボイス制度を導入しない場合は、特に何もする必要はありません。
ただし買い手が課税であった場合には納税額の増加・売上の減少が起こるため、取引を打ち切られる可能性があります。取引を打ち切られるとその分売上に悪影響を及ぼすため、何らかの対応をしなければなりません。
免税事業者として事業を継続する際には、消費税分を差し引いた取引額にするなど価格の面での交渉が必要でしょう。
また後述しますが、一定期間は免税事業者との取引分も仕入税額控除の対象として認められています。この間に売上を上げるなどの対応を行い、発行事業者登録を検討することもひとつの方法です。
買い手の免税事業者
買い手が免税事業者の場合、対応・検討することは何もありません。仕入税額控除の対象外であり、請求書は売り手側が発行するからです。
[https://sokkin-match.me/base/tax-system/invoice/6681]インボイス制度の支援措置を立場別に解説

インボイス制度の導入に伴い、事業者の負担を軽減するための支援措置が用意されています。
課税・免税それぞれの立場から見た場合に利用できる支援措置を確認していきましょう。
課税事業者への支援措置
課税事業者の立場から見た場合に利用できる主な支援措置は、以下の3つです。
2. 1万円未満の仕入れは請求書の保存不要
3. 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
それぞれの支援措置を詳しく確認していきます。
1万円未満の返品をした場合、適格返還請求書の発行が不要
課税事業者への支援措置として、1万円未満の返品・値引きをした場合には適格返還請求書の発行が不要です。
取引後、何らかの事情で値引き・返品対応を余儀なくされることがあります。その際には原則として、適格返還請求書を発行しなければなりません。しかし値引き・返品が発生するたびに適格返還請求書を発行すると会計・経理における事務処理が多くなり、日常業務に支障をきたす可能性があります。このような事務処理の負担軽減・煩雑化の回避を目的として、1万円未満の値引き・返品取引については適格返還請求書の発行が不要になりました。
1万円未満の仕入れは適格請求書の保存が不要
受領した適格請求書は原則として保存義務が課せられています。しかし以下の条件に該当する場合のみ、保存する必要はありません。
・仕入取引額1万円未満
・2023年10月1日~2029年9月30日までの取引分
上記はインボイス制度導入の際に設けられた支援措置です。ただし適用期間が設けられており、半永久的な支援措置ではありません。また期間についても税制改正で延長される可能性はゼロではないため、定期的に国税庁のホームページなどを確認することをおすすめします。
免税事業者からの仕入れにも一定割合の仕入税額控除が適用される(経過措置)
適格請求書等保存方式は、原則として発行事業者以外の課税仕入は仕入税額控除の適用が受けられません。しかしインボイス制度開始後6年間は経過措置として一定の割合の仕入税額控除が適用されます。
| 期間 | 割合 |
| 2023年10月1日~2026年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日~2029年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
(参照:5 経過措置|国税庁)
ただし、帳簿と請求書の両方で以下の要件を満たさなければなりません。
| 適用要件 | |
| 帳簿 | ・課税仕入先の氏名または名称 ・取引年月日 ・取引の内容(軽減税率対象項目および経過措置対象) ・課税仕入分の支払対価 |
| 請求書等 | ・発行者の氏名または名称 ・取引年月日 ・取引内容(軽減税率対象品目および経過措置対象) ・税率ごとの合計税込価額(軽減税率対象品目および経過措置対象) ・交付を受ける事業者の氏名または名称 |
(参照:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き|国税庁)
なお請求書については発行事業者以外から受領した請求書等において、「取引内容」および「税率ごとの合計税込価額」に軽減税率対象項目や経過措置対象の記載がない場合は、受領者の記載が認められています。

また請求書と帳簿は連動させなければならないため、軽減税率対象品目と経過措置対象のそれぞれに異なる記号を明記して記号の種類を請求書と帳簿でそろえておきましょう。
免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合の支援措置
免税事業者が発行事業者になった場合に利用可能な支援措置は、以下の3つです。
2. 小規模事業者持続化補助金の増
3. 2割特例
それぞれの支援措置を詳しく確認していきましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請期限が延長される
免税事業者が発行事業者に変更するためには、2023年3月31日までに税務署にて発行事業者登録の申請・手続きが必要でした。
しかし2023年4月以降の申請であっても、以下の優遇措置が適用されます。
・課税期間の初日までさかのぼってインボイスの発行が可能
発行事業者登録は申請から登録完了まで約1カ月かかります。例えば2月1日に申請を行った場合、登録番号が発行されるのは3月1日頃になってしまうのです。しかし登録申請を行う際には、登録希望日を明記することでその日にちでの登録が可能です。ただし、提出日から15日以降の制限がある点に注意してください。
また登録番号が発行された後は、課税期間の初日にさかのぼってインボイス発行が認められています。例えば、個人事業主が2024年11月20日に登録番号が発行されたとしましょう。課税期間は1月1日〜12月31日までなので、2024年1月1日までさかのぼってインボイス発行ができます。
小規模事業者への持続化補助金が上乗せされる
小規模事業者持続化補助金は小規模事業者などが自ら経営計画を策定して商工会議所・小高所の支援を受けながら販路開拓取り組みの支援目的で実施されており、通常は50〜200万円の補助金が支給されます。
通常枠・特別枠の2種類が設けられており、各枠組別の補助率や補助上限額は以下の通りです。
| 通常枠 | 特別枠 | ||||
| 賃金引き上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | ||
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ枠の赤字事業者は3/4) | ||||
| 補助上限 | 50万円 | 200万円 | |||
| インボイス特例 | 50万円(インボイス特要件を満たす場合) | ||||
(出典:小規模事業者持続化補助金|中小企業庁)
特別枠およびインボイス特例における申請要件は以下のように定められています。
| 申請要件 | |
| 賃金引上げ枠 | 事業内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上増額している事業者 |
| 卒業枠 | 小規模事業者としての従業員数を超えて規模拡大する事業者 |
| 後継者支援枠 | アトツギ甲子園のファイナリスト等になった事業者 |
| 創業枠 | 過去3年以内に「特定創業支援事業」の支援を受けて創業した事業者 |
| インボイス特例 | 免税事業者のうち適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者 |
(出典:小規模事業者持続化補助金|中小企業庁)
消費税の納税額が売上税額の2割になる特例(2特例)
2割特例とは、免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった場合に一定期間の売上消費税額を2割減額する経過措置です。
具体的な適用要件は、以下のように定められています。
・2023年10月1日以降に新規課税対象事業者
・2021年分および2022年4月~6月の課税売上高が1,000万円以下
・課税期間短縮適用外
・一般課税および簡易課税の申告対象外
(参考:インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート|国税庁)
上記の要件はすべて満たさなければなりません。
消費税の納税額は上記の計算式で算出しますが、適用期間は2023年10月1日〜2026年9月30日までと限定的なものである点に注意してください。
インボイス制度が個人事業主に与える影響

インボイス制度が個人事業主に与える影響は、免税事業者・課税事業者によって異なります。
それぞれの事業形態によって発生するメリット・デメリットを確認しましょう。
個人事業主が免税事業者のままでいるメリット、デメリット
個人事業主が免税事業者を継続する際に発生する主なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
| ・消費税の申告や納税が不要 ・インボイス制度対応のための申請や準備が不要 ・売上高1,000万円以下になればいつでも免税事業者に戻ることが可能 |
・取引先からの適格請求書発行要求への対応不可 ・取引数や売上が減少する可能性あり |
発行登録事業者として登録した場合、登録日を起算日として2年間は免税事業者に戻ることは認められていません。未登録の場合は一時的に売上高が1,000万円を超えて翌年以降に下回れば自動的に免税事業者に振り分けられます。
しかし買い手の取引先が課税事業者であった場合、免税事業者分は一定期間を過ぎると仕入税額控除の対象にならないため、取引を打ち切られたり契約金額を下げられたりするリスクが発生するでしょう。
個人事業主が課税事業者になるメリット・デメリット
個人事業主が課税事業者になる場合の主なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
| ・適格請求書の発行が可能 ・新規開拓で有利になる可能性あり |
・インボイス制度の対応が必要 ・消費税の申告と納税が必要 ・交付済み適格請求書の控えを保存 |
課税事業者として発行事業者に登録すれば適格請求書の発行が可能になるので、取引先からの要求にもこたえることが可能です。また既存の取引先との契約継続だけではなく、新規開拓の際にも免税事業者より有利に働くでしょう。
インボイス制度に関して気をつけるべき点を紹介

インボイス制度がスタートしたことで注意すべき点を紹介しましょう。
請求書を発行しない取引の対応を考慮する
すべての取引先がインボイス制度を導入して適格請求書を発行するとは限りません。免税事業者は適格請求書の発行が認められておらず、課税事業者であっても適格請求書発行の対応が困難との理由から依頼しても断られる可能性があります。
このような取引先との今後について、どのように対応するのか考慮する必要があるでしょう。
例えば以下のような対応方法があげられます。
・取引の打ち切り
事業規模によってはインボイス制度の導入が困難なケースもあるため、適格請求書発行事業者への登録を一方的に求めるのは現実的ではない場合があります。それよりも取引価格の引き下げ、または取引の打ち切りを検討することをおすすめします。
控除不能額を想定しておく
控除不能額を想定しておくことも重要です。
前述したようにすべての取引先で適格請求書の発行対応ができるわけではなく、未対応の請求書分は仕入税額控除の対象になりません。
控除不能額が多くなれば消費税の納税額は高くなり、売上は減少します。22029年9月30日までは経過措置として免税事業者からの仕入れも一定割合が控除対象となりますが、この期間を過ぎると適用から外れるので、控除不能額を把握して対応策を考えておきましょう。
インボイス制度や経費精算ルールを社内に周知させる
インボイス制度や経費精算ルールを社内に周知させておくことも気をつけるべき点のひとつです。
従業員のなかには、取引先との交際費などが発生するケースがあります。経理処理を行うにあたってこれらを経費計上する際には請求書が必要ですが、その際に従業員が受け取る請求書も適格請求書でなければなりません。
経費精算に関する社内ルールを整備する
経費精算については、どのようなケースでインボイスを受け取るのか把握し、ルールを明確に設定しておく必要があります。
さまざまなパターン・ケース別にマニュアルをあらかじめ作成し、誰でも確認できる状態にしておきましょう。
まとめ
個人事業主におけるインボイス制度の影響などを解説しました。
インボイス制度の導入に伴い、多くの事業主は対応を余儀なくされています。対応をしない場合には取引数・売上の減少などのリスクが発生する可能性があるため、事前に取引先と相談しておくことが重要です。
一度適格請求書発行事業者として登録すると、登録日を起算日として2年間は免税事業者に戻れず、消費税の申告・納税をしなければなりません。
事業規模・状況などを把握したうえでどのような対応をすればよいのか、本記事を参考にしつつ検討・考慮してください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか