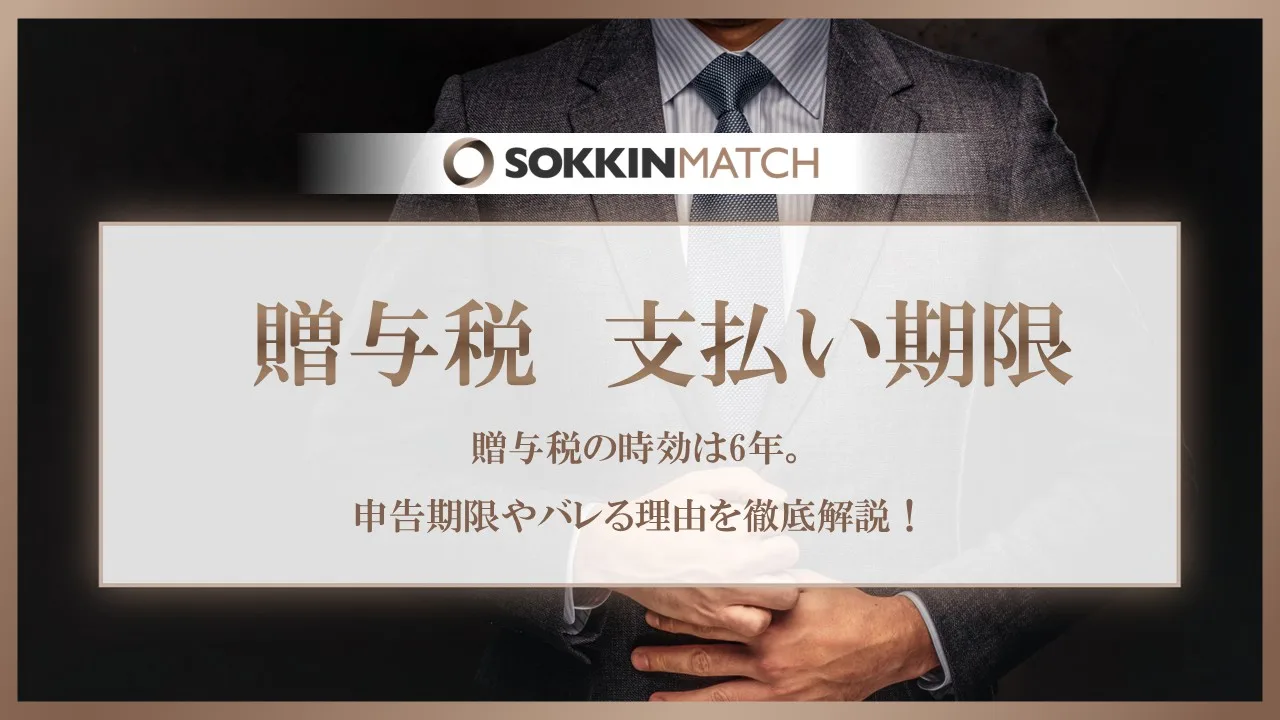今回は贈与税の期間について解説していきます。
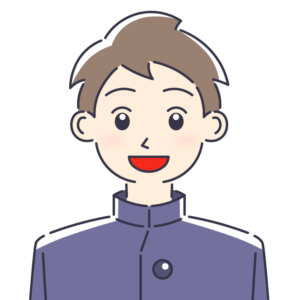
贈与税は個人が無償で財産をもらった時にかかる税金のことを指すのでしたよね!

その通りです!
親族から財産を譲り受けるとその金額に応じて課税される贈与税には、申告期間が設けられています。

申告期限を過ぎるとペナルティが課せられると聞いたことがあるのですが、それは本当ですか?

よく知っていますね!期限内に申告しなければ様々なペナルティが課せられるのは事実です。
ただし贈与税には時効があり、その期間を過ぎると納税の義務は消滅します。

税金に時効があるのですか?
贈与税の仕組みがイマイチ理解できていないです…
本記事では贈与税の申告期間・時効とともに、ペナルティの内容・非課税制度も紹介するので、贈与税を支払う予定がある人は参考にしてください。
▼ 贈与税について詳しく知りたい方はこちらから

贈与税の期限は通常の場合6年!
ただし贈与税には時効が設けられており、その期限は原則6年です。この期限は「生活が困窮して支払いが難しい」「自然災害に見舞われた」「贈与されていたことを知らなかった」など正当性があると認められた場合の期間であり、脱税のような悪質と判断された場合には7年に延長されます。

例えば祖父が生前贈与として、孫の銀行口座に500万円を入金したとしましょう。
「生前贈与の相談はあったが、銀行口座に振り込まれてたことは知らなかった」という場合、贈与税の時効は6年です。

なるほど!そのような場合のために時効が設定されているのですね!
では、「銀行口座に振り込まれていたことは知っていたが、申告・納税しなかった」
という場合はどうなるのですか?

その場合は脱税と判断され、時効は7年と1年延長されます。
贈与税は発生しません。
期限のカウントの仕方

これは後述しますが、3月15日が申告期限の最終日だからです。
例えば、2010年4月2日に生前贈与を受けたとしましょう。カウントは翌年2011年3月16日から始まり、通常なら6年後の2017年3月15日に時効成立です。
ただし実際にはこのような単純なことにはなりません。その理由は、税務調査によって判明すれば時効は不成立になる可能性があるからです。
先ほどの例で確認してみます。生前贈与は2010年4月2日であり、時効成立後の2020年8月16日に贈与品を売却しました。2023年の税務調査で贈与の事実があったと判断された場合、贈与日は税務調査の根拠となった2020年8月16日に設定される可能性があります。
実際の贈与日は2010年4月2日ですが、税務調査の根拠となった事象が2020年8月16日に行った贈与品の売却だったため、この日を贈与日として設定されてしまいました。すると時効のカウントは2021年3月16日から始まるので、2023年時点では時効が成立しておらず、ペナルティが科せられる可能性があります。
申告漏れがあるとペナルティが課される
申告漏れで発生するペナルティは以下の通りです。
・無申告加算税
・過少申告加算税
・重加算税
それぞれの罰金等について解説するので、参考にしてください。
延滞滞納税
延滞税は、納期限までに税金を納めなかった場合に課税される罰金です。
具体的には以下のようなケースに該当する場合に発生します。
・期限後の申告や修正申告で納税が発生した場合
・更正や決定処分により納税が発生した場合
(出典:No.9205 延滞税について|国税庁)
上記以外に中間納税額を納期限までに納めなかった場合も、延滞税の対象です。
算出する際に使用する税率は、延滞が発生してから完納するまでの期間によって以下のように異なるので早めに納税したほうが良いでしょう。
| 納期限翌日から完納まで | 原則税率(年率) |
| 2カ月以内 | 7.3% |
| 2カ月超 | 14.6% |
(出典:No.9205 延滞税について|国税庁)
ただし上記は原則税率であり、実際には特例基準割合を基準にした税率を適用します。

特例基準割合とは、毎年11月頃に告示される平均貸付割合を基準に決定される割合です。
2カ月以内の場合はこれに年1%を加算したもの、2カ月越えの場合は年7.3%を加算したものと原則税率を比較して低いほうの税率を適用します。
実際に使用する税率は毎年見直しが行われているので、半永久的に同じ税率を使用して計算するわけではありません。使用する税率は国税庁の「延滞税の割合」にて、毎年公開されています。自分で金額を計算する際には、このサイトで最新の税率を確認してください。
無申告加算税
無申告加算税とは、期間内に確定申告をしなかった場合に課せられる罰金です。
財務省が公表している具体的な課税要件は、以下のように規定しています。
2. 期限後の申告や決定について、修正申告や更正があった場合
(出典:加算税の概要|財務省)
加算税を算出する際の税率は増差本税の金額によって異なり、以下の通りです。
| 増差本税額 | 税率(年率) |
| 50万円以下 | 15% |
| 50万円超300万円以下の部分 | 20% |
| 300万円超の部分 | 30% |
(出典:加算税の概要|財務省)
ただし、期限内に確定申告を行わなかったからといって必ずしも無申告課税が課せられるわけではありません。
| 要件 | 軽減割合(年率) |
| ・正当な理由が認められる場合 ・法定申告期限から1カ月以内の期限後申告 |
0% |
| 更正や決定を予知しない修正申告や期限後申告 | 5% |
(出典:加算税の概要|財務省)
上記の要件を満たしていると認められれば無申告加算税の非課税対象になったり、5%で計算されたりします。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告・納税した税金の金額が本来の税額よりも少なかった場合に課せられる罰金です。
加算税を計算する際に使用する税率は、以下の2通りあります。
| 条件 | 税率(年率) |
| 原則 | 10% |
| 期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分 | 15% |
ただし、本来の納税額よりも少なく申告したからといって必ず過少申告加算税が課せられるわけではありません。以下の要件を満たしていると認められる場合は、課税対象外です。
・更正を予知しない修正申告の場合

原則として自主的に修正を行った場合には、課税対象外になる可能性があります。
重加算税
重加算税とは、意図的な隠ぺい・仮装が認められる場合に課せられる罰金であり、さまざまな種類がある加算税のなかでは最も重い罰則です。
重加算税はほかの加算税に代えて課せられる罰則であり、その加算税によって使用する税率が以下のように異なります。
| 加算税 | 税率(年率) |
| 過少申告加算税 | 35% |
| 無申告加算税 | 40% |
(出典:加算税の概要|財務省)

本来なら上記の加算税であっても、状況等が悪質と税務署によって判断された場合には重加算税として各税率をかけて計算した罰金が課せられるので注意してください。
▼ 贈与税の仕組みについて詳しく知りたい方はこちら

なぜ贈与がばれるのか
両親・親族からの贈与は申告しなくても税務署に知られてしまうことは多く、その理由として以下のようなケースがあげられます。
・相続税の調査
・法定調書
・不動産の登記名義
上記4つのケースを詳しく確認していきましょう。
税務署からの書類でばれる
贈与の事実を税務署に知られてしまう原因のひとつが、税務署から突然送付されてくる文書です。
税務署では毎年税務調査を行っていますが、1年分の対象者全員に対して実施されているわけではありません。税務調査は提出された申告書類のほかに預金口座なども参考にして行われており、1件を調査する時間は必然的に長くなります。
この税務調査の足がかりとして利用されているのが、税務署からのアンケート書類です。これは「お尋ね文書」とも呼ばれており、贈与の有無を調査する内容が明記されています。受け取った側は書類に書かれている内容に回答したうえで、期日までに返送しなければなりません。
回答の内容によって「贈与があったかもしれない」と税務署が疑いを持ち、その結果贈与の事実を知られてしまうのです。
相続税を調査する過程でばれる
相続税の調査過程で、贈与を知られてしまうケースもあります。
遺族の財産を相続した際には相続税が課せられますが、納税額を正しく算出するためには財産の調査が欠かせません。このとき、相続人の財産もあわせて調査されるので贈与の事実を隠していても知られてしまう可能性は高いといえます。
税務署では生前贈与も考慮して、数年前から調査を行うことが一般的です。調査の一環として銀行口座の入出金の事実確認も認められていることから、贈与税の有無は必然的にわかってしまいます。
法定廷調書を通してばれる
法定調書とは、以下にあげる4つの法律に基づいて税務署に提出しなければならない書類のことです。
・法人税法
・租税特別措置法
・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
(出典:No.7401 法定調書の種類|国税庁)
法定調書にはさまざまな種類がありますが、贈与税の場合は保険金の契約者と受取人が異なる際に保険会社から税務署に法定調書が提出されます。
保険料の支払者と受取人が異なる保険金を受け取った場合、贈与税の対象になるので申告・納税しなければなりません。行わなかった場合には保険会社から提出された法定調書にて税務署は把握できるので、受取の事実を知られてしまいます。
不動産の登記名義でばれる
不動産の登記名義から、贈与の事実が税務署に知られてしまうケースも少なくありません。その理由は税務署では全不動産の名義を含む情報を把握・収集しているからです。
また贈与を受けた不動産は所有者の名義を変更しなければならず、その手続きは法務省で行いますが、このとき法務省で名義が変更された旨の情報を税務署に提供して共有されることがあります。
また不動産を登記する際には、登録免許税を支払わなければなりません。この納付の事実は不動産関連の情報として税務署に把握されてしまうケースもあるのです。

このように不動産贈与については必ず行わなければならない手続き等が複数あり、その過程で税務署に贈与の事実が知られてしまうので隠すようなことはやめたほうがよいでしょう。
贈与税の申告期限
贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日までです。ただしこの期限は税金の納期限でもあることから、申告とあわせて納付も完了させなければなりません。
贈与税の申告手続きになれておらず、申告期限ぎりぎりの3月15日に申告書類の提出が完了して安心する人もいるでしょう。計算の結果次第では納税額が0円のこともありますが、発生している場合は忘れず納付も行ってください。
例えば2023年2月15日に250万円の贈与を受けたとしましょう。この場合、翌年2024年2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告と納付の両方を完了させなければなりません。
申告期間を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課せられて納めるべき税金の金額が高くなります。

悪質と判断された場合には刑事罰が課せられることもあるので、くれぐれも申告漏れをしないようにしてください。
申告が必要な場合
贈与税の申告が必要な場合は、主に以下の2通りです。
2. 相続時精算課税方式を利用
贈与税の課税方式には暦年課税方式と相続時精算課税方式の2種類があり、「1」は暦年課税方式に該当します。1年間の贈与限度額が110万円に設定されており、これを超えた場合には申告・納税をしなければなりません。
ただし、限度額は毎年1月1日にリセットされるので、例えば2021年に合計90万円の贈与を受けて翌年2020年に100万円の贈与を受けた場合は申告不要です。
一方の相続時精算課税方式とは2,500万円までの贈与分については非課税になる制度ですが、事前に税務署に制度利用の申告をしなければなりません。また、限度額を超えるとそれ以降は20%の税率で計算された税金が課税されるので注意してください。
申告が不必要な場合
贈与を受けたからといって、必ずしも申告しなければならないわけではありません。以下のケースに該当する場合は申告不要です。
・非課税制度の適用
・社会通念上で必要と認められる場合
それぞれの申告が不要な場合を詳しく確認していきましょう。
贈与されたお金が生活費や教育費として使われる場合
以下に該当する場合は、贈与分が生活費・教育費として認められるので申告は不要です。
例えば単身赴任や別居で互いに離れた場所で生活をしている夫婦間で、生活費の名目で500万円のやり取りが行われたとしましょう。年間控除額110万円を超えていますが、贈与者は受贈者に対して生活費として金銭を送っているので申告の必要はありません。

遠方で一人暮らしをしている子どもに生活費として親が年間110万円を超える仕送りをしていた場合も、
生活費・教育費として認められるので申告は不要です。
ただし以下に該当する場合は贈与があったと認識され、申告・納税しなければなりません。
受け取った分は、生活費・教育費として使わなければならない点に注意してください。
非課税制度の適用を受ける場合
贈与税にはさまざまな非課税制度が設けられており、要件を満たしたうえで適用を受ける場合には申告の必要はありません。
例えば以下のような非課税制度があげられます。
| 非課税制度 | 要件 |
| 教育資金贈与の非課税制度 | ・受贈者が教育資金管理締結日の時点で30歳未満 ・受贈者は直系尊属のみ(父母や祖父母) ・教育資金口座の開設・利用 |
| 結婚子育て資金の非課税制度 | ・受贈者の年齢が18歳以上50歳未満であること ・結婚・子育てを目的とした贈与であること(金銭または有価証券) ・金融機関との一定の契約に基づいていること ・上限額1,000万円(結婚資金の場合は上限額300万円) ・2025年3月31日までの期間であること |
いずれの制度もすべての要件を満たさなければならず、本来の目的とは異なる使い方をした場合には贈与税が発生するので申告しなければなりません。
社会通念上、必要と認められる場合
以下にあげるような社会通念上で必要と認められる場合も、申告は不要です。
・お祝い金
・中元・お歳暮

例えば退院のお祝い金として、5人の複数人の親せきから合計250万円を受け取ったとしましょう。基礎控除額の110万円を超えていますが、この場合は慶弔見舞金に当てはまるので贈与税はかかりません。

お祝い金と言えば、最近高校の入学祝いで、祖父母から50万円、おじさんから10万円、両親から50万円受け取りましたが、この場合は申告する必要がないということですか?

その場合、受け取った金額は110万円超となりますが、お祝い金として認められるので申告する必要はありません。ただし!1人からお祝い金として110万円を超える金額を受け取ると、常識の範囲内での金額ではないと判断されて贈与税が発生します。
期限内に納付できない場合はどうするの?
贈与税は納期限までに一括納付が原則ですが、金額によっては困難な場合もあるでしょう。その際は税務署に相談してください。
納税者の生活状況・納税額にもよりますが、一定の要件を満たすことで最長5年の分納が可能です。
2. 一括納付困難の証明が可能
3. 担保提供
「3」の担保提供は、納税額100万円未満かつ延納期間3年以下の場合は必要ありません。
ただし延納期間中は、本来の納税額とは別に利子税が発生します。税率は年6.6%で計算され、納税額に加算されます。
延納と分納で一見負担が軽減されるように感じますが、利子税の発生で納税額が高くなる点を忘れてはなりません。

この措置を利用する際は、利子税のことも考慮してください。
贈与税の時効についての注意点
贈与税の時効については、以下の点に注意しなければなりません。
・借金時効の援用
・時効はリスク大

それぞれの注意点について解説します。
不動産の贈与の時効は登記をした時からカウントされることもある
不動産贈与の場合、時効のカウントが登記時点からスタートされることがあるので注意してください。
税務調査で不動産の贈与が疑わしいと判明するのは、登記上の名義変更が行われるタイミングです。「なぜ贈与がばれるのか」でも触れましたが、税務署は不動産の情報を把握・収集しています。
例えば10年前に贈与されていた土地を、受贈者の他界をきっかけに名義変更したとしましょう。名義が変更された事実は法務局から税務署に共有されるので、贈与があった事実が知られてしまいます。
しかし贈与自体がいつ行われたのかまでは、税務署ではわかりません。そこで、名義変更された日から時効のカウントがスタートされてしまうのです。
借金時効の援助を使うと所得税がかかることがある
借金時効の援用とは、債権者が「時効を迎えたので借金返済を放棄します」と債務者に宣言することです。

例えば子が親に1,000万円の借金をしていたとしましょう。
5年後、親が子に「1,000万円は返さなくていい」と伝えると1,000万円が子から親に贈与されたように見えなくもないですよね。

その場合、一見親が子に1,000万円を贈与したように見えますね。

しかしながら実際には債務の消滅であり、借金時効の援用と判断されます。
債務が消滅すると所得税の課税対象になるので、1,000万円にかかる所得税を納税しなければなりません。
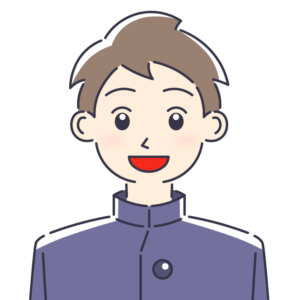
今度は所得税を払う必要が出てきちゃうんですね!
なお所得税にも贈与税同様に時効が設けられていますが、6年ではなく7年です。6年経って贈与税の時効が成立したと思っていたら、実は所得税の課税対象であり7年の時効まで1年残っていたというケースもゼロではありません。
時効を利用するのにはリスクが伴う
時効を利用するリスクとして、贈与が成立しているかどうかが問題です。
贈与が成立しているか否かは、以下の条件を前提としています。
いずれの条件も満たしていなければならず、どちらか一方が欠けていても贈与は成立していないと判断される可能性が高いでしょう。
税務署にて贈与不成立と判断された場合には、贈与税ではなく相続税の課税対象とみなされます。
基本的に相続は贈与の後から起こる事象であるため、仮に贈与税の時効期間を過ぎていたとしても贈与が成立してなければ無関係であり、相続税の支払いを命じられる可能性はゼロではありません。
まとめ
贈与税の時効について解説しました。
贈与税の時効は贈与が成立していることが前提です。不成立とみなされてしまうと時効もなくなり、贈与税よりも納税額が高くなりがちな相続税の課税対象になる可能性があります。

時効を利用して贈与税の納税から免れようとするのではなく、非課税制度などを利用して適切な節税対策を行うようにしてください!
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか