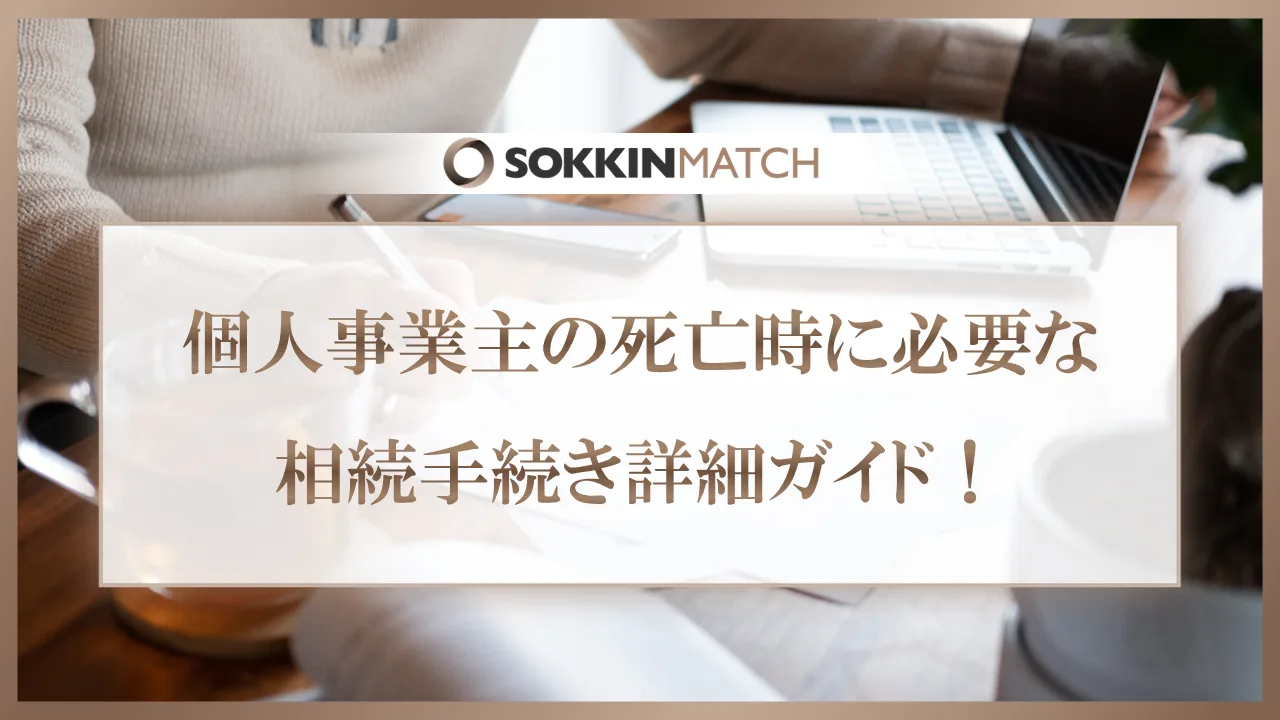個人事業主が他界した場合、対応しなければならないのは相続税などの税金回りのことだけではありません。事業主として事業活動を行っていたことから、継続・廃業を含めた今後の検討・対応も求められます。
相続税の手続きだけでも混乱を極める中、事業についても考慮しなければならない状態に戸惑う人もいるでしょう。
個人事業主って誰のこと?
個人事業主とは、独立・反復・継続のすべてを満たす事業活動を行っている個人のことです。
個人事業主と混同されがちな言葉としてフリーランス・法人があげられますが、これらは厳密には同一ではなく、以下のような違いがあげられます。
|
個人事業主
|
・事業活動を行っている個人 ・法人成りをしていないことが条件 |
|
フリーランス
|
・会社などの組織に属さない働き方 ・人物を指す場合あり |
|
法人
|
・法律で「権利」「義務」「資格を与えられた団体」 ・法務局への登記が必要 |
なお個人事業主として事業活動をするからといって、必ずしも開業届を提出しなければならないわけではありません。ただし開業届をしなかった場合には以下のようなデメリットが発生します。
・口座開設時に屋号の使用不可
・青色申告特別控除の対象外
・小規模企業共済への加入不可
・賃貸契約不可の場合あり(職業証明できないため)

開業届は事業開始から1カ月以内に届出書と青色申告承認申請書を管轄する税務署に提出するだけなので、本格的に事業活動する場合は提出しておいたほうがよいでしょう。
個人事業主の事業用資産
個人事業主の事業用資産は、以下のように区分されます。
・棚卸資産
上記の具体例や評価額の決定方法・計算式などを解説するので、参考にしてください。
▼ 個人事業主の確定申告についてはコチラ!

一般動産
一般動産とは、土地・家屋などの不動産に含まれない形のある資産のことです。事業用と一般家庭用に区分されており、以下のようなものがあげられます。
|
事業用
|
一般家庭用
|
| ・事業用の機械や装置 ・工具や備品 ・車両運搬具など |
・家具 ・衣服 ・非事業用車両運搬具など |
原則として事業用に分類されるものは事業活動で使用する動産であり、プライベートで使用する動産は一般家庭用です。
また一般動産とあわせて、以下のようなものがあることも覚えておいたほうがよいでしょう。
|
無体財産権
|
・別名「知的財産権」 ・特許権や商標権など形のない資産のこと |
|
無記名債権
|
・債権者が特定されていない証券のこと ・証券を所持している人が債権者 ・現金や預金通帳、国債や社債など |
|
付属設備
|
・一般動産に含まれない設備のこと ・電気設備、消火設備、浴槽設備など |
上記にあげたものはすべて一般動産には含まれないので注意してください。
一般動産の評価額
一般動産は原則として1組や1個ごとに評価し、その基準は実例価額です。「実例価額がわからない」「メーカー・モデルなどによって価額に差がある」などの理由に該当する場合は、精通者意見価格等を参考にすることもありますが、多くのケースでは実例価額を基準にして評価額を決定すると考えた用がよいでしょう。
ただし一般動産のなかには実例価額・精通車検価格ともに不明なものもあり、その場合は以下のような手順で評価額を決定しなければなりません。
2. 事業用動産の場合は製造年月日を起算日として課税時期までの償却費を合計
3. 非事業用一般動産の場合は減価償却費を計算
4. 新品価額から「2」または「3」で算出した金額をマイナス

なお償却費を計算する際には、国税庁で公開している「減価償却資産の償却率等表」の「定率法」の値を使用します。
棚卸資産
棚卸資産とは、第三者に販売することを目的に仕入れた物品のことです。いわゆる「在庫」と一般に呼ばれる資産のことを指しますが、厳密には以下のようなものが含まれます。
|
棚卸資産の区分
|
概要
|
| 商品・製品 | ・販売目的で仕入れたもの ・製品製造時に使用した原材料の残りなども含む |
| 半製品 | ・一定の加工が終了したもの ・そのままの状態での販売や貯蔵も可能 |
| 仕掛品 | ・製造途中の未完成品 ・そのままの状態での販売不可 |
| 主要原材料 | ・商品や製品を製造するための原材料 ・小麦粉や鉄板など |
| 補助原材料 | ・商品や製品の製造に必要な補助材料 ・調味料やクギなど |
| 消耗品の在庫 | ・自社で使用する目的で購入した消耗品 ・未使用の切手や印紙、文房具のストックなど |
棚卸資産には原材料も含まれ、完成品だけではない点に注意してください
棚卸資産の評価額
棚卸資産の評価は同一の種類または規格ごとにひとまとめにして評価しますが、その評価額の算出方法は資産の状態によって以下のように異なります。
|
棚卸資産の状態
|
評価額・評価方法
|
| 商品 | 課税時期の販売価格から経費などを差し引いた金額 |
| 製品または生産品 | 課税時期の販売価格から経費・消費税額を差し引いた金額 |
| 半製品または仕掛品 | 課税時期の原材料仕入価格から運賃・加工費などの経費を加算した金額 |
| 原材料 | 課税時期の仕入価格に運賃やその他の経費などを加算した金額 |

先生、資産の評価って決まった方法でしないとダメなんですよね?

原則はそうですね。でも、限定品とか価格が大きく変動する資産は難しいこともあります。
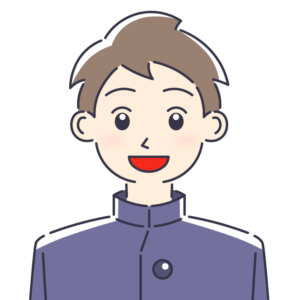
そういう時はどうするんですか?

なるほど、例外もちゃんとあるんですね!
事業用資産の評価額
事業用として所有している車両運搬具・機械などは、残存価額で評価する方法が一般的です。
事業用資産にはさまざまな種類がありますが、例えば商品の評価額を算出する際には以下の計算式を用います。
事業用資産の評価額算出時に残存価額を基準にするのは、毎年の確定申告時に減価償却をしているからです。車両運搬具・機械などは取得価額が10万円以上かつ耐用年数1年以上のものがほとんどであり、このような資産は確定申告時に減価償却をしなければなりません。
所得額・納税額の申告をする際に正確な計算をして算出している数字であることから、相続税の評価額算定時の使用が認められています。
個人事業主が死亡した時の事務処理
個人事業主が死亡した際、遺族が行わなければならない事後処理は主に以下の通りです。
2. 相続の意思決定
3. 死亡届の提出
4. 廃業届の提出
5. 準確定申告
6. 所有者情報の更新
各手順の事後処理方法を確認していきましょう。
1.相続人の確認
個人事業主が死亡した場合、最初に相続人の確認をしなければなりません。相続人の所在・人数などが確認できなければ、相続手続きができないからです。
あらかじめ遺言書が用意されている場合は、その遺言書を参考に相続人の所在・人数を確認します。しかし突然の不幸に見舞われるなど、遺言書がない場合は以下の手順で相続人調査を行わなければなりません。
2. 戸籍に記載されている「その前の本籍地」の戸籍謄本を入手
3. さらにその前の本籍地がある場合はその分も入手
4. 入手した戸籍謄本を参考に記載されている関係者の戸籍謄本を入手
5. 相続人が誰になるのかを確認
法定相続人にはあらかじめ順位が決定されており、被相続人の配偶者を筆頭に被相続人の子ども、両親、兄弟姉妹の順番で続きます。
2.相続の意思決定を行う
法定相続人の所在・人数等の確認ができたら、次に各相続人の相続意思決定を行わなければなりません。個人事業主の相続手続きのなかには事業関連のものも含まれるため、なかには相続を放棄したいと考える人も出てくる可能性があるからです。
|
相続の仕方
|
概要
|
| 単純承認 | ・無条件で全財産(負債・債務を含む)を相続 ・特別な手続き不要 |
| 相続放棄 | ・相続する権利そのもののを放棄 ・プラス資産もマイナス資産も放棄 ・事業を引き継ぎたくない場合 |
| 限定承認 | ・一部の財産のみ相続 ・プラス資産の範囲内でマイナス資産を相続 |
相続の時点で事業を引き継ぎたくない場合は、相続放棄をするしかありません。
しかし、事業の負債は大きいけれど多少の引き継ぐ意思はあるという場合は、限定承認を選択するとよいでしょう。限定承認ならマイナス資産の負担はプラス資産の範囲内に限定されるので、相続人個人の資産は守られます。
3.死亡届を提出
次に個人事業主の死亡届を提出しますが、被相続人が課税事業者の場合は自治体とは別に税務署での手続きも必要です。
|
提出先
|
各自治体 | 税務署 |
|
概要
|
・死亡者の氏名や死亡日時など ・死亡診断書への記入も必要 |
・課税事業者だった場合の手続き ・免税事業者の場合は不要 |
|
手続き対象者
|
親族、同居人、後見人など | 相続人 |
|
提出期限
|
・国内死亡:死亡日から7日以内 ・国外死亡:死亡日から3カ月以内 |
事由が生じた時点から速やかに |
(参考:法務省:死亡届、D1-15 個人事業者の死亡届出手続|国税庁)
各自治体に提出する死亡届は提出期限が厳密に定められていますが、税務署に提出する分については期限が設けられていません。これは手続き対象者が相続人に限定されており、相続人を決定するためには一定の時間が必要だからです。

期限が定められていない分、忘れるリスクが高まるので、相続人が決定したら忘れずに提出しましょう。
4.廃業届を提出
個人事業主が死亡した場合、法定相続人が後継者として事業継続をする意思があるかどうかにかかわらず、いったん廃業届を提出しなければなりません。
廃業届出書は開業届出書と同一であり、「届出区分」の欄にて「廃業」にチェックを入れた上で事業者名・住所などの必要事項を明記して開業届を行った税務署に提出します。
なお提出期限は個人事業主の死亡日から1カ月以内です。税務署に提出する死亡届に期限はありませんが、廃業届には期限が設けられているので忘れず作成・提出してください。
なお、個人事業主が課税事業者の場合は「事業廃止届出書」の提出も必要です。こちらは青色申告を取りやめる、または申告者を変更する年の翌年3月15日までに消費税を納税している税務署に提出しましょう。
5.準確定申告を行う
個人事業主が死亡した場合、忘れてはいけないのが準確定申告です。個人事業主として事業活動を行っている場合、所得税の申告・納税が必要ですが、本来の期間までに死亡した場合は相続人が個人事業主存命までの確定申告をしなければなりません。
所得税の申告・納税対象期間は、その年の1月1日から個人事業主の死亡日までです。また申告期限は、死亡日の翌日を起算日として4カ月以内に定められています。

例えば被相続人が8月15日に亡くなったとしましょう。相続人は1月1日から8月15日までの所得税の申告・納税を、12月15日までに行わなければなりません。
6.土地や預金、有価証券などの所有者情報の更新
死亡した個人事業主が土地・有価証券などを所有していた場合には、名義変更が必要です。
|
対象物
|
具体例
|
手続き場所
|
| 不動産 | 土地・事務所・駐車場など | 法務局 |
| 預金 | 普通預金・当座預金など | 銀行・信用金庫など |
| 有価証券 | 株券・社債 | 証券会社・信託銀行など |
変更手順は対象物によってはもちろん、遺言書・遺産分割協議の有無によっても異なります。相続関連の手続きに詳しくない場合は、手続き場所や税理士などの専門知識を要する人に相談して進めるようにしてください。
【課税事業者の場合】
個人事業主が課税事業者の場合、税務署への「死亡届出書」と「事業廃止届書」の提出が必要です。「死亡届を提出」と「廃業届を提出」の各見出しでも簡単に触れましたが、さらに詳しく解説します。
|
提出書類
|
概要
|
| 死亡届出書 | ・個人の課税事業者が死亡した場合に必要 ・「D1-15 個人事業者の死亡届出手続」から「個人事業者の死亡届出書」をダウンロード ・記載要領等を参考に必要事項を記入 ・提出時期は特になし |
| 事業廃止届書 | ・課税事業者が事業を廃止する場合に必要 ・事業主変更時にもいったん提出 ・「D1-14 事業廃止届出手続」から「事業廃止届出書」をダウンロード ・記載要領等を参考に必要事項を記入 ・提出期限は特になし |
上記いずれも特に提出期限は設定されていませんが、「事由が生じた場合に速やかに提出すること」と定められているので、早めに作成・提出してください。
【従業員を雇っていた場合】
個人事業主として事業活動を行う場合、従業員が事業主のみとは限りません。ほかの従業員を雇用して給与を支払っている場合もあり、その際には「給与支払い事務所棟の解説・移転・廃止の届出書」の提出義務が発生します。
国税庁の「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」内に申請書のリンク先が明記されているので、届出書を入手してください。
届出書と一緒に記載方法が明記された「記載要領等」もダウンロードできるので、これを参考にしながら必要事項に記入します。
「届出書の内容及び理由」欄は「廃止」の「廃業または精算結了」にチェックを入れましょう。
なお提出期限は個人事業主の死亡日から1カ月以内とされており、管轄する税務署に提出します。
事業を引き継ぐ時の事務処理
相続人が新たに事業を引き継ぐ際の事後処理は、主に以下の通りです。
2. 屋号の選択
上記以外に、従業員雇用の有無や青色申告の選択なども並行して行わなければなりません。
手順とあわせてそれ以外の事後処理についても解説するので、参考にしてください。
1.開業届を提出
法定相続人が死亡した個人事業主の事業を新たな事業主として引き継ぐ際には、開業届を提出しなければなりません。
届出書は廃業届を行う際に使用した申請書と同様で、「届出区分」の欄にて「廃業」にチェックを入れた上で事業者名・住所などの必要事項を明記して開業届を行った税務署に提出してください。
提出期限は個人事業主の死亡日から1カ月以内とされているので、誰が事業を引き継ぐか決まっていない場合は早めに新たな事業主を決定しましょう。
なお「廃業届で提出時に開業届も行っていた」「相続人個人が以前から事業活動をしている」などに該当する場合には、改めて提出する必要はありません。
2.屋号を引き継ぐか選択する
死亡した個人事業主の事業を継承する場合、大きな問題になるのが屋号です。
事業規模にもよりますが、「取引先が多い」「取引金額が高額」などに該当する場合、事業継承時に屋号を変更すると取引先が混乱する恐れがあります。また、飲食店などを経営している場合、屋号の変更は店舗名の変更を意味するため、店が変わったと勘違いされる可能性もゼロではありません。
よほどの理由がない場合は、事業継承時に屋号も引き継いだほうがよいでしょう。
屋号を引き継ぐ・引き継がないのいずれの場合も、特別な手続きは必要ありません。開業届時に使用する屋号を明記すれば事業主変更と同時に登録されます。
【従業員を雇う場合】
事業の継承時に従業員を雇う場合は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出が必要です。
申請する際の申告書類は個人事業主死亡時の手続き書類と同じ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を使用します。
届出書に記入する内容も個人事業主が死亡した際とほぼ同様ですが、「届出の内容及び理由」の項目のみ「開設」「移転」のいずれか該当する欄にチェックを入れてください。
|
引き継ぐ際の状況
|
チェック欄
|
| 事業活動なし | 「開設」の「開業または法人の設立」 |
| 給与支払のない事業活動をしている | 「開設」の「上記以外」 |
| 給与支払のある事業を展開中で、その事業に含める | 「移転」欄の「既存の給与支払事務所等への引継ぎ」 |
「届出の内容及び理由」の項目は、引き継ぐ際の相続人の状況によって選択するチェック項目は異なります。上記は一例ですが、参考にして頂き、どれに該当するかでチェック欄を確認してください。
【簡易課税制度を利用する場合】
継承した事業が課税事業者であった場合、簡易課税制度の利用が可能かもしれません。
簡易課税制度とは以下の要件を満たす事業にのみ適用される特例です。
・「消費税簡易課税制度選択届出書」の事前提出済
消費税を算出する際には国税庁が定めるみなし税率を使用して計算できるので、会計処理時の労力・時間の削減が期待できます。
上記の要件をすべて満たした状態で簡易課税制度を利用する場合は、「消費税簡易税制度選択届出書」を国税庁のホームページから入手してください。
なお提出期限は課税期間初日の前日までなので、早めに準備して申請を行いましょう。
【青色申告を選択する場合】
事業活動を継承すると確定申告の義務が発生しますが、申告方法には青色と白色の2種類があります。被相続人が青色申告を行っていた場合、事業継承とともに申告方法も継承します。
ただし事業そのものはいったん廃業届を提出して廃業しているので、対象事業における確定申告の方法は引き継がれません。「青色申告承認申請書」の提出が必要ですが、この申請書の提出期限は以下のように死亡日によって異なるので注意してください。
|
死亡日
|
提出期限
|
| その年の1月1日~8月31日 | 死亡日から4カ月以内 |
| その年の9月1日~10月31日 | その年の12月31日まで |
| その年の11月1日~12月31日 | 翌年の2月15日まで |

多くのケースでは、死亡日から1カ月以内に提出しなければならない開業届とともに提出します。しかし間に合わない場合は、上記の一覧表を参考にして各期限内に申請を行ってください。
▼ 青色申告の詳細についてはコチラ!
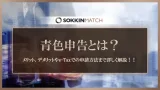
【家族や親族を雇う場合】
青色申告事業者で家族・親族を従業員として雇用する場合、青色事業専従者の届出が必要です。
この手続きは青色申告事業者のみに与えられる特例であり、事前に申請しておくと家族・親族に支払う給与を経費計上できます。家族・親族を従業員として雇用している青色申告事業者の場合、節税対策のために事前申請を行っていることが多いので事業継承をする際には忘れないようにしましょう。
国税庁の「A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続」ページ内に「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」のPDFファイルのリンクが掲載されているので、アクセスしてダウンロードしてください。
届出書とセットになった書き方を参考にしながら必要事項に記入し、管轄する税務署に提出します。
なお提出期限は、「経費算入する年の3月15日」または「その年の1月16日以降に継承した場合は、継承日から2カ月以内」です。
相続放棄の事務処理
「相続の意思決定を行う」の項目で相続放棄について触れましたが、相続放棄をする具体的なケースとして以下のようなものがあげられます。
・相続手続きを行いたくない
・相続争いに巻き込まれたくない
・遺産が少ない
生活が安定していて遺産が少ない場合は、相続の手続きなどに必要な労力・時間と見合わないと判断して相続放棄するケースも少なくありません。
相続放棄は自分で手続き可能です。
2. 申述書を作成
3. 申述書と必要書類をあわせて家庭裁判所に提出
4. 家庭裁判所から「照会書」を送付
5. 「照会書」に明記されている質問に回答して返送
6. 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」を送付
なお相続放棄は被相続人の死亡日から3カ月以内が期限なので、放棄したい場合は早めに必要書類などをそろえて家庭裁判所に提出してください。
相続税の減税対策
事業を継承すると相続税が発生しますが、規模・所得額によっては納税額が高くなる可能性があります。
そこで効果的な減税対策を紹介するので、参考にしてください。
個人版事業承継税制
個人版事業承継税制とは、個人事業主が事業を継承した場合に事業用資産にかかる納税の期間を猶予する税制です。
|
概要
|
|
|
対象者
|
・後継者 ・2019年1月1日~2028年3月31日までの相続や贈与 ・2019年4月1日~2026年3月31日までに個人事業承継計画の提出が必要 |
|
提出期限
|
相続開始から8カ月以内 |
認定申請書の提出は相続開始から8カ月以内ですが、税制の適用を受けるためには納税申告と担保提供も行わなければなりません。申告と納税額に見合う担保を提供する期限は相続開始から10カ月以内に定められているので、申告書類の作成と担保の準備をしてください。
なお税制の猶予期間中は3年に1回の割合で継続申出書の提出が必要なので、忘れずに申出書の作成・提出を行いましょう。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を80%下げる減税制度です。以下の要件を満たすことで相続税の計算のベースとなる土地の評価額が下がるので、節税できます。
2. 相続開始3年以前から対象の土地で事業活動を実施
3. 相続人が相続税申告期限までに事業継承および宅地保有
なお減額割合は事業用宅地の区分によって以下のように異なり、同一ではありません。
|
区分
|
要件
|
面積
|
減額割合
|
|
| 事業用 | 特定事業用宅地等 | ・特定事業用宅地等 ・特定同族会社事業用宅地等 |
400平方メートル | 80% |
| 貸付事業用 | 貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 50% | |
適用期間は、相続税の申告期間と同様の被相続人の死亡日から10カ月以内です。相続税の申告時に、遺言書の写しや相続人全員の印鑑証明書などを貼付して申請します。
法人化する
個人事業主としての事業活動を法人化すると、さまざまな控除制度が適用できるなどのメリットがあり、節税対策が可能です。ただしデメリットもあるので、法人化する際には両方を考慮したほうがよいでしょう。
|
メリット
|
デメリット
|
| ・給与所得控除の適用可能 ・配偶者(特別控除)の適用可能 ・扶養控除の適用可能 ・家族への役員報酬で所得分散が可能 ・赤字の繰越最大10年 |
・設立費用が必要 ・社会保険への加入必須 ・赤字決算時の納税義務が発生 |
上記のように法人化すれば、適用可能な控除制度が増えるなどのメリットは多数あります。
しかしその一方で設立費用が必要なうえに、赤字決算時にも税金を納めなければなりません。赤字の繰越期間は最大10年に延長されますが、金額によっては事業継続が困難な場合もあります。
事業継承は今後も事業活動を継続することが前提であることから、相続税の減税・節税対策という一時的な目的のために法人化を選択するのではなく、長い目で見てどちらがよいかを考えたほうがよいでしょう。
▼ 法人での節税対策はコチラ!

まとめ
個人事業主が死亡した場合の事務処理・減税対策を中心に解説しました。
個人事業主死亡後の事業関連における事務処理は、相続人が行わなければなりません。手続きによっては申請・提出期限が設けられていないものもありますが、ほとんどは死亡日を起算日として一定の期限が設定されています。
事業関連の事務処理期間は短いものもあるので、このような手続きに慣れていない場合は困難を極めることもあるかもしれません。
相続税もあわせて本記事を参考に知識・理解を深め、早めに準備をしておくことをおすすめします。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。