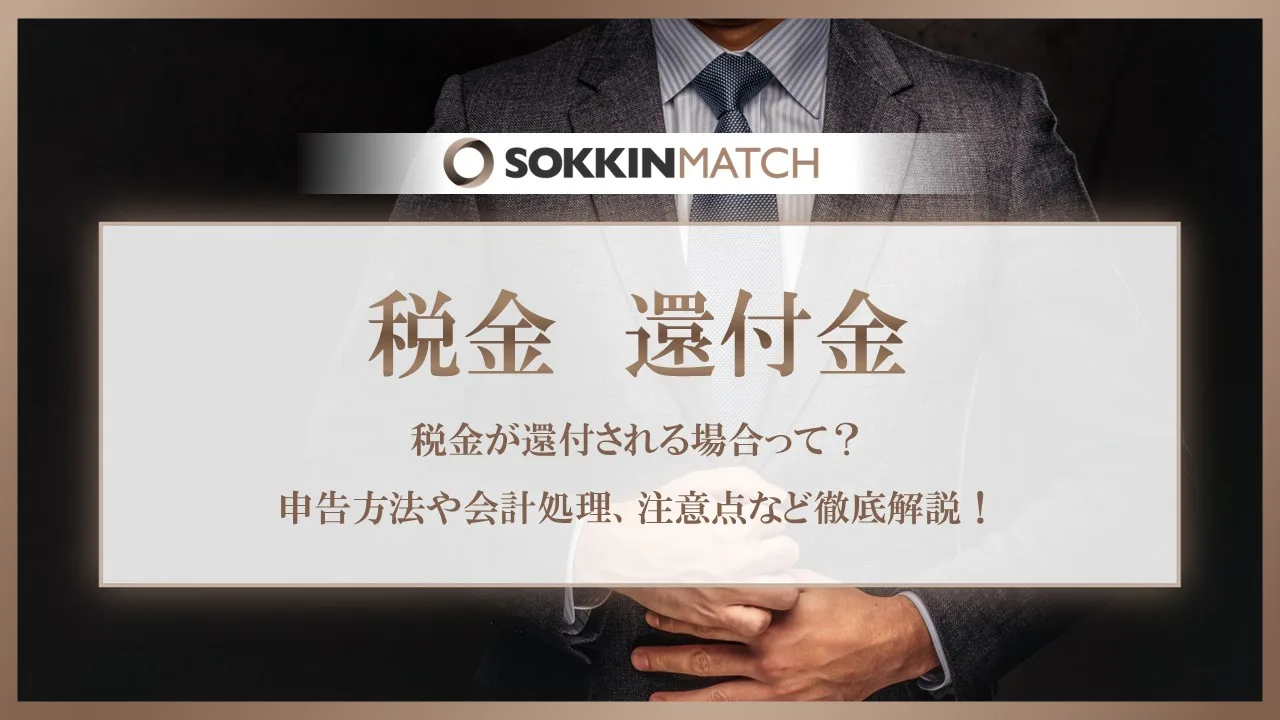還付金とは、税金を本来より多く払いすぎている場合に、還付の手続きを行うことで戻ってくるお金のことです。
確定申告や年末調整を行う際に、「自分は還付金を受け取れるのか」「金額はいくらになるのか」といった点が気になる方も多いのではないでしょうか。
また、所得税に限らず、消費税や法人税などの税金を払い過ぎている場合も、必要な手続きを行うことで還付金を受け取ることができます。
還付金ってなに?

たとえば、給与所得者は毎月の給料から所得税や住民税が天引きされていますし、個人事業主は予定納税として確定申告期限前に所得税の一部を先に納税しています。
ところが、年末になって確定する実際の税額が当初の予定より少なくなったときは、あらかじめ支払った税額が本来よりも多く、払い過ぎになっている場合があります。
このようなときに、還付の申請を行うことで、払いすぎた税金の返還を受けることができるのが税金の還付の仕組みです。この仕組みによって戻ってきたお金のことを還付金と呼びます。
年末調整で還付金をもらえるケース

ここでは、サラリーマンなどの給与所得者が、年末調整の手続きによって還付金がもらえるケースはどのような場合なのかをまとめて紹介します。
基本的な仕組みは、毎月給料から源泉徴収された税額が、年末調整によって決定した最終的な税額よりも多かった場合に、払い過ぎた税金が戻ってくるのが還付金です。
以下で還付金が受け取れる主なケースを紹介しますので、ご自身に当てはまるものがないか確認してみてください。
扶養対象者が増えた場合
扶養している親族の年齢などで控除額が変わり、家計の負担が大きくなる19歳以上23歳以下の親族は特定扶養親族として63万円が控除されます。複数人の扶養親族がいる場合は、人数分の控除を受けることができます。
年の途中で扶養対象者が増えたときは、年末調整の書類で扶養控除を申請することで還付金を受け取ることができます。
たとえば、その年に新たに子供の年齢が扶養控除の対象となる16歳になったり、自分で生活費を稼いでいた親族が仕事を辞めて扶養に入ったりする場合が考えられます。
扶養控除の控除額は12月31日時点の扶養親族の人数で決まります。

年の途中で扶養対象となった場合でも人数にカウントすることができます。
▼ 扶養対象者となる条件について詳しく知りたい方はこちら

結婚した場合
結婚した場合は配偶者控除が適用できますので、年末調整の書類で申告することで還付金を受け取ることができます。
配偶者控除は夫または妻がいる人が受けられる所得控除で、控除額は最大48万円です。
前年に配偶者がいなかった場合は、配偶者控除適用なしの金額計算で税金が天引きされています。年末調整で配偶者控除を申請することで、払いすぎた税金が戻ってきます。
本人または家族が障害者の場合
本人または配偶者、扶養親族のいずれかの人が障害者の場合は、年末調整で障害者控除を申請することで還付金を受け取ることができます。
障害者控除には3つの区分があり、以下のように控除額が変わります。
・特別障害者(40万円)
・同居特別障害者(75万円)
特別障害者は、障害等級が1級であるなど障害の程度が重い場合に適用されます。
障害者控除の対象者が複数いる場合は、人数分控除を受けることができます。
ひとり親の場合
納税者本人がひとり親に当てはまる場合はひとり親控除が適用できますので、税金が安くなり還付金が戻ってきます。
ひとり親控除の控除額は35万円です。
ひとり親とは、単身で子育てを行っている人のことで、いわゆるシングルマザーやシングルファザーのことです。

結婚歴は関係ありませんので、離婚してひとり親となった人も、過去に結婚したことがない人も対象となります。
ただし、子供を扶養していない場合は対象外となりますので注意してください。たとえば、子供が独立して同一生計でない場合や、子供がアルバイトをして所得額が年間48万円を超えている場合はひとり親控除を適用することができません。
夫と離婚・死別した場合
夫と離婚または死別した後に別の人と結婚していない女性は寡婦に当てはまりますので、寡婦控除を適用することができます。寡婦控除の控除額は27万円で、年末調整の書類に記入をするだけで還付金を受け取ることができます。
夫と離婚または死別した女性のうち、子供がいる人はひとり親控除の対象となりますので、寡婦控除の対象外です。
なお、寡婦控除は女性しか適用できないため、妻と離婚または死別した男性は対象外です。
個人で社会保険料を支払った場合
個人で社会保険料を支払った場合は、社会保険料控除の対象となります。支払った保険料額そのままが控除額となり、節税効果が大きいため年末調整で忘れずに申告するようにしましょう。
対象となる社会保険料には、国民健康保険や国民年金、労働保険など幅広くあります。

納税者本人だけでなく、家族のために支払った保険料も控除の対象となります。
例えば、大学生のお子さんに代わって親が国民年金保険料を支払った場合、その金額は親の所得控除の対象となります。
ただし、現在勤務している会社で加入している社会保険についてはすでに控除適用済みのため還付金が戻る対象とはなりません。
年末調整で社会保険料控除を申請して還付金が戻るのは、以下のようなケースです。
このような場合は、年末調整で申告することで還付金が戻ってきます。
生命・地震保険に加入している場合
生命保険や地震保険に加入して、保険料を支払った人は、生命保険料控除や地震保険料控除を受けることができます。

ただし、支払った保険料額そのままではなく、最大12万円が控除額となりますので注意しましょう。
生命保険料控除には病気や怪我などの生命保険だけでなく、介護医療保険や個人年金の保険料も含まれます。
これらの保険料控除は年末調整で申告できます。保険会社が発行する控除証明書を準備して、年末調整の書類に記入して勤務先に提出しましょう。
iDeCoに加入している場合
iDeCoに加入して毎月掛金を支払っている人は、小規模企業共済等掛金控除を受けられます。その年に支払ったiDeCoの掛金の金額を年末調整で申告することで、所得控除が適用され、還付金を受け取ることができます。
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済法で規定されている共済契約の掛金を支払った場合に、支払った金額分が所得控除される制度です。つまり、iDeCoに加入して掛金を支払うと、老後資金を積立しながら税金も安くすることができます。
住宅ローン控除を受けている場合
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けている人は、年末調整で住宅ローン控除用の用紙に記入して提出することで還付金を受け取ることができます。
ただし、対象となる住宅は、床面積が50㎡以上であることや、認定長期優良住宅または低炭素建築物に該当することなど、細かい適用条件があります。(No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁)
なお、住宅ローン控除の最初の1年目については、確定申告で手続きを行う必要があります。初年度の手続きが完了すると、2年目以降の控除申請用の書類が税務署から発行されますので、それを勤務先に提出することで還付金を受け取ることができます。
確定申告で還付金をもらえるケース
次に、自分で確定申告をすることによって還付金がもらえるケースをまとめて紹介します。
毎年確定申告を行う個人事業主はもちろん、サラリーマンなどの給与所得者も確定申告をすることで還付金がもらえる場合があります。
確定申告で確定した所得税額が源泉徴収税額より少ない場合
給与所得者以外の人でも収入源から所得税が源泉徴収されている場合があります。このような人は、確定申告で確定した所得税額が源泉徴収税額よりも少ない場合は、税務署から直接還付金を受け取ることができます。
たとえばフリーランスで仕事をしていて、クライアントから報酬を受け取る際に税金が源泉徴収される場合があります。フリーランスには年末調整の手続きがありませんので、自分で確定申告を行って各種の所得控除を適用することで還付金が戻ってきます。
その他に、株取引の利益で生活している人や、年金受給者は収入源から税金が源泉徴収されていますので、確定申告をすると還付金が戻ってきます。
確定申告で確定した所得税額が、予定納税額より少ない場合
確定申告で確定した所得税額が予定納税額より少ない場合は、予定納税で本来の税額より多く納税していますので、払いすぎた税金が還付金として戻ってきます。
たとえば、高額の設備投資を行って経費が増えた場合や、業績が悪化して赤字になった場合に、予定納税額が実際の所得税額より大きくなります。こういったケースでは、例年通り通常の確定申告を行うだけで還付金が発生することになります。
確定申告でのみ適用される控除を年末調整済みの人が申告した場合
会社員や公務員などの給与所得者が確定申告をして還付金が戻ってくるケースもあります。
給与所得者は年末調整で所得控除の申請ができますので、納税手続きが簡略化されています。
しかし、以下のように勤務先で手続きができない控除もあります。
上記の控除については、自分で確定申告をして税務署に直接申告することで還付金を受け取ることができます。
以下でそれぞれの控除について解説します。
医療費控除
医療費控除では、病院の治療費や入院費用、医薬品の購入費用などを年間で10万円以上支払ったときに、支払い額に応じて控除を受けることができます。
医療費控除は年末調整では申告できないため、具体的な医療費の支払い明細や領収書などを準備して確定申告をする必要があります。
医療費控除の申請内容が認められれば、年末調整で計算した金額よりも所得税額が安くなりますので、税務署から直接還付金を受け取ることができます。
また、医療費の総額が10万円に達しない場合でも、セルフメディケーション税制で控除を受けられる場合もあります。これは自身で健康診断を行うなど病気の予防に努めている人が医薬品を一定額以上購入した場合に、医療費控除とどちらかを選択して適用できる控除です。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制で、どちらか控除額が大きい方を選択して申告するようにしましょう。
雑損控除
雑損控除は、災害や盗難などの被害にあって損害を受けたときに納税の負担を軽減するための所得控除です。地震のような自然災害だけでなく火災のような人為的な災害や、盗難や横領などの被害も対象となります。
雑損控除の控除額は以下のうち多い方の金額です。
2.(災害関連支出の額 – 保険金などで補てんされた額) – 5万円
雑損控除の適用を受けるには、確定申告書を作成し、損害状況を証明する書類を添付して税務署に提出する必要があります。申請が認められれば納税額の負担が軽減されるため、還付金として戻ってきます。
寄付金控除(ふるさと納税)
寄付金控除は、国や地方自治体、特定公益増進法人に対して寄付を行ったときに、寄付額に応じて控除が受けられる制度です。その年に寄付した金額から2,000円を引いた金額が控除額となります。
寄付金控除の身近な例としてはふるさと納税があります。インターネットなどを利用してふるさと納税を取り扱っているサイトで好きな自治体を選んで寄付を行うと、その寄付額から2,000円を引いた額の控除が受けられます。さらに、ふるさと納税では寄付先の自治体から返礼品を受け取れますので、実質的な節税にもなります。
寄付金控除を受けるには確定申告が必要です。ただし、給与所得者の場合は確定申告なしでふるさと納税の控除が受けられる「ワンストップ特例制度」がありますので、そちらを活用するとよいでしょう。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、自分が住むための家を新築したり、長期優良住宅としてリフォームしたり、購入したりする際に住宅ローンを利用した場合に、年末のローン残高に応じて所得税や住民税が控除されます。
住宅ローン控除を受けるには、初年度のみ税務署での確定申告が必要です。
2年目以降は勤務先の年末調整で控除が適用されるため、手続きが簡略化されます。ただし、初年度に税務署で確定申告を行わないと控除が受けらませんので注意しましょう。
特定支出控除
特定支出控除は、給与所得者が業務で必要な支払いを自己負担で行ったときに受けられる控除です。対象の支出は、通勤費や転勤時の引越費用、単身赴任から帰宅するための旅費、制服や作業服の費用、資格取得費用、研修費用、書籍代などがあります。
ただし、対象となるのは業務を行ううえで必要な支出のみで、給与の支払者(通常は雇用主)の証明が必要です。特定支出控除は勤務先の年末調整では手続きができませんので、自分で確定申告を行う必要があります。
業務で必要な支払いを行い、それが特定支出控除の対象となると思われる場合は、まずは勤務先の担当者に相談してみましょう。
年末調整で控除の申告漏れがあった場合
年末調整では扶養控除や配偶者控除、各種の保険料控除など、基本的な所得控除は申請できます。しかし、知識不足や記入ミス、記入忘れなどで本来受けられる控除が正しく申告できないことも考えられます。
年末調整で控除の申告漏れがあった場合、そのままにしておくと還付金を受け取ることができません。しかし、翌年の2月16日〜3月15日の期間に自分で確定申告を行い、改めて正しい控除の申告を行えば、還付金を受け取ることができます。
なお、個人事業主が確定申告を行った際に控除の申告漏れがあった場合も、期限内に再度確定申告書を作成して提出し直せば、再提出した申告書に記入した控除が適用されます。
会社を退職した場合
会社を退職した場合で、退職時に年末調整を受けていない場合は、その会社の給料から天引きされた所得税額は、本来の納税額より多い可能性が高いです。これは、年末調整を受けていないため、各種所得控除が適用されないまま源泉徴収税額が計算されているからです。
この場合は、年が明けてから自分で確定申告を行い、適用できる所得控除をすべて申請することで還付金が受け取れる可能性が高いです。
赤字が出た場合
個人事業主が事業で赤字を出した場合、確定申告をすることで還付金が受け取れる可能性があります。
ただし、請求すれば必ず還付が受けられるわけではないため注意が必要です。たとえば、赤字の原因となる必要経費に事業と関係のない支出が含まれていたりすると、税務署から指摘を受けてしまいます。還付を受けるためには、正確な記帳や必要書類の準備が必要となります。

あらかじめ青色申告の承認を受けておく必要がありますので注意しましょう。
還付申告を行おう!
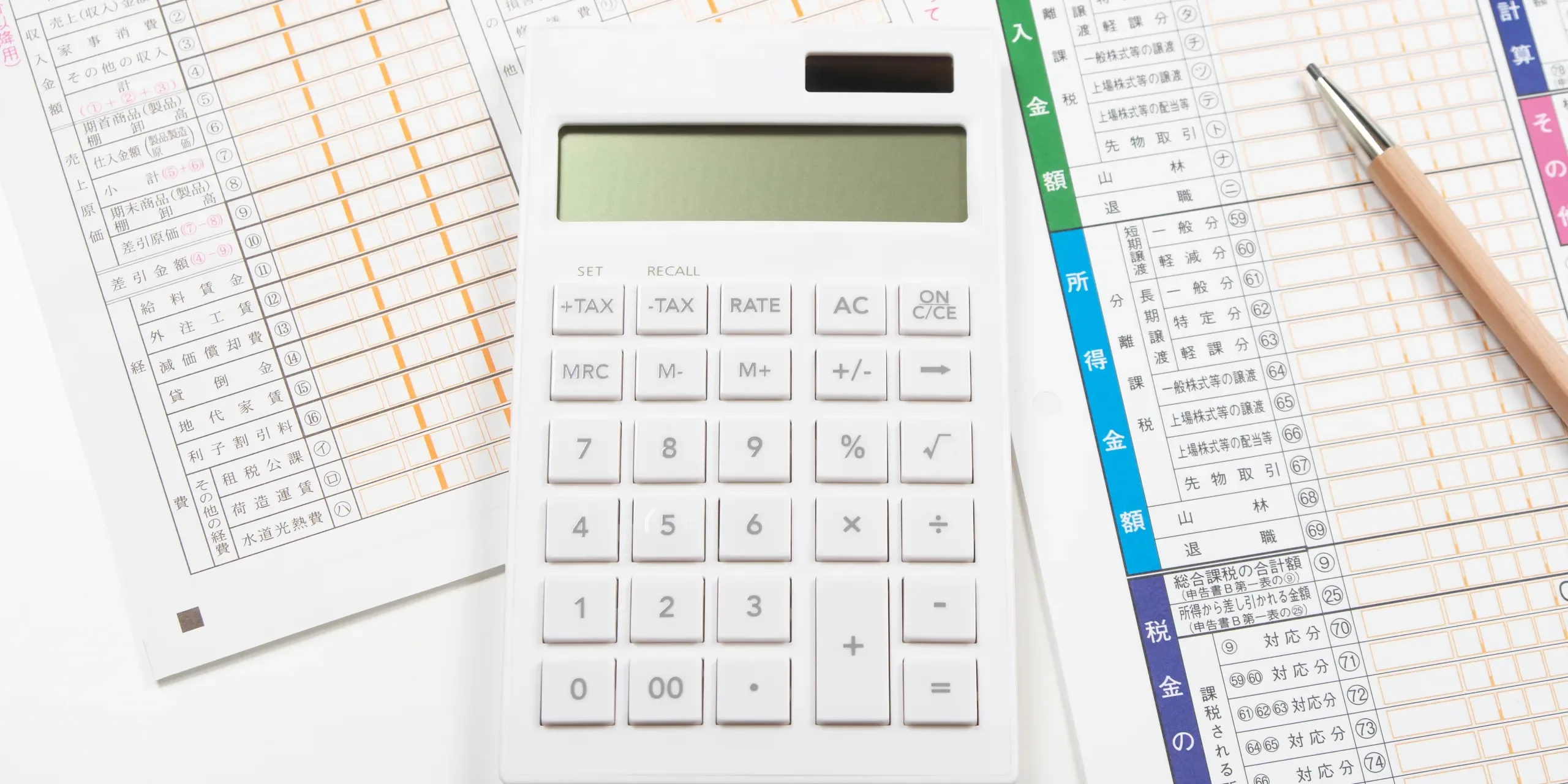
年末調整を行った人や確定申告をしていない人で、本来の税額より多く納税している場合は還付申告を行うことで還付金を受け取ることができます。
ただし、還付申告は確定申告と同じ申告書で行いますので、確定申告を行う人は還付申告を別で行う必要はありません。
以下で、所得税の還付申告の手続き方法や申告書の記入方法を詳しく解説します。
還付申告に必要な書類
還付申告に必要な書類は以下のとおりです。
・本人確認書類
・控除を受けるための証明書
申告書の提出時には、マイナンバーカードなどの本人確認書類の写しを添付します。また、保険料控除を受けるときの控除証明書や、医療費控除を受けるときの医療費の明細書など、控除を受けるための証明書類も準備しておきましょう。
還付申告の提出方法
記入した申告書は以下の方法で提出します。
・郵送
・税務署に持ち込み
e-Tax
e-Taxはインターネットを使って申告書を電子データとして送信して提出する方法です。紙の申告書を作成せず自宅で手続きできるのがメリットですが、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホかICカードリーダーを準備する必要があります。
郵送
税務署に持ち込み
受取場所の記入
確定申告書が準備できたら、必要事項の記入を行いましょう。
還付金の受け取りに関する項目は、確定申告書第一表の右下に下の画像のような「還付される税金の受取場所」という欄があります。
還付金を銀行振込で受け取る場合は、希望する金融機関の口座情報を記入します。

振込以外の方法としては、郵便局の窓口で直接受け取ることもできます。その場合は郵便局名等の欄に希望する受け取り場所を記入しましょう。
所得額の記入
次に、「所得金額等」の欄にその年の所得額を記入していきます。
①〜⑫の欄がありますが、その年に発生した所得の項目のみ記入し、発生していない所得は空欄のままにしておきます。

たとえば、給与所得者で勤務先の給料以外に収入がなかった人は、⑥の給与所得の欄に金額を記入し、その他は全て空欄にします。次に、⑫の合計の欄に給与所得の金額をそのまま記入すれば完了です。
副業で事業所得や雑所得などがある人は、その所得金額を適切な欄に記入し、全ての所得の合計額を⑫に記入します。
控除額の記入
次に、申請する所得控除の控除額を「所得から差し引かれる金額」の欄に記入していきます。
所得控除は全部で15種類ありますので、自分が対象となる控除の欄のみを記入し、対象外のものは空欄にしておきます。最後に、すべての控除額を合計して㉙の合計の欄に記入しましょう。
年末調整で申告できない所得控除は、㉖〜㉘の3種類です。ふるさと納税を行った場合は、㉘の寄付金控除の欄に控除額を記入しましょう。
なお、住宅ローン控除については、この欄ではなく以下で説明する「税金の計算」の欄で記入します。
税金の計算
次に、「税金の計算」の欄のうち、自分の申告内容に該当する項目を記入していきましょう。
住宅ローン控除を受ける人は㉞の住宅借入金等特別控除の欄に区分と控除額を記入します。
給与所得者の還付申告では、㊽の「源泉徴収税額」の欄が重要です。勤務先から発行された源泉徴収票に記載されている金額を正確に記入しましょう。この源泉徴収税額と実際の所得税額の差額が還付金として戻ってきます。
個人事業主が支払った予定納税額が本来の税額より多い場合は、㊿の欄に正しく金額を記入することで還付金を受け取ることができます。
還付金の受け取り時期
確定申告を提出してから還付金を受け取れるまでの期間は、約1ヶ月〜1ヶ月半程度かかることが多いです。ただし、e-Taxの方が手続きが早く進み、還付金の受け取り時期も若干早くなります。
申告方法ごとの還付金の受け取り時期の目安は以下のようになります。
| 確定申告の方法 | 還付金の受け取り時期の目安 |
| e-Taxで申告 | 約3週間程度 |
| 郵送または税務署に持参で申告書を提出 | 1ヶ月〜1ヶ月半程度 |
できるだけ早く還付金を受け取りたい場合は、e-Taxで申告するようにしましょう。
還付金の計算方法

還付申告を行うことでどのくらいの金額の還付金が受け取れるのか、自分で事前に計算することができます。
以下の条件で実際に還付金の計算シミュレーションを行ってみましょう。
・収入:400万円
・給与所得控除額:124万円
・基礎控除額:48万円
ここでは計算方法を分かりやすくするため、基礎控除以外の所得控除は適用なしでシミュレーションしています。配偶者控除や医療費控除など、その他の控除が適用できる人は、控除額にプラスしてください。
還付金の計算は以下の手順で行います。
2. 源泉徴収税額との差額を計算する
以下でそれぞれのステップを具体的に解説します。
step1 所得税額を計算
まず、年末時点で確定した収入や所得額、適用できる所得控除などをもとに、その年の正確な所得税額を計算します。
この所得税額が実際に納税する税額なので、源泉徴収された税額が所得税額よりも大きい場合に差額が還付金として戻ってきます。
所得税額を計算する手順は以下の通りです。
2. 課税所得額 = 所得額 – 所得控除額
3. 所得税額 = 課税所得 ×税率 – 控除額
4. 復興特別所得税額 = 所得税額 × 復興特別所得税率
5. 納税額 = 所得税額 + 復興特別所得税額
今回のシミュレーション条件で、実際に所得税額を計算してみましょう。
2. 課税所得額 = 276万円 – 48万円 = 228万円
3. 所得税額 = 228万円 × 10% – 97,500円 = 13万500円
4. 復興特別所得税額 = 13万500円 × 2.1% = 2,740円
5. 納税額 = 13万500円 + 2,740円 = 13万3,240円
なお、所得税の税率と控除額については国税庁ホームページに記載があります。復興特別所得税の税率は2.1%です。
参考:所得税の税率|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)
step2 源泉徴収税額との差額を計算
勤務先の給料から源泉徴収された金額からステップ1で計算した所得税額を差し引いて、残った金額が還付金の金額です。
計算式にすると以下のようになります。
源泉徴収税額の調べ方は、勤務先が発行してくれる源泉徴収票という書類に記載されていますので、その金額を使います。1年間で複数の会社に勤務した人は、それぞれの会社から源泉徴収票が発行されますので、全ての勤務先の源泉徴収税額を合計します。
今回の条件では以下のような計算になります。
今回のシミュレーションでは、26万6,760円の還付金が受け取れる見込みとなります。
還付金について知っておくべきこと

ここでは、還付金について知っておくと便利なことや注意点についていくつか紹介します。
①追加徴税の可能性がある
還付金を受け取るつもりで確定申告書を作成していて、実際に計算をしてみると源泉徴収税額の方が少ないというケースもあります。このような場合は逆に追加徴税となり、納税額が増えることになりますので注意が必要です。
たとえば、年末の時点で扶養親族の人数が減るなどして、所得控除の控除額が下がるといったケースがあります。
このようなケースでも、本来支払うべき所得税を納税していますので、損をしているわけではありません。追加徴税を避けるために申告をしないということは認められませんので、必要な手続きは行うようにしましょう。
②還付金はさかのぼって申告できる
国税の還付金は、その年のみでなく過去5年間までさかのぼって申請することができます。
たとえば、適用できる所得控除があることに後になってから気付いたという場合は、その年だけでなく過去の年度分の還付金も受け取ることができます。
③受け取りは銀行振込か郵便局窓口
所得税の還付金の受取方法は、銀行振込か郵便局窓口での受け取りのいずれかを選ぶことができます。
確定申告書第一表の右下に「還付される税金の受取場所」という記入欄がありますので、振込希望の口座情報か、または窓口で受け取りたい場合の郵便局名を記入しましょう。
④還付金がある場合は国税還付金振込通知が届く
申告内容が認められて還付金が受け取れるときは、振込み前に国税還付金振込通知が届きます。
通知書には還付金額や還付金の受け取り口座、振込の手続き日などが記載されていますので、受け取れる還付金の正確な金額をあらかじめ知ることができます。
⑤振込までは時間を要する
還付申告を行ってから還付金が振り込まれるまでに、通常1ヶ月から1ヶ月半程度の期間がかかります。特に、申請が込み合う時期は振込まで日数がかかることがありますので注意が必要です。
また、確定申告の提出書類に不備があった場合など、手続きのミスによって還付金が振り込まれないこともあります。振り込まれるはずの還付金がなかなか振り込まれないときは、税務署に問い合わせをしてみましょう。
e-Taxで還付申告をした場合は、WEB版e-Taxソフトのマイページにログインして、「還付・納税関係」の中の「還付金処理状況を確認する」を選択することでオンラインで確認できます。
郵送や持ち込みで申告した場合で処理状況を知る必要があるときは、管轄の税務署に直接問い合わせを検討してみましょう。
還付金の会計処理

ここからは、還付金の会計処理について見ていきましょう。
様々なケースにおいて、受け取った還付金をどのように処理すればよいか解説します。
中間納付額や見込納付額が確定納付額より多かった場合
中間納付額や見込納付額が確定納付額より多かったときは、「未収入金」の勘定科目を使います。「未収入金」は本業の営業活動とは直接関係のない債権に対して使う科目です。
また、その税金の種類によって「未収法人税等」としたり、「未収消費税等」としたりする場合もあります。
以下で、法人税の場合と消費税の場合の実際の仕訳例を紹介します。
法人税の場合
まず法人が法人税の還付金を受け取ったときの仕訳方法を見ていきましょう。
法人税の申告で40万円を納税していて、確定した法人税額が30万円だったケースを例とします。この場合は40万円を納付した際に「仮払法人税等」で処理しますが、最終的には10万円が還付されます。
決算時には以下のような仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
| 法人税等 未収還付法人税等 |
300,000円 100,000円 |
仮払法人税等 | 400,000円 |
還付金の受取時には以下のように仕訳します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 預金 | 100,000円 | 未収還付法人税等 | 100,000円 |
消費税の場合
次に、消費税の還付金を受け取るときの仕訳例を解説します。
消費税の記帳方法は税抜経理方式と税込経理方式の2種類があります。どちらを選択しているかによって仕訳方法も変わります。
ここでは、仮払消費税が40万円、借受消費税が20万円で、20万円が還付される場合の処理を解説します。
税抜き処理方式の決算時は以下のように仕訳します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 仮受消費税 未収消費税等 |
200,000円 200,000円 |
仮払消費税 | 400,000円 |
次に、還付金の受取時は以下のような仕訳となります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 預金 | 200,000円 | 未収消費税等 | 200,000円 |
税込処理方式の決算時は以下のように仕訳します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 未収消費税等 | 200,000円 | 雑収入 | 200,000円 |
還付金の受取時は以下のような仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
| 預金 | 200,000円 | 未収消費税等 | 200,000円 |
個人の還付金を事業用口座で受け取った時
個人事業主が個人で支払う税金を事業用口座で受け取ったときは「事業主借」の勘定科目を使って仕訳を行います。
事業主借は、個人的なお金を事業で使ったときの勘定科目で、事業用口座に事業の売上以外の入金があったときにも使用します。そのほかに、仕事用の交通費や消耗品などを個人のお金でかったときにもこの勘定科目を使います。
ここでは個人事業主の個人の所得税で3万円の還付金が発生し、事業用口座で受け取ったときの仕訳例を紹介します。
・還付金が判明したときの仕訳方法
| 借方 | 貸方 | ||
| 未収入金 | 30,000円 | 事業主借 | 30,000円 |
・還付金を受け取ったときの仕訳方法
| 借方 | 貸方 | ||
| 預金 | 30,000円 | 未収入金 | 30,000円 |
納付と還付が同じ会計期間内の時
事業所税として5万円を現金で支払い、後日過払いであると判明し、還付金2万円を振込で受け取ったケースの会計処理方法は以下のようになります。
・支払時
| 借方 | 貸方 | ||
| 租税公課 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
・受取時
| 借方 | 貸方 | ||
| 預金 | 20,000円 | 租税公課 | 20,000円 |
還付金の会計処理の注意点

還付金の会計処理を行うにあたって、気を付ける必要のある注意点について解説します。
適切な勘定科目の選択と正しい会計処理方法の適用
税金の納付や還付金の受け取り時期、その他の条件で勘定科目が変わりますので、適切なものを選択して使用する必要があります。
税金の支払いと還付金の受け取りが同じ会計期間内のときは反対仕訳で処理できますが、会計期間が違うときは処理が少し複雑になります。
また、個人事業主が事業用口座で還付金を受け取ったときは、事業と関係のない還付金でも仕訳が必要になりますので注意しましょう。
益金に算入する還付金と不算入の還付金がある
会社の所得の計算方法の基本は「所得 = 益金 – 損金」です。益金は収入のことで、損金は支出と考えるとわかりやすいでしょう。
還付金を受け取ったときは、税金の種類によってその還付金を益金に算入する場合と、不算入とする場合があります。
税金の納税時に損金として算入しないことになっている税金は、還付金を受け取ったときも益金に算入しません。以下のような還付金は益金に不算入となります。
・住民税の還付金
・所得税の還付金
・外国税の還付金
・欠損金の繰戻しによって発生する還付金
上記のような税金以外(事業税や利子税など)は、原則として納税時に損金参入しますので、還付金を受け取ったときは益金に算入します。
消費税の還付金を受け取るには?

ここからは、消費税の還付金の受け取りについて解説します。
消費税の還付金を受け取れる事業者には要件があり、対象者のみ還付申告が可能です。申請方法も他の税金と異なりますので注意が必要です。
消費税の還付を受けられる事業者の要件
消費税の還付を受けられる事業者の要件は以下のとおりです。
・原則課税を選択していること

課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、消費税の納税が免除されます。この場合は、消費税の還付を受けることができません。
原則課税とは消費税の課税方式のひとつで、仕入れにかかる消費税と売上にかかる消費税の実際の金額を正確に計算する方式です。課税方式として原則課税を選択している事業者は、消費税の還付を受けることができます。
これらの要件を満たした事業者が、消費税の還付が受けられるケースを以下で紹介します。
輸出企業で、売上の大半が課税対象でない場合
海外に商品を輸出したり、免税店で商品を販売するときは免税となりますので、売上にかかる消費税が発生しません。
輸出企業のように、売上の大半が輸出の取引や免税店での販売の場合は、仕入れにかかる消費税の方が多くなる可能性が高いため、消費税の還付を受けられる場合が多くなります。
収支が大幅に悪化した場合
消費税の還付を受けられる事業者の要件を満たしていれば、仕入れや経費の支出時に支払った消費税が、売上にかかる消費税より多い場合に、消費税の還付を受けることができます。
そのため、売上が急激に減少したり、収支が大幅に悪化したり、赤字になった場合は消費税の還付を受けられる可能性が高くなります。
高額な設備投資を行った場合
上記は売上が減少した場合ですが、逆に経費の支出が大きくなった場合も消費税の還付が受けられる場合があります。
たとえば、事業用の設備や建物、社用車など、高額な設備投資を行った場合は、経費の支出時に高額の消費税を支払っています。売上は同じでも支出が多くなると、消費税の還付を受けられる可能性が高まります。
消費税の還付金を受け取る方法
消費税の還付金を受け取るためには、税務署での手続きが必要です。具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
2.「消費税の還付申告に関する明細書」を作成する
3.「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」を作成する
4. 必要書類を税務署に提出する
このように、消費税の申告に必要な書類を作成して提出するのが基本的な手続き方法となります。
申告期限
申告期限は個人事業主と法人とでそれぞれ異なります。個人事業主は1月1日〜12月31日までの課税期間で消費税を計算して納税しますが、法人は個別に課税期間を設定するためです。
・法人の申告期限…課税期間が終了する日の翌日から2ヶ月以内
上記のように、還付の申告期限は、消費税の申告期限の日と同じ日になります。
必要書類
消費税の還付を受けるために準備する必要書類は、以下のとおりです。
・消費税の還付申告に関する明細書
・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
消費税の確定申告書は、消費税を納税するために使う通常の確定申告書と同じものを使用します。
上記3種類の書類がどのような書類なのか、記入する内容などを以下で解説します。
1.確定申告書の記入
まず、消費税の還付申告を行うための確定申告を作成します。
申告書は消費税を納税するために使う通常の確定申告書と同じものを使います。個人事業主と法人とで申告書の様式が異なりますので注意してください。
事業者名などの基本的な情報を記入し、売上高や消費税額などを順番に記入していきます。
2.明細書の記入
次に、「消費税の還付申告に関する明細書」の記入を行います。
上の画像のように、用紙2枚分の記入が必要です。
1枚目には、還付申告を行う理由と、課税売上に関する事項を記入します。輸出取引があった場合も1枚目にその明細を記入します。
続いて2枚目には課税仕入れに関する事項を記入します。仕入れ金額の明細、取得した棚卸資産の明細、所得した固定資産の明細の3つに分けて記入していく様式になっています。
3.計算表の記入
3つめの必要書類は「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」です。
この書類には、課税売上高や売上割合、控除対象の仕入税額などを記入していきましょう。金額計算を行う際には、1円未満の端数が出た場合には切り捨てにします。
作成した3種類の書類を期限内に税務署に提出することで還付申告の手続きが完了します。
まとめ
この記事では、税金の還付金について、還付金が発生する条件や金額の計算方法、会計処理方法などを解説しました。
所得税の還付金を受け取るための手続きは、会社員は主に年末調整で行い、個人事業主は確定申告で行います。医療費控除や初年度の住宅ローン控除のように、会社員でも確定申告をしないと還付金を受け取れないこともありますので注意しましょう。
また、適切な手続きを行うことで所得税だけでなく法人税や消費税の還付金を受け取ることもできます。ただし、税金の種類によって申請に必要な書類が違ったり、会計処理が異なりますのでその点にも注意が必要です。
それぞれのケースに応じた申請方法や注意点を再確認し、間違いのない手続きを行うことで払い過ぎた税金を確実に取り戻しましょう。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか