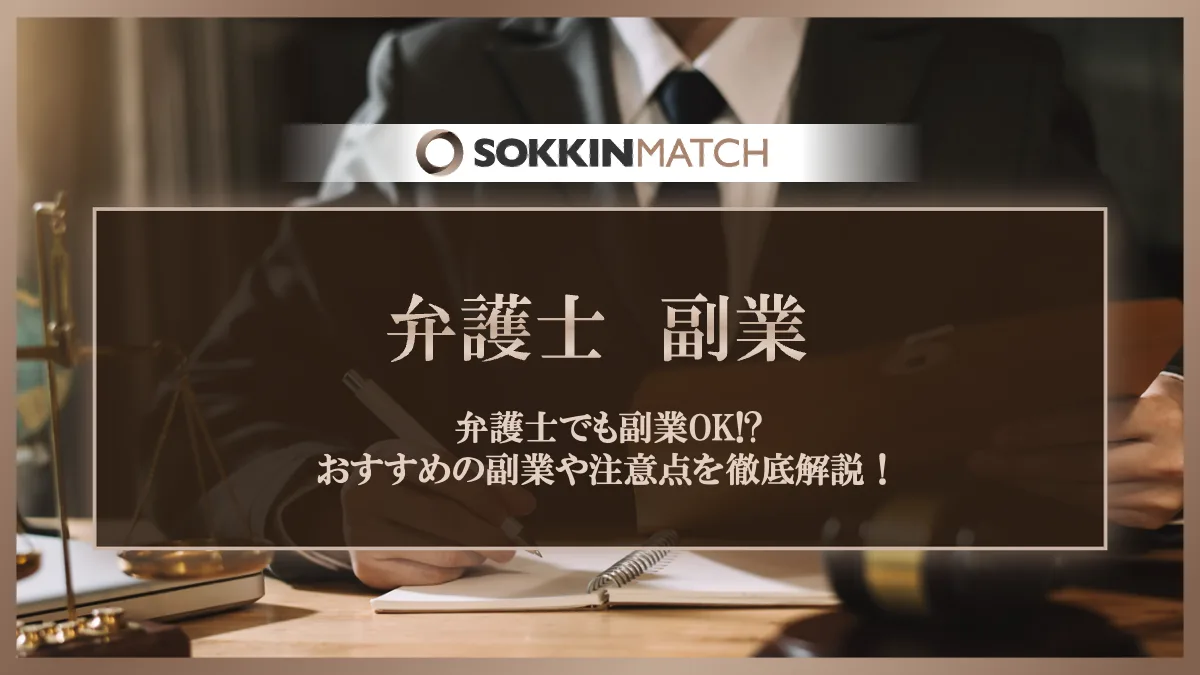さまざまな資格があるなかで、取得・合格の難しさから資格四天王のひとつにも数えられている弁護士。その弁護士業界にも、副業の波が押し寄せています。
しかしそのなかで、「弁護士が副業をしてもよいのか」「副業でどれだけ稼げるのか」といった不安・疑問を抱いている人も少なくありません。弁護士という立場上、さまざまな迷いが生じるのでしょう。

本記事では弁護士の副業事情について解説します。副業の可否・おすすめの副業・注意点なども含めて幅広く網羅して紹介するので、ぜひ参考にしてください。
▼ 副業について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
弁護士って副業OK?
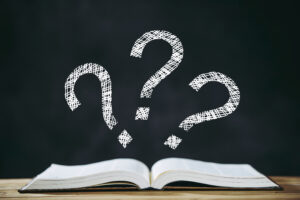
弁護士はその立場上、副業してもよいのか疑問に感じる人もいるでしょう。
「禁止だった場合、弁護士資格をはく奪されるかもしれない」「弁護士としての信頼を失墜させたらどうしよう。」といった不安を抱いている人も少なくありません。
このような不安・疑問を解消するために、弁護士における副業の原則と可能要件について解説します。
副業は原則可能
2018年1月に厚生労働省によって策定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、安全・秘密保持などの観点で問題があると判断できる場合を除いて推奨するように明記されています。
公務員など一部の職種については副業を禁止していますが、この禁止対象に士業は含まれていません。よって弁護士も、原則では副業が可能です。

弁護士が本業とは別に副業をしたからといって、法的な罰則が科せられることはありません!
副業可能要件
国の方針としては弁護士業を含めて、副業が推進されています。
しかし弁護士がその職業に従事するうえで守らなければならないのは、国の方針だけではありません。弁護士には弁護士法というものがあり、この法律に明記されている内容も守らなければならないのです。
弁護士法では第30条にて副業に関する許可要件が明記されています。具体的には次に掲げる場合において、指定されている内容等を所属弁護士会に事前届出をしなければなりません。
|
事前届出が必要なケース
|
届出内容
|
| 自ら営利目的の業務を営む | 商号および当該業務内容 |
| 営利目的の業務における取締役・執行役など | ・商号もしくは名称はまた氏名 ・本店もしくは主たる事務所の所在地または住所 ・業務内容 ・役職名 |
(参考:弁護士法 | e-Gov 法令検索)
そのほかにも弁護士法の第22条では、所属する弁護士会および連合会の会則を守らなければならないとしています。弁護士法以外にも守るべきルール等が設けられているので、副業する際には事前にこれらの確認を怠らないようにしましょう。
弁護士法の「営利を目的とする業務」って何?

前項目にて、営利目的の業務に該当する場合には事前に所属弁護士会への届出が必要であると解説しました。弁護士法第30条に明記されている「営利目的の業務」とは、具体的にどのようなもののことを指しているのでしょう。
結論から申し上げますと、営利目的業務についての明確な基準は示されていません。一般的に、以下に該当する場合は営利目的とは判断されず、事前の届出も不要です。
・個人の資産運用
ただし副業の業務内容・条件等によっては、営利目的の業務に該当するのかどうか判断に迷うこともあるでしょう。
弁護士の基本は弁護士法第1条に明記されている「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」を守らなければなりません。このイメージを損なうような仕事をしてはならないのが原則です。
判断に迷う場合は、所属弁護士会に相談してください。副業として考えている仕事の具体的な内容などを提示し、判断を仰ぐとよいでしょう。
また事前の届出は、明らかに弁護士のイメージを失墜させると判断されない限りは基本的に受理されます。「相談する時間がない」「所属弁護士会が遠い」などの理由に該当する場合は、判断に迷ったら届出を出しておくと無難です。
弁護士におすすめな副業

弁護士におすすめの副業をいくつか紹介します。
予備校講師
予備校講師は、弁護士のイメージを損なうことなく活動できる副業としておすすめです。弁護士を目指す人たちに知識・スキルを伝えれば、自分の知識の定着・スキルアップも期待できるでしょう。
予備校というと通学のイメージがあるかもしれません。しかしインターネットの普及に伴い、オンライン講座も増えつつあります。
オンライン講座なら指定の学校に赴く必要はなく、時間・場所を選ばずに活動が可能です。スキマ時間を上手に活用できる働き方ができるので、本業の弁護士業務との両立もしやすいでしょう。
ただし、オフライン・オンラインのいずれも講義を始める前の準備をしなければなりません。講義内容・資料作成だけにとどまらず、講義中に実施する小テストの作成・採点も業務内容に含まれるケースがあります。

講義自体はオンラインを選択すればスキマ時間を活用できますが、そのための準備に時間と労力を削られる可能性があるので注意してください。
法務顧問
法務顧問とは、企業・会社の法律に関する問題の解決・事前回避を行う仕事です。
企業・会社での法律に関連したトラブルは、社内規定・労務・契約関連など多岐にわたります。このような多種多様なトラブルに直面しないようにありとあらゆるケースを想定して、的確なアドバイスをしなければなりません。
また実際にトラブルが発生した場合には、紛争問題・訴訟に対応するケースもあります。そのため主な業務内容は、弁護士業としてのそれとほぼ同じといえるでしょう。
顧問という立場から企業・会社と個別に契約を締結するケースが多く、報酬面は副業案件としては割高です。本業とは別に副業でもしっかり稼ぎたい場合には、おすすめの副業といえます。
コンサルタント
コンサルタントとは企業・会社が抱える経営についての課題・問題点を明らかにして、具体的な解決策を提案する仕事です。
企業・会社の経営には法律的な問題・課題が発生するケースが多く、それらをいかにうまく解決するかが企業成長のカギを握っています。しかしこれらの問題・課題の多くは法律が関係していることから、社内だけで解決することは困難でしょう。そこで有力な候補として挙がってくるのがコンサルタントです。
一見すると前述した法務顧問と業務内容が似ていると感じるかもしれません。法務顧問は企業・会社が事業活動をしている限り業務が続くので、契約期間は長めです。一方のコンサルタントはプロジェクトごとに契約することになるので、顧問ほど契約期間は長くなりません。
メディア出演
メディア出演は、コメンテーターとして出演する仕事です。
以前はテレビ・ラジオが主流でした。しかし近年インターネットの普及に伴い、ネット配信番組でもコメンテーターとしての出演を求められるケースが増加しています。メディアとしての範囲が広がったことで、コメンテーター・専門家として出演する機会は増えたといえるでしょう。
一度でもメディア出演をして評価が高ければ、定期的な依頼につながる可能性はゼロではありません。そのためその「一度」の出演をいかにして勝ち取るかが、重要なカギを握っているといえます。
執筆業(法律系)
執筆業とは、文章を書く仕事のことです。弁護士の場合、法律に関する知識・スキルを活かした案件・仕事で活躍できるでしょう。
執筆業といっても、雑誌・書籍などに掲載するだけではありません。近年ではWebコンテンツ用の記事作成の依頼が増えてきました。特に専門家を対象とした法律関係のWebコンテンツ作成の依頼は、年々増加傾向にあります。その背景にはインターネットの普及に伴い、誰もが手軽に法律についての問題解決を調べられるようになったからでしょう。
Webコンテンツ用の記事作成の場合、単価は1文字単位で発生するケースが主流です。法律関係の場合は専門知識を必要とすることから、ほかのWebコンテンツ用の記事よりも1文字単価が高めに設定されています。
また他人が作成したWebコンテンツの監修をする案件も多くあり、こちらも報酬は高めです。

副業の場合、副業としての実績数が注目されますが、法律関係の執筆業の場合は弁護士としての実務経験等を証明すれば、ライターとしての経験がなくても高額報酬が獲得できるでしょう。
YouTuber
Youtuberとは、YouTubeを活用して動画配信をする稼ぎ方です。弁護士の場合、法律関連の動画を作成・配信することで収益化が期待できます。
具体的な収益化の方法として、以下のようなものがあげられるでしょう。
・アフィリエイト
短期間で収益が期待できる副業ではない点に注意してください。
弁護士が副業することのメリット

弁護士が副業するメリットを確認していきましょう。
収入源が増える
副業をすることで、単純に収入源が増えます。
例えば、弁護士事務所に所属して活動していたとしましょう。将来独立開業を目指していた場合、本業の収入だけでは足りないかもしれません。事務所を構える際にはさまざまな手続きが必要であり、その際の手数料も含めた初期費用がかかるからです。
またどのような状況・理由で、弁護士としての業務がストップするかわかりません。収入が弁護士活動としての本業のみだった場合、その業務がストップすると収入源が絶たれてしまいます。
副業も並行して始めておけば、貯蓄・独立開業の資金集めなどへ回すことが可能です。
新たな人脈を構築できる
新たな人脈が構築できる点も、副業するメリットのひとつです。
本業で弁護士として活動していると、人脈は弁護士活動の範囲に限られてしまいます。どこかの事務所に所属している場合は、なおさら人脈の範囲は狭くなるでしょう。
副業は、さまざまな業界・職種の人たちとの縁ができやすい仕事です。副業で仕事を進めるなかで、弁護士活動では出会うことがなかった業界・職種で活躍する人たちとの人脈を構築できるでしょう。このような縁が広がり、新たな仕事・案件が舞い込むチャンスもあります。
新たな知識・経験が本業に活かせる
新たな知識・経験が得られる点も、副業のメリットとしてあげられるでしょう。副業で選択できる業界・職種は多種多様だからです。
例えば副業としてYoutuberを選択したとしましょう。Youtuberとして活動して副業収入を得るためには、フォロワー・視聴者の興味・関心を引く話し方・伝え方をしなければなりません。多くの人たちの興味・関心をひきつける話術は、弁護士業でも重要なスキルのひとつです。
話術のスキルレベルはYouTubeなら、フォロワー数・閲覧数に反映されるので比較的容易に確認できます。
弁護士が副業することのデメリット

弁護士が副業することで得られるのは、メリットだけではありません。
副業することで発生するデメリットを紹介するので、前述のメリットとあわせて参考にしてください。
本業のパフォーマンスが低下する
副業を始めると、本業のパフォーマンスが低下する可能性があります。副業に集中しすぎる可能性が発生するからです。
副業でどのような職種を選択するのかにもよりますが、以下のような理由から力配分が副業に傾きすぎるリスクが高まります。
・副業の仕事のほうが楽しい
これらは理由の一例ですが、このような状態が著しくなると本業がおろそかになる可能性があるので注意が必要です。
プライベートの時間が減少する
プライベートの時間が減少する点も、副業のデメリットといえるでしょう。
基本的に副業は、本業のスキマ時間を活用して行います。本業のスキマ時間は、言い換えるならプライベートの時間です。その時間を副業時間にあてることになるため、必然的にプライベートの時間は減少します。
プライベートの時間が減少すると、以下のような問題が発生するかもしれません。
・家族・友人知人と疎遠になる
いずれも体調管理・プライベートな人間関係という観点から、よいとはいえないでしょう。
弁護士の社会的評価に影響を与える恐れがある
弁護士としての社会的評価に影響を与える恐れがある点も、副業のデメリットといえるかもしれません。
弁護士法第1条では、「社会正義の実現」が掲げられています。これは言い換えるなら社会正義という立場上、弁護士としての評価に悪影響を与えてはならないということです。
副業として選択した職種によっては、「弁護士なのに」といったよくない印象を与えるケースもゼロではないのです。
本業が弁護士である以上、副業をする際にはその本業・社会的地位に悪影響を及ぼさないように配慮することが重要といえるでしょう。
弁護士が副業する際の注意事項

弁護士が副業する際の注意事項を紹介します。
副業の適切性を見極める
副業を始める際には、その職種・業種の適切性を見極めてください。
弁護士として活動するかたわら、そのイメージ・地位を失墜させるような業務内容ではないかのチェックはしておくべきでしょう。
また将来的にリスクを負う可能性が少しでもあるような職種も、選ぶべきではありません。
弁護士という立場を考慮したうえで、副業として適切かどうかの判断・見極めを行ってください。
就業規則を確認する
就業規則を確認することも重要です。
厚生労働省が公表している副業・兼業のガイドラインでは、雇用主側に安全な労働状況の確保などを理由に就業規則での副業禁止を認めています。
これを受けて、就業規則にて副業やそれに付随する活動を禁止している企業・会社も少なくありません。
弁護士もその立場上、就業規則にて副業を禁止している可能性があります。禁止しているにもかかわらず隠れて副業を行い、そのことが知られてしまうと減給・解雇といったペナルティが科せられるかもしれません。
ただし、個人事業主として活動している弁護士の場合は、従業規則が存在しませんので、安心して副業を始めることができるでしょう。
利益相反に注意する
弁護士として副業する場合は、利益相反にも注意してください。
副業でも弁護士に関連した職種を選択した場合、利益相反が起こる可能性はゼロではありません。特に法務顧問・コンサルタントといった職業を副業として選択すると、業務内容が弁護士活動と似ていることから、知らない間に利益相反をしているケースもあるでしょう。
情報管理を徹底する
情報管理は徹底してください。
弁護士はその業務上、クライアントの個人情報・機密情報を入手できる立場にあります。
本業で知り得た情報を、副業でうっかり漏らすようなことがあってはなりません。たとえ故意であったとしても、弁護士としての信頼を失墜させる重大な行為です。最悪の場合、弁護士としての地位を失うことになるかもしれません。
副業情報は公開されることを心得ておく
副業の情報が公開されます。弁護士法第30条にて、副業を届け出た弁護士の情報を名簿に記載するとあるからです。
名簿に記載された内容は誰でも閲覧請求が可能なため、不特定多数の人に見られる可能性があります。副業の届出を行った場合にはその内容も公開されます。
このことから、名簿に掲載されても本業である弁護士活動に悪影響を及ぼさないような副業を選択したほうがよいでしょう。
弁護士が副業で成功するためには

弁護士が副業で成功するためのポイントを紹介します。
目標金額を明確にする
副業で成功するためには、あらかじめ目標金額を明確にしておくとよいでしょう。
最終的な金額を設定し、そこにたどり着くために小さく分けた金額をさらに設定しておくことをおすすめします。
さらに小さく分けた目標金額のほうには、期間も設定してください。ある程度のゆとりを考慮して期間を設定しておくことで、さらに達成しやすくなります。
継続する
副業は継続することが重要です。
副業を始めてすぐに、充分な収入が得られるとは限りません。副業は副業としての実績に左右されることが多く、実績数が少ない場合は報酬が低くなる可能性があります。
実績数を稼ぐためには、継続するしかほかに方法がありません。思うような結果が得られないからと早々に諦めるのではなく、長期的な活動を考えて継続しましょう。
スキマ時間を利用する
スキマ時間を利用することも、成功のカギです。
例えば移動時間に副業に関連する情報収集をしたり、SNSで営業活動をしたりできるでしょう。
副業を成功させるためには、どれだけの時間を副業に避けるかが重要といえます。少ない時間も徹底的に活用しましょう。
スキル・知識を拡充する
スキル・知識を拡充することも大切です。
副業は実績を含めた市場価値が重視されるため、新たな知識の獲得・スキルアップは欠かせません。
前述で紹介したスキマ時間の活用法なども参考にして、自身の市場価値を上げるために勉強・経験の強化を図りましょう。
成功者をTTPする
成功者の真似をすることも、成功への近道です。
副業で成功している人を真似ることで、思い通りの結果が得られることも少なくありません。
そのためには成功している人を徹底的にリサーチすることが重要です。その人の一日のスケジュールなどもチェックし、徹底的に真似てみましょう。思わぬ発見ができて、早い段階で副業で成功できるかもしれません。
まとめ
弁護士の副業事情について解説しました。
弁護士の副業は、国の方針として認められているので可能です。しかし弁護士には弁護士法をはじめとするさまざまなルールが設けられており、これらを守らなければなりません。また立場上、弁護士としての地位・イメージを揺るがすような行為も厳禁です。

本記事では副業を始めるメリット・デメリットとあわせて、注意点なども解説しました。これらを参考にして頂き、弁護士という立場を忘れないようにしながら副業を始めてください。
副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは
世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか